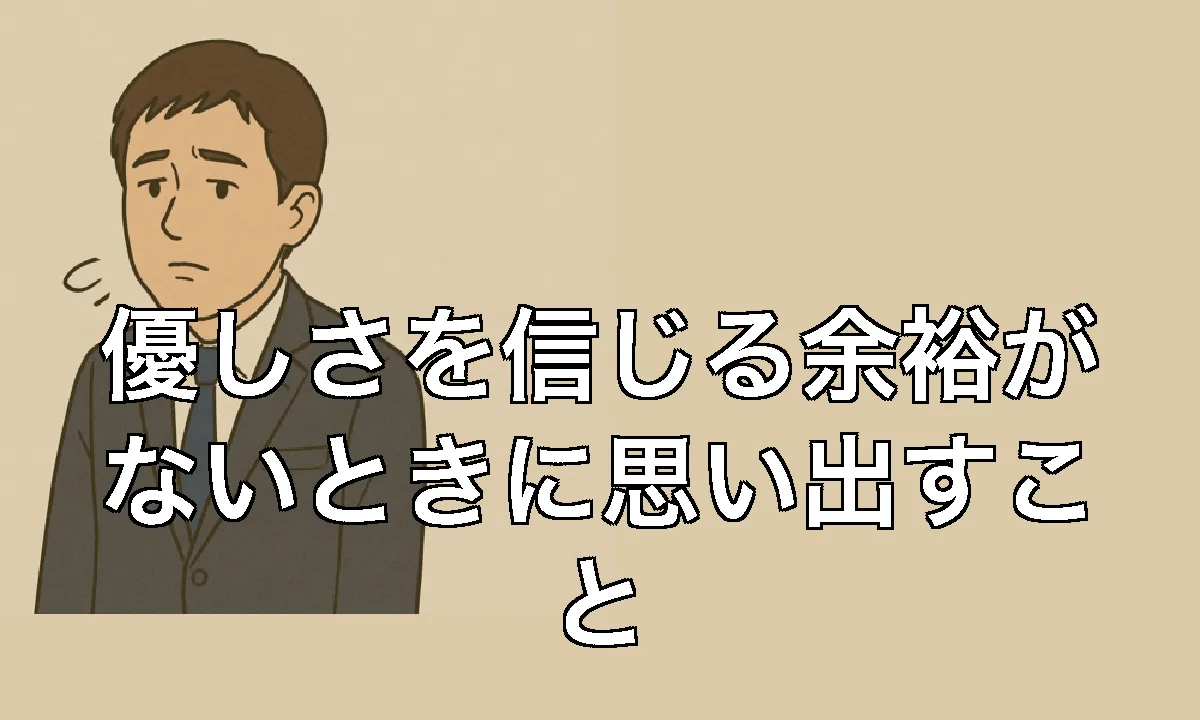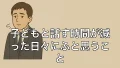なぜ優しさが疑わしく感じるのか
誰かがこちらに手を差し伸べてくれたとき、素直に「ありがとう」と言える自分がいなくなっていたことに、ある日ふと気づきました。疲れているときほど、誰かの親切が逆にプレッシャーになったり、「何か裏があるのでは?」と疑ってしまう。私も司法書士として日々多くの人と関わる中で、心のどこかに「警戒」が染みついてしまったように思います。誰もが忙しく、余裕を持てない時代だからこそ、優しさを疑ってしまう感覚は案外、普通なのかもしれません。
裏があるように感じてしまう瞬間
ある依頼者から「いつもありがとうございます」と菓子折りをいただいたとき、真っ先に思ったのは「何かやましいことでもあるのか?」でした。冷静に考えれば、ただの感謝の気持ちだったのでしょうが、そう素直に受け取れない自分がいました。親切や好意の裏に「見返り」や「期待」があると思ってしまうのは、たぶん、自分がそういう世界で生きていると思い込んでいるから。傷つきたくないという防御反応なのだと思います。
人の好意を素直に受け取れなくなる時
例えば、コンビニの店員が「温めますか?」と笑顔で聞いてくれたとき、ふと「マニュアルだからやってるだけだろ」と思ってしまった自分に嫌気がさしたことがあります。そうかもしれない。でも、そう決めつけることで何か大事なものを失っていないかとも思うのです。好意を素直に受け取れないというのは、自分自身が「受け取ってはいけない」と無意識に思い込んでいるからかもしれません。
他人の善意より先に責任が頭に浮かぶ
司法書士という仕事柄、人の善意よりも「リスク」や「責任」が先に頭をよぎる癖があります。例えば「これお願いしていいですか?」という一言にも、「それでトラブルになったら俺のせいだろ」と思ってしまう。責任感が強いと言えば聞こえはいいですが、それが人の優しさを受け取る妨げになっていると感じることもあります。やさしさを「問題の火種」ではなく「一瞬の癒し」として見られる心の余裕がほしいと、心から思います。
信じて裏切られた過去がこびりつく
昔、信じて任せたスタッフに横領まがいのことをされたことがあります。それ以来、「信じる」という行為自体に慎重になってしまいました。その人のせいで、何人もの誠実な人のことまで疑ってしまっていた。時間が経っても、その時の傷はしっかり根に残っていて、優しさを受け入れる瞬間に「また裏切られたらどうしよう」と反射的に構えてしまう。自分を守るための防御反応だと頭では分かっていても、それを解除するのは簡単じゃありません。
司法書士という仕事の性質がもたらす孤独
司法書士という仕事は、感謝されることもある一方で、ミスをすれば責任は全て自分に返ってくる立場です。成果が見えづらい上に、社会的にも“わかりにくい仕事”とされることも多く、誤解されたり過小評価されたりする場面もあります。その中で「自分は本当に人の役に立っているのか?」と疑心暗鬼になることがあり、結果として、人の言葉や優しさに対しても距離を取ってしまうことがあるのです。
感謝よりも苦情が先に届く仕事
何か問題が起きたとき、まず最初に連絡が来るのは司法書士です。「なんでこんなことに?」と怒り口調で始まる電話。説明すれば落ち着いてくれる方も多いのですが、感謝の声よりも怒りの声のほうが記憶に強く残るものです。どれだけ丁寧に仕事をしても「当然」と思われがちで、ミスがあれば「許されない」。そんな毎日の中で、優しさに触れても、「どうせ一時的なものだろう」と心を閉ざしてしまう癖がつきました。
「ありがとう」を受け取る隙間がない
事務員さんが「今日は残業になってすみませんね」と言ってくれたとき、私は「いや、大丈夫です」としか答えられませんでした。本当は「ありがとう」と言いたかったのに、頭の中は次の仕事の段取りでいっぱい。感謝を表現することも、受け取ることも、余裕がなければできないのだと痛感しました。余裕がなければ、人の優しさはただの「ノイズ」になってしまう。それが、いまの自分の現実です。
見えにくい仕事の成果と報われなさ
不動産の名義変更を終えても、依頼者の反応は「あ、終わったんですね」で終わることが多い。こちらは何十枚も書類を確認し、法務局とのやりとりにも神経をすり減らしているのに、その苦労は外からは見えません。成果が見えない、認められにくい。それが積み重なると、誰かが優しい言葉をくれたとしても「本当に分かってくれてるのか?」と心のブレーキがかかってしまうのです。
相談の重さに引きずられる日常
ときには相続や借金、家族間の揉め事など、人生の重たい場面に立ち会うこともあります。依頼者の苦しさや怒りに寄り添おうとすればするほど、自分の心が削られていくのを感じます。だからといって冷たくなりたくはないけれど、自分を守る術を身につけないと持たない。優しさを表現することも、受け入れることも、バランス感覚が必要な仕事です。
それでも優しさに助けられてきたこと
どれだけ優しさを疑っても、思い返せばそれに救われてきた瞬間は確かにありました。それを思い出せるかどうかが、また一歩を踏み出すきっかけになるのかもしれません。信じるのが怖くても、感謝を言えなくても、それでも誰かの気持ちは届いていた。そう思える瞬間が、ほんの少し心をやわらかくしてくれるのです。
昔の同僚の何気ない一言
もう何年も前、同業の先輩がふと「稲垣くん、ちゃんとやってるの見てるよ」と言ってくれたことがあります。褒め言葉でもなく、慰めでもないその一言が、なぜか胸に残っています。見てくれている人がいる、気にかけてくれている人がいる。それだけで、少しだけ自分を許してあげられた気がしました。優しさとは、派手な行動じゃなくて、さりげない言葉や態度の中にあるのかもしれません。
事務員さんの小さな気遣いに気づくまで
毎朝、私が出勤する前に机の上に置かれている湿布薬。特に何も言わず、ただ置いてあるだけ。でも、肩こりに苦しんでいた私には、それがどれだけありがたかったことか。最初は「気を遣わせて悪いな」と思っていましたが、ある日ふと「自分だってそういうことしてもらいたいと思ってるじゃないか」と気づいたのです。優しさは、気づいた瞬間から温かさに変わる。そう思えるようになりました。
優しさを受け取るにも準備がいる
優しさは、ただそこにあるだけでは伝わらない。受け取る側の心に余裕や準備がなければ、それは通り過ぎてしまうだけ。疲れているときや、落ち込んでいるときほど、それに気づけない。でも、ふとした瞬間に「あ、優しさだったんだ」と気づけたとき、自分自身にも少し優しくなれたような気がします。だからこそ、焦らなくていいのだと思います。
自分の優しさを忘れていたことに気づく
昔、困っているお年寄りに書類の内容を丁寧に説明したら、何か月も後にその方のご家族がわざわざお礼に来てくれたことがありました。私はその親切をすっかり忘れていました。それくらい自然にやったことだったのです。思えば、私自身も誰かに優しくしていた。自分の中にある優しさを思い出すことが、他人の優しさを信じる第一歩なのかもしれません。
優しさを信じるのではなく認めるという選択
優しさを「信じる」ことに抵抗があるなら、まずは「ある」と認めるだけでいい。誰かの好意や気遣いを完全に受け入れられなくても、それを否定しないだけで心が少し楽になります。人の優しさを信じる前に、自分の感覚を信じる。そのプロセスがあるだけでも、日々の暮らしはずいぶん違って見えるようになります。
信じなくていい でも無視しない
「この人、親切だけど裏があるかもな」と思ってもいい。でも、その優しさを完全に無視するのではなく、「もしかしたら本気で気にかけてくれてるのかもしれない」と想像してみる。その小さな「余地」が、やがて信じることへの橋になる気がします。完全に心を開かなくてもいい。ただ、閉じきらない。それだけでも十分です。
「疑い」と「距離感」がくれる安心
優しさを疑うことは、決して悪いことではありません。むしろ、自分を守るための健全な反応でもあると思います。でも、疑いすぎてすべてを遮断してしまうと、逆に自分が苦しくなる。だからこそ「少し距離を置く」ことは有効です。無理に近づこうとせず、でも完全に遠ざけもしない。その距離感が、安心と回復の土台になります。
もらった優しさはそっとポケットに
今は信じられなくても、いつか必要になる日が来るかもしれません。そのときのために、誰かの優しさを「今すぐ感謝しなきゃ」と思わずに、そっと心のポケットにしまっておく。そんなふうに受け取ることだってありだと思うのです。感情の整理がつくまで、時間が必要なときもあります。無理せず、ゆっくりでいいのです。
ありがとうを声に出せるタイミングを待つ
「ありがとう」と言いたくても、言えない日があります。気持ちが追いつかない、言葉が重すぎる、そんなときは無理に出す必要はありません。でも、タイミングはいつか来ます。自分の中で気持ちが落ち着き、素直に感謝を伝えられる日がきっと来る。そのときまで、焦らずに待てばいいのだと、私は思います。