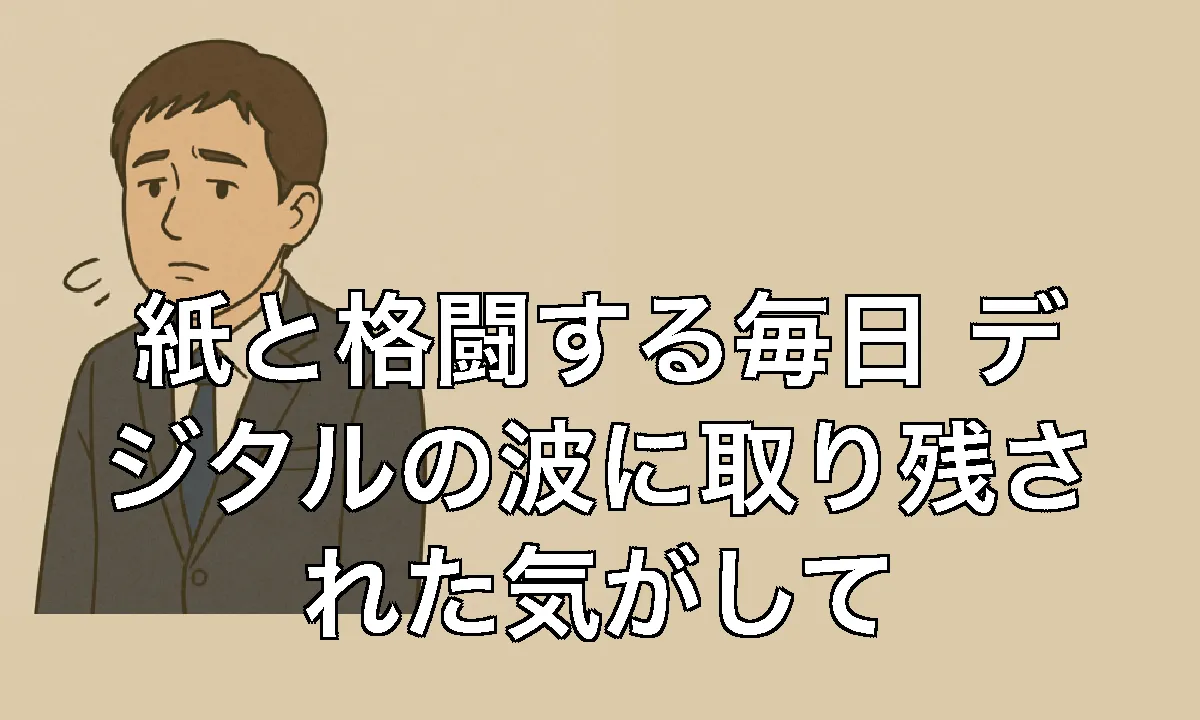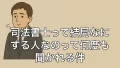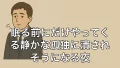デジタル社会にFAXが居座る現実
世間では「DX」「ペーパーレス」「電子契約」などといった言葉が飛び交っていますが、司法書士という職業においては、いまだに紙とFAXが主戦場です。制度的にはオンライン申請やクラウドでのやりとりも可能になってきています。けれど、現実は違います。朝から晩まで、事務所のFAXが「ジーッ」と紙を吐き出し続ける音が鳴り響いている。まるで「ここは昭和か」と言いたくなるような光景ですが、それが私たちの“今”なのです。
業界全体が紙文化から抜け出せない理由
実際、司法書士業界が紙にしがみついているのには理由があります。クライアントの多くが高齢で、FAXや書類の郵送が当たり前という感覚のまま時代を止めてしまっている。中には「PDF? それって印刷できるんですか?」と真顔で聞いてくる方も。仕事をスムーズに進めるには、こちらが合わせるしかない。そして合わせるということは、紙と格闘する日々を意味します。正直、体力も気力も削られます。
法務局と役所の紙信仰の根深さ
法務局や役所とのやりとりも例外ではありません。「念のため紙で一部ご送付ください」と言われることがまだまだ多い。オンライン申請しても、補正の通知は電話かFAX。データの世界に生きていると思いきや、紙の世界に無理やり引き戻される。こっちは「クラウドにアップしました」と言っているのに、向こうは「紙で見ないとわからない」と返してくる。これではデジタル化なんて夢のまた夢です。
FAX文化が残ることへの諦めと慣れ
もう慣れましたよ。朝出勤してまずFAX機の確認、夜も最後に紙が詰まっていないかチェックしてから帰宅する。昔は「時代遅れじゃないか」と怒りすら感じていました。でも今は「まあ、そういうもんか」と思えるようになってしまった自分がいます。これって進化じゃなくて、たぶん諦めです。だけど、これで業務が回っているのも事実。そんなジレンマを抱えながら、毎日FAXの音を聞いています。
メールじゃダメなのかという疑問
何度も思いました。「これ、メールで済むのに」と。でも相手が「FAXで送ってください」と言えば従うしかない。特に相続関係の案件では、お年寄りとのやりとりが多く、「メール?見ないよそんなの」とあっさり言われることも。だからこそ、FAXという手段は今でも現場で根強く使われているのです。しかもその手間は全部こっちにくる。心の中で「こっちは手紙配達人じゃない」と何度思ったことか。
添付ファイルは印刷前提の世界
メールにPDFを添付しても、「印刷してから送ってください」と返される。だったら最初から紙で出せばいいという話になり、結局はFAX。自分でPDF作って、プリンター動かして、さらにFAX機に通す。三段活用みたいなものです。こんな面倒な流れが、いまだに当たり前に行われているのがこの業界です。若い人に話すと「え、それ何の修行ですか?」と笑われる。笑いごとじゃないんですがね。
紙でしか安心できない人たち
何かトラブルがあったとき、「紙があるから大丈夫」と言う人がまだまだ多いです。電子データの保存よりも、手元にある紙のほうが信用できるという価値観。その気持ちはわからなくもないですが、効率の良さは完全に無視されています。しかも「紙はあとで見返せるし」と言われると、確かに…と納得してしまう自分もいます。これも諦めでしょうか、それとももう紙に取り込まれてしまった証拠なのか。
うちの事務所もFAXとの戦い
自分の事務所に限って言えば、FAXがなければ回らないのが現実です。たった一人の事務員が、ひたすら紙を確認して、スキャンして、ファイルして、時には書き損じて…という流れを毎日繰り返している。私自身も手伝います。FAX機の紙詰まりと格闘したり、トナーが切れたのに気づかず白紙が送られてきたり。そのたびに「この時間、何の意味があるのか」と虚無感に襲われるのです。
朝一番の仕事はFAX紙の整頓から
朝9時、まずやるのはFAX受信トレイの確認です。深夜に送られてきた書類がぐちゃっと重なっていて、誰からのものか分からない。時には重なって文字が潰れていたり、紙が湿っていたりして、読み取れないことも。朝の貴重な時間を「並べて乾かす」「内容確認」「仕分け」に使う。メールならクリックひとつなのに、FAXだとその前に3工程あります。朝からもう、どっと疲れるのです。
インク切れトラブルで始まる一日
さらに追い打ちをかけるのがインク切れ。最近も、重要な書類が真っ白な状態で出てきて「は?」となったことがありました。しかも送信元は「送ったはずですよ」と主張してくる。いや、こっちは真っ白ですから。再送依頼もFAXでしか受けられず、電話で説明しながらお互いの機械を操作するというカオスな展開に。なんかもう、これが令和の風景とは思えません。タイムスリップした気分になります。
シュレッダーが止まらない
一日が終わると、机の上には紙の山。処理済みのFAXやコピー、使い終わったチェックリスト。それらをまとめてシュレッダーにかけるのですが、これがまた地味に時間を食う。しかも細断ゴミがすぐ溜まるので、ごみ袋の交換も日課です。業務とは関係ないけれど、確実に労力を奪ってくるFAX処理の後始末。これはもう、“仕事のような仕事じゃない何か”です。時間泥棒と言っても差し支えないと思っています。
電子化しようとして挫折した話
私も何度か電子化を試みました。クラウドサービスを導入しようとしたり、スキャンを自動化しようとしたり。でも結局、現場のニーズと一致しない。特に年配の依頼者や役所とのやりとりは「紙じゃないと困る」と言われる。結果、デジタルとアナログの二重対応になり、むしろ効率が悪くなる。まるで泳げないのに二刀流で水泳大会に出るようなものです。全然スムーズにいきませんでした。
スキャナ導入も思ったより面倒だった
コンビニに置いてあるような複合機を導入したこともありました。ところが、スキャンしたファイル名の付け方、保存場所、共有方法など、細かいルールが定まらない。事務員にも負担がかかり、「前のほうが楽でした」と言われる始末。結局、最終的には「スキャンは必要なときだけで」と消極的な運用に落ち着きました。紙の海から抜け出すはずが、結局は波に飲まれて漂ってるだけという結末です。
結局紙で保管する現実
スキャンしてPDFで保存しても、結局「紙でも残しておこうか」となってしまう。つまり、電子と紙のダブル保管。保管スペースも二倍、手間も二倍。なんのために電子化したのかよく分からなくなる瞬間です。しかも紙のほうが見やすいとか、探しやすいとか、そういう理由で紙に手が伸びてしまう。人間の習慣って、便利さだけじゃ変わらないのかもしれません。情けないけど、これが現実です。
誰のためのデジタル化なんだろう
政府や自治体が掲げるデジタル化。目的は分かりますし、便利になることも多いでしょう。でも現場で働く人間からすると、「誰のための改革なんだろう?」と思うことも多い。制度だけが立派に進んで、現実の業務は相変わらずFAXと格闘。改革の波が届く前に、こっちはもう疲れ果ててしまいそうです。未来を見据えるのも大事ですが、今この瞬間の苦労も、もう少し見てもらいたい。切実な願いです。