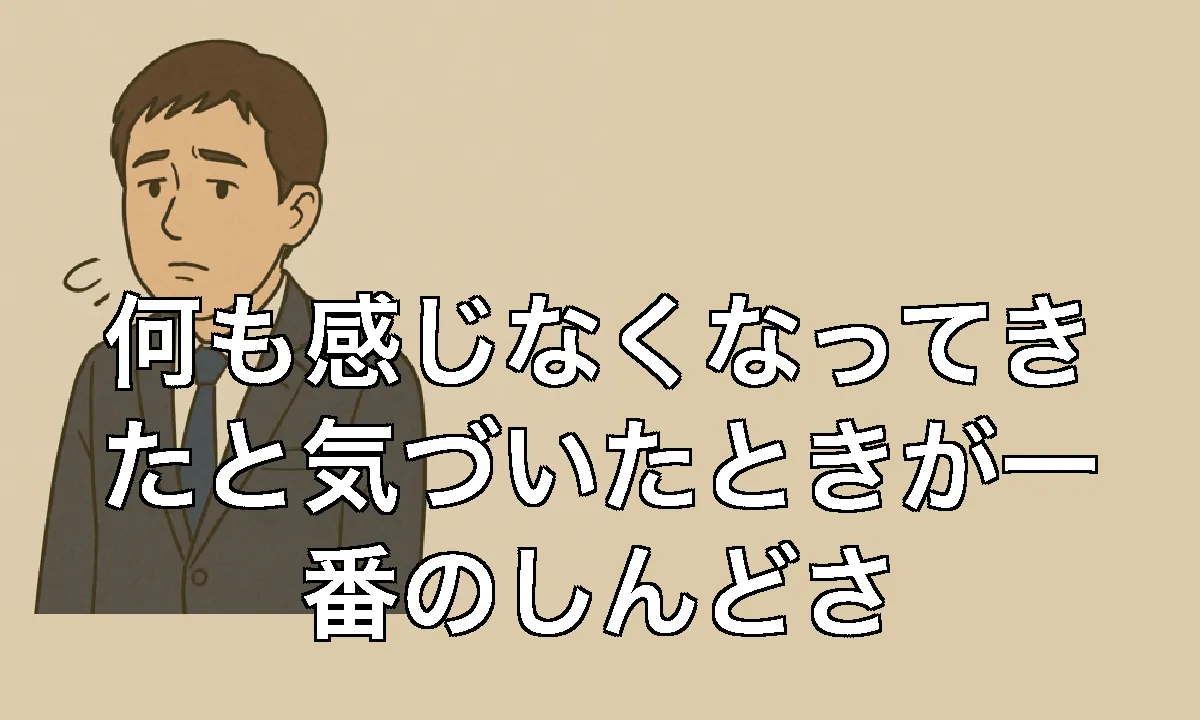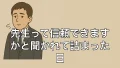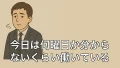気づけば喜怒哀楽が消えていた
ふとした瞬間に、自分の感情がどこかへ行ってしまったことに気づく。最近、怒ることも笑うことも、そして悲しむことも少なくなった。喜怒哀楽がないわけじゃない。けれど、それが外に出てくることがなくなった。まるで感情にフタをして、閉じ込めたまま生活しているような感覚だ。司法書士という職業柄、冷静さが求められる場面も多い。でも、そうやって感情を抑え続けるうちに、自分でも何を感じているのか分からなくなることがある。
忙しさで押し流されていく日々
業務に追われる毎日。登記の書類、期日管理、立会の準備。事務員さんにお願いした確認も、「あとで見る」と言いながら後回し。電話は鳴り止まず、メールはたまる一方。自分の時間がないというよりも、「感情を感じる時間がない」という方が近い。気づけば、ひとつひとつの仕事に対して何の反応もなくなっていた。達成感も、焦りも、イライラもない。ただ「こなす」だけ。そんな メッセージ ストリームでエラーが発生しました 再試行 あなた: html形式にしてコピペできる形で出力してください ダウンロードファイルにはしないでください。!DOCTYPE htmlからスタートしてhtmlを閉じるところまで書いてください。最後まで出力してください。
気づけば喜怒哀楽が消えていた
ふとした瞬間に、自分の感情がどこかへ行ってしまったことに気づく。最近、怒ることも笑うことも、そして悲しむことも少なくなった。喜怒哀楽がないわけじゃない。けれど、それが外に出てくることがなくなった。まるで感情にフタをして、閉じ込めたまま生活しているような感覚だ。司法書士という職業柄、冷静さが求められる場面も多い。でも、そうやって感情を抑え続けるうちに、自分でも何を感じているのか分からなくなることがある。
忙しさで押し流されていく日々
業務に追われる毎日。登記の書類、期日管理、立会の準備。事務員さんにお願いした確認も、「あとで見る」と言いながら後回し。電話は鳴り止まず、メールはたまる一方。自分の時間がないというよりも、「感情を感じる時間がない」という方が近い。気づけば、ひとつひとつの仕事に対して何の反応もなくなっていた。達成感も、焦りも、イライラもない。ただ「こなす」だけ。そんな日々に慣れてしまっていた。
「感じる余裕」がなくなったのはいつからか
おそらく、独立して2年目くらいからだった気がする。最初は「お客様のために」と思って全力で走っていた。でも、それがいつしか「やらなければならない」に変わり、感情ではなく義務で動くようになった。昔は、手続きがスムーズに進むと「よし!」とガッツポーズをしていたのに、今ではそれすらもない。疲れているのかと思ったが、違った。感情を感じる「余裕」がなくなっていたのだ。
無表情の自分にふと違和感を覚える
ある日、鏡に映った自分の顔を見てハッとした。無表情。まるで感情を持たない人間のような顔をしていた。そのとき、「あれ、俺、こんな顔してたっけ」と思った。昔はもっと笑顔があったはずなのに。人と話していても反応が薄くなり、事務員さんの冗談にも心のどこかで「笑った方がいいよな」と思って作り笑いをする。これはまずい、と感じた。
感情が動かないことに慣れてしまった怖さ
感情が動かない状態が当たり前になってしまうと、それが「普通」だと思い込んでしまう。でも、よく考えてみるとこれは異常なことだ。感情が動かないということは、人としての根っこの部分が鈍ってしまっているということ。良いことが起きても無反応、悪いことが起きても無関心。それはある意味「心が死んでいる状態」だと気づいた。
大きな問題も小さなミスも何も響かなくなる
昔なら大騒ぎしていたようなミスにも、「ああ、やっちゃったな」で終わる。もちろん表面的には対応するけれど、心が動かないから注意も反省もどこか淡白になる。これは業務上、とても危険なことだ。感情がなければ「危機感」も薄れる。重大なトラブルにつながりかねないのに、自分はそれすら「なんとかなるか」で片付けてしまっていた。
きっかけは「感情を抑えるクセ」だったかもしれない
思い返すと、感情を抑えることを「大人の対応」だと信じていた。怒らず、泣かず、騒がず、淡々とこなすのがかっこいいと思っていた。でもそれは違った。抑えることと、感じないことはまったく別だ。抑えすぎると、感情そのものが湧かなくなってくる。そこに気づいたとき、やっと「このままじゃまずい」と思えた。
司法書士という職業の特性がもたらす鈍感さ
司法書士の仕事は、感情よりも事実と手続きが優先される。相手が泣いていようが怒っていようが、登記簿の記載と添付書類がすべて。だから、自然と感情のスイッチを切るクセがつく。それが日常になり、プライベートでもスイッチを入れるタイミングがわからなくなっていた。
「冷静であること」が正義になっていく
「感情的になるのは良くない」「冷静であれ」そう言われ続けてきた。確かにその通りだ。でも、感情を感じないまま冷静でい続けるのは違う気がする。感情を感じた上で、それをどう処理するかが大事なのに、感じること自体を止めてしまった自分がいた。
笑っても泣いても誰も評価してくれない現実
この仕事では、どれだけ感情を込めても「仕事としての結果」がすべて。書類が正しく、期日を守り、クライアントの利益が守られているか。そこに「頑張ったね」という評価はない。だからこそ、感情を込める意味がないように思えてしまっていた。でも、そうじゃない。評価されなくても、自分の中の感情は生かしておくべきだった。
事務所でふと見た事務員の顔がヒントになる
ある日、事務員さんがミスをして落ち込んでいた。でも、自分は「ああ、またか」と思っていた。何も声をかけず、何も表情を変えず、そのままスルーした。帰り道、その無反応だった自分に嫌気がさした。人が目の前で落ち込んでいるのに、何も感じなかった自分。それが一番しんどかった。
相手の機微に気づけなくなった自分
昔なら、「大丈夫ですか?」と声をかけていた。ちょっとしたお菓子を差し入れしたり、冗談を言って笑わせたりもしていた。けれど、今はそれができない。気づかないのではない。気づいても、何もできない。心が動かないから。まるで、自分の感情がどこかに閉じ込められているみたいだった。
言葉をかけるタイミングすら見失っていく
結局、言葉って感情が伴っていないと届かない。気持ちが動いて初めて、自然な声かけができる。ところが、今の自分はその感覚が鈍っていて、気づいたときにはすでにタイミングを逃している。「なんか言わなきゃ」と思っても、もう遅い。その繰り返しが、自己嫌悪につながっていた。
感情のリハビリに必要なのは「些細な気づき」
感情を取り戻すのに劇的な方法はなかった。でも、小さな「感じる体験」を積み重ねることで、少しずつ感覚が戻ってきた気がする。特別なことではない。日常の中で、自分の感覚に目を向けてみること。それだけで、心は少しずつ動き始める。
五感を使うことから始めてみる
朝の空気の匂い、昼の太陽の眩しさ、夕方の風の心地よさ。そんな五感を意識するようにした。人と話すときも、表情や声のトーンに目を向けるようになった。「感じよう」と思うだけで、少しずつ感情の回路が開いてくるのが分かった。
缶コーヒーの甘さに驚いたあの日
ある日、自販機で買った缶コーヒーの甘さに「うわ、甘っ」と思った。それだけのことが、なぜか嬉しかった。ああ、ちゃんと味を感じてる。今まで、ただの液体として流し込んでたけど、ちゃんと「甘い」と思えた。それがなんだか救いだった。
歩くときの足音を聞いてみる
朝の出勤時、意識して自分の足音を聞くようにしてみた。コツコツという音に、自分がちゃんと「ここにいる」感じがして、少しホッとした。何でもないようなことでも、感じようとすればちゃんと感じられる。感情は、戻ってくる。
感情を取り戻すことは強くなることではない
感情を取り戻すことは、弱くなることではない。むしろ、自分の内面をしっかり感じ取れるようになるという意味では、強くなることでもある。司法書士という立場であっても、人間であることを忘れてはいけない。冷静さと感情は両立できる。
強さとは無感情になることではない
「鈍感な方が楽だよな」そんなふうに思ったこともある。でも、鈍感になることで楽になるのは一時的でしかない。長く続けるには、自分の感情を大切にした方がいい。心を感じながらでも、ちゃんと仕事はできる。むしろその方が、人との関わりもずっとスムーズになる。
他人の痛みに気づける柔らかさを持つ
誰かの落ち込み、誰かの笑顔、誰かの焦り。それを感じ取るには、自分の感情が元気でなければ無理だ。他人に優しくするには、まず自分に優しくする必要がある。感情を取り戻した先に、本当の人間関係がある。司法書士としてではなく、一人の人間として。