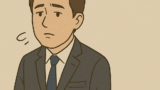午前九時の依頼人
冷房の効いた待合室
冷房が効きすぎた待合室に、ノースリーブのワンピース姿の若い女性がぽつんと座っていた。小さな封筒を握りしめ、視線は床の一点を見つめている。無表情で、しかし何かを我慢しているような目だった。
受付にいたサトウさんが、いつもの無機質な声で告げる。「シンドウ先生、予約の方です」俺はソファから重い腰を上げた。まだ朝なのに、もう疲れていた。
記憶に残らない登記簿
過去と未来が交差する地番
依頼は、相続登記だった。だが、不思議だったのは登記簿に記された地番。俺が覚えている限り、その住所には建物なんてなかった。少なくとも、10年前に現地を通った時には、ただの空き地だったはずだ。
「ここに家なんて、ありましたか?」そう尋ねると、彼女は小さくうなずいた。「確かにあったんです。私が育った家です」――その言葉に、背筋がざわついた。
サトウさんの疑念
目線のわずかな揺れ
面談を終えたあと、サトウさんが言った。「先生、あの人、何かを隠してますよ」冷たくも的確な指摘に、俺は曖昧にうなずいた。俺も、彼女のあの微妙な目線のズレが気になっていた。
「でもまあ、遺産争いで何かごまかすのはよくある話だしな」なんて言い訳を口にしたが、自分の中でもその言葉は響かなかった。
見えない証明の正体
公図に現れない敷地
市役所で公図を取り寄せると、そこには地番すら存在していなかった。代々の土地台帳にも、その区画の履歴はない。存在しないはずの場所に、家があったというのか?
「幽霊屋敷かよ…」と呟いた俺に、隣の職員が怪訝な目を向けた。やれやれ、、、まるで週刊少年ジャンプの読みすぎだ。
未来に置き去りにされた名前
委任状の筆跡
提出された委任状の筆跡は、美しい丸文字だった。しかし、過去に存在したとされる被相続人の名前は、住民票にも戸籍にも存在しなかった。存在しない人間が、相続できるわけがない。
「先生、もしやこれは…」とサトウさんが言いかけたところで、事務所の電話が鳴った。彼女は不満そうに受話器を取ったが、その目はまだ何かを考えているようだった。
不自然な登記原因
日付のズレが示すもの
提出された遺言書の日付は、3年後になっていた。「これ、未来の日付ですよ?」サトウさんの言葉に俺も思わず二度見した。どう見ても筆跡は一致しているし、印鑑も本物だった。
しかし、現実の中に未来の日付が現れた時点で、この話は“謎”から“異常”へと変わった。
忘却された証人の登場
通夜に現れた老人
その週末、俺は近隣の寺で偶然にも彼女の通夜を見かけた。まだ若いはずの依頼人が、急死したという。「そんな…先週まで、元気だったのに」俺は呆然とした。
そこで声をかけてきたのが、背の曲がった老人だった。「あの子は、未来に生きすぎたんだよ」――その一言で、俺の中にあった違和感が全てつながった。
わたしが彼女に見たもの
名前も知らない依頼人
俺はふと、彼女の名前を思い出せないことに気づいた。カルテを見返しても、どこにも名前の記載がない。ただの記憶違いか?それとも――彼女は最初から、存在していなかったのか?
なんだって?俺は幽霊と面談していたってことか?そんなオチ、某国民的アニメでもやらないぞ。
サトウさんの冷たい一言
「どうせまた騙されてますね」
事務所に戻った俺に、サトウさんは冷たく言い放った。「先生、また変な依頼に首突っ込んで。やれやれって顔してますけど、いつも自分からですよね」
俺は苦笑いを浮かべながら、熱い缶コーヒーを開けた。缶のふたが開く音が、妙に虚しく響いた。
未来に消えた証明の行方
登記の奥に眠る決意
翌日、法務局から連絡があった。「提出された登記書類、一切記録に残っていません」俺は書類棚を開いた。封筒の中は、空だった。すべて、消えていた。
記録も、記憶も、名前すら残らない依頼人。それでも、あの日俺が話した言葉と、彼女のまなざしだけは、妙にリアルに覚えていた。
証明されないものも、この世には存在するのだ。そう思いながら、俺は今日もまた、次の依頼人を迎える。