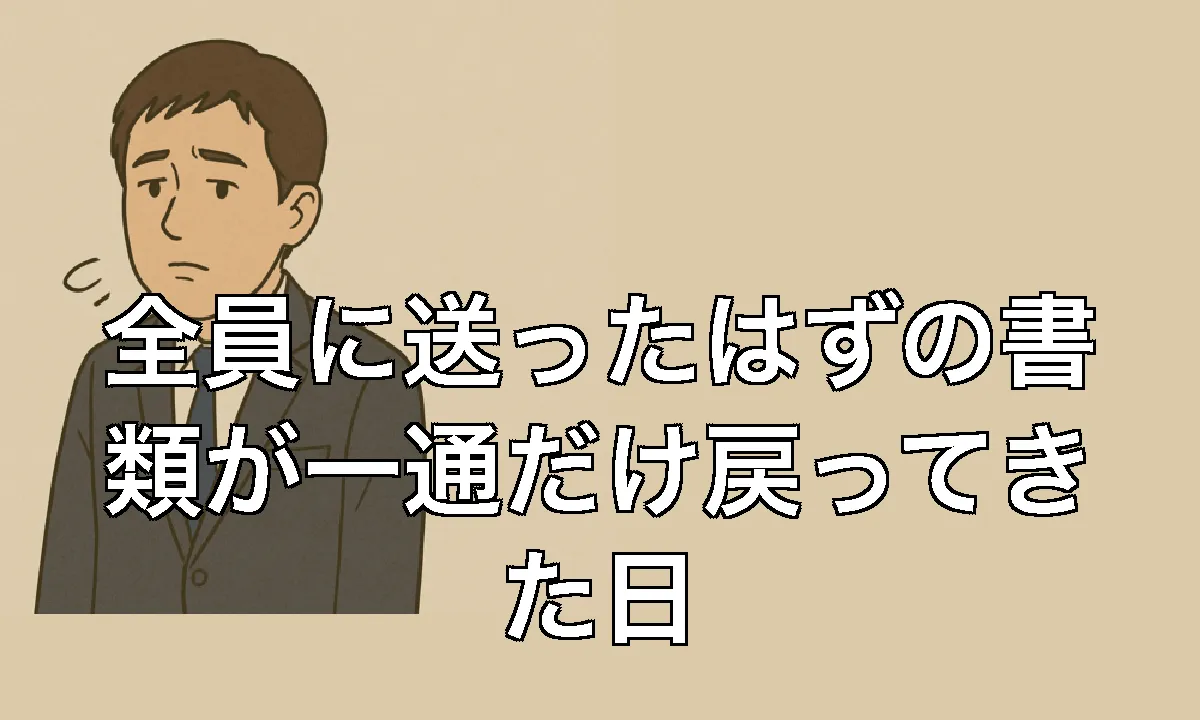ある朝ポストに戻ってきた封筒があった
その朝は、いつもと変わらない静かな始まりだった。事務所に出勤してポストを開けると、見覚えのある自分の字が書かれた封筒が一通。まさかと思って差出人を確認すると、やっぱり自分だった。数日前、相続人全員に送った登記関係の書類の一つが宛先不明で戻ってきたのだ。確認には確認を重ねたはずなのに、それでもこういうことは起こる。冷や汗がにじんだ。
全員に送ったはずの相続書類
案件は、地方に住むご高齢の方の相続手続き。相続人は全国に散らばっており、書類を郵送でやり取りするしかなかった。正確に言えば、9通中8通は確かに届いていた。だが、1通だけが不達。しかも、それがいちばん大事なキーパーソンだったから事態は深刻だった。住所も電話番号も、依頼者からの情報に従って入力した。それでも届かないことがあるのが、この仕事のやっかいなところだ。
名簿とチェックリストを何度も確認した
郵送前、私はチェックリストを手に、名簿と一通ずつ照らし合わせて確認した。封筒に貼る宛名ラベルは事務員さんが印刷してくれたものだが、それも再確認したし、貼る段階でも手で宛先を読み直した。それでも、何かが抜けていたのだろうか。人間は完璧じゃない。特に、疲れていると見落としが生まれる。そんな自分に、また情けなさを感じるのだった。
それでも見落としは起きるもの
司法書士としての仕事は「正確で当たり前」という前提がある。でも、完璧なんて幻想だと最近よく思う。言い訳にはならない。依頼者にしてみれば「一通届かなかった」だけで、その後の進行がすべて止まる。こちらとしては“書類が戻ってきた”ことだけで、胃がキリキリ痛み出す。人間の作業には、どうしてもmissing valueが混ざる。そこに苦しむ毎日だ。
一通届かないだけで全体が止まる現実
たった一通の不達。それだけで全体の手続きが滞り、関係者全員に迷惑をかける。効率も何もあったもんじゃない。けれど、それがこの業界の現実だ。一人が書類に押印できないだけで、他の全員が待たされる。依頼者から「まだですか?」と電話が鳴るたびに、こちらも胃がキリリとする。
書類が一人に届かないだけで全員に迷惑が
この相続案件では、受け取る相続人の中に一人でも反応がなければ、登記申請はできない。全員の印鑑と委任状が揃って初めて動ける。戻ってきた書類の主は、東京在住の長男。高齢者施設に入っているとのことで、住所変更があったらしい。連絡を取り直すのも簡単ではなかった。本人に連絡が取れるまで、他の8人には「すみません、もう少しお待ちください」と言うしかない。
クライアントの信頼感がじわじわ下がる
こうしたトラブルは、仕事の本質に関わってくる。たとえ自分に非がなくても、クライアントの目には「進まない司法書士」と映る。そうすると、最初は丁寧だったやり取りが徐々に冷たくなってくる。信用というのは築くのに時間がかかるのに、失うのは一瞬だ。こんな時、独立したことを後悔しないと言えば嘘になる。
謝って済む話じゃないときもある
「」と言うのは簡単だ。けれど、それで解決するわけじゃない。特に相続人同士の関係があまり良くない場合は、こうした遅延が火種になる。誰かが「まだか」と言い出すと、別の誰かが「こっちは悪くない」と応戦し、関係がギスギスし始める。司法書士はその間に立たされる。心をすり減らす役目が増えるだけだ。
事務所の体制の限界を思い知る瞬間
この一件をきっかけに、私は事務所の体制の見直しを本気で考えるようになった。いくら「二人三脚」とはいえ、実質的には私ひとりが判断し、背負っている。忙しい日々の中で、ちょっとした抜けや確認不足が命取りになる。やれることは限られていると痛感する。
人手不足は日常茶飯事
都会なら事務員をもう一人雇うことも考えられるが、ここは地方。求人を出しても、なかなか来ない。来たとしてもパート希望や未経験の方がほとんどで、すぐ即戦力とはいかない。結局、事務員さんに頼りきりになり、その人が休む日はフル稼働。電話、郵送、書類作成、来所対応。自転車操業という言葉がまさにぴったりの日々だ。
事務員さんだって完璧じゃない
うちの事務員さんはよくやってくれている。でも、人間だもの。印刷ミスや貼り間違い、ダブルチェック漏れは誰にでもある。自分でも同じミスをする。だからこそ、フォロー体制が必要なのに、そこまで手が回らない。悪循環の中でもがいている感覚がある。
でも結局責任は自分にくる
司法書士は代表者だ。どんなに事務員がミスしたとしても、それは「代表者の管理責任」とされる。依頼者からの怒りの矛先は、最終的に自分に向く。だから苦しい。言い訳もできない。孤独な戦いだと感じる瞬間が多すぎる。
独り身の夜にふと漏れるため息
一通の書類に振り回された日は、家に帰っても気持ちが晴れない。晩ごはんを食べる気にもならず、ソファに沈んで天井を見ているうちに、気づけば1時間経っていたりする。誰かに話を聞いてほしいと思っても、誰もいない。結局、冷蔵庫からビールを出して、ぼんやりとテレビをつけるだけ。そんな夜が、たまにじゃなく頻繁にある。
誰かに相談したいけど相手がいない
元野球部の同期たちは、みんな家庭を持って忙しそうだ。LINEを送っても「今度また飲もうな」と定型文が返ってくるだけ。深夜に電話なんてできない。結局、自分の中で悶々と考えて、また次の日を迎える。この閉じたループから抜け出す術があれば、誰か教えてほしい。
野球部の仲間とは話が噛み合わない
たまに会っても、彼らの話題は子育てや家のローン、PTAの話。こっちは相続登記の期限や書類の不備、依頼者との調整。噛み合うわけがない。昔は同じグラウンドで汗を流していた仲間なのに、今では別世界の住人のようだ。それが、また寂しい。
孤独と愚痴のループから抜け出せない
愚痴を言えばスッキリするかと思いきや、逆に自己嫌悪になる。「なんでこんなこと言ってるんだろう」と自分を責める。でも、言わずにはやっていけない。独り事務所の現実は、愚痴を口にできる相手がいるだけで救われるのかもしれない。たった一人の話し相手が、どれだけ貴重かを痛感する。
それでも今日もまた書類を封筒に詰める
朝になれば、また仕事が始まる。昨日の失敗を引きずったままでも、郵便物は待ってくれない。今日もまた、新しい案件の書類を封筒に詰める。念入りに確認しながら、二重チェックをして、それでもどこかで「また何かあるかも」と不安になる。そんな日々を、なんとか続けている。
司法書士という仕事が嫌いになれない理由
面倒だし、疲れるし、孤独だし。だけどこの仕事が嫌いになれないのは、やっぱり誰かの人生の一部に関われるからだ。相続で揉めていた家族が、書類を通じてちょっとだけ歩み寄れたとき。その瞬間に立ち会えたとき、少しだけ救われた気になる。それがあるから、まだやれている。
誰かの人生に関わっているという感覚
司法書士の仕事は書類のやり取りが主だけど、その背景には人間ドラマがある。家族の歴史や人間関係、遺産という名の過去。そうしたものに触れ、整理し、未来に渡す。そんな仕事って、なかなかない。面倒だけど、やりがいがある。それが唯一の救いかもしれない。
届くべきところに届いたときの安堵感
だからこそ、全員の署名が揃い、登記が完了したときの安堵感は格別だ。書類が「無事届いた」と聞いたときには、心からホッとする。それだけで一日報われたような気がする。今日もまた、封筒に願いを込めて、投函する。失敗を恐れながらも、前に進むしかない。