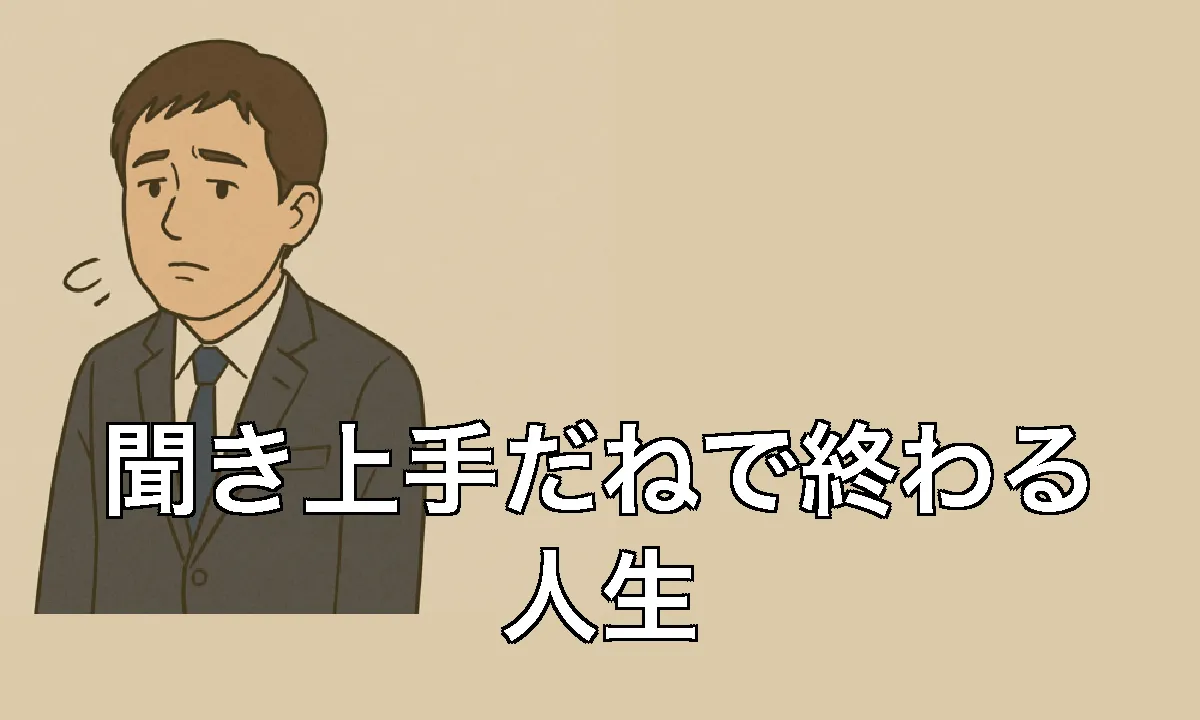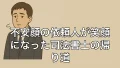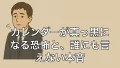聞き上手だねで終わる人生
褒め言葉なのにちっとも嬉しくない
「聞き上手だね」って、たしかに悪い言葉じゃない。むしろ褒めてるつもりなんだろう。ただ、これが何度も続くと、心のどこかで「またか」と思ってしまう自分がいる。言われ慣れてしまったのか、それとも、その言葉の裏にある「そこ止まり」の雰囲気が透けて見えてしまうのか。会話の場では笑って返すけど、内心では「じゃあ俺の話も聞いてくれよ」とつぶやいている。司法書士という仕事柄、依頼者の話に耳を傾けるのは当然。でも、それが私生活にまで染み出してしまって、自分の言葉を飲み込むクセが染み付いたのかもしれない。
聞き役に徹するうちに自分の感情が消えていった
気づけば、誰かが話しているときに「それはね」と割って入ることがなくなった。若いころはもう少し自己主張もしていたと思う。今では、話を聞きながら「ふんふん」「なるほど」と相槌を打つだけ。自分の考えを話すのが、なんだか怖くなってしまった。たとえば飲み会の席で昔の野球部時代の話をしようとしても、「いや、俺の話なんかどうでもいいか」と引っ込めてしまう。話すことで誰かの機嫌を損ねたくない、波風を立てたくない、そんな気持ちが先に来る。だけどその分、自分の感情を表に出す機会もどんどん減っていった。
自分の話をすることへの罪悪感
人の話を聞くのが「いいこと」とされる一方で、自分の話をすることにはなぜか抵抗がある。これは育ってきた環境のせいもあるのかもしれない。親から「人の話をちゃんと聞きなさい」と教わってきたが、「自分のことを話しなさい」とは言われなかった。司法書士の現場でも、相手の話を引き出すことが求められる。そのクセが、プライベートでも抜けない。誰かに「ちょっと聞いてよ」と言いかけて、「いや、こんな話、迷惑かもな」と飲み込んでしまう。そんな自分に、時々がっかりする。
相手が求めてるのは共感じゃなくて肯定
話を聞いてほしいだけの人は、実は多い。でも、その多くは「共感」ではなく「肯定」を求めている気がする。「それは大変だったね」ではなく「それでいいんだよ」と言ってほしいのだろう。こちらが少しでも異論をはさむと、空気がピリつくこともある。そんな経験を何度かして、私はますます「うん、うん」とうなずくだけの人間になってしまった。だからこそ、「聞き上手だね」と言われると、むしろ「便利に使われてるだけじゃないか」とさえ思ってしまうのだ。
司法書士という職業の性質も拍車をかける
司法書士の仕事は、依頼者の悩みや希望を丁寧に聞き出し、法律や手続きで形にすること。つまり、聞き手であることが前提にある。そこにプロ意識を持って臨むのは当然としても、問題はそれが職場を越えて私生活にまで入り込んでくることだ。仕事を終えて家に帰っても、聞き手モードが解除できない。電話でも、飲み会でも、デートでも、常に「聞いてばかり」になっている。
話を遮らないのがプロの基本?
登記の相談を受けるとき、依頼者の話を途中で遮ることはできない。相続の話などは感情も複雑だし、事実関係を正確に把握するには、最後までじっくり聞く必要がある。その習慣が身につきすぎて、プライベートでも誰かの話を遮ることができなくなってしまった。かといって、自分が話し出すと、相手が退屈そうな顔をしてる気がして、すぐ話をやめてしまう。これって結局、職業病なんだろうか。
正確さと冷静さが求められる現場
司法書士は感情を抑えて、冷静に判断することが求められる。法務局の対応ひとつ取っても、感情的になったら負けだ。だから仕事中は、ぐっと感情を押し殺して、事務的に処理を進める。そのスキルが身についてしまうと、嬉しいことや悲しいことがあっても、顔に出せなくなってしまう。喜怒哀楽が乏しくなった自分を、ふとした瞬間に鏡で見て、「これが大人ってやつか…」とため息をつく。
優しそうで終わる対人関係の虚しさ
「優しそうな人ですよね」と言われることがある。でも、そこに「付き合いたい」とか「もっと話したい」というニュアンスは含まれていないことが多い。ただただ、「害がなさそうな人」というだけ。モテないのも納得だ。実際、女性と二人きりで食事しても、恋愛に発展することはまずない。相手は私に「安心感」を求めているだけで、「魅力」は感じていないのだろう。そう気づいてから、むしろ自分から距離を取るようになった。
恋愛や友人関係でも同じパターン
仕事だけでなく、プライベートでも「聞き役ポジション」に固定されていると、人間関係がどこか歪んでくる。会話が双方向ではなく、一方通行になってしまうからだ。飲み会でも、デートでも、誰かの話を延々と聞いているだけの自分に気づいたとき、「俺、ここにいる意味ある?」と思ってしまうことがある。
聞いてばかりで印象には残らない
人は、自分のことを話してくれた相手に親近感を持つ。だから、聞いてばかりだと、意外と印象に残らないのだ。何度か会った人に「どんな人だったっけ?」と言われたことがある。そのとき、話してなかった自分を思い出して、「ああ、そりゃ覚えてないよな」と納得した。でも、その一方でちょっと悔しかった。聞き上手は、確かに会話の潤滑油にはなるけど、記憶に残る存在にはなりにくい。
誰かの物語のモブキャラみたいな存在感
まるで、自分の人生が誰かの物語の背景になっているような感覚。主役でも脇役でもなく、ただのモブキャラ。そんなふうに感じる瞬間がある。とくに、結婚式の二次会や同窓会など、人の幸福が集まる場では、自分がただの「聞き役」として存在していることが、やけに鮮明に見えてしまう。誰かの幸せを祝っているようでいて、自分が取り残されている現実が、心にじわりと染みてくる。
好意があったとしても癒やし枠止まり
「癒やされる」と言われたことがある。でも、そこから先に進んだことは一度もない。恋愛感情ではなく、安心感だけを求められている。たとえば職場の女性が、嫌な上司の愚痴を言いに来る。私は「そっか、それは大変だったね」とうなずく。でも、それで終わる。連絡先を聞かれることもなければ、プライベートに踏み込まれることもない。ただただ、ガス抜き役として消費されているような気がする。
聞き上手の呪いからどう抜け出すか
じゃあ、聞き上手のままで終わる人生を変えるにはどうしたらいいのか。その答えは簡単じゃないけど、まずは「話すこと」に少しずつ挑戦していくしかないと思っている。自分のことを話すのは、最初は抵抗がある。でも、伝えることでしか伝わらないことも、きっとある。
たまには話を遮ってもいい
会話のキャッチボールでは、時にはボールを奪うくらいの強さも必要だ。相手が話し続けているときに、勇気を出して「ちょっと待って、それってさ…」と割って入る。そうすると、案外すんなり聞いてくれたりする。自分の話が下手でもいい。言いたいことがあるなら、話すべきだ。聞き上手を捨てろとは言わないが、話し下手のままでいる理由もない。
感情を出すことは迷惑じゃない
「こんなこと言ったら迷惑かな」と思って、感情を押し殺してきた。でも、それが相手にとって本当に迷惑かどうかなんて、言ってみないと分からない。むしろ、人間味のある言葉や反応こそが、相手との距離を縮めてくれる。怒ってもいいし、笑ってもいい。疲れたら「疲れた」と言えばいい。そんな当たり前のことを、少しずつ取り戻していきたい。
話す力もトレーニングで磨ける
私は司法書士だから、言葉を扱う仕事をしていると思われがちだけど、実は話すことは苦手だ。でも、文章を書くのと同じで、話すことも練習すれば上達する。最近は、あえて日常の些細なことを話すようにしている。今日のランチが美味しかったとか、事務員さんとの会話で笑ったこととか。そんな小さな話題からでも、自分の言葉を少しずつ取り戻していける気がしている。