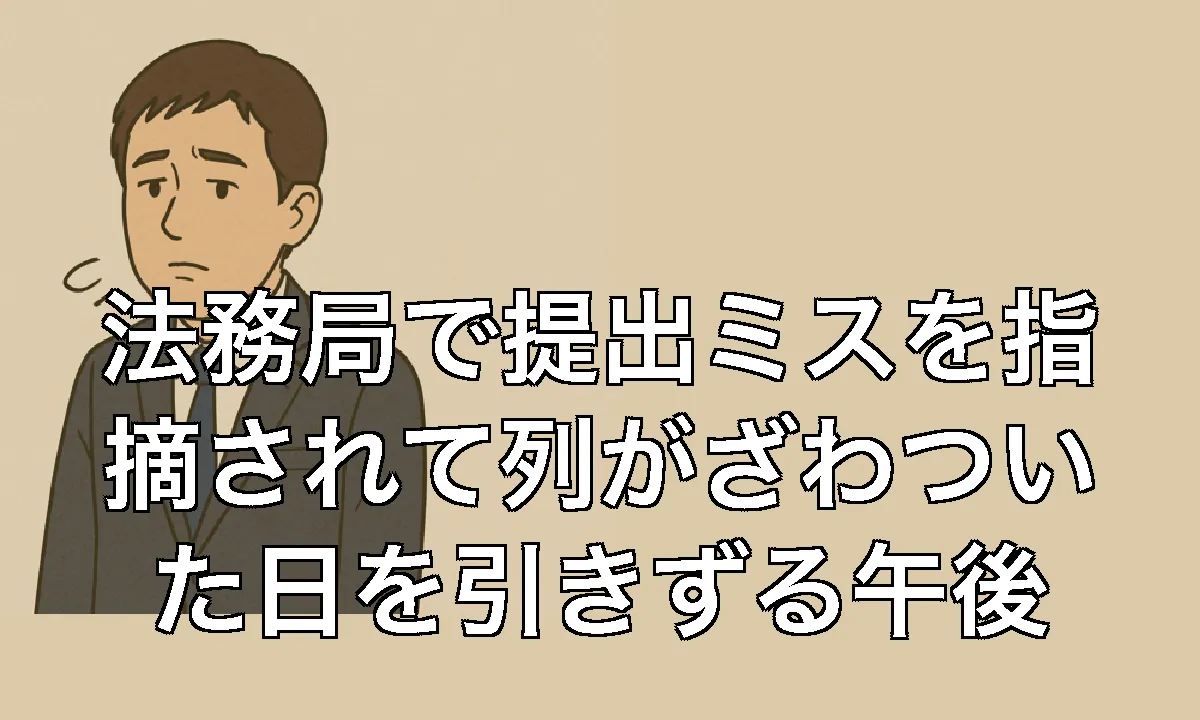あの日の法務局で味わった居たたまれなさ
朝からバタバタしていて、依頼人に急かされるように書類を仕上げたその日。自分ではちゃんと確認したつもりだったのに、いざ法務局の窓口で提出した瞬間、「こちら、印鑑証明が添付されていませんね」と静かに言われた。まるで地雷を踏んだかのような気まずい空気。うしろに並ぶ数人が「おや?」と首を傾げている気配を感じ、背中にじっとりと汗をかいた。あのときの冷たい視線、今でも思い出すと胃が重くなる。
たった一つのチェック漏れが呼び起こすトラウマ
「しまった」と思った瞬間、頭の中は真っ白。印鑑証明のコピーを取り忘れていたことに気づいたが、もうどうにもならない。そもそも、こういう時のために自分の中でチェックリストを作っていたはずなのに、朝の電話ラッシュで完全に頭が回っていなかった。あの日のミスは、ただの手続きのミスではなく、自分の管理能力を否定されたような気がして、それがまた堪える。小さな失敗が、なぜか心の深いところまで刺さってくるのがこの仕事の怖さだ。
あの列の視線が刺さるようで震えた
提出カウンターのすぐ後ろにできていた列の存在が、急に巨大な圧力に感じられた。「あの人、またミスか?」なんて思われているのではと勝手に妄想が膨らみ、顔が引きつるのが自分でもわかる。実際、誰も声には出さないけれど、静かなざわめきと足踏みの音が余計に心をざわつかせる。何でもないような手続きの場が、失敗ひとつでまるで晒し者のような舞台に変わる瞬間。それを味わうたびに、「もう二度とここでミスはできない」と、半ば強迫観念のように思うようになった。
申請書に戻された朱色のチェック
訂正を求められた書類には、朱色のペンでぐるりと囲まれた箇所があった。その色が目に飛び込んできた瞬間、もう反論の余地はなかった。法務局の職員は淡々としているが、その朱色のインクには「あなたの確認不足ですよ」という無言のメッセージが詰まっているようで、見ているだけで胸が苦しくなる。人間、ミスはするものだけど、この仕事ではその一つが依頼人の信頼を失う大きな引き金になる。だからこそ、赤ペン一本がこれほどまでに精神に刺さるのだと思う。
心の中で何度も「俺のせいじゃない」と唱える
本音を言えば、「こんなの俺のせいじゃない」と叫びたい瞬間もある。依頼人がギリギリに書類を持ってきて、「これでお願いします」と言われれば、こっちに確認の余裕なんてないこともある。なのに、提出ミスとして窓口で指摘を受けるのはこっち。自分が悪いのはわかっている、でも「理不尽だな」と思ってしまうこともある。そんなモヤモヤを抱えて、次の依頼に向かわなければならないのが司法書士のつらいところ。
元請けからの急な依頼と納期のプレッシャー
その日の書類も、実は元請けの事務所から前日の夜に急遽回ってきたものだった。「明日の午前中には出してください」と言われて、眠い目をこすりながら内容を確認したけれど、時間も気力もギリギリだった。言い訳にはならないが、こういう無茶な依頼が多いのもこの業界の実情。自分ひとりではどうしようもない納期やプレッシャーに押されながらも、「なんとかこなす」ことが当たり前になってしまっている現状に、いつも心がすり減っていく。
慌てて印刷した書類に潜む罠
朝一で印刷したその書類、実は前のバージョンがプリンタに残っていたのを気づかずに提出してしまったのだ。ファイル名も似ていて、慌てていると確認ミスをしてしまう。たったそれだけのことが、法務局の窓口で「業務の信頼性」という重たいレッテルに繋がるのだから、冷や汗が止まらない。こういう小さな罠が潜んでいるのが司法書士の仕事の怖いところで、何度経験しても、完璧には防げないのが現実だ。
法務局の空気に飲まれた瞬間
法務局という場所には、妙な緊張感が漂っている。言葉少なな職員、無表情の来所者、そしてミスが許されない雰囲気。だからこそ、一つの不備が起きたとき、その空気に飲まれてしまいそうになる。静けさが逆にプレッシャーとなり、こちらの些細な動作すら重く感じる。ミスをしても、怒鳴られるわけではない。ただ、あの“沈黙”がつらいのだ。
後ろの列がざわつくあの独特の雰囲気
私の背後には、10人ほどの列ができていた。手続きを急ぐ人たちの気配がヒリヒリと背中に突き刺さるようで、書類をカバンに戻す手にも力が入らない。誰かが小声でため息をついたのが聞こえた。きっと私のせいだ。そう思うと、次の提出に向けてすぐに体勢を立て直すことが難しくなる。ミスそのものより、その場の空気が自分を追い詰めていくのが、この仕事の厄介なところかもしれない。
誰かのため息が胸に刺さる
たった一つのため息が、まるで「早くしてくれよ」と言われているように感じる。実際、誰がため息をついたのかもわからない。もしかしたら他の理由かもしれない。でも、その音が自分の心に突き刺さるほどには、私は余裕を失っていたのだと思う。この職業は、他人の気配に敏感になりすぎる瞬間がある。過剰な自己責任感が、他人の音すら自分への非難と感じさせる。だからこそ、自分で自分を守る工夫が必要なのだ。
職員の無表情がより冷たく見える
指摘をしてくれた法務局の職員は、丁寧で冷静だった。ただ、その無表情が逆に冷たく感じてしまうのは、こちらが動揺しているからだろう。普段なら何とも思わない言い回しが、あの日は「またか」と言われているように響いた。もちろん被害妄想だとわかっている。でも、そのときはもう、逃げ出したいくらい恥ずかしくて、惨めだった。笑い話にできるのは、もう少し時間が経ってからだろう。