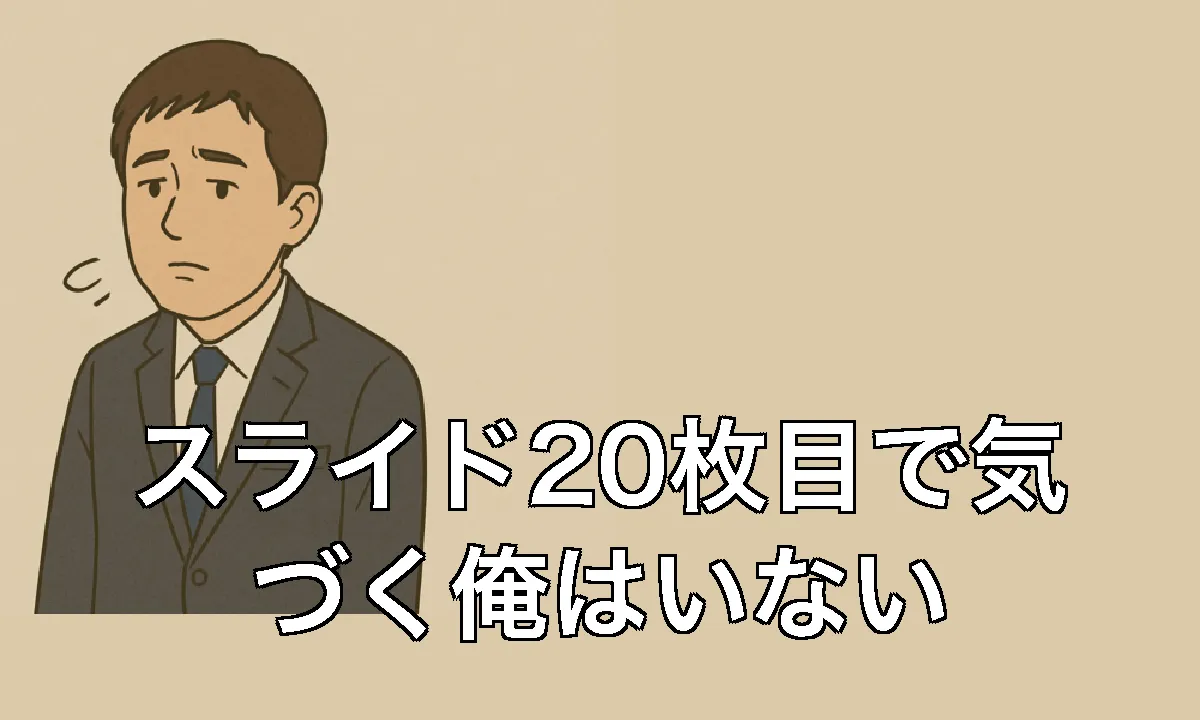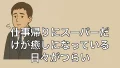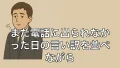なぜこんなに作っているのかがわからなくなる瞬間
ある日の夜、締切前の資料作成に追われていた。頭の中は「とりあえず枚数を揃えなきゃ」でいっぱい。けれどスライドを積み重ねるほど、自分の中にあった「何を伝えたいのか」という芯がどんどん霞んでいく。そもそも、こんなに必死に図や言葉を整えて、誰のためになっているのか。誰も頼んでいないのに、自分で自分を追い込んでいることにふと気づいて、ペンを置いた。あの「俺、何してるんだろ」感は、士業という名前の仕事をしている身には案外つきまとうものだ。
資料作成は仕事か作業か
本来、資料は「伝える」ための手段であって、それ自体が目的ではない。でも、実務ではいつの間にか逆転してくる。「このフォントでいいのか」「この表現は固すぎるかも」と悩んでは修正。しまいには、A4一枚の提案書に三時間以上かけるなんてこともある。司法書士のような“正確さ”が命の仕事をしていると、どんなアウトプットにも完璧を求めがちだ。でも、その姿勢が資料作成を“意味ある仕事”から“無限ループの作業”に変えてしまうことがある。
相手のために作ってるはずなのに自分がいない
ある依頼人向けに説明資料を作っていたとき、「この人、本当にここまで読んでくれるのか?」という疑念が湧いた。でも止まらない。なぜかというと、「自分がここまで調べて考えたことを、きちんと形にして伝えたい」という気持ちがあるから。でも同時に、それは“伝えたい自分”の姿をきれいに見せたいだけなんじゃないかという不安にもなる。結果、俺が作ってるのは「相手のための資料」ではなく、「頑張ってる自分を証明する証拠資料」になっていることがある。それに気づいた瞬間、俺はいなかった。
スライドが増えるたびに遠のくゴール
「とりあえず30枚は必要だよね」と誰が決めたのか。士業の世界では、“丁寧さ”が信頼につながるから、つい資料の量で安心しがち。でも、その丁寧さが空回りする瞬間もある。スライドが増えるたびに「伝わる」から「疲れる」になる。それでもやめられないのは、自分の中の“怖さ”が原因だ。情報が足りなかったらどうしよう、誤解されたらどうしようという不安。だからスライドは増える。でも、ゴールは近づかない。いや、むしろ遠のいていく。
「伝える」より「整える」に必死になる
PowerPointに向かう時間が増えるほど、「伝える」よりも「整える」作業ばかりになる。スライドの左右バランス、フォントサイズ、箇条書きの順番……。一つひとつに神経をすり減らして、肝心の中身が手薄になってしまうことがある。「これって必要?」と思いながらも、何となく安心したくて資料を整える。伝えるための本質がぼやけてくると、見栄えに逃げる。でもそれは自己防衛だ。間違ったことを言っていない自信がないから、見た目を完璧にしようとするのだ。
パワポのデザインを気にする夜
俺は司法書士だ。デザイナーじゃない。でも、深夜2時に色味のグラデーションを調整していた自分がいる。「もうちょっと落ち着いた青のほうが信頼感あるかな」とか考えていると、何かがズレていることに気づく。でもやめられない。なぜなら、手を動かしていないと“仕事してる感”がなくて不安になるから。実はその夜、翌朝に依頼者から「こんなに丁寧にありがとうございます」と言われた。でも正直、それで報われたかと言えば、そうでもなかった。
文字数との戦いに魂を削られる
スライド1枚に入る情報量には限界がある。だから要点をまとめなきゃいけない。でも、「削る」っていう作業は「自分が何を伝えたいか」を問われる作業だ。だからしんどい。いっそ長文のWordで出したほうがマシなんじゃないか、なんて思ったこともある。とはいえ、読みやすさや視認性を考えると、やっぱりスライドに戻ってくる。伝えるために削る。削ってもなお伝わる言葉を探す。そんな地味で苦しい作業に、毎回“自分”が削られていくような気がする。
資料が完成したときの「達成感のなさ」
やっと終わった。印刷も済んだ。さて、これで準備万端――のはずなのに、胸の中には変な空虚感が残る。時間も労力も注いだのに、「終わったー!」と喜べない。ある意味、自己満足にも届かない。資料作りって、やった分だけ必ず評価されるわけでもないし、誰にも見られず終わることもある。そんなとき、「俺、何のためにこれ作ったんだっけ?」という思いがよぎる。まるで無人の観客席に向かって、延々とプレゼンしている気分だ。
誰も見ないかもしれないという恐怖
一度、役所提出用の説明資料を必死に作ったことがある。提出当日、先方から「特にそこまでは見てませんから」と言われたときのあの感情は、なかなか言葉にできない。怒りとか落胆ではなく、ただただ虚無。見られる前提で丁寧に作るのがプロの仕事だとはわかってる。でもやっぱり、「誰の目にも触れないかもしれない資料」に何時間もかけた自分を、どう納得させればいいのか。この問いに答えはないまま、次の資料作成が始まる。
完成した頃には肝心の中身に自信がない
資料が完成した瞬間、「本当にこれでよかったのか?」という疑念が必ず湧いてくる。作ってる途中は必死すぎて見えなかったものが、最後に冷静になると一気に襲ってくる。「回りくどいかも」「余計なこと書いたかも」「そもそも論点ズレてるかも」。それは、時間をかけたぶんだけ、怖くなる。しかも、最初に感じていた“違和感”を無視して作り続けたツケが、最後にドンとやってくる。そうして、「俺は何してたんだろ」という気持ちがまた湧く。
じゃあどうすればいいのか
この虚しさをどうすればいいのか。それは「資料を作らない」という話ではない。むしろ「資料との向き合い方」を変える必要がある。相手に届くものを作るには、自分自身の理解が整理されている必要がある。つまり、「資料の中身」より前に、「自分の頭の中」を整理する時間をしっかり取るべきだ。結果的に、それが一番の時短にもなるし、自分が納得できるものに近づける。効率のためではなく、自分を見失わないために“考える時間”が必要なのだ。
「まとめる」の前に「考える」を優先する
俺の場合、資料作成を始めるとすぐPowerPointを開いてしまう。でも、最近はまず紙に「何を伝えたいか」をメモするようにしている。図や言葉じゃなく、“感情”で書いてみる。たとえば、「この人には安心してもらいたい」とか、「面倒だと思われないように説明したい」とか。そうすると、後からスライドに落とし込むときに迷いが減る。不思議と作業時間も短くなる。いきなり“整える”のではなく、まず“考える”。地味だけど、それが一番の近道だ。
全部伝えようとするのをやめる勇気
司法書士の性なのか、「誤解されないように全部説明しておこう」とする癖がある。でも、それが逆に伝わらない原因になることもある。ある日、依頼者に「すみません、よくわかりませんでした」と言われたとき、ハッとした。丁寧すぎて情報過多になっていたのだ。思いきって、要点だけをシンプルに伝える資料に変えたら、「わかりやすいですね」と言われた。全部を伝えようとせず、「ここだけ伝わればいい」と割り切る勇気も必要なのだと学んだ。
第三者に話すことで整理がつく
資料を作る前に、誰かに内容を話してみるのも有効だ。事務員さんでも、同業者でも、友人でもいい。話すことで「自分が何を大事にしているか」「何が論点か」が見えてくる。言語化できないものは、スライドにも落とし込めない。だから、一人で悶々と考える前に、まず口に出してみる。元野球部の感覚で言えば、素振りばかりしてないで、実際にボールを打ってみるみたいなもんだ。壁打ちでもいい。話すことで、自分の「芯」が少しだけ見えてくる。
孤独な資料作成に負けないために
一人事務所、一人資料作成。一人で背負うものが多い士業にとって、資料作りは“自己対話”に近い。だからこそ、自分が迷子にならない工夫がいる。資料作りで心がすり減ったときは、無理に頑張らなくていい。「何してるんだろ」と感じること自体、ちゃんと考えている証拠だ。迷いながらでも、ちゃんと前には進んでいる。その感覚を忘れなければ、資料の中に“自分”はちゃんといる。
誰のための仕事かを思い出す
依頼者の顔が思い浮かぶとき、資料作成のモチベーションは回復する。「あの人の不安をなくしたい」と思えば、作業ではなく“仕事”に戻る。形式じゃなく本質に戻れる。そのためには、依頼者との会話や背景を大切にすることも必要だ。俺はいつも机の隅に、笑顔だった依頼者のメモを貼っている。たったそれだけで、「俺はいま、ちゃんと意味のあることをしてる」と思い出せるから。
疲れたら一旦やめてうまい飯を食う
夜遅く、煮詰まって何も進まないときは、さっさとあきらめてラーメンでも食べに行く。そんな日があってもいい。士業だからって、24時間完璧でいる必要はない。自分を追い詰めすぎると、資料だけでなく心まで壊れる。適度に力を抜くことが、実は“プロらしさ”だったりもする。スライド20枚目で「俺はいない」と気づいたら、いったん手を止めて、うまい飯でも食ってこよう。それが一番、立て直す近道だ。