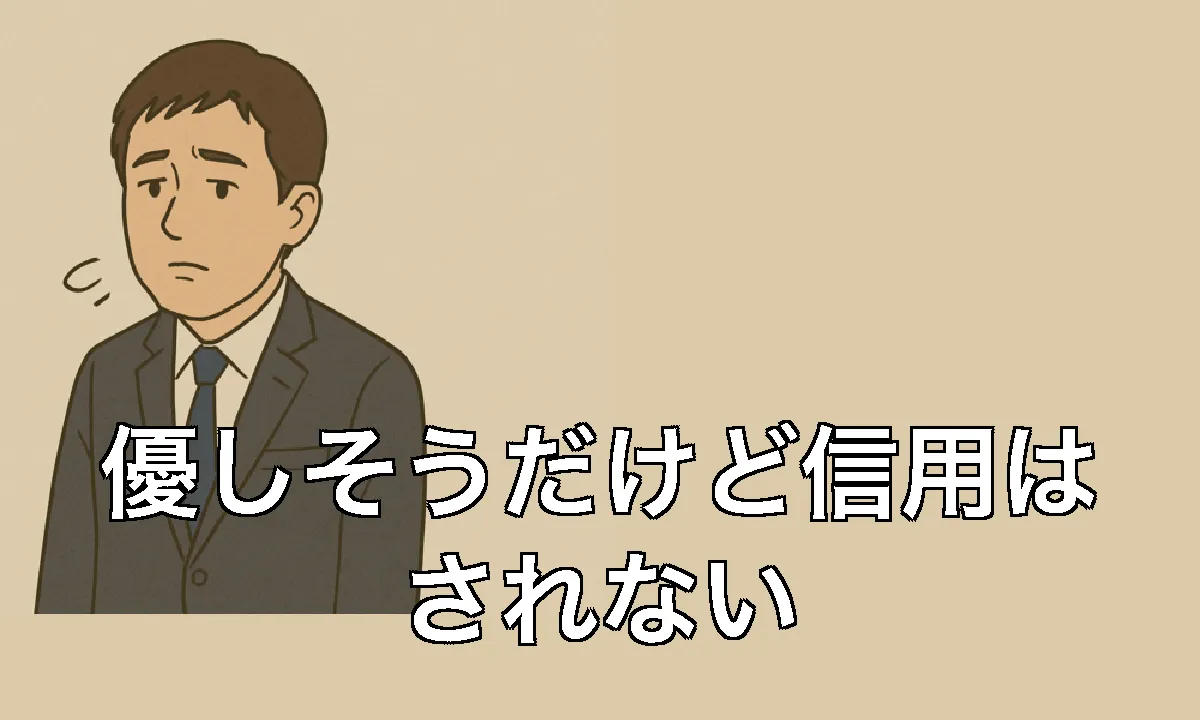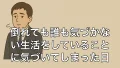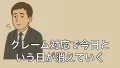人からは「優しそう」と言われるが
「先生って優しそうですね」──初対面の方によく言われる言葉だ。確かに、争いごとは嫌いだし、声を荒げることもない。見た目も強面ではない。だけど、その一言の後に続く空気には、なぜか薄っすらとした距離感がある。「でも、それだけじゃないよね」という含み。優しそうな人って、どうも“責任ある立場”には向いていないと見られることがある。信頼と優しさって、同じ土俵では測れないのかもしれない。
第一印象で得をするタイプかと思いきや
優しそうという第一印象は、たしかに敵を作りにくい。相談もしやすいと思われる。でもそれはあくまで“入り口”の話。本格的に仕事を任せようとする場面になると、別の目で見られ始める。特に司法書士という立場では、法的な判断や厳しい局面での対応が求められる。「この人に任せて大丈夫かな?」と、不安を抱かれてしまうことがある。実際、僕のところに来た依頼者が、他の事務所に乗り換えた理由が「もっとハッキリ言ってくれる人がいい」というものだった。
笑顔で返すと逆に軽く見られる現実
例えば、相手が怒っていたり、不安でいっぱいの時に、こちらが笑顔で「大丈夫ですよ」と言ったとしよう。こちらとしては安心させたいだけなのだが、逆に「本気で考えてくれてるのか?」と疑念を持たれてしまうことがある。僕は昔、かなり深刻な相続トラブルの相談に乗った際、緊張を和らげようと軽く冗談交じりで話したら、依頼者に泣かれてしまったことがある。それ以来、笑顔にも慎重になった。
「なんでも許してくれそう」に見えるという呪い
優しそうに見えるというのは、時に「何をしても怒らない人」と勘違いされる危険性がある。期日を守らない依頼者、料金を踏み倒そうとする依頼者、連絡なしで来なくなる人。強く出られないのを見抜かれている気がしてならない。学生時代、野球部のキャプテンにいじられ役として扱われていた僕は、たぶんその頃から「怒らない人」枠に入っていたんだろう。優しさが仇になる瞬間というのは、じわじわとくる。
優しさが災いする場面
優しさは人を救う力もあるが、自分を追い込む刃にもなる。仕事の現場では特にその傾向が強く、断れなかったことによる負担やストレスは、日常的に積み重なっていく。「つい引き受けてしまった」が積もると、心のどこかに「なんで俺ばっかり」という愚痴が溜まる。そしてそれが疲労感や無力感につながるのだ。
強く言えないことが仕事で不利に働く
たとえば、書類の提出が遅れているのに、それを強く催促できない時がある。「お忙しいところすみませんが…」と毎回柔らかく言っていたら、相手も真剣に受け止めてくれない。ある時、不動産の名義変更でギリギリの期限の案件があった。催促を遠慮していたせいで、結果として申請が間に合わず、相手にも迷惑をかけてしまった。僕の優しさが、結果的に誰も得をしない状況を生んだのだ。
依頼者に都合よく扱われる恐怖
「ちょっと無理を聞いてほしいんですが…」と前置きされて頼まれることが増える。「先生ならやってくれると思って」と。気づけば休日返上、夜間対応、報酬未確定の相談…。最初は「頼られている」と思っていたけれど、実際は“都合のいい人”になっていただけだった。僕の中で線を引く勇気がなかった。それは優しさではなく、自己防衛の下手さかもしれない。
理不尽を飲み込んでしまう自分にもイライラ
いざという時、「なんであの時もっと強く言えなかったんだ」と自分を責める。理不尽な要求や態度に対しても、咄嗟に反論できず、後で一人になってから怒りが湧いてくる。帰り道の車の中でひとり言のように愚痴をこぼす。優しさとは、耐えることじゃない。わかってはいるけど、瞬時に強く出るのが苦手だ。それが積み重なって自己嫌悪につながっていく。
司法書士という職業との相性
司法書士は信頼がすべての仕事だ。そしてその信頼は、「優しいかどうか」ではなく、「任せられるかどうか」で決まる。いくら人当たりが良くても、厳しい局面で毅然と対応できない人間は、仕事では通用しない。これは何度も身をもって痛感している。
信頼されるために必要な「厳しさ」
本当に信頼されるためには、時には依頼者に対してNOを突きつけることも必要だ。たとえば法的に無理な要求にはきっぱりと伝える、無理なスケジュールには断る、料金についても曖昧にせず説明する。そういった“厳しさ”が実は本当の意味での誠実さにつながる。僕自身、優しさと信頼はイコールじゃないと学ぶのに何年もかかった。
「優しさ」と「甘さ」はまったく別物
依頼者のことを思って譲歩することが、逆にその人のためにならないこともある。甘やかすことと寄り添うことは、似て非なるもの。「優しいですね」と言われて舞い上がっていた頃の自分に、「それは信用とは違うんだよ」と言いたい。本当の優しさとは、相手の未来を考えて時に厳しくなることだと、今は思っている。
人間関係でも同じことが起きている
仕事に限らず、私生活でも「優しい人」は都合よく扱われやすい。友人からのお願いを断れずに予定を潰したり、恋愛では「いい人」で終わってしまったり。特に僕のように、気を遣いすぎるタイプは、深く踏み込まれることなく、どこか“壁”を作られてしまう。
友人知人から頼られるが深くは踏み込まれない
「困った時に相談しやすいけど、付き合うには物足りない」そんな立ち位置に長年いる気がする。誕生日に誰からも連絡がないくせに、困った時だけLINEが来る。一度だけ、勇気を出して自分の悩みを打ち明けたことがあるが、相手は軽く流して話題を変えてしまった。それで余計に人に本音を言うのが怖くなった。
恋愛対象としては見られない優しさの限界
「優しい人が好き」なんて言葉は、あまり信用していない。実際にモテるのは、自分の意見をはっきり言える強さを持った人だ。僕は告白して「いい人なんだけど…」で終わるパターンが何度もあった。優しさは魅力にはなり得るけど、それだけでは足りない。芯の強さや頼りがいも、同時に求められるのが現実なのだ。
優しさをどう活かせばよかったのか
優しさが誤解されることがある一方で、正しく活かせばそれは強みになる。大切なのは「優しいだけ」ではなく、「優しくてもしっかりしている」と思わせること。優しさを基盤にした強さを身につけていく必要がある。
優しい人間でもブレない軸が必要だった
僕に足りなかったのは、ぶれない「軸」だった。どんな状況でも、自分の価値観や信念を持ち、それを貫く勇気。それがあるだけで、人からの見られ方は変わる。軸のない優しさは、ただの風に流される人になる。優しい顔して、しっかり者。そんな理想像を今からでも目指したい。
断ることができる優しさへ
最近は、無理な依頼や過剰な要求に対して「できません」と伝えるようにしている。もちろん言い方には気を遣う。でも、自分を守ることが相手のためにもなる。断ることで信頼を失うこともあるけれど、むしろ誠実さが伝わる場合も多い。優しいだけの司法書士から、信頼される司法書士へ。その一歩は「断ること」だった。
優しさは見せ方次第で武器にもなる
優しさが弱さに見られるのか、強さに見られるのかは、見せ方一つで変わる。僕はそのことを40代になってようやく理解した。優しさに裏打ちされた知識、誠実な対応、そして毅然とした態度。この3つが揃った時、優しさはようやく「信用」に変わる。だから今、僕は“優しそうだけど…”で終わらない自分を目指している。