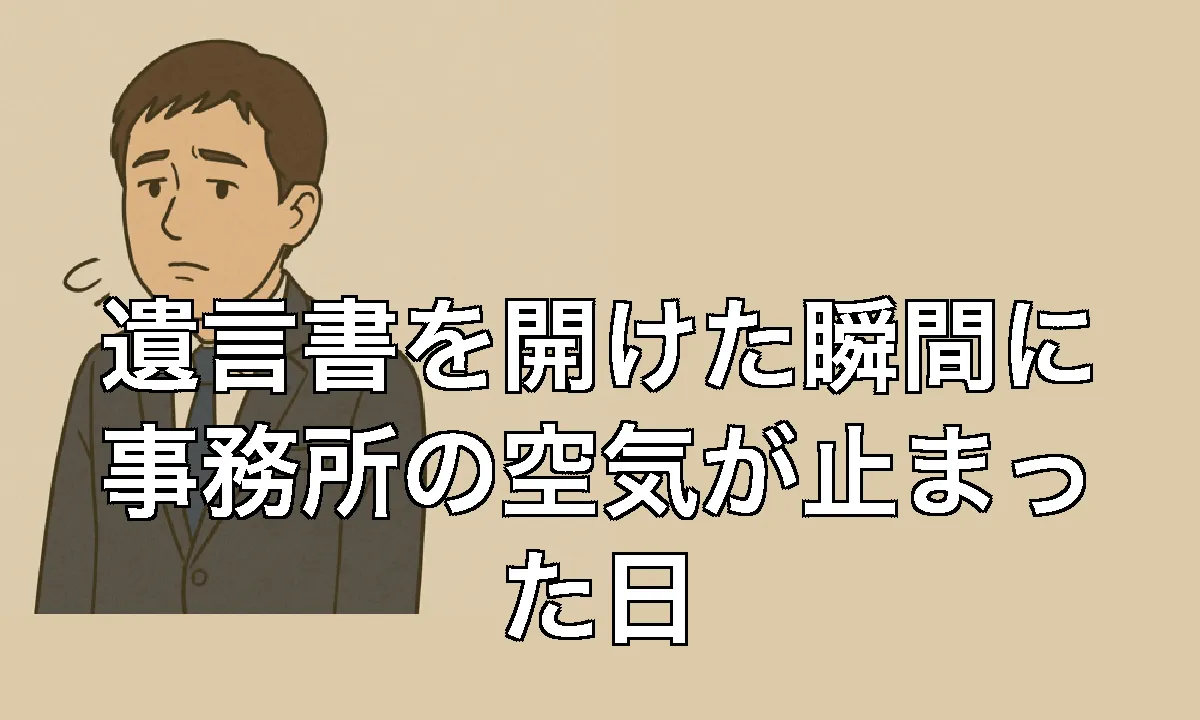あの日いつも通りに始まった朝
その日は特に何の変哲もない、ただの平日だった。朝9時に事務所を開けて、コーヒーを片手にメールチェック。デスクの上には、昨日から預かっていた遺言書の封筒。予定では午前中に相続人の一人が立ち会いのもと開封する段取りになっていた。封筒の厚みも、書類の枚数も、正直よくあるパターンで、心のどこかで「今日もいつも通り終わるだろう」と思っていた。
普通の開封作業のはずだった
依頼人が亡くなってすぐの遺言書開封は、たいてい空気が重たい。それでも「またこの仕事か」と思いながら封を切るのが日常だ。遺言書の内容に驚くことはたまにあるが、それも数年に一度の話。このときも、特に身構えることもなく、事務員の女性に立ち会ってもらい、静かに封を開けた。
「中身に驚かないように」と自分に言い聞かせていた
遺言書に関しては常に中立を意識している。感情を交えると、仕事に支障が出るし、相続人同士の揉め事に巻き込まれるリスクもあるからだ。だから、「何が書いてあっても驚かない」と、職業柄自分に言い聞かせてきた。でも、このときばかりは、その“訓練”が通用しなかった。
封筒の手触りが少し違っていたことに今さら気づく
今思えば、封筒を手に取った瞬間、ほんの少し違和感があった。紙が少し古びていて、筆跡も独特で、なにかこう…重たかった。けれどそのときは、いつものように開けてしまった。まさか、自分の常識を揺さぶるような内容が書いてあるなんて、夢にも思わなかった。
遺言書の中に潜んでいた違和感
封筒を開き、一枚目の便箋を読んだ瞬間に、頭の中が真っ白になった。まず最初に感じたのは「おかしい」という感覚。まるで、自分が過去に読んできたどの遺言書とも異なる雰囲気があった。感情的で、かつ具体的。そして、それが遺された家族の運命を大きく変えてしまうような内容だった。
読み始めてすぐに空気が変わる
「この遺言は、私が唯一心から愛した人への贈り物です」——。読み上げた瞬間、事務所の空気がピリッと張りつめた。そこに書かれていたのは、法定相続人には一切財産を残さず、第三者と思しき人物にすべてを譲るという内容だった。しかもその人物の名前は、相続人たちが聞いたこともない人だった。
名前が一人分多かった
リストに載っていた名前は全部で4つ。しかし、生前聞いていた家族構成から考えると、多い。一人だけ浮いている名前があった。念のため戸籍を調べたが、やはり血縁関係はなし。遺言書には「彼女は私の恩人」とだけ書かれていた。
想定していた内容がまるで覆された瞬間
これは、誰もが予想していなかった。相続人の顔は凍りつき、事務所の中に静寂が流れた。「これ、どういうことなんでしょうか」と聞かれても、自分には何も答えられなかった。ただ、職務として淡々と手続きを進めるしかなかった。
依頼人の顔が浮かばなかった
何度か打ち合わせをした記憶はある。けれど、その内容があまりに淡々としていたこともあり、深く心に残っていなかった。書類上は何も問題ない。でも、本当にこれがその人の“想い”だったのかと、ふと疑念がよぎる。
誰のための遺言か分からなくなる不思議な感覚
遺言書は、法的には「本人の最終意思」とされる。けれど、その意志が本当にその人の本心だったのかは、書かれた言葉だけではわからない。感情の裏には背景があり、選ばれなかった人の気持ちは、どこにも書き残されていない。
依頼人に聞けなかったことが山ほどある
今さら悔やんでも仕方ないが、もっと話を聞いておけばよかった。どうしても気になることが、いくつも浮かんできた。遺言書の中の名前、それを託された意味。答えはもう、誰にも聞けない。
対話不足のツケがまわる
短い面談で済ませてしまったのは自分の判断だった。忙しい日々の中で、つい効率を優先してしまった結果がこれだ。形式通りに受け取った遺言書の封筒が、こんなにも人の心を乱すとは思いもしなかった。
「もう少し聞いておけばよかった」が遅すぎる
人が亡くなってしまえば、もう話はできない。当たり前のことなのに、毎回それに打ちのめされる。生きてるうちに聞けること、確認できること、それを怠ったのは、自分の未熟さだった。
この仕事の「正しさ」ってなんだろう
法的に正しいことと、人として納得できることは、しばしば矛盾する。今回の件で、それを痛感した。自分は果たして「正しい仕事」をしているのか。いや、そもそも「正しい仕事」ってなんなんだろう。
形式は守った でも心はどうだったか
書類に不備はなかった。署名も押印も立派だった。でも、それが本当に本人の心の声だったかと言えば、断言できない。形式に甘えて、気持ちを置き去りにしていないか。自分の仕事に、そんな問いが突きつけられた気がした。
法律と気持ちの間にある深い溝
相続や遺言の世界は、感情が渦巻く。法律は冷静だけど、人は感情で動く。だからこそ、どちらも大事で、どちらも足りないと誰かが傷つく。そんな現実を、改めて突きつけられた。
最後に依頼人が教えてくれたこと
あの遺言書が、結果として依頼人の“人生最後の声”だった。賛否はある。でも確かに、何かを伝えたかったのだと思う。その想いに、自分はどう応えるべきだったのか——今もまだ、答えは出ていない。
遺言は人の記憶そのもの
書かれた言葉は、故人の思い出と直結する。その一文で泣く人もいれば、怒る人もいる。そう思うと、軽々しく取り扱ってはいけないんだと痛感する。だからこそ、たとえ愚痴ばかり言いたくなる毎日でも、真摯に向き合う意味がある。
死後に届く声が自分の背中を押すこともある
今回の一件で、「自分はまだまだだな」と思った。でも同時に、こうした出来事に出会える仕事をしていることに、不思議な誇りも感じた。誰にも褒められないし、モテもしないけれど、それでも今日もこの仕事を続けている。