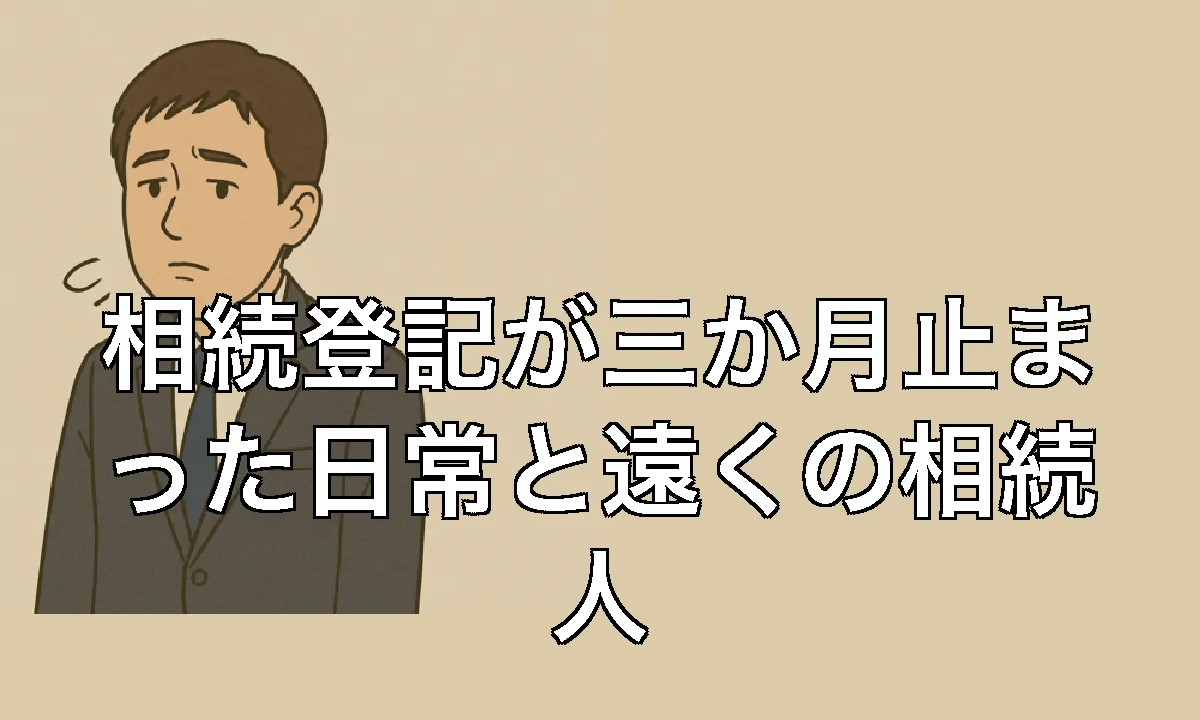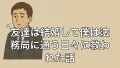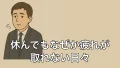相続登記は待ってくれないけれど人は待てない
司法書士という仕事には「淡々と処理を進める」という側面がある。しかし実際には、そんなにスムーズに進む案件ばかりではない。特に相続登記は、関係者が多ければ多いほど、何かしらの“つまずき”が発生する。そして今回は、相続人の一人が「海外在住」という条件が、見事に地雷となった。思えば、最初の相談時から何か嫌な予感はしていたのだが、それがまさか3ヶ月もの停滞を生むとは、さすがに予想していなかった。
連絡が取れないと仕事は止まる
最初に違和感を覚えたのは、戸籍収集の段階だった。ある相続人の住所欄が「ロサンゼルス在住」となっており、日本国内に連絡先が一切ない。念のため依頼者に確認すると、「あ、あの人はあまりメール見ないですね。時差もあるし」と軽く言われた。いや、軽く言わないでほしい。こちらは書類の確認や署名の送付、本人確認の段取りなど、やるべきことが山のようにあるのだ。だが現実は非情で、こちらがいくらメールを送り、何度電話をかけても、返事が来たのは1週間後だったり、ひどい時は既読すらつかない。
そもそも海外在住ってどういうこと
海外に住んでいると、相続の場面で不便が多いのはわかっている。だが、登記の実務において「海外在住」という情報だけでは何の助けにもならない。どこの国か、言語は何か、郵便物は受け取れるのか、すべて確認しないと何も進まない。こちらも英語が堪能というわけではないし、英訳証明の手配をすべて司法書士がやる義務もない。しかし、依頼者は「なんとかしてもらえませんか」と言う。なんとかしなければいけない空気だけが、じわじわとプレッシャーになって襲ってくる。
メールの返信が一週間に一度
例えば「この書類に署名して返送してください」とお願いしてから、返事が来たのが10日後。内容も「Got it.」だけ。いや、それだけじゃわからないから。フォームは読んでくれたのか?署名したのか?送ってくれるのか?こちらは日本の行政と法律のタイムラインで動いていて、日付のズレが致命傷になることもある。待っている間も、他の仕事は当然あるわけで、常にどこかに「例の案件、進んでないな…」という重りを抱えている状態。精神的にじわじわとやられる。
三か月かかりましたって誰のせいでもないけれど
結局、件の相続人から必要書類がすべてそろい、登記申請が完了するまでにかかった期間は、ちょうど三か月。もちろんこちらも出来る限りの段取りはしたし、他の相続人からの書類は早々に集まっていた。だが、ひとりの遅れが全体の進行を止めてしまう。これはもう責めることもできない。誰のせいでもない。でも、「誰のせいでもないこと」が、これほど苦しいとは思わなかった。事務員にも何度か「まだ届いてないんですか」と聞かれ、そのたびに「そうなんだよ」としか返せなかった。
依頼者に説明するつらさ
もっとも気を遣うのは、依頼者への説明である。「進捗はどうですか?」と聞かれて「海外の方が遅れてまして」と答えるしかないが、毎回同じような返事になると、こちらとしても申し訳なさと気まずさが入り混じる。説明すればするほど「言い訳っぽく」聞こえるし、かといって黙っていたら「進んでない」と思われる。言葉を選ぶ毎日に、何度かため息も漏れた。
書類が一枚足りないという絶望
やっと届いた国際郵便、封を開けると、まさかの署名欄が空白。何かの手違いか、それとも単純なミスか。こちらの指示書にはマーカーまで引いてあったのに…。その瞬間、「もう一度送ってください」と言う気力が、ほんの少しだけ枯れた。だが言わないと始まらない。また連絡して、また待って。まるで、登記ではなく手紙のやり取りを仕事にしているような気持ちになった。
海外の住所って本当に必要なんですか
登記の世界では「住民票がないから代わりに…」というケースも少なくない。だが、海外住所の証明というのは本当に厄介で、在留証明や現地の住所証明が必要になることもある。それらは外務省の証明が必要だったり、領事館に足を運んでもらわないといけなかったり、とにかく手間がかかる。こちらでどうにもならない部分も多く、やきもきする毎日が続くのだ。
翻訳証明の手配で半泣き
例えば、現地の住所を証明するための英文証明書が届いたのだが、それを日本の法務局に提出するには日本語訳が必要。そしてその訳に「翻訳者の署名」が求められる。最初は自分で訳そうかと思ったが、「職印を押した第三者翻訳」と明記されているのを見て断念。結局、外部に翻訳証明を依頼し、また日数がかかる。いったい私は司法書士なのか、翻訳事務代行なのか、わからなくなる。
時差に泣かされる深夜のやりとり
夜9時に送ったメールに、朝5時に返事が来る。返信に気づくのは午前中、そこから作業をして、次の返事はまた翌日の深夜。やりとりが一往復するのに丸二日。業務のリズムが完全に崩れていく。依頼者からの電話は昼間に来るが、情報はまだ揃っていない。そのたびに「もう少々お待ちください」と繰り返す自分の声が、どんどん小さくなっていく。
心が折れる国際郵便の遅延
やっとの思いで送り返した書類が、なぜか税関で止まる。調べても理由はわからない。追跡番号だけが頼りで、いつ届くかも読めない。こちらは法務局との期限調整もあるのに、郵便事情に振り回されている現実。こんな時、「国内にいればなあ…」という気持ちがふとよぎる。でも、相続人の都合を責めるわけにもいかず、ただただ届くのを待つしかない。
それでも今日も登記は進む
文句を言いたくなる日は多い。でも、依頼者は悪くない。相続人も悪くない。海外にいる事情も、それぞれの人生だ。だからこそ、私たち司法書士がやるべきことは、黙って前に進めることなのだと思う。途中で何度もくじけそうになったけれど、最終的に登記が完了したとき、ふと気づいた。「こんなに苦労したのに、誰にも伝わらないなあ」と。
三か月を越えて得たもの
この案件を通じて得たもの。それは「待つことに慣れない」姿勢だったと思う。仕事である以上、効率もスピードも求められる。けれど、人を相手にする限り、予想通りにいかないことも多い。そこでイライラしてしまうのではなく、「どうすれば次につながるか」を考える力。それが、今回の一番の学びだった。
相続人にも事情があるということ
こちらが「なんでこんなに遅いんだ」と思っている間、向こうは向こうで慣れない日本の書類に困っていたかもしれない。サイン一つにも戸惑いがあったかもしれない。そう思えば、もう少しだけ優しくなれる気がする。事務的な手続きにも、やっぱり“人間”が関わっているのだと、改めて感じた。
他人を責めずに手を動かす覚悟
誰かを責めても、書類は進まない。だから、自分がやれることをやる。それだけの話なのに、それがなかなか難しい。独身の夜、事務所で一人、コーヒーをすすりながら思った。「今日も終わらなかったけど、明日は少し進めるかもしれない」。そんなふうに思える自分でいられたら、まだやっていけるのかもしれない。