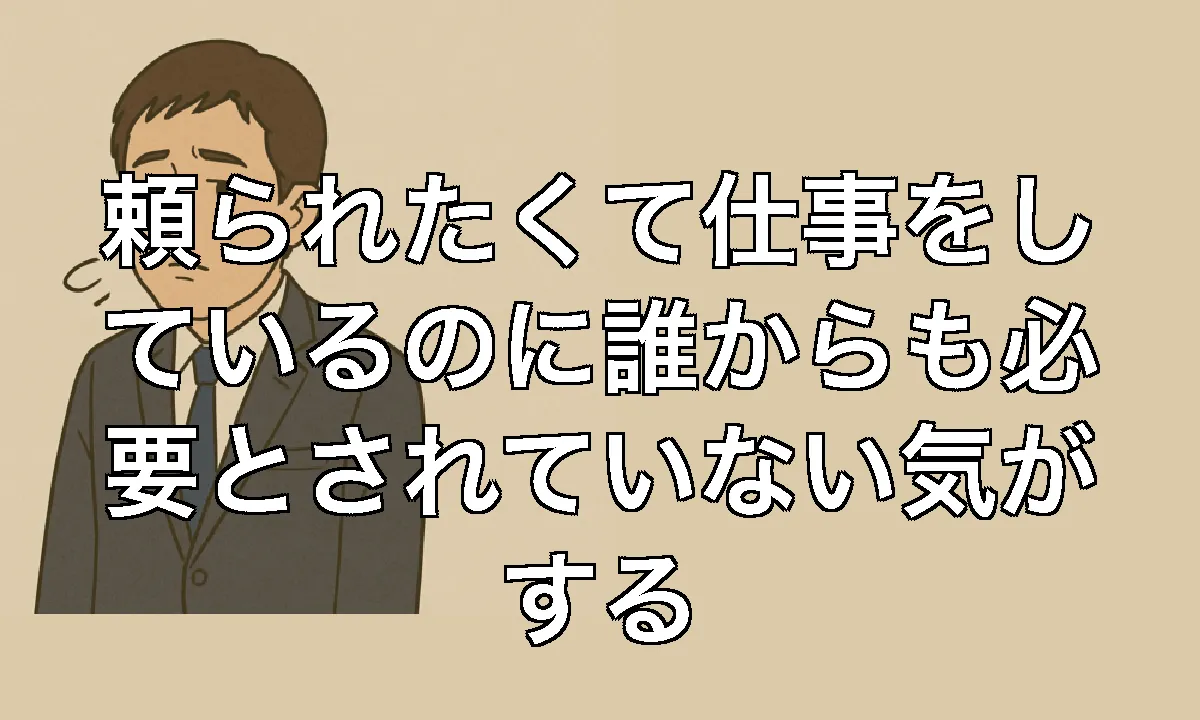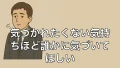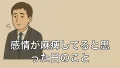頼られることが原動力だったはずなのに
司法書士という仕事を選んだのは、人の役に立ちたいという思いがあったからだ。登記や相続といった書類の向こう側には、誰かの困りごとや不安がある。自分がその一助になれれば、それが何よりの報酬になる。そんな風に思っていた。最初は、本当にその思いだけで走ってこれた。けれど、いつの間にか「頼られてる」と感じる機会が減っていった。仕事はある、忙しさもある。でも「誰かのためにやっている」という実感だけが、どこかに落ちてしまったような気がしてならない。
あの頃の自分は誰かの役に立ちたかった
思い返せば、新人時代はわからないなりに必死だった。知識も経験も足りなかったが、「頼ってもらえたこと」が嬉しかった。たとえそれが、役所に書類を持っていくだけのことでも。「ありがとうございます」「助かりました」という一言が、次の日の自分の背中を押してくれた。誰かの支えになれる。それだけで、多少の無理も我慢できた。あの頃の自分は、見返りではなく「存在意義」を探していたように思う。
「ありがとう」が嬉しくて走っていた新人時代
ひとつ忘れられないエピソードがある。開業前、事務所勤務の頃、ある年配の女性の相続登記を担当したときのことだ。不安でいっぱいだった様子のその方が、手続きが終わった帰り際、深く頭を下げて「あなたがいてくれてよかった」と言ってくれた。あの一言だけで、自分が司法書士を目指した意味が報われた気がした。その後も同じような場面はあったはずなのに、年々それを実感できなくなってきたのは、なぜなのだろう。
雑務でも笑顔でやれたあの頃の原動力
今では面倒に感じるような、郵送手続きや細かな書類整理も、かつては張り切ってやっていた。先輩に「これやっといて」と頼まれるだけで、「任された」と嬉しかった。あの感覚はどこへ行ってしまったのだろう。事務員に「これお願い」と言っても、特に何も返ってこない毎日。やりがいの原点は、自分の中からではなく、人との関わりから生まれていたのだと痛感する。
今感じているのは誰にも求められていない感覚
仕事があるのに、なぜか「自分が必要とされていない」ような虚しさがつきまとう。これは贅沢な悩みなのかもしれない。でも、案件の数や売上とは関係なく、「人に頼られる」という感覚が薄れてくると、心のどこかにぽっかり穴が開いたようになる。人の役に立っているはずなのに、ただ機械的に処理しているだけのような毎日。そんな矛盾に、自分でもどう折り合いをつけていいかわからない。
感謝よりも納期と責任ばかりが重くなる
依頼が増えると、当然責任も増える。でも、それに比例して感謝の言葉が増えるわけではない。むしろ、「間に合いますか?」「まだですか?」というプレッシャーだけが積み重なる。最近は「やって当然」という空気が漂っていて、結果を出しても「次もよろしく」で終わってしまうことが多い。人に頼られるというより、使い捨ての便利屋になっているような感覚に陥る。
必要とされているのではなく「使われている」
「この仕事はあなただからお願いしたい」と言われることが、めっきり減った。むしろ、「誰でもできるけど、近いから」とか、「前もお願いしたから」という理由ばかり。自分でやっている意味って何だろうと考えてしまう瞬間が増えた。昔はもっと、相手との信頼関係や温度感があった気がする。今は、淡々とした業務依頼と請求書のやり取りだけになってしまったようで、正直寂しい。
依頼じゃなくて命令に変わったときの気持ち
ある日、依頼者から「〇日までにやっといてくださいね。急いでますから」と言われたとき、内心ガッカリした。「お願いします」でもなく、「お忙しいところすみません」でもなく、ただの命令口調。別に言葉遣いひとつで怒るほど狭量ではないけれど、積み重なると心がすり減っていくのを感じる。仕事のやり取りも、人と人との関係なのに、それが忘れられているのが辛い。
事務所経営者としての孤独
開業して十数年。独立すれば自由になれると思っていたけれど、その分、孤独との付き合いも濃くなった。事務所に相談できる同僚はいないし、事務員には気を遣う立場。責任はすべて自分持ち。うまくいかないときに、どこに吐き出せばいいのかわからない。たまに「先生は自由でいいですよね」と言われるが、心の中では「自由という名の孤独です」とつぶやいている。
相談できる相手がいない日常
友人ともだんだん疎遠になって、仕事の愚痴を気軽に話せる相手も減ってきた。周りは家庭を持ち、忙しくしているし、自分だけが取り残されているような気分になるときもある。こっちだって好きで独りなわけじゃない。たまには「それは大変だね」と言ってくれる人が欲しいだけ。でもそれを言えない自分が一番やっかいなのかもしれない。
事務員にすら気を遣ってしまう自分
事務員は真面目にやってくれている。でも、自分の機嫌が悪いと空気が悪くなるのがわかるから、余計に気を張ってしまう。「経営者なんだから、機嫌を顔に出すな」と思っているが、人間だから限界はある。ミスがあっても怒れず、かといって放っておくとこちらが損をする。孤独と我慢の両立が続くと、どこかで爆発しそうになる。
本音を言えないのは甘えだと思ってきたけど
これまでずっと、「弱音を吐かないのが大人」だと思っていた。元野球部の性分もある。だけど最近は、それが逆に心のしんどさを倍増させていると気づいた。誰かに「もうちょっと楽になってもいいんじゃないですか」と言われたとき、思わず涙が出そうになったのを今でも覚えている。本音を言える場があるだけで、こんなに救われるんだと、あのとき初めて知った。
それでもこの仕事を続けている理由
不満や孤独を感じながらも、なぜ司法書士を続けているのか。それは、ほんの小さな一言が、また前を向かせてくれるからだ。「助かりました」「先生に頼んでよかった」――たったそれだけで、胸の奥がふっとあたたかくなる。それがなかったら、たぶんもう辞めていたと思う。今でも、そんな言葉に救われている自分がいる。
たまに届く一言が救いになる
毎日じゃなくていい、毎月じゃなくてもいい。でも年に数回でも、誰かが心から感謝してくれると、「やっててよかった」と思える。その一言のために、また地味な書類と向き合える。華やかさはないけれど、確かに誰かの人生の一部を支えているのだという実感。それだけが、今日も机に向かう理由になっている。
「先生に頼んでよかった」の重み
本当に困っているとき、人は「この人に頼みたい」と思ってくれる。その瞬間が、司法書士としての醍醐味だ。最近、ある高齢の依頼者が「息子にも相談したけど、やっぱり先生に頼もうと思って」と言ってくれた。それだけで、数ヶ月分の疲れが吹き飛んだ気がした。「この人でなければ」という感覚。それがほしくて、ここまで続けてきたのかもしれない。
誰か一人でも思い出してくれたら
結局、頼られたいという気持ちは、自己満足かもしれない。でも、たとえ一人でも、「あの先生がいて助かった」と思ってくれる人がいれば、それでいい。モテなくても、独身でも、報われない日が続いても。そんな誰かの記憶の中に、自分という司法書士が残っていれば、それがきっと、自分の存在価値なのだと思う。