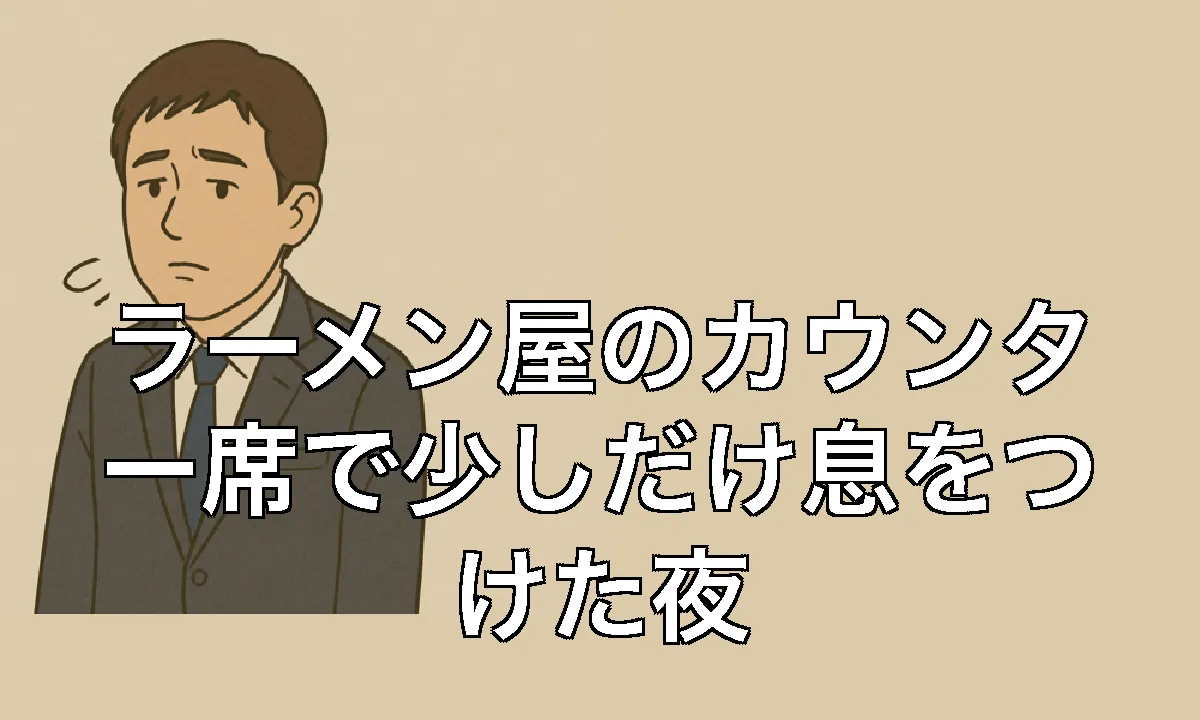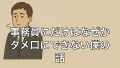仕事帰りの足が勝手に向かう場所
夜の帳が下りる頃、ようやく事務所を出る。今日も電話は鳴り止まず、書類の山とにらめっこしているうちに一日が終わっていた。家に帰っても誰もいない。冷蔵庫の中には賞味期限切れの豆腐。温め直す気力すら湧かない夜がある。そんな時、気づけば足が向いているのがあのラーメン屋のカウンター席だ。特別うまいというわけでもない、けれどあの狭い空間と湯気が、なぜか今の自分にはしっくりくる。
事務所を出る瞬間の虚しさ
毎日決まった時間に出勤して、決まったように電話を取り、登記簿をめくり、印鑑証明を取り寄せて、申請書を提出する。ルーチンに慣れすぎて、何の感情も湧かなくなっている自分に気づく。事務員の彼女が「お疲れ様です」と言って帰ったあとの事務所の静けさが、なぜかやけに耳に残る。照明を落としてシャッターを閉める瞬間、「今日も誰ともまともに話してないな」と思うと、胸に小さな虚無が広がっていく。
帰宅しても誰もいない現実
仕事で疲れた体を引きずって家に着いても、玄関の電気はもちろんついていない。独り身歴が長くなると、この静寂に慣れてしまうけれど、本当は慣れたくなかった。夕飯を作る気力もなく、テーブルの上には買い置きのカップ麺。テレビの音がやけに大きく感じるのは、心の中にぽっかり空いた空洞のせいかもしれない。元野球部だった頃の仲間も、みんな家庭を持っている。集まる機会もなくなって久しい。
コンビニ飯にすら気力が湧かない日
一時期はコンビニ弁当で済ませる日々が続いたが、最近はその選択肢すらしんどく感じる。何を食べても味がしない、というより、食べる行為そのものが面倒になっていた。そんなある日、ふと脳裏によぎったのが、駅前の古びたラーメン屋だった。数年前に一度だけ入ったことがあったが、その時は特に印象にも残らなかった。なのに、その日だけは「なんとなく、あそこなら」と思わせる何かがあった。
赤提灯と湯気に吸い寄せられて
寒い夜だった。吐く息が白くなるなか、駅前の路地裏にあるその店に足が向いた。小さな赤提灯が揺れていて、ガラス戸の向こうには白い湯気と湯切りの音。店内のテレビからはプロ野球のニュースが流れていて、その音がなぜか心に刺さる。暖簾をくぐると、店主が「いらっしゃい」とぶっきらぼうに言う。けれどその声が、やけにありがたく感じた。
看板の明かりが心に灯る理由
「営業中」の看板が出ているだけで、少しだけ安心する夜がある。外の世界がどれだけ冷たくても、ここだけは変わらずそこにある。どこにでもある町のラーメン屋だけど、何かにすがるような気持ちで戸を開けた。自分以外にもスーツ姿の男が数人、カウンターに沈み込むように座っている。その姿が、なぜか自分の写し鏡のように思えた。
暖簾をくぐる一瞬のためらい
一歩入るか入らないかで迷うのは、カウンター越しの空間があまりに近すぎるからかもしれない。誰かに見られるわけでもないのに、なぜかちょっとだけ恥ずかしい。でも今の自分に必要なのは、「話さなくても済む空間」だった。オーダーは「塩ラーメン」。一番あっさりしていて、一番しみる味。食べ終わるころには、心の中のざわめきが少しだけ収まっていた。
カウンター席に座るという救い
この歳になると、誰かと一緒に食べる機会も減る。かといって、完全に一人きりの食事は、どこか空しい。でも、ラーメン屋のカウンター席は違う。誰かがいて、でも誰も話しかけてこない。この絶妙な距離感が、疲れた心をそっと包んでくれる。
誰にも話しかけられない安心感
普段は「人と話さないとダメになる」なんて言いながらも、実際には人と話すこと自体にエネルギーを使い果たしている。司法書士という仕事柄、言葉を使う機会は多い。だが、その言葉には責任や正確性が求められ、自然体ではいられない。ラーメン屋では、何も気にせず黙って座っていられる。それがどれほどありがたいことか、実際に体験してみないとわからない。
ちょうどいい距離感がありがたい
隣の席との間隔は狭い。けれど、誰も他人を気にしない。それがこのカウンター席の良さだと思う。店主は淡々とラーメンを作り、常連客は黙々と食べる。テレビの音と湯切りのリズムだけが流れる空間に、自分の存在を委ねられる。会話もない、スマホも見ない、ただ「食べる」ということに集中できるこの空間は、無意識のうちに自分を救ってくれていたのだ。
店主の背中に感じる職人の気配
カウンター越しに見える店主の動きは実に無駄がない。黙々と麺を湯に入れ、湯切りし、具材を手際よく盛りつける。派手さはないけれど、長年続けてきた者だけが持つ所作の美しさがある。自分の仕事にも通じる何かを感じた。書類を丁寧に整え、ミスなく処理する作業の積み重ね。それは誰に褒められるわけでもないが、確実に誰かの人生を支えている。ラーメン屋の店主も、そんな存在に見えた。
ラーメン一杯に教えられたこと
塩気の効いたスープをすすりながら、ふと涙が出そうになった。理由はわからない。でも、自分の中にたまっていた何かが、溶けていくような感覚があった。日々の生活に追われ、感情を押し殺していた自分が、ほんの少しだけ息をつけた。それがラーメン一杯だったということに、救われた気がした。
沈黙の中で聞こえる自分の声
誰とも話さない時間が、時には必要だ。特に「話すこと」が仕事の一部である自分にとってはなおさらだ。湯気の中にじっと座っていると、いつの間にか、頭の中に浮かんでくるのは「本当はどうしたいのか」という問いだった。普段は忘れてしまっているが、自分にもまだ夢がある。新しいサービスの立ち上げ、他士業との連携、そういったことを考える余裕が少しだけ戻ってきた。
書類の山に追われる日々との対比
昼間は書類の束に囲まれて、常に締切に追われている。お客さんの顔を見る余裕もなく、ただ流れ作業のように手を動かしていると、何のためにこの仕事をしているのかわからなくなることがある。そんな日々とはまったく別世界のような、ラーメン屋のカウンター席。目の前のラーメンを、ただ黙って味わうという行為に、逆に「意味」があるように感じた。
「いただきます」が久々に自然に出た
実は、ここ最近「いただきます」と声に出して食事を始めた記憶がない。でも、この店で、思わず口にしていた。誰かに見せるためじゃなく、自分のための言葉だったのかもしれない。そう思うと、食べ終わった後の「ごちそうさま」も、少し誇らしく感じられた。何かを取り戻せたような気がして、また明日も、頑張ってみようと思えた。