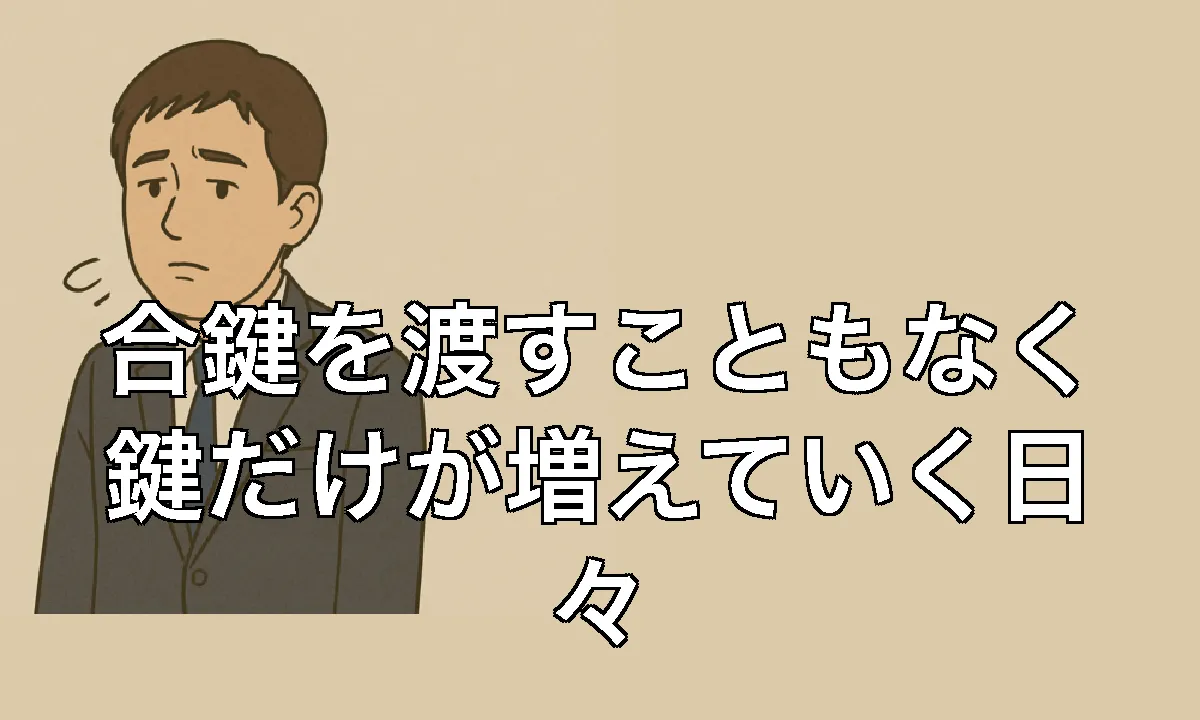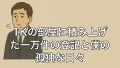合鍵を渡すこともなく鍵だけが増えていく日々
「先生、また鍵、増えました?」
サトウさんが、机の上の小袋を指差して、ニヤリと笑った。
確かに。最近、事務所の引き出しの中にある“未使用の合鍵”がやけに増えてきた。新規の管理物件や、成年後見の仕事に伴うものだ。いや、少なくとも表向きはそうだ。
けれど、たまにポケットの中でジャラ、と鍵が鳴るたび、何かが胸の内で引っかかる。「誰かに渡すかもしれないから」そう言って作った合鍵。でも、結局その「誰か」は現れず、袋にしまわれるだけ。
鍵を預かる仕事をしていても
司法書士という職業は、鍵を渡すことにも似ている。信頼の証として、不動産や財産の「入口」を整える。でも、俺の私生活は、鍵を渡す相手もなければ、訪ねてくる人もいない。
かつて、事務所を立ち上げた頃、勢いだけで合鍵を3本も作った。ひとつはサトウさんに渡した。他の2本は、当時付き合っていた彼女に渡すはずだった。結果は──渡せなかった。
元野球部という肩書きは今や物置きの奥
「お前キャプテンだったよな」と同級生に言われても、ピンとこない。あの頃は、ベンチに戻れば誰かがいた。ミスしても「ドンマイ」と声が返ってきた。
今は違う。カギを回して事務所に入る。静寂が出迎えてくれる。応援歌も、ノックの音もない。
合鍵という名の幻
大学の頃、付き合っていた彼女に「鍵、渡そうか?」と何度も言おうとして、結局言えなかった。サザエさんのマスオさんでさえ「ただいま」と言えば「おかえり」が返ってくる。あれはフィクションだけど、羨ましい。
鍵を渡すことで関係が深まるなんて思っていなかった。ただ、玄関で鍵を探す時間を共にするくらいの関係が、あってもよかったんじゃないか。そんなことを、45歳になってから考えている。
鍵は語る 寂しさと少しの希望を
「渡す相手がいなくても、鍵って役に立ちますよ」
ある日サトウさんが、ふとそんなことを言った。
たぶん、俺がまた新しい鍵を作ったときだったと思う。「そうだな」と笑って返したが、内心では涙が出そうだった。
机の中で鳴る鍵の音
誰にも渡せなかった鍵たちは、今日も机の中で静かに存在している。
それでも俺は、また鍵を作る。使う予定のない鍵。渡す予定のない鍵。けれどそれは、希望のようなものかもしれない。誰かと一緒に帰る未来を、ほんの少しだけ夢見て。
……やれやれ、、、夢見たって、鍵じゃなくて、人を探さなきゃな。
俺はそっと引き出しを閉じた。鍵の音がカチャリと鳴った。まるで、閉じ込めた心の音のように。