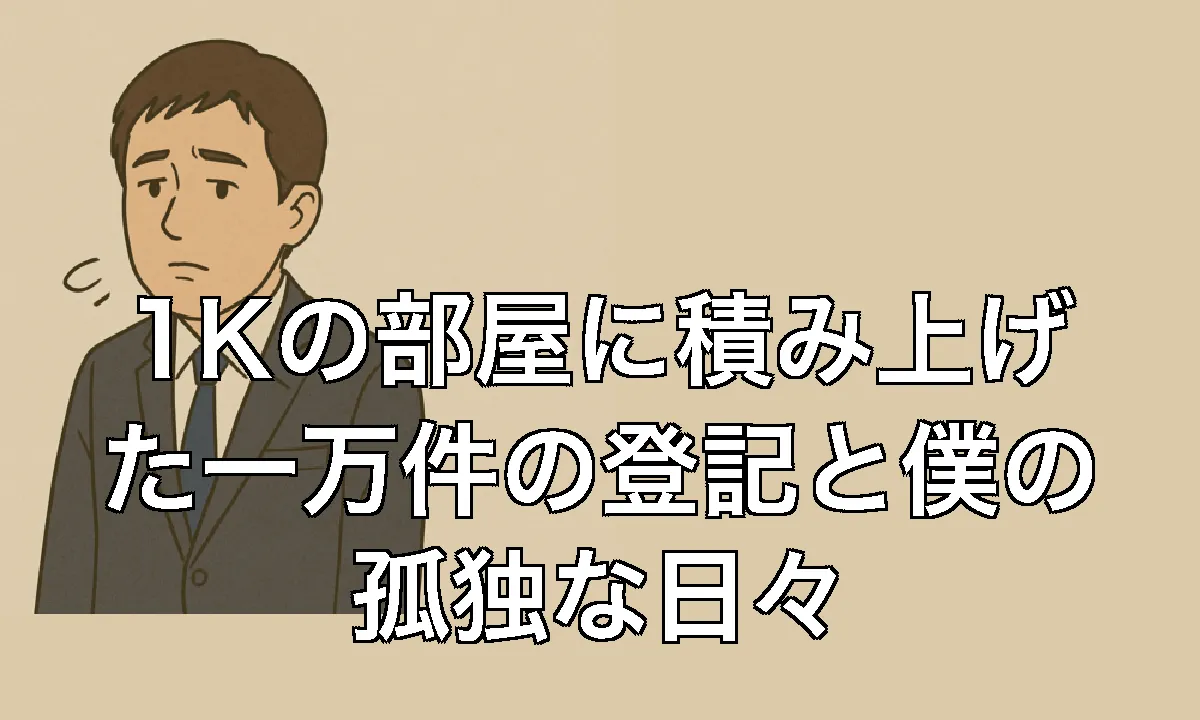はじめに 一万件の登記と一人暮らしの現実
六畳一間の部屋に、書類が溢れている。1Kというには広すぎる書類たちの存在感。いや、実際は部屋が狭いだけだ。
ひとり暮らしを始めたばかりの頃、この部屋にはまだ余白があった。畳の縁も見えた。けれど今では、机の上も床の上も、棚の中も書類と印鑑で埋め尽くされている。
「1万件目、か」
独りごちた声が、狭い部屋にむなしく響いた。
登記書類の山に囲まれた生活
六畳の床が見えなくなる日
朝目覚めると、すでに自分の足元にあるのは枕ではなく登記簿だった。夢の中でも登記事項証明書を確認していた気がする。司法書士という仕事は、夢の中まで正確性が求められるようだ。
紙とハンコと一人ごと
「この物件、なぜ毎回表題部がこんなに読みにくいのか」
「“之印”が消えかけてるじゃないか」
独り言が多くなるのは、孤独の副作用だろう。いや、もはや副作用というより、もれなくついてくる標準装備だ。
司法書士という仕事を選んだ理由
なぜあの時この道を選んだのか
昔、野球部のベンチでふと「資格っていいな」と思った。思えばそれがすべての始まりだった。あのときの自分に、「モテるようにはならんぞ」と教えてやりたい。
合格してもモテるわけじゃない
合格発表の掲示板の前で、歓喜する受験生たちのなか、僕は冷めた缶コーヒーを片手に「さて、次は何年独りでやることになるのか」と考えていた。
開業 初めての部屋 初めてのクライアント
家賃三万五千円の1Kから
開業時、1Kのこの部屋が僕のすべてだった。机も無理やり押し込み、ファイルボックスを重ねて棚の代わりにした。FAXは鳴らない日もあったけど、鳴ったときは本当にうれしかった。
サトウさん登場 そして世界は少し変わった
彼女がやってきたのは、開業して3年目。経理が壊滅的だった僕にとって、救世主だった。頭の回転が速く、しかも押し付けがましくない。
ただし口調は鋭い。「先生、それ、日付間違ってますよ?昨日の日付です」
「やれやれ、、、」と思わず漏れる。僕の中ではもはや口癖だ。
一万件の登記 そこにあった物語たち
不動産の数だけ人生がある
名義変更、相続、売買、贈与……どの書類の向こうにも、誰かの人生があった。中には「この土地、誰も知らないと思いますけど、戦時中に…」と語り始めた年配の依頼人もいた。
「物件には、それぞれのドラマがあるんだな」
そう思ったのは、ある意味、僕も登記される側の人生を見守ってきたのかもしれない。
誰の記憶にも残らない手続きの重み
でも、こちらの名前はどこにも残らない。司法書士は、正しくて目立たないことが仕事なのだ。まるで名探偵コナンの黒タイツモブのように、常に背後から支えている。
書類に埋もれる生活で失ったもの
休日ってなんでしたっけ
テレビのサザエさんを見ることもなくなった。というか、気づけば日曜の夕方がただの締切前夜になっていた。「あ、今日って日曜か…」という絶望。
湯船の中でも登記の夢を見る
リラックスのはずのお風呂でも、登記事項の読み合わせをしていた自分に気づいて、泣きたくなった日がある。
「やれやれ、、、」と思いながら、もう一度湯に沈んだ。
登記と孤独とささやかな救い
深夜二時のコンビニとレジの彼女
いつも夜食を買うコンビニの、レジの彼女。名前は知らない。けど、あの「温めますか?」の声に、何度か救われた気がする。
「登記、順調ですか?」と彼女が言ったとき、僕は一瞬、怪盗キッドに正体を見破られたような気持ちになった。
サトウさんの言葉に救われる日
「先生、たまには外で昼食にしましょう」
そう言ってくれる人がいるだけで、人生は少し変わる。
登記という孤独な作業のなかで、人とのつながりは確かに存在する。
おわりに 登記は誰かの未来のために
この部屋から始まる次の物語
1万件目の登記を終えた僕は、机の片隅にひとつの付箋を貼った。
《次は、自分の登記でも書いてみようか。住所変更とか、婚姻とか。》
まだ誰も現れてないけどさ。
そして今日もまた紙と格闘する
窓の外では、また季節が変わろうとしている。
僕の部屋の中では、まだ一件目のように登記が始まっている。
やれやれ、、、
今日も、六畳一間の法務局は営業中だ。