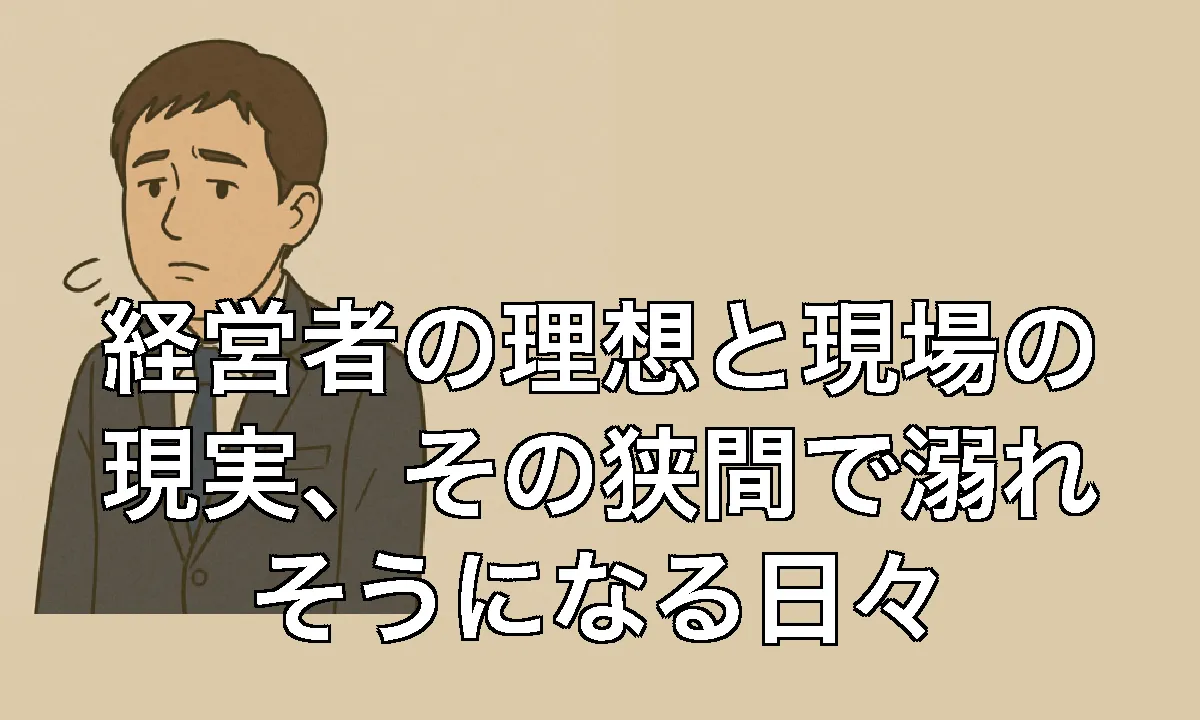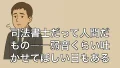経営者の理想と現場の現実、その狭間で溺れそうになる日々
理想ばかり語る「経営者の自分」が嫌になるとき
経営者として事務所の方向性を示さなければならない立場にある自分。でも、口では「これからはこういうサービス展開も検討したいですね」なんて言っていても、内心は「現場の処理すら追いついてないのに何を言ってんだ」と冷めた目で自分自身を見ていたりする。理想を語るのは悪いことじゃない。だけど、それに押しつぶされそうになる瞬間がある。
現実的なことを言えば「夢がない」と言われ
昔、地元の異業種交流会で「実務が追いつかないから、これ以上案件増やすのは難しいんですよね」と正直に言ったら、「それじゃ成長止まりますよ」と鼻で笑われた。そのとき思った。「成長って、誰のための?」って。自分のキャパは超えないし、事務員も疲弊してるのに、なぜ夢を語ることが偉いみたいになってるんだろう。
数字を見て悩むのはいつも自分だけ
売上も支出も、全て自分の責任。事務員には言わないけど、毎月の請求書の山を見るたびに胃がキリキリする。なのに、外部からは「事務所経営って儲かるでしょ?」と言われる始末。通帳の残高が減っていくのを見て、現実と理想の乖離に頭を抱える時間は、誰にも見えない夜の仕事だ。
でも「やるしかない」と自分に言い聞かせるしかない
「やるしかない」って、便利な言葉だと思う。本当はもうやりたくないときも、それを心の中で唱えていると、自動的に体が動き出す。情熱とか理想じゃなく、ただ「止まったら終わる」という怖さで走り続けてるような感じ。そういう感情って、経営者ってより、むしろランナーに近いのかもしれない。
「現場」を回すのも、支えるのも、たった二人だけ
僕の事務所は、僕と事務員の二人だけ。多い日は一日8件の電話対応に追われ、同時に登記書類の確認、送付、訪問対応が続く。ごく普通の1日が、すでにテンパっている状態。誰かが体調崩したら即崩壊。そんな綱渡りを、何年も続けている。
事務員さんに甘えすぎている自覚はある
うちの事務員さん、ほんとによくやってくれてる。だけど正直、甘えてる自覚がある。書類の整理からお茶出しまで、何でもお願いしてしまっている。それに気づくたび、「一人で抱え込んじゃってごめん」と思う。でも、任せられる人が他にいない。このループから抜け出せないことに、また自己嫌悪が募る。
でも正直、限界ギリギリのところで支え合ってる
お互いギリギリの中で仕事してるからこそ、変な絆みたいなものがあるのも事実。事務員が帰った後、彼女がつけた付箋に「今日もお疲れさまでした」って書いてあるのを見て泣きそうになったことがある。限界の中で誰かが一緒に頑張ってくれてる、それだけで救われることもある。
「もう一人雇えば?」と言われても、その余裕がない
「人を増やせば?」と簡単に言われることがある。でも、地方の司法書士事務所ってそんなに余裕ない。求人出しても応募も来ないし、来ても即戦力とは限らない。教える時間もないのに人を入れるリスクは、現場を知らない人には理解されにくい。
「経営判断」という名の孤独
何かを決めるとき、相談相手がいないというのは地味にキツい。ダメな方向に行っても、「決めたのは自分だから」という責任が常につきまとう。相談できる人がいたらと思うことは多々あるけれど、結局、誰も僕の現場の内情なんて知らない。
相談できる相手がいない恐怖
「それって自分で決められるからいいよね」と言われることがある。でも、決めることが怖いことだと知らない人の言葉だ。誰かに「それで大丈夫」と背中を押してもらいたくなるときだってある。でも、そんな相手はいない。どこかで「甘え」と言われる気がして、誰にも言えずに飲み込んでしまう。
判断ミス=即赤字、誰のせいでもなく自分の責任
たった一つの決断で、数十万円の損失が出ることもある。それは誰かのせいじゃなく、自分の選択の結果。従業員に負担をかけまいと無理して受けた案件で、自分の時間が足りなくなり、結果として信用を失いかけたこともある。経営って、結局は自己責任の連続なんだ。
でも「成功すれば経営者のおかげ」みたいな風潮
世間的には、何かがうまくいけば「やっぱり経営者の手腕ですね」と言われる。でも現実は、現場のがんばりとか、運とか、タイミングとか、いろんな要素が重なってるだけ。全部を背負わされる構造って、本当に不公平に感じることがある。