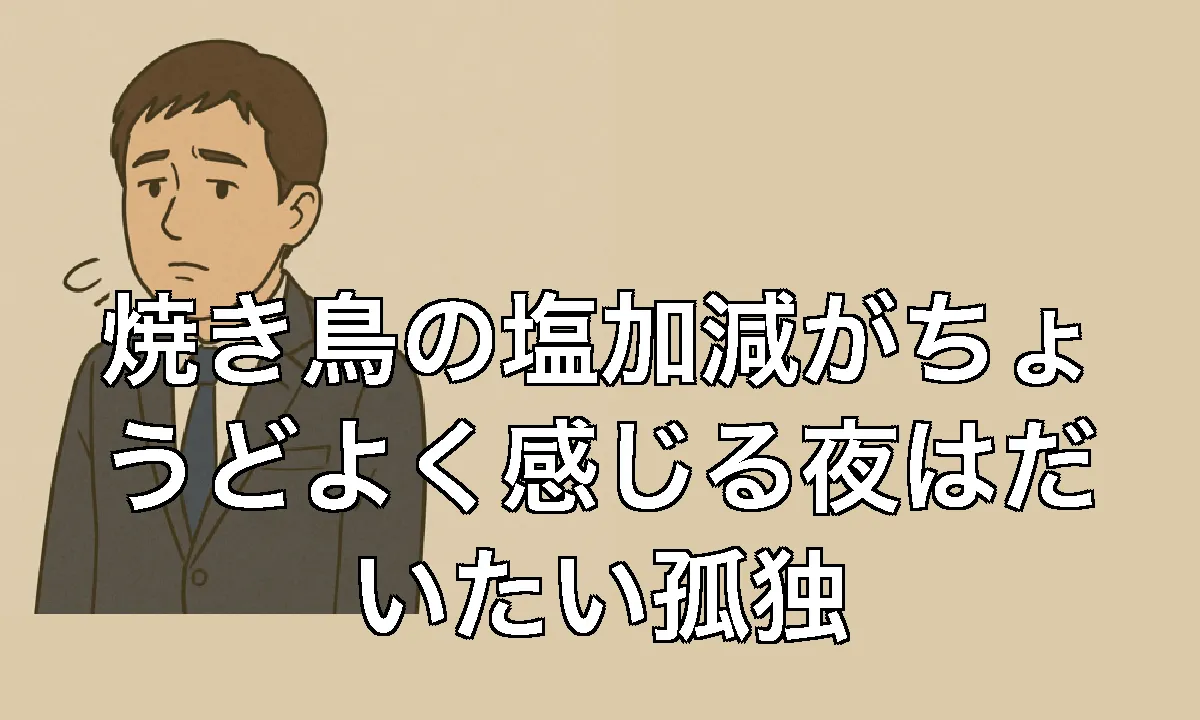一人焼き鳥の夜にふと思うこと
「焼き鳥でも食って帰るか」。そんな独り言を、帰りのコンビニの前で無意識につぶやいていた。今日は少し早く事務所を出られた。といっても20時前。誰も待っていない部屋に帰るより、焼き鳥の煙にまみれた方が、まだマシな気がしてくる。カウンター席の端っこに腰を下ろし、「塩で」と注文する。出てきた焼き鳥は、いつも通りの塩加減。でも今日はなんだか、それが妙にちょうどよく感じた。しみる。やけにしみる。
塩加減に心が左右される日もある
たかが塩、されど塩。その日の気分によって、塩の感じ方がこんなにも違うのかと驚く。濃いと怒られてる気がするし、薄いとやる気をなくした自分を映しているようだ。味覚って、心の鏡なのかもしれない。だからだろうか、今日の塩加減がちょうどよく感じるということは、少し疲れてはいるけど、まだ自分は折れていないという証拠かもしれない。誰かと笑い合って食べた焼き鳥じゃないけれど、このしょっぱさだけは確かに、今の自分を肯定してくれていた。
濃いとしょっぱくて泣きそうになる
以前、仕事で大きなミスをした日があった。登記の確認ミス。補正で済んだが、依頼者の表情は今でも脳裏に残っている。その夜、やけ酒まがいで入った焼き鳥屋で頼んだ塩は、妙に濃かった。涙腺が刺激されたのは塩のせいか、自分への怒りか。焼き鳥の塩味が、心の傷口に塗られた塩のように沁みて仕方なかった。「ちゃんとやれよ、自分」と、自分に対して箸を投げたくなったあの夜は、今も忘れられない。
薄いとなんだか物足りない人生みたいで
逆に、あまりに淡泊な塩加減だと、心まで味気なくなる。誰かと分かち合うことのない毎日は、うっすらとした味の焼き鳥と似ている。何かが足りない。けれど、それが何かははっきりしない。恋人がいないことなのか、家族との時間がないからなのか、それとも自分が望まなかった未来を生きているからなのか。焼き鳥の味が薄いだけで、そんなことまで考えてしまうのだから、やはり孤独というのは、味覚にまで忍び込んでくる厄介な存在だ。
元野球部のくせに弱音ばっかりだなと思う
高校の頃はキャプテンだった。誰より声を出し、誰より泥まみれで練習した。あの頃の仲間とはもう連絡もとっていない。あれほど一緒にいたのに、今では名前すら忘れかけているやつもいる。今の自分があの頃の自分を見たら、何て言うだろう。「お前、泣き言ばっかりじゃねぇか」って怒鳴られそうだ。でも、あの頃の俺は、司法書士の仕事の孤独さや、地方で一人で事務所を回す苦しさなんて、想像すらしてなかったんだ。
声を張っていたあの頃の自分とは真逆
法務局の帰り、電車の中で「今日は全然声を発していないな」と気づく日がある。電話もメールも少ない日は、誰とも喋らず一日が終わる。そんな日は帰り道の「いらっしゃいませ」がやけに沁みる。高校球児だった頃は、どこにいても自分の声が響いていたのに、今ではそれを求める相手もいない。年齢を重ねたら自然に家庭ができて、なんとなく人並みの人生になると思っていたが、どうやら現実は、塩よりもしょっぱい。
バットを置いてから随分経ったけど
司法書士という仕事は、バットを振る代わりに、判を押す日々だ。ひたすら地味で、誰かに見られることもない。汗はかかないが、心は時々ぐったりと疲れる。元野球部の筋肉はすっかり落ち、代わりに目の下のクマと、疲れた胃袋が残った。そんなとき、焼き鳥の塩加減が「ちょうどいい」と思えるだけで、少しだけ救われる気がする。スポットライトが当たらなくても、自分なりの生き方があると、思いたくなる夜だ。
事務所の灯りと焼き鳥の煙
事務所の蛍光灯は、蛍のように静かに灯っている。22時を過ぎた時間に残っているのは、たいてい自分一人だ。書類の山に囲まれた中で、「もうやってられん」と立ち上がる瞬間が、焼き鳥屋へのスイッチになる。暖簾をくぐると、煙とタレと塩の香りに包まれて、「やっぱりここだ」と思う。事務所には疲労しかないが、焼き鳥屋には、ささやかな癒しがある。孤独を感じながらも、なんとか生きている自分を認める場所だ。
遅くまで残業して帰っても誰もいない
「ただいま」と言っても返事はない。冷蔵庫に何かあるわけでもない。だから、寄り道したくなる。誰にも気づかれず、誰にも責められず、煙に紛れて時間を消せる場所。それが、近所の焼き鳥屋だ。特別美味しいわけじゃない。でも、ここの塩加減は、自分の疲れ具合をちゃんとわかってくれているような気がして、通ってしまう。店員に話しかけられることもほぼないけれど、それがちょうどいい距離感で、安心できる。
ひとりの机にコンビニの袋
誰もいない事務所の机に、コンビニで買ったおにぎりと缶コーヒーを置いたこともある。でも、それを見て「俺は何してるんだ」とむなしさに襲われる日もあった。コンビニの袋は、孤独の象徴だ。味気ない食事、誰にも語れない愚痴、静かすぎる室内。そんな日が続いたあとに、焼き鳥の煙の中でひと息つけたとき、「食べ物で人は救われるのかもしれない」と思った。コンビニじゃなく、誰かが焼いてくれた焼き鳥に、心が動いた。
電話も来ない夜は焼き鳥を炙る
忙しい日が続いたあと、急に電話が鳴らない夜がくると、少し怖くなる。「自分、忘れられたのかな」なんて思ってしまう。そんなときは、自分で焼き鳥を炙ってみる。コンロで串をくるくる回しながら、塩を振る。振りすぎてもしょっぱすぎるし、少なすぎても物足りない。その塩梅が、まるで人間関係みたいだなと笑ってしまう。焼き鳥の塩加減を探る夜は、自分の心の調整作業でもある。
事務員のありがたさをしみじみ思う
彼女がいてくれて、どれだけ助かっているか。毎日雑務をこなしてくれて、連絡もきちんとまとめてくれる。自分が外回りのときも、しっかり守ってくれる。その存在に甘えてしまうこともあるが、いない日があると、急に現実が牙をむいてくる。どんなに優秀な司法書士でも、一人でできることには限界がある。だからこそ、「塩加減」をわかってくれる相棒がいることの大切さを、つくづく思い知らされるのだ。
彼女が休んだ日の絶望感
「今日はお休みですか」と聞かれた瞬間、頭の中が真っ白になった。郵送の準備も、連絡の返事も、山ほどあるのに、すべて一人でこなさないといけない。誰に愚痴をこぼすわけでもなく、ただ黙って手を動かす。焼き鳥でいえば、串を打って、焼いて、提供するまで全部やるようなもの。そんな日は、どんなに塩加減を工夫しても、美味しく感じない。やっぱり誰かがいてくれるから、ちょうどいい味になるんだと思う。
孤軍奮闘が続くと塩加減も狂う
仕事が立て込みすぎると、頭の中も味覚も鈍ってくる。ミスが怖くて慎重になりすぎて、逆に効率が悪くなる。そんな時期に食べる焼き鳥は、いつもの味じゃない。塩を振っても味がしないのは、心が麻痺している証拠だろう。たまには少し休んで、塩梅を取り戻さないといけない。仕事も人生も焼き鳥も、ちょうどいい加減が一番難しくて、でも一番大事なんだと、こうして夜中に思う。