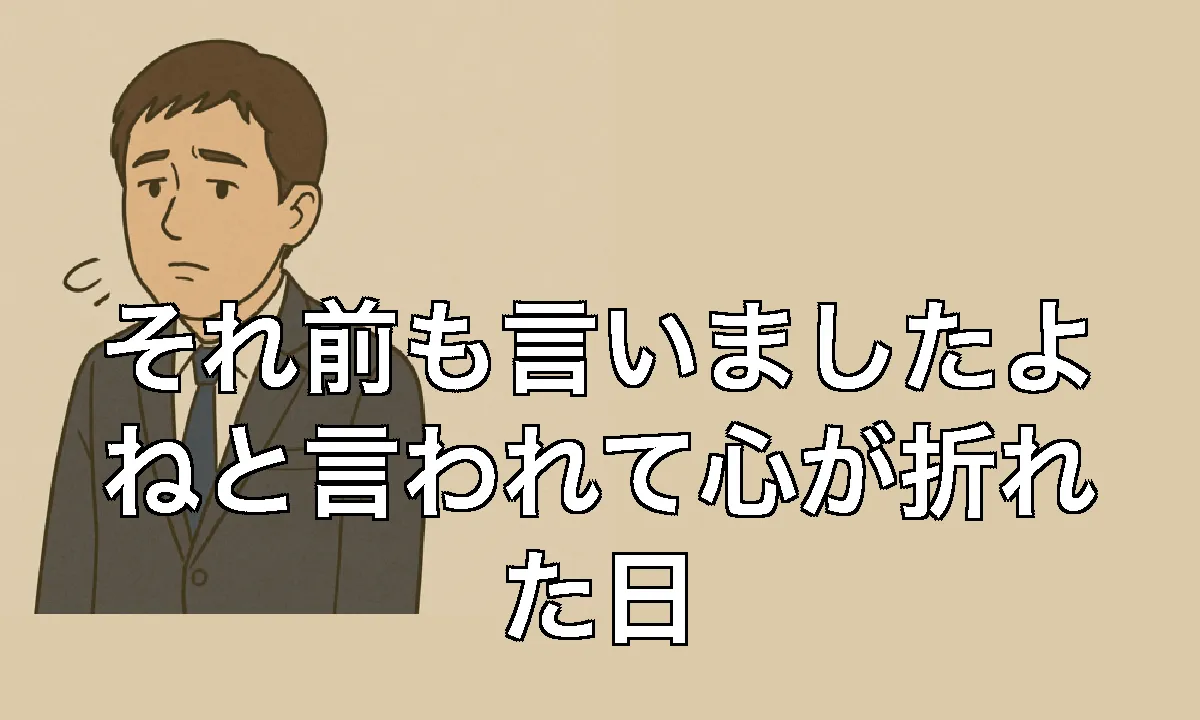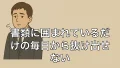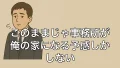その一言が胸に刺さる瞬間
日々の業務の中で一番きつかった言葉を挙げるとしたら、「それ前も言いましたよね」かもしれません。単なる確認の言葉なのに、なぜこんなにも心に刺さるのか。地方の小さな司法書士事務所で、僕は一人事務員さんとともに案件を回しています。限界ギリギリのスケジュールの中、クライアントからその一言をぶつけられた瞬間、心がスッと凍るような感覚がありました。野球部時代に監督から怒鳴られた時のような、あの感覚に近いです。
打ち合わせ中に飛んできた鋭い言葉
その日は、不動産の名義変更の件でクライアントとのZoom打ち合わせ中でした。僕の確認ミスがあったのは確かですが、慎重に進めようとして再確認したところ、「それ前も言いましたよね」と返されました。たしかに同じことを聞いたのかもしれない。でも、そう言われると、まるで無能の烙印を押されたような気がして、言葉が出ませんでした。ふと、昔バッターボックスで見逃し三振したとき、ベンチで無言だった監督の顔を思い出しました。
こちらの確認不足か相手の配慮不足か
自分が悪いのはわかっている。でも、相手の言い方にも少しだけ引っかかりを覚えたのです。クライアントだって忙しいし、繰り返し説明するのが面倒だという気持ちはよくわかります。ただ、その一言がこちらに与えるダメージは、想像以上に大きい。確認という行為自体が責任回避のように思われがちですが、こちらとしては必死の確認なんです。
言われた瞬間の沈黙がつらい
一番つらかったのは、その言葉の後に流れる沈黙です。相手も自分も、何かしら気まずくなる。頭の中では「なんでこんなことで動揺してるんだ」と思いながらも、心は立て直せないまま時間だけが過ぎていきました。昔、エラーした後の守備でボールが飛んでくるたびに緊張していた自分を思い出しました。歳を取っても、心の弱さはそう簡単に克服できないようです。
「あの時ちゃんと伝えたはず」では足りない世界
司法書士の仕事は「言ったかどうか」ではなく、「書面で残っているかどうか」がすべてです。それはわかっていても、つい口頭のやりとりで済ませてしまったり、相手に任せてしまったりすることもあります。「あの時伝えた」と自分では思っていても、証拠として残っていなければ無意味。まるで試合でいくら声を出してもスコアに反映されないのと同じです。
言った言わないが通じない業界のリアル
「言った」「聞いてない」のやりとりは、実はどの業界でもあると思いますが、司法書士業界では特にシビアです。記録に残っていないことは、まるで最初から存在しなかったかのように扱われる。それがどれだけ苦しいか。自分の記憶と相手の記憶が食い違ったとき、立場が弱いのは常にこちらです。だから、ミスを避けるにはメモや録音が必要になりますが、それがまた精神的に重荷になるのです。
記録を取ることに神経をすり減らす日々
確認のためのメール、通話の録音、議事録作成…。そうした記録作業に追われて、肝心の業務が後回しになることもしばしばあります。「本当に自分は司法書士をやってるのか?」と疑問に思うほど、机の上は付箋とメモだらけ。記録を残すための努力が、本業を圧迫している感覚すらあります。とはいえ、それを怠れば「前も言いましたよね」とまた言われるリスクがある。まるで、延々と続くバント練習のようです。
責任はすべてこちらにあるという前提
司法書士という職業は、常に「こちらが悪い」という前提の上で成り立っています。相手の書類に不備があっても、相手が間違っていても、説明不足と見なされるのは僕たち。たとえるなら、味方のエラーでもベンチにいる自分が怒鳴られるような理不尽さ。それでも、黙って笑って謝らないと仕事が回らない。そんな現実があります。
立会での緊張感と無力感
登記の立会では、時間も場所も限られた中で書類の不備がないかを確認しなければなりません。そこで何かひとつでも抜けがあると、まるでこちらのせいのように責められる。心の中では「そちらの書類ですけど…」と思っていても、口には出せません。僕が若かった頃、先輩が「立会で怒られない奴はプロじゃない」と言っていたのを思い出します。今なら、その言葉の裏にある苦笑いの意味がよくわかります。
完璧を求められるのに凡人な自分
求められるのは完璧。なのに僕は凡人。書類のミスは命取りなので、何度も何度も確認するのですが、それでも見落とすことがある。人間だから当然のことだと思いたいけれど、この世界ではその言い訳は通用しません。プロ意識という名のプレッシャーが常にのしかかってきて、知らず知らずのうちに自分を責めてしまう。気がつけば、休日でも「ハンコ忘れてないか」と不安になる日々です。
相手の機嫌ひとつで空気が変わる
特に士業の世界では、「あの人は信用できるかどうか」がすべてだったりします。こちらがどれだけ丁寧にやっても、相手の機嫌が悪ければ評価はマイナス。思えば、野球部の時もそうでした。どれだけ打っても、監督が不機嫌ならベンチ行き。努力ではどうにもならない場面があるという現実に、何度も心を折られてきました。それでも立ち上がってきたけれど、今も変わらないものがあります。
それでもやるしかないという現実
じゃあ辞めればいいじゃないか、と言われればそれまでです。でも、それができない理由がある。仕事に誇りがないわけじゃないし、何より依頼してくれる人がいる。たとえ報われない日があっても、感謝の言葉ひとつで救われることもある。だから、今日も僕はデスクに向かいます。
愚痴を吐く場もなくただ事務所に戻る
怒られても、凹んでも、終わったら無表情で事務所に戻ってくる。事務員さんが「お疲れさまでした」と言ってくれる、そのひと言に救われる。でも、彼女にも余計な気を遣わせたくないから、愚痴は吐かない。ひたすら無言でコーヒーを淹れて、ため息ひとつ。そんな日々が積み重なっていきます。
事務員さんの優しさに救われる瞬間
ある日、何も言っていないのにチョコレートを机に置いてくれた事務員さん。「甘いものでも食べてくださいね」と言われただけで、涙が出そうになった。孤独な戦いの中で、誰かが気づいてくれるだけで、心は救われるものです。モテない人生だけれど、人の優しさに触れることは、何よりも嬉しい瞬間です。
でもその人にも気を使いすぎて疲れる
優しさが嬉しい反面、「あ、この人にまで気を使わせてるんだな」と思うと自己嫌悪がやってくる。元々、他人に頼るのが苦手な性格なので、余計にその気持ちは強い。誰かの厚意をそのまま受け取るのが下手なんです。そういうところもまた、自分の仕事に向いてないんじゃないかと悩む一因になっていたりします。
一人の夜にふと思い出して凹む
夜、一人でカップ麺をすする。テレビからはお笑いの声。でも心はなぜか沈んでいる。「それ、前も言いましたよね」と言われた場面がふと頭をよぎる。言葉って不思議です。たった一言で一日が台無しになったり、何度も思い出して自己否定したりするんです。
「前も言いましたよね」と言われるたびに自信が削られる
たとえ事実でも、そう言われるたびに「やっぱり自分はダメなんだ」と思ってしまう。仕事の実力以前に、人として劣ってるんじゃないか、なんて考えてしまうこともあります。子どもの頃、間違えても許してもらえた時代が懐かしくなります。
それでも辞めない理由は何なのか
それでも辞めずに続けているのは、どこかで「それでも誰かの役に立ちたい」と思っているから。誰かの不安を取り除けたとき、「ありがとう」の言葉をもらったとき。その瞬間がある限り、この仕事は続けていける気がします。つらいけれど、僕にとっては、それが生きてる実感なのかもしれません。