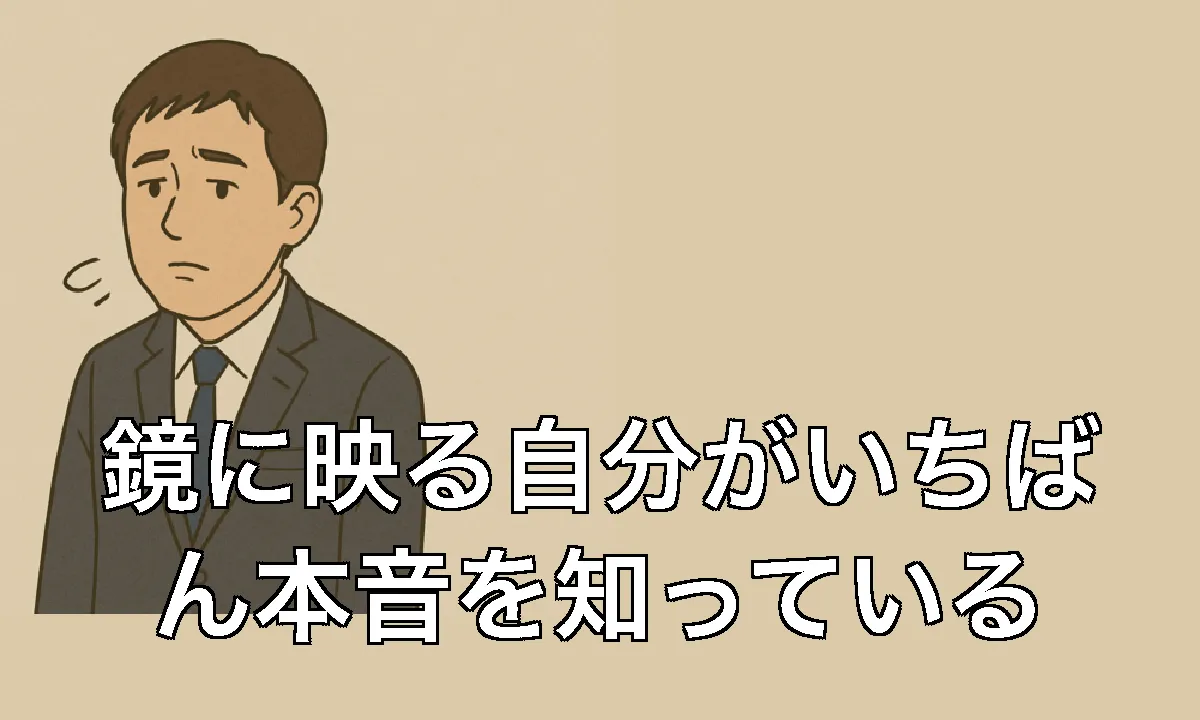朝の洗面所で立ち止まる理由
毎朝、顔を洗うために洗面所に立つ。それはただの日課のはずなのに、ある朝ふと鏡を見た瞬間、何とも言えない重たい気持ちが込み上げた。髪は乱れ、目の下にはクマ、頬は少しやつれて見えた。昔はこんな顔じゃなかったのに――そう思いながら、ため息混じりに顔を洗う。司法書士としての日々に追われる中で、自分の表情をまじまじと見ることなんてほとんどなかった。けれど、鏡はそんな自分の現実を黙って突きつけてくる。忙しい、余裕がない、誰にも頼れない。誰にも言えない愚痴が、鏡の中の自分にだけは伝わっている気がして、しばらくその場を動けずにいた。
ただ顔を洗いたかっただけなのに
最初はただ顔を洗おうとしただけだった。なのに、鏡に映る自分の表情が、あまりにも「疲れてます」と言っていて、思わず固まってしまった。昨日、深夜まで書類を確認していたツケか、右目だけ充血していた。肩こりもひどくて、首を回すたびにゴキゴキと音が鳴る。司法書士の仕事って、外から見れば「先生」かもしれないけれど、実態は地味で孤独だ。対人関係に気を使い、期限に追われ、責任に押し潰されそうになる。そんな中でふと鏡を見ると、自分の「限界値」が可視化されてしまう気がして怖いのだ。
疲れよりも驚きが先にくる日
疲れているのは自覚していたけど、こんなにも顔に出ていたのかと驚いた。自分の顔なのに、どこか他人のように感じる瞬間がある。特に朝、頭も心もまだ起きていない状態で見る鏡は容赦がない。昔は元野球部で体力には自信があったはずなのに、今じゃ階段を上るだけで膝が痛む。体力も気力も、少しずつ削られている実感がある。それなのに「まだ頑張らなきゃ」と気合だけで動いている。鏡の中の自分が「おい、そろそろ無理してるぞ」と警告してくるような気さえした。
顔色ではなく目の奥を見てしまう
一番気になるのは、目の奥の表情だ。目は口ほどにものを言うというけれど、まさにその通りで、自分の目がどこかうつろだったり、何かを諦めているように見えたりする。笑っているつもりでも、目が笑っていないことに気づくと、一気に現実に引き戻される。司法書士という職業は、人の人生に関わる仕事だからこそ、常に冷静でいる必要がある。でもその分、自分の感情には無頓着になってしまう。鏡はそのツケを、無言で映し出すのだ。
誰もいない職場の鏡が告げる現実
事務所に誰もいない時間帯、ふとトイレの鏡を見たとき、まるで別人がそこにいるような気がした。書類の山を片付けて、ようやく一息ついたタイミングで見る自分の顔は、いつもより何倍も老けて見える。お客さんと対面するときは笑顔を作るけれど、その仮面が外れたあとの顔は、仕事の疲弊と孤独が混ざり合ったものだ。鏡の中にいるのは、「司法書士の先生」ではなく、ただの45歳独身男性。そこには、誰にも見せない弱さが、ありありと映っていた。
笑っているつもりでも目が笑ってない
顧客対応の際は、なるべく穏やかに、優しく話すよう心がけている。でも、それが本当に伝わっているのかは分からない。なぜなら、自分自身が「ちゃんと笑えているかどうか」を不安に思っているからだ。鏡で自分の笑顔を確認すると、口元は笑っていても、目は無表情なことに気づく。これじゃあ、説得力なんてない。信頼感を与える前に、自分の中に信じる力が欠けていたら、相手には届かないのかもしれない。鏡の中の目は、そう問いかけてくる。
事務員さんの「大丈夫ですか」の重み
事務員の女性が、たまに「先生、大丈夫ですか」と声をかけてくる。その言葉が逆に堪える日がある。自分では「まだやれる」「全然平気」と思っていたつもりでも、外から見て「無理してる」と分かってしまうほど疲れが顔に出ていたということ。普段、感情をあまり表に出さない性格だけに、余計に鏡や他人の言葉が胸に刺さる。優しさが、痛い。気遣いが、申し訳ない。でも、その言葉があるだけで少し救われるのもまた事実だった。
何も言わない鏡がいちばん正直
人は優しさで見逃してくれることがある。でも、鏡はそうじゃない。ただ淡々と、今の自分をそのまま映す。化粧で隠すわけにもいかず、男の顔にはシワもクマもそのまま出る。そんな鏡の前で、たまに自問する。「自分はこのままでいいのか?」。答えなんて簡単には出ない。でも、鏡の前で立ち止まる時間は、少なくとも「自分と向き合っている時間」には違いない。誰もいないその空間だけが、自分を偽らずにいられる場所になっていた。
司法書士という肩書が語らないもの
「先生」と呼ばれることに、最初は誇らしさもあった。だけど今では、肩書が一人歩きしているように感じることもある。名刺にはしっかり印刷された資格名。でも、その裏で、自分自身のことはどれだけ理解できているだろうか。書類を通じて他人の人生を扱う日々。なのに、自分の人生は置き去りにされているような感覚がある。鏡を見るたびに、その「置き去り」が顔に浮かんでいる気がして、なんとも言えない虚無感に包まれる。
責任と信頼の裏で置き去りになるもの
司法書士は信用で成り立つ仕事だ。だからこそ、常に冷静でいなければならない。でも、それが続くと、いつしか自分の感情を「ノイズ」として切り捨ててしまうようになる。怒りや悲しみ、疲労や焦り。全部抑え込んで「仕事の顔」に切り替える。その繰り返しで、本当の自分がどこにいるのか分からなくなることがある。気づけば、自分を一番知っていたはずの自分自身が、最も遠い存在になっていた。
仕事で誤魔化せても鏡は誤魔化せない
仕事中は「忙しいから」「これが終われば」と思考停止して走れる。でも、家に帰って顔を洗うとき、その言い訳は通用しない。鏡の前では、今日の疲れも、心のザラつきも、全部そのまま現れる。どれだけ外で頑張っても、どれだけ周囲に「問題ありません」と装っても、鏡は誤魔化せない。だからこそ、自分を取り戻すために必要なのは、もしかしたら「仕事を頑張ること」ではなく、「自分の顔と向き合うこと」なのかもしれない。
肩書より疲れのほうが目立ってきた
昔は「司法書士です」と言えば、ちょっとはカッコつけられた。でも今は、肩書よりも顔のくたびれ具合の方が先に目に入る。名刺を出す前に、「この人、大丈夫かな」と思われていないか心配になる。もう若くないし、無理もきかない。それでも仕事は待ってくれない。結局、肩書なんて紙の上の話で、現実の自分は、毎日クタクタになって鏡と向き合っているおっさんだ。それを受け入れるところから、また立ち上がるしかないのだと思う。
それでも明日は鏡を見て出かける
正直、鏡を見るのが怖い日もある。でも、それでも毎朝、顔を洗い、鏡の前に立つ。そこには変わらない現実がある。でも、変えられる未来もあると信じていたい。司法書士の仕事は、地味だけど人の役に立つ仕事だ。今日も誰かの人生をちょっとだけ支えているかもしれない。だったら、疲れていても、しんどくても、まずは鏡の前で顔を整えて、今日を始める。それが、自分にできる最低限の誠実さだと思っている。
仕事があるだけで救われている現実
もし仕事がなかったら、きっともっと沈んでいたと思う。誰にも会わず、誰にも必要とされず、鏡の前で落ち込むだけの毎日。考えただけでもつらい。だから、どんなにしんどくても、仕事があるということは救いだ。誰かに求められていること、誰かに感謝されること。それが、しんどさの中でも前を向ける理由になっている。だから今日も、鏡に映る顔に「よし、行こう」と声をかけて、仕事へと向かう。
自分を映す鏡より他人の笑顔を見たい
最終的に、自分の顔をどうにかしたいわけじゃない。他人の笑顔を見たい。その笑顔を生むために、自分が少し頑張れるなら、それでいい。だからこそ、鏡はあくまで確認用。真の目的は、誰かの問題を一緒に解決したり、不安を少し軽くしたりすること。それができた日は、鏡の中の自分も、少しだけマシに見える。そんな日が続けばいいと、心から思う。