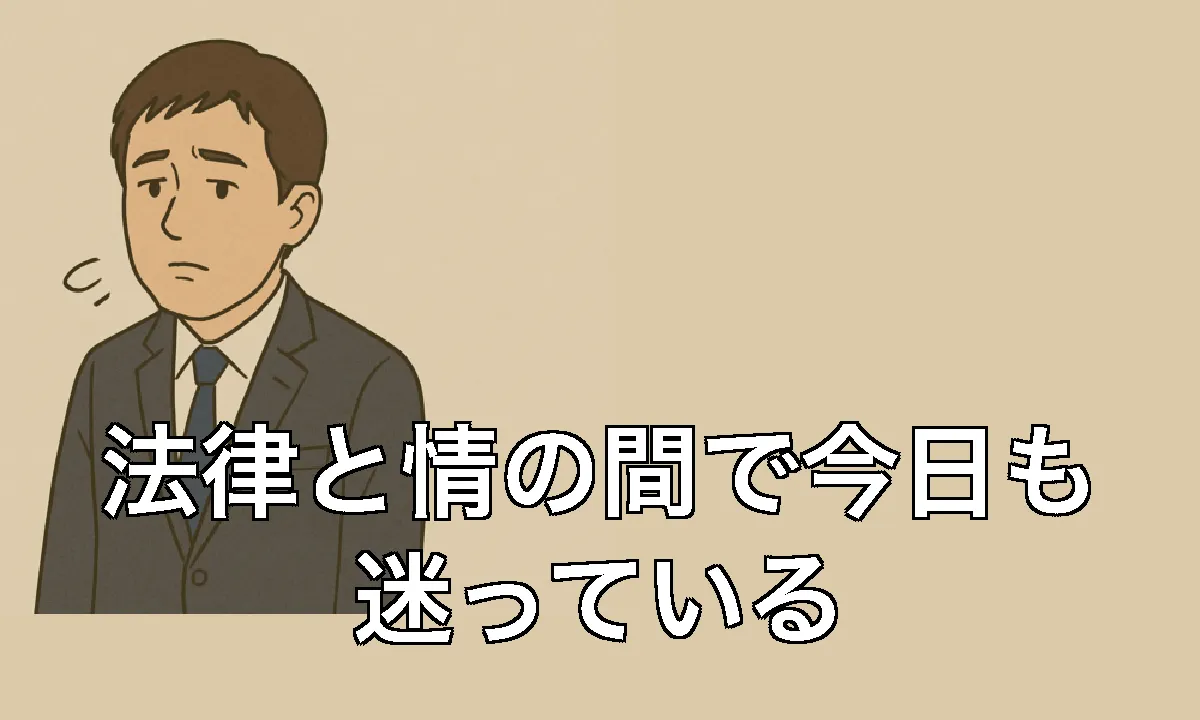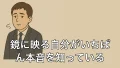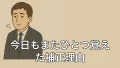法律と情の間で今日も迷っている
書類に書けない人の気持ち
司法書士という職業は、法律に基づいて粛々と業務をこなしていくものだと思われがちですが、現実はそう単純ではありません。毎日のように、法的な正しさと依頼人の感情の間で心を揺さぶられる場面があります。書類には決して現れない「その人の事情」や「背景」を前にして、私は時折、自分の役割に戸惑いを覚えるのです。これはきっと、誰かの正しさを証明する仕事の中にある、見えない感情との闘いなのでしょう。
法的に正しいことが正解なのか
「先生、法律的にはこれってOKなんですか?」そう尋ねられるたびに、私は言葉を選びます。法律的には正しい。でも、それがその人の人生にとって本当に良い選択かは、また別の話です。以前、相続放棄の件で相談に来た女性がいました。兄にすべての財産を渡したいと言っていましたが、形式的には自分にも分け前がある状況。けれど、その方は「私は母と仲が悪かったから…」と口ごもっていました。法的な説明はしましたが、心の整理が追いついていないのが伝わってきて、なんとも苦しい気持ちになりました。
依頼人の涙に何も言えなくなる瞬間
とある朝、離婚に伴う財産分与の件で女性が相談に来られました。調停がこじれにこじれ、最終的には彼女のほうが不利な条件で合意することになったのですが、「もうこれ以上争いたくないんです」とぽろっと泣かれた瞬間、私は何も言えませんでした。こちらとしては、まだ戦える要素があると感じていた。でも、もうその人の心が限界だったんですね。依頼人の涙は、法の正義よりもずっと重く響くことがあります。
正しさの前に立ち止まる自分がいる
書類に「正」と書けば済むものではないと、日々実感しています。たとえば成年後見の申立で、親族間の思惑が交錯する中、誰が後見人にふさわしいのか判断を求められたとき、私は明らかに悩みました。単に法律の知識をふるえば済む話ではなく、人間関係や家族の歴史が絡んでくる。私はあくまで第三者で、冷静であるべきだと自分に言い聞かせても、やはり迷いは生まれます。正しさを貫くには、自分の感情を脇に置く覚悟も必要なのかもしれません。
人情を汲んだつもりが裏目に出ることもある
いい人になろうとすることが、時に事態を悪化させることがあります。私はその「優しさ」が裏目に出て、後悔したことが何度もあります。「情けは人のためならず」と言いますが、現場ではその情けが誤解やトラブルの種になることもあるのです。
先生ならわかってくれると思ってからの地雷
以前、ある高齢の依頼人が私に対して「先生なら察してくれると思ってね」と前置きして、口頭で伝えただけの内容を反映させた遺言書の下書きを希望してきたことがありました。私は「一度は確認しましょう」とやんわり伝えたのですが、「じゃあ、他の先生に頼みます」と突っぱねられてしまいました。結果、その方とは疎遠に。後日、その遺言をめぐって親族間で大揉めしたと風の噂で聞き、胃がキリキリしました。わかってあげたい気持ちと、リスク回避とのバランスはいつも難しい。
一度の情けがトラブルの元になる現実
登記費用の分割払いを許可した依頼人が、結局3年経っても完済できず、その間に「まだ完了してないのか」と不満をぶつけてきたことがありました。こちらとしては、事情があると聞いたからこその対応だったのに、「分割を認める=なあなあで済む」と誤解されたようです。優しさのつもりが信用を失う結果になると、本当にがっくりきます。私は商売人ではないですが、甘さは時に自分を傷つける刃になると痛感しました。
机上の理想と現実の狭間で
資格取得の勉強中、六法を片手に「すべては理詰めで解決できる」と思っていた自分が、今となっては少し恥ずかしいです。現場に出てみると、どんなに条文を覚えていても、それだけでは通用しない場面の連続。理想と現実は、常に食い違っています。
教科書に載っていない感情処理
試験勉強の中では、心の揺れ動きなんて一切扱われませんでした。けれど、いざ仕事となると感情の処理こそが一番厄介です。法律は冷たいけれど、人は温かい。依頼人が話しているとき、私はしばしば「この人の気持ちをどこまで汲んでいいのだろう」と悩みます。ときには雑談の中にこそ本音があり、書面には決して現れない情報が山ほどあるのです。言葉をどう受け止め、どこまで対応すべきか。経験だけが頼りの、模範解答のない仕事です。
マニュアル通りじゃない現場の声
「家を売るってどういう気持ちですか?」と聞いたら、ぽつんと「ごめんね」と言われたことがあります。マニュアルでは決済の段取りだけを覚えれば済むかもしれませんが、実際には人生の節目に関わる重みがあります。「家族に言えないけど、先生には言っておきたい」とポツリと漏らされるようなとき、私はプロとして振る舞う一方で、ただの聞き役でいたくなることもあります。
そんなこと法律じゃないからでは済まされない
「それ、法律じゃ扱えませんよ」と言ってしまえば楽なんですが、そういう返答を期待していない人も多いんです。「どうしたらいいか分からない」という状態の人に対して、あまりにも事務的な言葉を返すと、こちらへの信頼は簡単に崩れます。法律は万能じゃない。けれど、その隙間を埋めるのが、たぶん私たちの仕事なんでしょう。
日々の業務に潜む小さな葛藤
朝から晩まで、細かな書類と格闘していると、ふとした瞬間に虚しさが襲ってきます。「これは本当に意味のあることか?」「誰かを救えているのか?」そんな自問自答は、もう癖のようになってしまいました。けれど、やっぱり続けているのは、心のどこかに「誰かのためになりたい」という気持ちがあるからだと思います。
自分の気持ちを封じ込める癖
感情を出すと舐められる、弱みを見せると信頼されない、そんな思いから私はどんどん無表情になっていきました。でも、家に帰って1人でご飯を食べていると、ふとした瞬間に涙が出ることもあります。結局、自分の感情を押し殺してばかりだと、どこかで爆発してしまうんですよね。人の感情には寄り添っても、自分の感情には鈍感でいるのが、司法書士の性なのかもしれません。
それでも誰かの役に立ちたくて
「先生のおかげで助かりました」その一言があるだけで、一週間分の疲れが吹き飛ぶことがあります。ごくたまに、そういうことがあるんです。その瞬間のために、また机に向かってしまう。たぶん私は、人に感謝されることでしか、自分の存在価値を見出せないのかもしれません。
仕事の中にある孤独との付き合い方
この仕事をしていると、誰にも弱音を吐けない時間が続きます。どんなに困っていても、最終判断はすべて自分。責任もすべて自分。誰かに相談したくても、簡単にできる話でもない。それが、地方の小さな司法書士事務所の現実です。
決めるのはいつも自分だけ
「これで良いのだろうか?」と迷っても、結局は自分が決断しなければならない。たとえば、登記のタイミング、文言の選定、報酬の請求ひとつとっても、誰も最終的な指示はくれません。自営業の自由の裏には、すべての責任を背負う孤独があります。
誰にも相談できない判断の重み
たまに「その判断、誰かに相談した?」と聞かれると、ギクリとします。相談できるならしてますよ、と言いたくなる。でも、実際は一人で考えて決めて、そして何かあれば一人で謝る。それが仕事なのです。そんな重みが、時に肩にのしかかりすぎて、立ち上がれなくなる日もあります。
間違っていませんよと言われたい
一番欲しいのは、正解じゃなくて「大丈夫ですよ」という誰かの言葉なのかもしれません。私も人間ですから、自信をなくすこともあります。事務員さんがたまに「先生、ちゃんとやってると思いますよ」と言ってくれるだけで救われます。そんな些細な言葉に、人はどれほど支えられているか、最近になってようやく気づきました。
支えてくれるのは結局ルールよりも人
どんなに正確なマニュアルや判例を持っていても、支えてくれるのはやっぱり「人」です。人の言葉、気持ち、行動。法律の中にいるけれど、それを支えるのは人情なのかもしれません。
事務員さんの一言に救われる日
「今日は帰っていいですよ」「私やっときますから」たったそれだけで、どれほど助けられてきたことか。事務員さんには、もう頭が上がりません。私の愚痴も笑って聞いてくれるし、ミスを責めずに受け止めてくれる。こんな人がいるから、私は今日も司法書士を続けられているのかもしれません。
野球部時代の声かけを思い出す
元野球部だったころ、「声を出せ」「仲間を信じろ」と言われ続けていました。今思えば、それが一番の原点だった気がします。声を出すことで自分を奮い立たせ、仲間の声で勇気をもらっていた。法律の世界でも、あの時の声かけがどれだけ必要かを痛感しています。