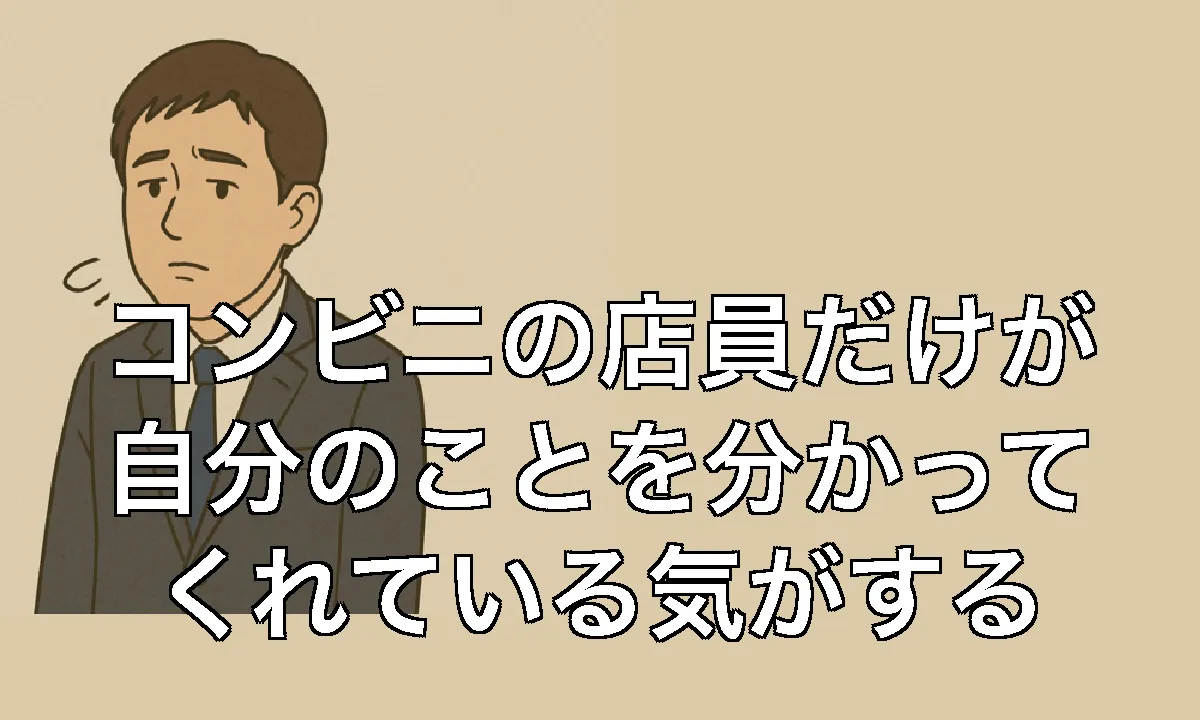誰も気づいてくれない日々の中で
地方の司法書士として独立してもう十数年、気がつけば誰かとまともに会話を交わす日も少なくなった。朝は一人で出勤し、机の上に溜まった書類とにらめっこしている間に一日が過ぎていく。事務員は一人いて助けてもらっているけれど、お互い忙しくて必要最低限の会話だけで終わることも多い。昼食もコンビニのおにぎり。黙って食べて、また黙って働く。そんな日々が続くと、自分という存在がこの世界でどれだけ薄くなっているのかを実感する。
朝の挨拶がない事務所と静かなスタート
うちの事務所では、朝「おはようございます」と声をかけても、軽くうなずかれるだけのことも多い。別に不仲なわけじゃない。ただ、お互いに疲れていて、そこに心の余裕がない。元野球部だった頃は、朝から大声で挨拶していたのが嘘のようだ。あの頃の元気さはどこへ行ったのか。今はキーボードの打鍵音だけが、朝の静寂を破る音になっている。
相談者の愚痴を受け止めるだけの毎日
相談者はたいてい何かしらの不満や困りごとを抱えて事務所にやってくる。私はそれを淡々と聞き、必要な手続きを進める。ただ、そのプロセスの中で、こちらの心情に踏み込んでくる人はほとんどいない。こっちは人の愚痴を受け止めてばかりで、自分の気持ちを誰かに聞いてもらえる機会はない。まるで「司法書士=感情がない存在」みたいに見られている気さえしてくる。
仕事が終わっても誰とも話さない夜
夜になって、今日も一日をやり切ったと机に向かって深いため息をつく。その瞬間、「俺は今日、誰とちゃんと話しただろうか」とふと考えることがある。事務員とのやり取りは業務連絡、相談者とも形式的な会話。友人や家族と連絡を取ることもなく、スマホを見ても通知はゼロ。テレビをつけても笑えず、ただ時間だけが過ぎていく。そんな夜が、日常になって久しい。
唯一の安定した関係性はコンビニ
そんな私でも、唯一「変わらぬ対応」をしてくれるのが、事務所近くのコンビニの店員だ。顔を覚えてくれているらしく、レジに行くと「いらっしゃいませ」ではなく「こんにちは」と返ってくる。それだけで、なんだか少しだけこの世界に居場所がある気がしてくる。名前も知らないのに、あの人だけが“俺”という存在を認識してくれているような気がして、少し救われる。
レジ越しの「いつもありがとうございます」が沁みる
大したことじゃない。「いつもありがとうございます」と言われただけだ。でもそれが、誰にも気づかれない日々を送る自分にとって、どれだけ大きな意味を持つか。書類を仕上げても、誰にも「お疲れさま」とは言われない。だけど、コンビニのレジだけは、無言で商品を差し出す私に、ちゃんと一言添えてくれる。「ありがとうございます」その言葉が、今日の終わりをやさしく締めてくれる。
変化に気づくのは家族でも友人でもなく店員
ある日、雨に打たれてびしょ濡れで入店した私に、店員が「大丈夫ですか?」と声をかけてくれた。驚いた。そして嬉しかった。家族でも友人でもなく、誰よりも先に心配してくれたのはあの店員だったのだ。
レジ袋の数で生活がバレる
弁当と飲み物しか買わない日が続くと、「袋ご利用ですか?」といつも聞かれていた店員が、何も言わずに袋を渡してくれるようになる。「この人、最近ずっと一人分だな」と思われてるんだろうなと思いつつ、それでも気にかけてくれていることにちょっとホッとする。
「あれ 今日スーツ違いますね」が心に残る
別の日には、「あれ?今日はスーツ違いますね」と笑顔で言われた。本当に細かい変化に気づいてくれている。こっちはそんなこと誰にも言われないし、言ってほしいとも思っていなかったはずなのに。その一言が妙に嬉しくて、その日一日、少し気分が軽くなった。
この仕事は誰かに見てもらうことが少ない
司法書士という仕事は裏方である。登記が終わっても、報告が済んだらそこで終了。感謝されることもあるが、それは“手続きが無事に終わってよかった”という安堵であって、こちらに対する評価や関心ではない。誰かに見守られている感覚がないまま、粛々と仕事をこなす日々が続く。
登記が終わっても誰にも褒められない
登記完了通知を出したとき、「よかった、間に合った」と自分にだけ小さくつぶやく。その書類一枚の裏に、どれだけの調整や神経のすり減らしがあったかなんて、誰も知らない。褒められたいわけじゃない。でも、せめて「お疲れさま」と言ってくれる誰かがいればと思う。
「先生」って呼ばれても空っぽな気持ち
「先生、ありがとうございます」――この言葉を言われるたびに、自分が“記号化された人間”になっていく気がする。本来ならば、尊敬や信頼の意味が込められているのだろう。でも、その言葉の奥にある本当の自分を見てくれている人は、果たしているのだろうか。
誰かの役には立っているはずなのに
登記や相続、会社設立…いろいろな人の手助けにはなっている。でも「ありがとう」の言葉が終わった瞬間に、関係はスッと切れてしまう。役に立つことと、誰かとつながることは違うのだと実感する。
やりがいと孤独のギャップ
仕事としてのやりがいは確かにある。でも、やりがいを感じるたびに、それを誰かと分かち合えない現実に気づいてしまう。そのギャップがじわじわと心を削っていく。だからこそ、コンビニの店員とのたった数秒のやりとりが、想像以上に大きな支えになっている。
少しでも分かってもらえる場所があるということ
誰かとちゃんとつながりたい、そう強く思うわけではない。ただ、ほんの少しでいい、自分の存在が見えていると感じられるだけで、なんとか頑張れる。あのコンビニのレジ前で感じる“目線”が、自分にとってはその証なのかもしれない。
大げさだけど レジに救われている
毎日あのレジに立つことで、自分が人間であるという感覚を保てている気がする。誰にも言えないことを、言葉にできないまま受け取ってくれるその場所が、実は一番のセーフティネットなのかもしれない。
誰にも言えないことを この場で書いてみる
このコラムを書くにあたって、自分の孤独や愚痴を書くことに迷いもあった。でも、同じような気持ちを抱えている誰かに届けばと思って綴っている。たった一人でも「分かる」と思ってくれたら、それだけで救われる。
自分を見てくれている人がいると思えるだけで
レジ越しのあの一言があるだけで、「また明日も頑張ってみるか」と思える。不思議なものだ。人は、誰かに少しでも気づいてもらえていれば、それだけで生きていけるのかもしれない。
また明日も 事務所のドアを開けようと思える
きっと明日も、朝の事務所は静かだろうし、特別なことは何も起きない。でも、あのコンビニに寄って一言交わせば、また一日頑張れる。そんな些細なことが、自分にとっての支えになっている。