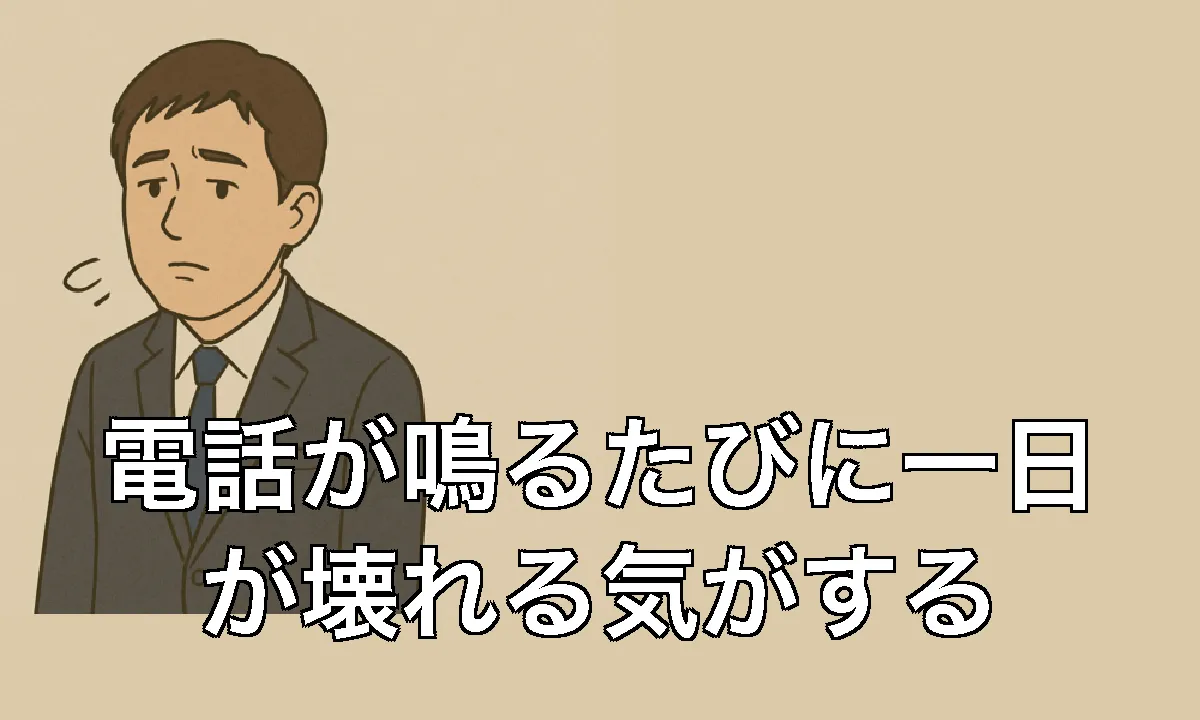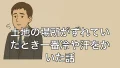朝の静けさを破る一本の着信
朝の書類整理がようやく一区切りついて、コーヒーを一口すすろうとしたその瞬間。事務所の電話が鳴った。着信音が妙に鋭く響いて、心臓が一瞬ドクンと跳ねる。たった一本の電話なのに、これからの一日が崩れていくような気がしてならない。電話というのは、こちらの都合を一切無視して割り込んでくる存在だ。せっかくの集中時間も、リズムも、あっという間に壊されてしまう。特に予定が詰まっている日は、一本の電話が“地雷”にしか感じられない。
それは依頼かクレームか不安しかない
着信表示を見ると、知らない番号。心のどこかで「新しい依頼かもしれない」と期待しつつも、同時に「またクレームか、トラブルか」と胸がざわつく。過去に、午前中の一発目の電話がとんでもないクレームだったことがあった。地元の相続案件で、書類の確認ミスを突かれて、土下座まではいかないが、相手の怒声に一時間耐えたことがある。それ以来、“朝イチ電話恐怖症”がしっかりと身体に染みついてしまった。
番号が非通知だと体がこわばる
非通知でかかってくる電話には、特別な種類の恐怖がある。名乗る気がない相手というだけで、こちらは構えるしかない。行政機関か、怒っている依頼人か、あるいは営業電話か。いずれにせよ、心を削られる準備を強いられる。昔、夜中に非通知でかかってきた電話が、泣きながら「父の遺言が見つかった」と話す遺族からだった。切実な話だったけど、その一件以降、非通知はどこか“事件の予兆”のように思えてしまう。
出なきゃいけない でも出たくない
鳴っている電話に出るべきか、無視すべきか。ほんの数秒の間に、頭の中で天使と悪魔がケンカを始める。結果として、だいたい出る。だけど、そのたびに思う。「また、自分の時間が奪われる」。これが毎日だ。積み上げるはずだった仕事が崩れて、終業時間も見えなくなっていく。電話対応が減るだけで、人生の幸福度はきっと上がる。そう思いながら、また今日も、鳴る電話に手を伸ばす。
司法書士という仕事に付きまとう“即応”のプレッシャー
この業界にいると、「すぐ返事をくれる人が信頼される」という風潮がある。だから電話が鳴ったら、出るべき。出たらすぐ答えるべき。できないなら折り返すべき。…そんな“べき”が、ずっと首に巻かれている。何をするにも、電話に怯え、即答を求められ、ミスは許されず、言葉を慎重に選ばなければならない。これが積み重なると、「電話が怖い」というよりも、「人と関わることそのもの」が重たくなる。
電話が鳴るだけでスケジュールが狂う
例えば、10時から14時まで登記の書類を集中して仕上げる予定だったとしても、10時05分に一本電話が入るだけで、14時には終わらなくなる。ペースが崩れるし、内容によっては急ぎの書類作成を差し込まなければならない。地方の事務所は、都心ほど分業化されていないから、一人があらゆる業務を抱えることになる。だからこそ、「電話1本」の重みが違うのだ。
予定の組み立てなど意味をなさない日もある
タスク管理アプリで予定を組んでも、手帳にびっしり書き込んでも、意味がないときがある。電話が次々にかかってきて、飛び込み相談や緊急書類の対応に追われる。予定の意味なんて、夕方にはどこかへ消えてしまう。計画通りに終わる日は奇跡で、ほとんどが「今日も無理だった」の繰り返しだ。それでも「忙しいから仕方ない」と自分に言い聞かせてる。でも、ほんとは嫌なんだ。
それでも断れない 地方の現実
断ったら、次はもう来ない。地方では評判がすべてだ。親族同士がつながっていて、ひとつの失敗が何十人に伝わることもある。だから、無理してでも対応する。できる限り丁寧に、できる限り早く。それが信用に繋がると信じてやってきたけれど、最近ふと思う。「本当に自分がやりたい仕事って、こんなだったっけ」と。
事務員一人では受けきれない負担
うちの事務所は、自分と事務員さんの二人だけ。人を増やせればいいのだろうが、地方で司法書士事務所の求人に応募してくれる人なんてほとんどいない。そもそも利益構造的に雇用の余裕もない。だから、電話も、書類も、登記申請も、全てを自分で抱え込むことになる。負担が積もっていく感覚に、最近は身体も正直になってきた。
一人でこなすしかない庶務の山
司法書士というと、カッコいい仕事と思われることもあるけれど、実際は“庶務の塊”だ。押印の確認、郵送、ファイリング、領収証の整理、電話対応……どれも一つひとつは大したことがないようで、積もるとどっしり重い。事務員に頼むにも、結局指示が必要で、それがまた手間になる。結果、「もう自分でやったほうが早い」となり、何でも一人で抱えることになる。
共有できない孤独な判断の連続
「どう対応するか」は毎回自分で決める。たとえば依頼人からのクレームに対して、「謝るべきか、押し切るべきか」「文書で残すべきか、電話で済ますか」――誰かに相談したくても、すぐそばに“同業者の壁打ち相手”がいない。孤独に判断し、孤独に責任を負う。それが司法書士の日常だ。
ミスが許されないことへの無言の圧
司法書士のミスは、依頼人の損失に直結する。特に登記関係は、ほんの一文字の誤記が命取りになる。だから常に緊張感の中で仕事をする。でも、それが電話対応中にも求められるのが辛い。即応と正確性。その両立は、正直なところ無理がある。だけど、誰もそれを口に出してはくれない。