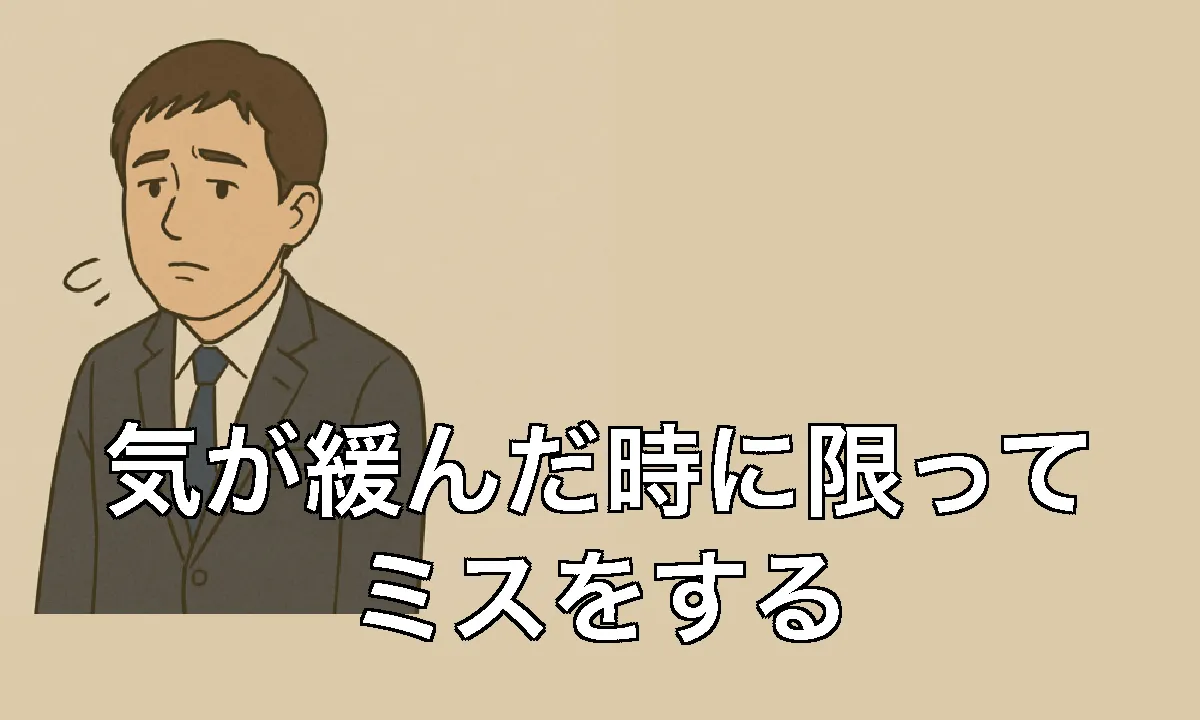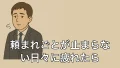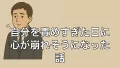気が緩んだ時に限ってミスをする
長く司法書士をやっていると、ふと気が緩む瞬間というものがある。毎日のように書類を作り、登記を申請し、依頼人とやりとりする。いつものルーティンに慣れてくると、「これは大丈夫だろう」と確認の手を抜いてしまうことがある。ところがそういう時に限って、信じられないようなミスが発生するのだから、皮肉なものだ。忙しさの中でも、油断が一番の敵だと改めて思い知らされる。今回は、そんな「慣れ」が引き起こすミスについて、自身の体験を交えて書いてみたい。
一息ついた頃にやってくる落とし穴
忙しい時期をなんとか乗り越えて、事務所の空気も少し落ち着いてきた。そういうとき、人は自然と肩の力を抜く。僕も例外ではなかった。久々に早く帰れそうだと時計を見た瞬間、「もう今日は大丈夫だろう」と心が緩んでいた。その帰り際、ふと「あの書類、送ったかな?」と頭をよぎる。でもそのときにはもう机の上にカバンが置かれていて、確認するのが面倒になってしまうのだ。結果、送付し忘れたまま週末を迎え、月曜に依頼人からの電話で青ざめる羽目になる。小さな油断が信頼を損なう。そういう瞬間が、落とし穴の正体だ。
安心感が呼ぶ見落とし
ある程度慣れてくると、書類のチェックも「大丈夫だろう」と流してしまいがちになる。以前、抵当権抹消の登記で、必要書類の一部を確認しないまま申請してしまったことがある。依頼人から「銀行に言われたまま全部渡してあるはずです」と言われていたため、つい信じてしまった。しかしよく確認すれば、その中の書類が実は旧住所のままになっていた。法務局から補正の連絡が来て、事務員と二人で顔を見合わせた。書類は揃っていても、内容までは確認しなければならないという基本中の基本を、安心感が邪魔してしまうことがある。
「もう大丈夫」という油断
登記申請後に「完了通知を待つだけ」となると、つい気が抜ける。あるとき、共有物件の所有権移転で、持分割合を一部誤って記載していたことがあった。申請前のチェックでは事務員に任せていたのだが、「もう大丈夫だよね」と僕も軽く見てしまっていた。その結果、登記完了後に相手方から「これ、違いますよね」と指摘され、結局更正登記をやり直すことに。登記完了が「終わり」ではなく、「確認の始まり」であることを痛感した。プロとして恥ずかしい話だが、だからこそ伝えておきたい。
慣れと経験がミスを呼び寄せる瞬間
経験を積んだ者ほど、自分の感覚を信じがちだ。僕も20年以上この仕事をやってきて、ある程度のパターンが頭に入っているつもりだった。でも、それが逆に「これはこうだろう」という決めつけにつながり、ミスの温床になる。たとえば、住所変更登記に必要な書類を「これで十分」と判断して省いてしまったことがあった。そのときも「いつものケースと同じだ」と思い込んでいた。しかし、ちょっとした特殊事情があり、書類の一枚が足りなかった。ルールは同じでも、事案は毎回違う。そう思い直さなければならない。
自信がついた頃のトラップ
司法書士になりたての頃は、何度もマニュアルを見返していた。それが今では、頭の中に全部入っているつもりになっている。でも、記憶は完璧ではない。ある日、不動産登記の際に記載する「原因日付」を間違えたことがある。理由は単純、「確か〇日だったな」という記憶に頼ったからだ。実際には、その日ではなかった。経験に頼りすぎると、逆にマニュアルを開かなくなる。初心者の頃よりも、今の方がミスに対して無防備なのかもしれない。怖いのは「自信」と「省略」が同居するこの罠だ。
「これはいつものやつ」で済ませた代償
法人の役員変更登記。これは比較的ルーティン化していて、件数も多い。だからこそ、油断が入り込む。ある時、前回と同じ会社の変更登記を請け負った際に、「また同じ内容だろう」と思い込んで、前回のファイルをコピペして使った。ところが、今回は取締役の辞任ではなく解任だった。その違いに気づかず、そのまま申請してしまった。結局法務局から指摘され、再度作り直し。依頼人にも頭を下げるはめに。似ている案件ほど要注意。似ていても、全く同じではない。そこに落とし穴がある。
過信がもたらす判断ミスの連鎖
一つのミスが次のミスを呼ぶ。それはまるでドミノのようだ。ある日のこと、朝から気持ちに余裕がありすぎたせいか、事務員とのやりとりで小さな言い違いをした。その後、書類の確認を任せたはずが、彼女は違う案件と勘違いして別のファイルをチェックしていた。普段なら気づいたはずのその誤解を、僕も受け流してしまった。そのまま提出した書類には当然のように誤りがあり、補正がかかった。チームの中で起こる小さな油断が、連鎖的にミスを生む。それを防ぐのは、緊張感の共有しかない。
手を抜いたわけではないけれど
「手を抜いた」とまでは言えない。でも、「気が抜けていた」ことは否定できない。仕事に慣れてくると、どうしても効率重視になり、気持ちに張りがなくなる。登記の電子申請で必要なファイルを添付し忘れたとき、まさにそんな感じだった。普段なら二重チェックしているはずの操作も、その日はなぜか「まあ大丈夫だろう」と通過してしまった。その結果、法務局から「添付ファイルがありません」との連絡。深夜、再送信しながら、PC画面の前で一人落ち込んだ。やはり、確認は気持ちの問題でもある。
ルーティンに潜む盲点
仕事が「作業」になってしまうことがある。それは慣れの副作用だ。毎日同じような書類を作っていると、ある種の思考停止状態に陥る。以前、相続登記の申請で、住所の番地の数字を一桁間違えたことがある。入力中にふと電話が鳴り、話しながら手を動かしてしまったのが原因だ。「あとで確認しよう」と思って忘れてしまい、誤ったまま提出。結局、補正を出し直す羽目に。手慣れた仕事こそ、一つひとつに意識を向けなければならない。ルーティンの中にこそ、盲点は潜んでいる。
後悔先に立たずの体験談
後悔というのは、何かが起こったあとにしかやってこない。ミスをした時、あの瞬間に戻れたらと思う。でも時間は戻らない。司法書士という仕事は、信用が命だ。だからこそ、ミスは心に重くのしかかる。僕自身、何度も「こんなはずじゃなかった」と思った。今回は、特に印象に残っている失敗を2つ紹介しよう。
ある登記申請でやらかした話
不動産の贈与登記を請け負ったときのこと。必要書類はすべて預かっていたと思っていた。しかし、登記原因証明情報が古い書式のままで、贈与契約書に署名日と印鑑の不一致があった。それに気づかず申請してしまい、補正指示。しかも依頼人が旅行中で、連絡も取れず数日放置されてしまった。焦る中で何度も書類を見返したが、すべては「気が緩んで確認を怠った」ことに起因していた。あのとき、「あと1回チェックしていれば」と思ったのは今でも忘れられない。
事務員の「いつも通りです」への過信
ある会社の役員変更登記で、事務員が「前回と同じなので、形式もそのままでいいですよね」と確認してきた。僕も「そうだね、同じはず」と答えてしまった。しかし、実際には取締役の任期満了日が変更されていて、議事録の日付がズレていた。事務員の言葉に頼ってしまった自分の責任を痛感した。いくら信頼しているとはいえ、最終確認は自分でやらなければならない。油断はチームワークの中にも忍び込んでくる。それに気づいたのは、痛い思いをした後だった。
ミスを乗り越えるための自戒と工夫
ミスは避けられない。でも、ミスを減らす工夫はできる。僕自身、幾度も失敗を繰り返した末に、自戒としてのルールを作るようにした。それは「確認作業の形式化」と「自分を疑う習慣」だ。気を引き締めるという抽象的な言葉ではなく、具体的に何をどうやるかを決めておくことが大事だと痛感している。
確認リストの見直しとチェック体制
事務所では、現在すべての業務に対してチェックリストを導入している。どんな小さな案件でも「口頭で確認したからOK」ではなく、リストに記入して「確認済み」とするルールを徹底。手間は増えたが、ミスは確実に減った。また、事務員ともダブルチェックの体制を作るようにした。お互いに確認しあうことで、緊張感も保てるようになった。慣れた仕事ほど形式化して意識化することで、安心感を排除している。
気持ちを引き締めるルーティンの再構築
朝一番のメールチェック後、必ず書類確認の時間を設けるようにした。コーヒーを一杯飲んでから、机に向かって無音で書類を見る。そう決めてから、集中力が上がったように思う。小さな習慣でも、それが「気持ちを引き締めるスイッチ」になる。元野球部だからか、ルーティンの大切さは身に染みてわかっている。だからこそ、「気の緩み」を防ぐには、習慣を自分の味方につけるのが一番だと思っている。