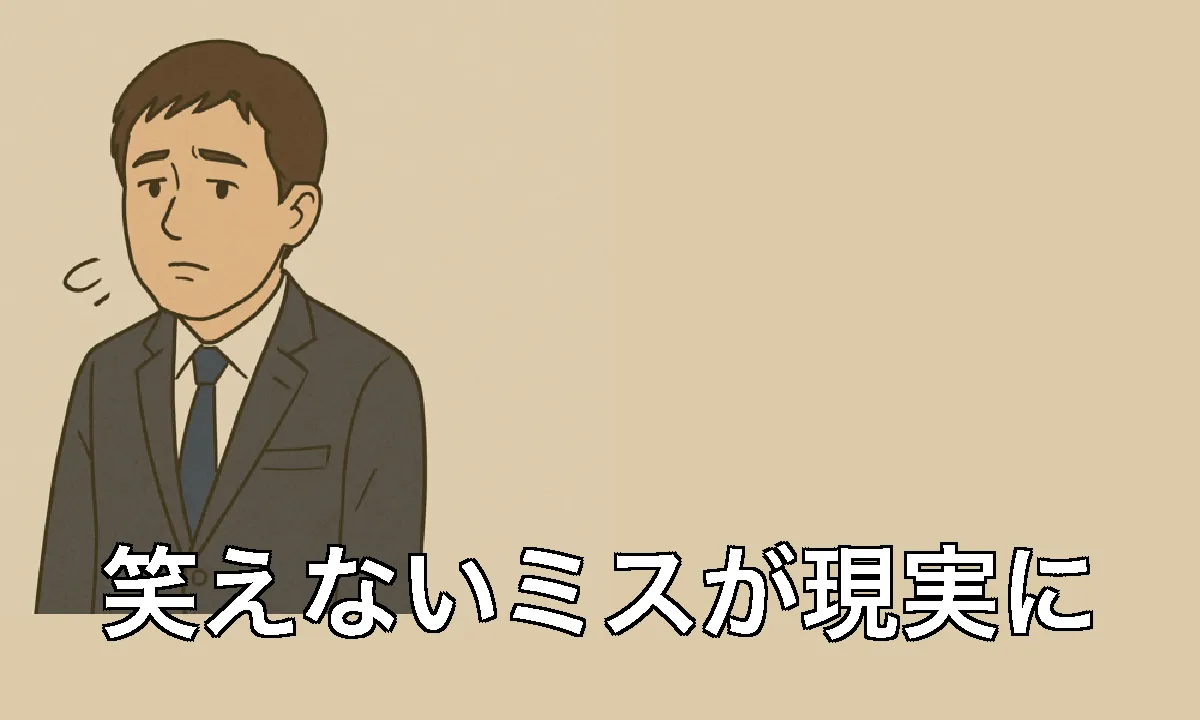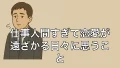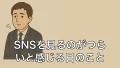些細な確認漏れが命取りになる
司法書士という仕事は、正確さが命だ。1文字の誤字、1行の漏れ、それだけで依頼人の信頼を一気に失う。ある日、登記識別情報の交付書類に住所の番地がひとつ抜けていた。内容的には大きなミスではないが、提出し直しが必要になり、登記完了が予定より数日遅れてしまった。依頼者は怒りをあらわにし、「プロなんでしょ?」と冷たく言い放った。自分でも「なんであんな初歩的な確認を怠ったのか」と頭を抱えた。忙しさに紛れて、丁寧さを失っていたのだ。
「ちょっとしたミスでした」は通用しない世界
「ほんのちょっとのことですから」と思ってしまう瞬間が怖い。たしかに、たった1行、たった1文字。しかしその1つが積み重なると、大きなトラブルになる。登記業務では、ミスはそのまま「法的効力の欠如」につながりかねない。たとえば、所有者氏名の漢字1文字が違っていただけで、法務局から「補正してください」と連絡が来る。その時点で依頼者からの信用は揺らぎ始める。自分が「ちょっと」と思っても、相手は「ありえない」と思っている。重い現実だ。
見落とした一文字が引き起こした地獄
以前、相続登記の案件で被相続人の名前「高橋一郎」の「一」を「壱」と記載してしまった。まさかの変換ミス。しかもそれに気づいたのは、登記申請後の補正通知が来てからだった。依頼者に説明する時の自分の声は、震えていたと思う。信頼を寄せてくれていた依頼者の目が、明らかに曇っていた。言い訳もできず、ただ「」と頭を下げるしかなかった。あの夜は一睡もできなかった。まさに“笑えないミス”の典型だった。
依頼者の怒りより自分への失望が辛い
依頼者が怒って当然だという気持ちと同時に、「自分はこんな簡単なこともできないのか」という自己嫌悪が襲ってくる。怒鳴られたら「申し訳ない」と思うが、静かに失望されたときの方が辛い。感情のない「わかりました、結構です」という言葉の冷たさは、胸に突き刺さる。心のどこかで「俺、司法書士に向いてないのかな」とまで考えた。責任感が強いほど、自分への失望も深くなる。そんな日は、夜にビールを飲んでも、まったく酔えなかった。
事務員一人の現場で起きるすれ違い
私の事務所には、事務員が一人だけ。彼女は真面目でよくやってくれている。ただ、私の指示が曖昧だったり、確認を怠ったりすると、すぐに業務にズレが生じる。先日も「登記原因証明情報をまとめておいて」と伝えたつもりが、私の頭の中のフォーマットと彼女の理解がまるで違っていて、結果として作業のやり直しになった。これは完全に私の指示ミス。お互いに「分かっているはず」という思い込みが積み重なると、大きなエラーを生む。
業務分担のつもりが「丸投げ」になっていた
事務員にお願いする仕事を「業務分担」と思っていたけれど、実際はただの「丸投げ」だったことに気づいたのは最近だ。細かい内容を確認せずに渡してしまい、トラブルになって初めて「あ、説明が足りなかったんだ」と反省する。例えば、委任状の添付を忘れたまま提出してしまい、補正通知が来たのは彼女のせいではなく、完全に私の確認不足だった。仕事を任せるというのは、責任も一緒に持つということ。それができていなかった。
何も言わない=わかってくれてる、ではない
「阿吽の呼吸」という言葉があるが、そんなものは幻想だ。何も言わずに通じ合える関係なんて、漫画やドラマの中だけだと思った方がいい。以前、私が「登録免許税の計算、お願い」と言ったとき、事務員は固定資産税評価額からの計算だけで済ませていた。実際には課税価格の修正が必要なケースだったのだが、それを私が伝えていなかった。伝えてなければ伝わらない。基本的なことだけど、忙しくなるとつい忘れてしまう。
「言わなくてもわかるだろ」は危険な幻想
若い頃の自分は、職人気質で「背中で語る」みたいな昭和の美徳に憧れていた。しかし実務においては、具体的な指示と丁寧なコミュニケーションが何よりも重要だ。「言わなくてもわかるだろ」と思った瞬間が、事故の始まり。誤解があれば補正、最悪の場合、登記不受理ということもありえる。指示を出す方こそ、明確に。相手の理解を前提にせず、確認を怠らない。今では「言い過ぎなくらいがちょうどいい」と思うようになった。
自分の甘さに気づいた午後三時
ある日の午後三時、軽い眠気と空腹のなかで作業をしていた。疲れもあって、集中力は散漫。そのとき作った登記申請書が、あとから見たらミスだらけだった。なぜこんなにも簡単なところで?と自分でも呆れるような内容。午後三時という時間帯は、集中が切れやすい魔の時間。昼過ぎに集中力が落ちることはわかっていたのに、なぜその時間に大事な作業を任せてしまったのか。自分の体調と向き合う余裕すらなかったのだ。
ルーチンワークの落とし穴
毎日同じ作業をしていると、「慣れ」が邪魔になる。何十件と処理してきた内容でも、「いつも通り」で済ませてしまうと、肝心な部分を見落とすことがある。登記の目的の選択を間違えて申請してしまった時も、まさにそのパターンだった。思考停止のまま入力し、確認せずに提出。あとで事務員に「あれ、これ違ってませんか?」と言われて、冷や汗が止まらなかった。慣れている仕事ほど、改めてチェックが必要だと実感した。
訂正と謝罪は終わりではなく始まり
ミスをした時に謝罪するのは当然だが、それで終わりだと思っていたら大間違いだった。謝罪のあとに待っているのは、信頼回復のための再スタート。たとえば、相手が「もう大丈夫です」と言ってくれても、実際には心のどこかで「またやるんじゃないか」と思われている。失った信頼は、すぐには戻らない。むしろ、以前よりも慎重で、丁寧でなければならない。自分自身を律し続ける必要がある。それが精神的にもきつい。
信頼を取り戻すには倍の労力がかかる
一度失った信用を取り戻すには、普段の倍、いやそれ以上の努力が必要になる。普段から連絡をマメにしたり、提出前の確認を二重三重に行ったりすることで、ようやく「前回のことはもういいよ」と言ってもらえる。信頼は、一つひとつの行動の積み重ねでしか得られない。言葉ではなく、態度で示すしかない。地道だが、それしか方法はないのだと、痛感する日々だ。
それでも続ける意味を探す夜
「なんでこんなに神経をすり減らしてまで、この仕事をしてるんだろう」と思うことは正直ある。それでも、依頼者が「助かりました」と言ってくれたときの一言で救われる。小さな「ありがとう」が、次の日を乗り越える力になる。報われる瞬間は少ないが、ゼロではない。だから今日もまた、机に向かって書類を見つめている。続ける意味を探しながら。
独身司法書士のつぶやきに込めた戒め
正直、独身でいることが寂しくないわけではない。仕事が忙しすぎて、誰かと向き合う余裕もなかったのかもしれない。夜、誰にも「おつかれさま」と言われず、コンビニ弁当を温める音だけが事務所に響く。その静けさの中で、「今日もミスせずに終わった」と思える日は少ない。それでも、誰かの役に立っている実感だけが、細い糸のように自分を支えてくれている。
「笑い話になる日が来る」と自分に言い聞かせて
今は笑えないミスも、いつか誰かに話せる日が来ると信じている。あの時は辛かった、でも今はこうやって笑って話せる。それが理想だ。だけど現実は、まだ笑う余裕はない。必死にこらえているのが精一杯。でも、それでも続ける。失敗の経験は、誰かにとっての教訓になるかもしれない。だから、ここに書き残しておく。
自分を責めすぎず、他人にも厳しくなりすぎず
完璧主義でいたつもりが、ただ自分にも他人にも厳しいだけになっていたと気づいたとき、少し肩の力が抜けた。人はミスをする。自分も、事務員も、依頼者だって。だからこそ、フォロー体制や二重チェックの仕組みが大切なんだと、今では思えるようになった。人の優しさは、ミスを責めないことではなく、ミスを一緒に乗り越えていこうとする姿勢だと思う。
そして今日も、ひとり飯を噛み締める
事務所にひとり残って、冷めたご飯をゆっくり噛み締める。ミスのない一日だったか?いや、そんな日はめったにない。でも、それでも今日を終えられたことに感謝して、明日に備える。きっとまた、何かやらかすかもしれない。それでも前を向くしかない。ひとり飯は、今日の反省と明日への決意を込めた、私のささやかな儀式になっている。