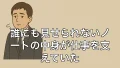事務所でひとりまたひとりという現実
開業当初は「一人でもやっていける」と息巻いていた。けれど現実は違った。日々の業務に追われながら、ふと手を止めると、そこに人の気配がないことに気づく。事務所という空間に、ひとりきりで書類を広げている時間が長くなるほど、自分がどこか透明な存在になっていくような錯覚に襲われる。誰にも見られていない仕事、誰にも褒められない努力。黙々とこなすのが性に合っていると思っていたが、そうじゃなかった。静かすぎる日々は、心に隙間風を吹き込む。
事務所に響くのはキーボードの音だけ
朝から晩まで、聞こえるのは自分が打つキーボードの音。時折、コピー機の音や、電話の着信音が混じるくらいだ。かつては野球部で、仲間の声が飛び交う中で汗を流していた。それに比べて今は、声を発する機会すらほとんどない。お客様と電話で話すときに、かすれている自分の声に驚くこともある。誰かと笑い合う時間、世間話をする時間、そんな当たり前がここにはない。静かすぎて、自分がそこに存在しているのかさえ曖昧になる。
誰かと交わす言葉がない一日
今日は誰とも喋らなかった。そんな日が、週に何度もある。コンビニの店員との「ありがとうございます」すら、唯一の会話になる日もある。かつての自分なら考えられなかった。人とのやり取りが好きでこの仕事を選んだはずなのに、気がつけば書類だけを相手にする日々。独身ということも手伝って、家に帰ってもまた無言。言葉が出てこなくなる。喋らなければ、思考すらも錆びつくような気がしてくる。
無音の中で進む登記書類の山
とはいえ、仕事は山ほどある。登記の申請、不動産の名義変更、相続関係の書類作成。誰とも会話をしなくても、業務は確実に進む。そしてそれがまた、孤独を強めていく。機械のように正確にこなすことを求められる司法書士の仕事は、感情を挟む余地が少ない。無音の中で、一枚ずつハンコを押していく自分が、まるでベルトコンベアに乗っている部品のように感じられてくる。
事務員もまた去っていくという寂しさ
事務員がいた時期もある。でも、長くは続かなかった。最初は慣れない業務にも頑張ってついてきてくれたが、次第にこちらの余裕のなさが空気を重くしたのかもしれない。給料も高くない。残業も多い。そして、何よりも「楽しくなさそうな雰囲気」が出てしまっていたのかもしれない。結局、「やっぱり続けられません」と告げられ、また一人に戻った。
気を遣ってくれる優しさが逆につらい
やめていった事務員は、皆いい人だった。こちらが忙しそうにしていると気を遣ってくれて、そっとお茶を差し入れてくれるような優しさを持っていた。でも、その優しさに甘えてしまう自分がいたのも事実だ。うまく感謝を伝えられず、「ありがとう」よりも先に「これ急ぎだからお願い」と言ってしまう。人間関係の温度管理が下手なのだと、今更ながら痛感している。
一緒に頑張ろうの言葉が心に残る
かつての事務員が退職前に言った「一緒に頑張ろうと思ってたんですけどね」という言葉が今も胸に残っている。あの一言に、申し訳なさと情けなさがぐっと押し寄せた。あの時、もっと話を聞いてやれていれば。もっと笑えていたら。自分の余裕のなさが、人を遠ざけていたのかもしれないと思うと、ただただ悔しい。
優しさだけではやっていけない世界
司法書士という職業は、誠実さと正確さが求められる。もちろん優しさも大事だが、それだけでは通用しない。感情を込めすぎてもいけない。心を閉じすぎてもいけない。そんな中途半端なバランスを常に保たなければならない。人に優しくすることで自分がすり減っていくこともある。だからといって、優しさを捨てたら、自分が何のためにこの仕事を選んだのか分からなくなってしまう。
書類は感情を持たない
毎日向き合っているのは、書類だ。書類に感情はない。間違いがあれば修正され、遅れれば指摘されるだけ。誰かが「頑張ったね」と言ってくれるわけではない。それでも一つ一つ丁寧に仕上げていく。感情を押し殺してでも、正確であることが第一優先。それが司法書士という仕事の宿命だと分かってはいるけれど、時折その冷たさに心がこわばってしまう。
冷たくても正確にが正義になる
「感情を交えるな」と言われて育ったわけじゃないけれど、仕事においては、冷静さが評価される。温かい言葉よりも、期限内の処理。どれだけ丁寧でも、間違っていれば意味がない。結果として、冷たくなってしまった自分に気づく日もある。お客様とのやりとりすらも、どこか機械的になっているのかもしれない。それがいいのか悪いのか、自分ではもう判断がつかなくなっている。
怒られないための優しさが自分を消す
優しくしようとすると、今度は怒られたくないという気持ちが先に出る。クレームを避けるための配慮、波風を立てないような言い回し。いつしか、それは本来の自分の言葉ではなくなっていった。本音はどこかに押し込め、穏やかであることだけを優先するようになった。優しさの皮をかぶった恐怖心。それが続くと、自分がどんな人間だったのかも、よくわからなくなってくる。