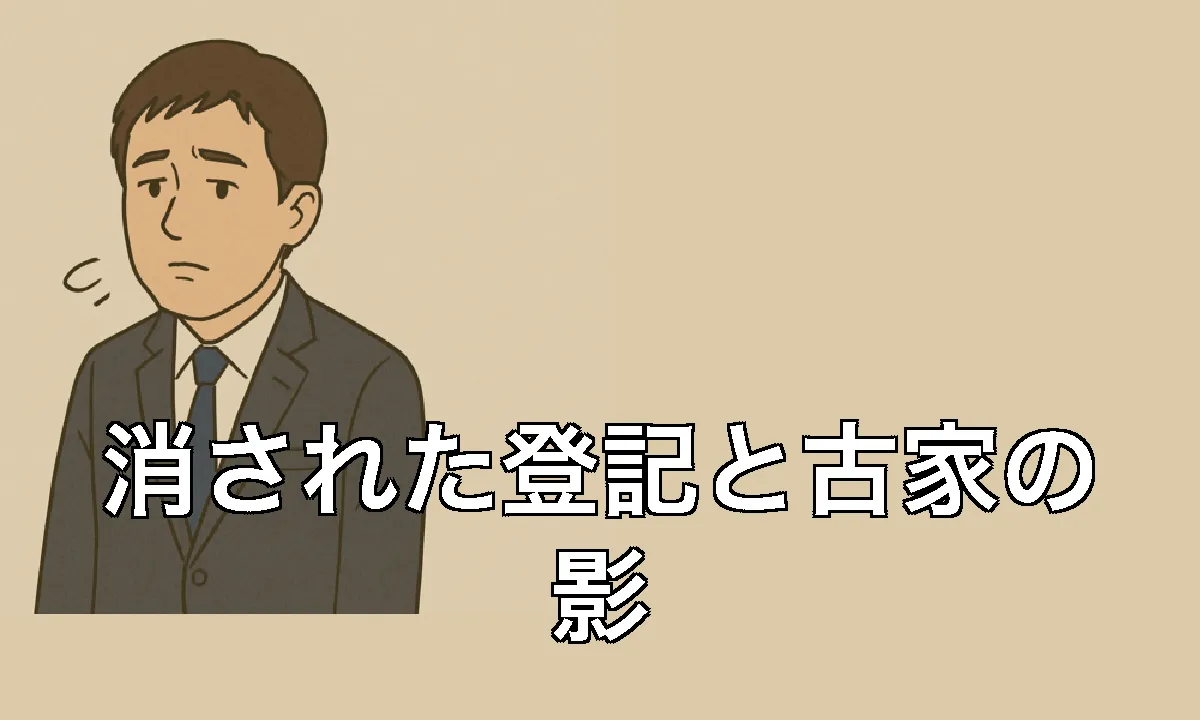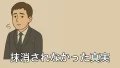古びた家と依頼人の訪問
午後の陽射しが斜めに差し込む事務所の扉が、きぃ…と鳴って開いた。見慣れない中年男性が、しわの寄った帽子を脱ぎながら入ってきた。肩の荷が重そうで、最初の一言が妙に深刻だった。
「あの……この家なんですけど、存在しないらしくて」
その言葉に、少しだけ背筋が伸びた。司法書士という職業は、時にこの世の“存在しないもの”と向き合うことになる。
突然の訪問者は手に何も持たず
登記簿の写しも、権利証も、本人確認書類すらなかった。ただ、その目だけが真剣だった。手ぶらで訪ねてくる客の多くは、何かを隠しているか、失っている。
「祖父の家なんですが、取り壊しが決まってまして。でも不動産屋に言われたんです。登記が無いって……」
未登記家屋。その単語が頭に浮かぶのと同時に、面倒な仕事の予感が立ち上がった。
未登記家屋という言葉の重さ
世の中には“あるけどない家”が存在する。法律上の存在と、物理的な存在が乖離するこの状態は、司法書士にとって最もやっかいな事象の一つだ。
「そもそも、どうして登記しなかったんでしょうかね?」と彼が言う。
なぜかその質問が、ずっと胸の奥でざらついた。
「この家は存在しないんです」
「建物図面にも表題登記にも何も載っていないんです」そう言って見せたのは、不動産屋からの簡易な調査報告だった。
存在しない建物に関わる手続きを、どう進めろというのか。やれやれ、、、また厄介なパズルの時間だ。
一筋縄ではいかない。そう思ってサトウさんを見ると、すでにパソコンに向かっていた。
地図に載らない家の謎
昔の住宅地図を片っ端から調べてみた。すると、昭和50年の白黒コピーにだけ、その家が載っていた。
「名前が書かれてないですね」とサトウさん。確かに、建物の存在はあるが所有者の記載がない。
サザエさんのオープニングで背景に映る一軒家のように、誰も気に留めず、存在だけがぼんやりしている家。
登記簿に記録されない理由
「もしかして…建てたけど、名義変更しなかったのでは?」と私がつぶやくと、サトウさんがぴたりと手を止めた。
「表題登記もないとなると、建てた人すら分からないってことになりますね」
謎は深まる。登記されなかった理由は、ただの怠慢か、それとも何かを隠したかったのか。
かすれた名義人と消えた権利
昔の住宅ローン記録を調べると、わずかに「ハセガワ」という名前が出てきた。
だが、その人物の現在の住民票は存在せず、戸籍も途中で除籍されていた。相続も行われていない。
つまり、その家は今、誰のものでもない。だが実際には、依頼人の叔父が住んでいたという。
登記原因証明情報の不在
登記申請には“なぜこの名義になるのか”という理由が必要だ。だが、その根拠となる書類が一切見つからない。
「相続放棄したんじゃ?」と依頼人は言ったが、それも記録に残っていなかった。
ないない尽くしの状況。まるで名探偵コナンで、何も証拠が無いのに真相に迫るあの感じ。だが現実はもっと冷たい。
床下から見つかった封筒
翌週、依頼人から電話があった。「取り壊しの前に、床下から古い封筒が見つかりまして…」
封筒の中には手書きのメモと、薄汚れた書類が入っていた。昭和の固定資産税通知だった。
「これって…証拠になりますか?」と不安そうに差し出されたそれが、鍵になるとは誰も思っていなかった。
サトウさんの冷静なひとこと
「これ、筆跡を専門家に見てもらいましょう。もし建築時の申請者と一致すれば、登記の根拠になります」
私は驚いて口を開けた。「さすがだな……」
「当たり前です。私はあなたと違ってうっかりしませんから」と塩味の効いた返事。
廃屋に遺された遺言書の断片
その書類の束には、薄れて読めないが“この家は息子に譲る”と読める箇所があった。
それは正式な遺言書ではなかったが、状況証拠としては有効になり得た。
ここから、すべてが動き出す。
筆跡は誰のものか
筆跡鑑定の結果、書類と古い納税証明書の名前は一致。建てたのは依頼人の祖父だった。
だが、当時の法律では表題登記をしなければ建物は登記簿に載らないままだ。
だからこそ、この家は存在していても、“法的に存在しない家”だった。
過去の名義変更を遡る
表題登記を新たに申請し、所有権移転の準備に入った。だが、登記原因が「相続」となるにはもう一つ材料が必要だ。
それは、所有者が他界していることの証明だった。除籍謄本が必要になる。
そしてそれは、役場の奥底にひっそりと残されていた。
昭和五十年に起きた何か
除籍されたのは、ちょうど家が建った翌年だった。火災があったと記録にある。
その火事で、元の名義人が亡くなっていた。しかしその死が、家族の間で語られることはなかったらしい。
まるで、その家ごと記憶から消されたかのように。
元所有者の息子の失踪
もう一人の相続人、つまり依頼人の叔父が長年行方不明だった。
「行方不明者として申請すれば、他の相続人だけで登記が進められる可能性があります」と伝えると、依頼人は黙ってうなずいた。
法は冷たく、しかし整然としている。心の整理は、また別の話だ。
近所の古老が語った伝説
古老の証言によれば、「あの家はな、ずっと持ち主がいない言われてたんだ」
けれど、庭木は手入れされていた。誰かがそこに“心”を残していたことだけは確かだった。
それが家を守り続けた理由だったのかもしれない。
相続されなかった家の行方
手続きは完了し、ようやくその家は“この世に存在する家”となった。
依頼人は取り壊すかどうか悩んでいるようだった。家そのものより、そこにある思い出を失うことに迷いがあったのだろう。
その気持ちは、私には少しだけわかった。
兄弟間の確執と口約束
どうやら、家を巡る揉め事は昔からあったようだ。だが、記録に残っていないことは、法の世界では“無かったこと”になる。
「話し合って解決したかったな…」と依頼人が漏らす。
だが、その願いはもう誰にも叶えられない。
やれやれ、、、意外な所有者
最終的にその家の所有者となったのは、依頼人ではなく、叔父の婚外子だった。
DNA鑑定により血縁関係が証明され、相続権が発生した。誰も知らなかったもう一人の“家族”。
やれやれ、、、司法書士にできるのは、記録を繋ぐことだけだ。
すべては家の裏の畑にあった
畑には、かつての所有者が残した梅の木があった。梅の木の下に、小さな陶器の壺が埋まっていた。
中には、手紙と写真が一枚。「この家が幸せでありますように」
誰が残したかは分からない。ただ、それだけで十分だった。
静かな事務所に戻る午後
事務所に戻ると、サトウさんが言った。「お茶、飲みます?」
「ああ、いただこう」と答えると、彼女が珍しく湯呑みを持ってきた。
その湯呑みに、少しだけ春の匂いがした。
お茶を淹れたのは意外にも
「あなた、今日はまともでしたね」と彼女は言った。
「やれやれ、、、褒められてる気がしないんだが」
けれどその午後は、不思議と悪くなかった。