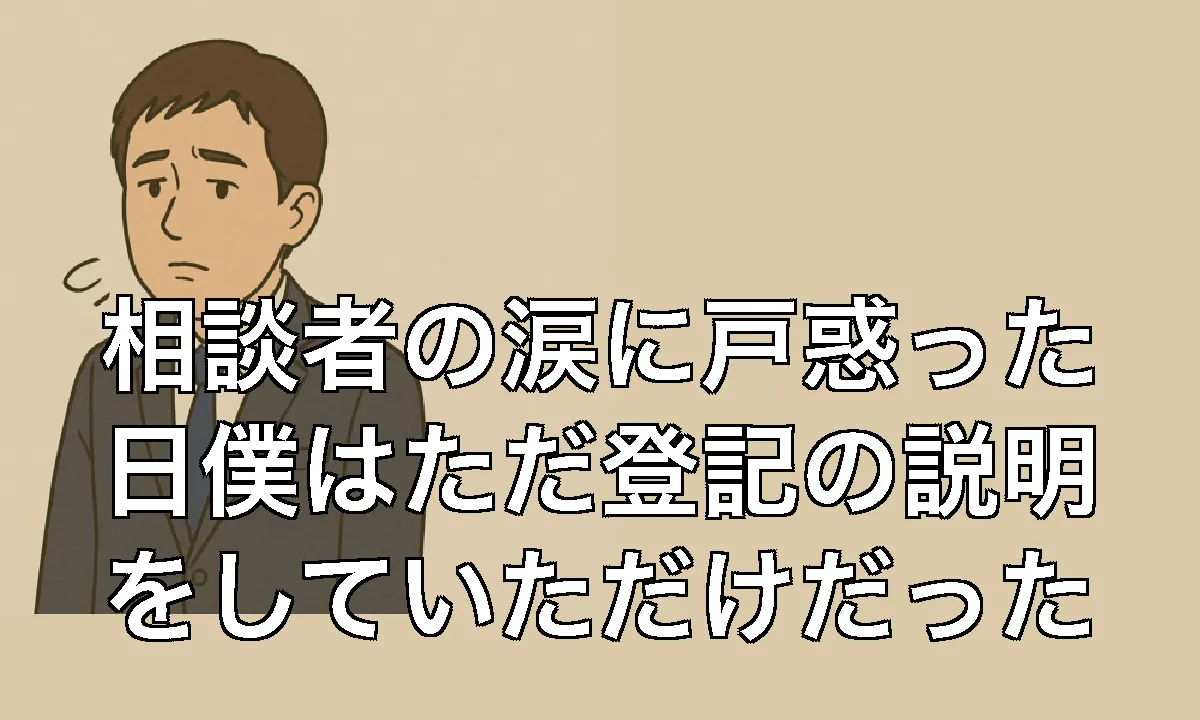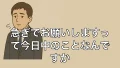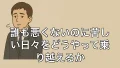泣き出した相談者と沈黙の時間
その日、相談に来たのは30代後半くらいの女性だった。戸籍の話から始まり、相続登記の手順を淡々と説明していたはずだった。特に感情を揺さぶるような話をしたつもりはなかったし、こちらはいつも通り事務的に対応していた。それなのに、突然、彼女は下を向き、肩を震わせて涙を流し始めた。僕は言葉を失い、ただ座っているしかなかった。時計の秒針の音すら大きく感じるほど、沈黙が長く重かった。
静まり返った相談室に響いた嗚咽
狭い相談スペースの中で、涙の音があんなに大きく響くとは思わなかった。紙の資料をめくる手も止まり、僕は顔を上げられずにいた。なにか言わなくては、と思えば思うほど、喉が詰まり、結局何も言えなかった。司法書士としての僕は、言葉で導くのが仕事のはずだ。けれど、感情があふれた場面では、正解がどこにも見つからない。彼女が何に対して涙を流していたのか、そのときの僕には察することもできなかった。
こちらの説明が悪かったのかという不安
話し方が冷たかったのか。余計なことを言ったのか。それとも何かを思い出させてしまったのか。答えのない問いが頭の中をぐるぐると回った。僕は「登記の説明だけをしていた」つもりだったが、相手にとっては故人の記憶や複雑な家族関係に触れる行為だったのかもしれない。そう考え始めると、自分の無神経さが浮き彫りになる気がして、苦しくなった。
涙の背景を推し量れない自分への苛立ち
僕はこの仕事を15年以上やってきて、それなりに経験も積んできたつもりだ。けれど「人の気持ちを読む力」については、まったく成長していないように感じる瞬間だった。相談者の涙の理由がまるで見当つかない。そのことが、自分がただの登記処理屋になっているようで、恥ずかしかった。そして何より、その涙にすら戸惑ってしまう自分が情けなかった。
司法書士という仕事の限界を感じる瞬間
この仕事は、法律に基づいて、手続きを淡々と進めることが本質だ。けれど、相続や離婚、借金整理といった分野は、感情の渦の中に踏み込む場面がどうしても多くなる。そのたびに「自分は専門家としての力しか持っていない」と痛感する。書類の正確さでは人を救えない。けれど、慰めの言葉をかけるスキルも持ち合わせていない。そんな中途半端な立場に、たびたび無力感を覚える。
感情に寄り添うことの難しさ
「共感」と「干渉」の境界線はあまりに曖昧だ。泣いている人に「大丈夫ですか?」と声をかけるべきか、それともそっと黙って寄り添うべきか、僕はいまだにその判断がつかない。間違えば傷を深くしてしまうかもしれないという恐れもある。相手の気持ちを尊重するとは、具体的にどうすればいいのだろう。何度もそう自問しているが、答えはまだ出ない。
事実だけでは救えない場面の増加
昔は、正確な登記と早い対応が喜ばれると思っていた。実際それで感謝されたことも多かった。けれど、最近は「心の引っかかり」を抱えてくる人が増えているように感じる。単なる手続きだけで満足してもらえない。求められているのは、人間としての対応であり、共に立ち止まる時間だ。それができない自分は、果たして「頼れる専門家」と言えるのだろうか。
士業では足りないもの
士業とは「士(さむらい)」という名前がつくほど、昔は尊敬される立場だったのかもしれない。でも今の時代、その肩書だけでは信頼されない。むしろ「冷たい人」と思われがちなのかもしれない。法的に正しいことを言っても、それが心に届かなければ意味がない。僕に欠けているのは、おそらく「人としてのあたたかさ」なんだと、ようやく気づいた。
元野球部の癖でなんとかしなきゃと思ってしまう
野球部時代の癖で、困っている人を見るとすぐ「自分が何とかしなきゃ」と思ってしまう。責任感とも言えるけれど、たいていは空回りだ。今回もそうだった。涙に戸惑って、なんとか場を収めようと焦ってしまい、かえって何もできなかった。バットを振るように、反応してしまう。だけど、人生は試合じゃないし、正解のスイングなんてないのかもしれない。
解決したいのに空振りばかり
手続きで困っているなら、それは得意分野だ。でも心の問題になると、とたんに空振りが増える。慰めようとして失言になることもあるし、沈黙が気まずくて逆効果なこともある。結局「よかれと思って」が裏目に出るのだ。技術で乗り切れない場面に弱い。それが自分の弱点だと認めざるを得ない。
正解を探す癖がかえって邪魔になる
いつも「正解」を求めてしまう。これが正しい言い方か、適切な対応か、法律的にOKか。だけど、感情に「正解」なんてあるのだろうか。相談者の涙に、正しい対応があると信じ込んでいた自分が滑稽に思えてくる。たぶん、大切なのは正解ではなく「一緒にその場にいること」なのかもしれない。
ときには何もできない自分を認める勇気
無力な自分を否定せずに受け入れる。それが、最近ようやくわかってきた気がする。なにもできない時間も、意味があるのだと。何も言わずにただ隣にいること、目を逸らさないこと。その不器用な優しさこそ、司法書士としてではなく、人として必要なものかもしれない。
事務員の一言に救われた午後
相談者が帰ったあと、ぼんやりしていた僕に、事務員の彼女がぽつりと「泣けたってことは話せたってことですよ」と言った。その一言が、胸にじんと沁みた。僕はずっと「泣かせてしまった」と自分を責めていたけれど、彼女のその言葉で少し救われた。支える側にも、支えてくれる誰かが必要だと、あらためて思った。
泣けたってことは話せたってことですよ
事務員の何気ない言葉に、どれだけ救われたことか。彼女は専門的な知識もなく、手続きにも関与しない。でも、人の気持ちを感じる力は僕よりずっとある。机に向かってばかりじゃ見えないものがある。結局、言葉より「想い」なのかもしれない。
隣にいる人の存在が沁みる
ひとりでやっているようで、実は誰かが隣にいてくれている。それが事務員だったり、たまに来る先輩だったりする。人を支える仕事は、案外、自分が支えられていないと続かない。気づいたときには、少し泣きそうになっていた。
相談者の涙を忘れない理由
あの日の相談者の涙は、今でも心に残っている。何もできなかった自分の姿とともに、確かに覚えている。その無力さが、僕を変えるきっかけになった気がする。きっとこれからも、完璧にはなれない。でも、それでも、寄り添おうとする気持ちは、忘れずにいたいと思う。
登記が終わっても終わらない物語
書類が完成し、登記が終わったあとも、相談者の物語は続いていく。そして、その中に、僕がほんの少しでも関われたこと。それが、司法書士としての誇りなのかもしれない。泣いた相談者に、僕は何を渡せたのか。答えはわからない。でも、その問いを忘れずにいたい。
専門家としてではなく人として接する覚悟
「士業」という肩書きに縛られず、「人」として相談に向き合う。それが、今の自分にできる精一杯の誠実さだと思う。完璧じゃなくても、共に迷って、共に悩む。そんな司法書士でありたいと、心から思った。