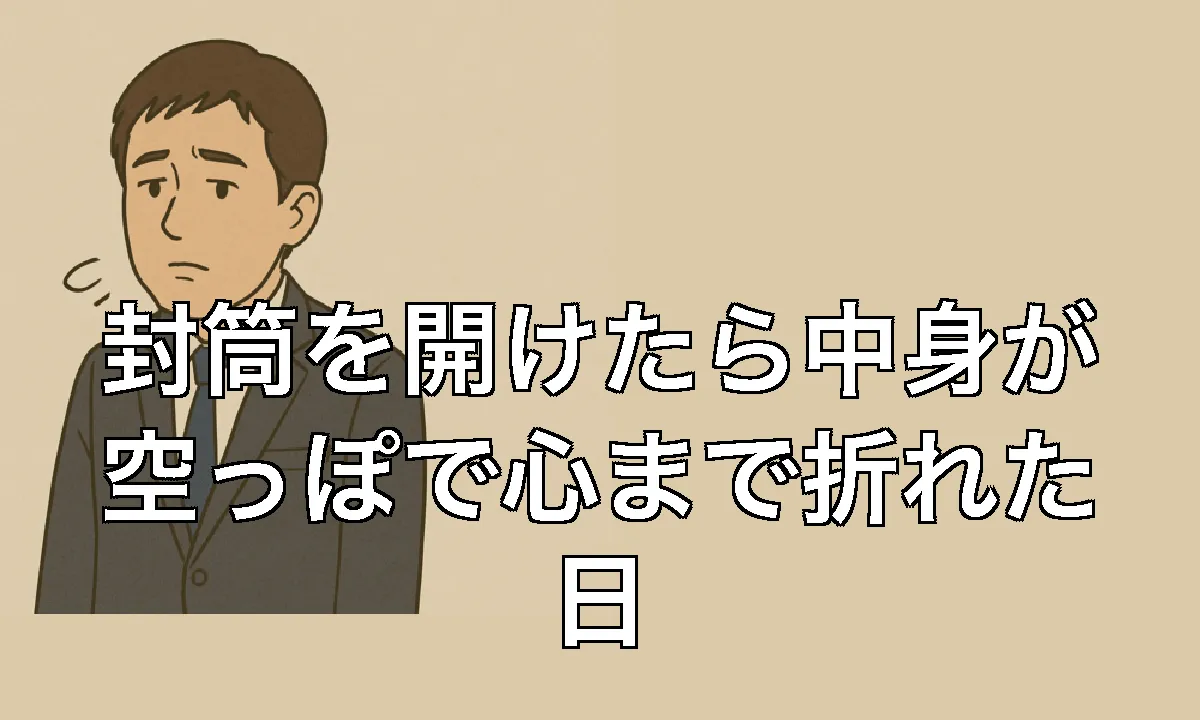開けた瞬間に広がる虚無感
その日はたしか、雨が降っていた。なんだか肌寒くて、朝から妙に肩が重かった。そんな日には、なにかひとつでも嬉しいことがあればいいなと淡い期待を抱いてしまうものだ。ポストに投函されていた一通の封筒を見つけたとき、心が少しだけ浮いた。差出人は取引先。きっと支払いか、書類の確認だろう。帰ってお茶を淹れながら、封を切った。その瞬間、紙が一枚も入っていないと気づいたときの、あの言いようのない落胆。まるで、自分自身が空っぽであると突きつけられたようだった。
一日の終わりに届いた一通の封筒
仕事の合間に届いた郵便物をそのままにして、夜になってから開けるのが習慣になっている。期待はしていなかったつもりだったけど、少しでも「何か」が入っていると思っていた。せめて誤送の手紙でも、支払いの確認でも、何かしら手がかりがあると思っていた。でも、封筒の中には本当に何もなかった。白くて虚無な空間だけが残っていた。重みのないその封筒を、しばらくぼーっと眺めていた。
ちょっとした期待があっただけに
封筒を開ける前、何かが報われるような気がしていたのかもしれない。今月は特に忙しかったし、登記の修正対応も二度手間になって胃が痛くなるような思いをしたばかり。だからこそ、封筒の中身に自分の努力の結果が詰まっているような錯覚すらしていたのかもしれない。期待が大きかった分、空っぽだったときの落差がひどくて、思わず天を仰いだ。
その中身がゼロだったという絶望
「空っぽって、こんなに破壊力あるんだな」と、思わず声に出た。なによりも、これは単なる封筒ではなく、自分が誰かから必要とされているかどうかを測るリトマス試験紙のように感じていたことに、自分で驚いた。事務員さんにも話せないし、そっとゴミ箱に入れて何事もなかったかのようにふるまったけれど、内心は結構なダメージだった。
報われない努力という名の重圧
司法書士として日々業務をこなす中で、目に見えないプレッシャーに押しつぶされそうになる瞬間がある。毎日遅くまで仕事をして、法務局に何度も足を運び、クライアントの要望を可能な限り叶えようとする。でも、その努力は褒められることも、評価されることもない。逆に、ちょっとしたミスや勘違いで「対応が遅い」と叱られることもある。正直、やるせなさを感じる日も多い。
書類も登記も期日も守っているのに
どんなに完璧に準備しても、書類の受け取り側の都合や気分で振り回されることがある。たとえば、登記完了の連絡をした後、数日経ってから「やっぱり表記を変えたい」と言われたり。「今さら?」と思うような依頼も、結局こちらが受け止めないといけない。期限内に完了しているのに、評価されるどころか、文句を言われることさえあるのがこの仕事だ。
それでも誤解やクレームは飛んでくる
メールの文面一つで相手の機嫌を損ねることもある。少しでも表現が硬ければ「冷たい」と言われ、丁寧すぎると「まわりくどい」と言われる。内容ではなく“印象”が問題にされるこの世界に、正直うんざりすることもある。特に最近は、感情的なやり取りが増えていて、些細な誤解がトラブルに発展するケースも少なくない。
誰も気づかない地味な努力
書類を一枚出すまでに、どれだけ確認を重ねているか。ミスを防ぐための見直し、過去の記録との突合、時には管轄の役所へ電話で確認。そういった作業のひとつひとつは、誰にも見えない。だけど、それがなければこの仕事は成り立たない。表に出ない地味な努力こそが、司法書士の本質なんじゃないかと感じる瞬間もある。
孤独な机と今日の溜息
一人事務所というのは、思っている以上に孤独だ。もちろん事務員さんがいてくれるだけでもありがたい。だが、自分の責任はすべて自分で背負う。誰かに判断を委ねることもできず、何か問題が起きたら、自分がすべての矢面に立つ。ときどき、誰かに弱音を吐けたらと思う。でも、それを許してくれる人は、この仕事の中にはなかなかいない。
事務所に響くのはキーボードの音だけ
朝の9時に開けた事務所は、日中もほとんど静まり返っている。来客があるわけでもなく、電話が鳴らない時間が続けば、本当に「このまま誰にも必要とされなくなるんじゃないか」と思ってしまう。キーボードのタイピング音だけがリズムを刻み、時折、事務員さんが書類のコピーを取る音が響くだけ。そんな日常に、自分は馴染んでしまっている。
事務員さんの優しさが唯一の救い
うちの事務員さんは本当に気が利く。言葉数は少ないけれど、空気を読む力がすごい。こちらがイライラしているときは黙っていてくれて、疲れているときはお茶をそっと置いてくれる。気づけば、その存在にずいぶん救われてきた気がする。だけど同時に「こんなことで感謝してる自分、やばくないか」とふと情けなくなる。
それでも根本的な寂しさは埋まらない
日々の業務に追われながらも、ふと一息ついたときにやってくるのは、言いようのない寂しさだ。誰かと仕事の愚痴を言い合える関係もなく、休日に一緒に出かける相手もいない。事務所という箱の中に、役割としての自分しか存在していないような錯覚に陥るとき、このままでいいのかと頭を抱える。
昔の自分をふと思い出す
あの頃は、未来に期待していた。高校の野球部で、泥だらけになってボールを追いかけていたとき、自分が将来、封筒を開けて虚無に打ちのめされる人生になるとは思っていなかった。あのときの熱量は、いまどこに消えてしまったのか。自分でもわからないけれど、時々ふと、あの頃の自分に会いたくなる。