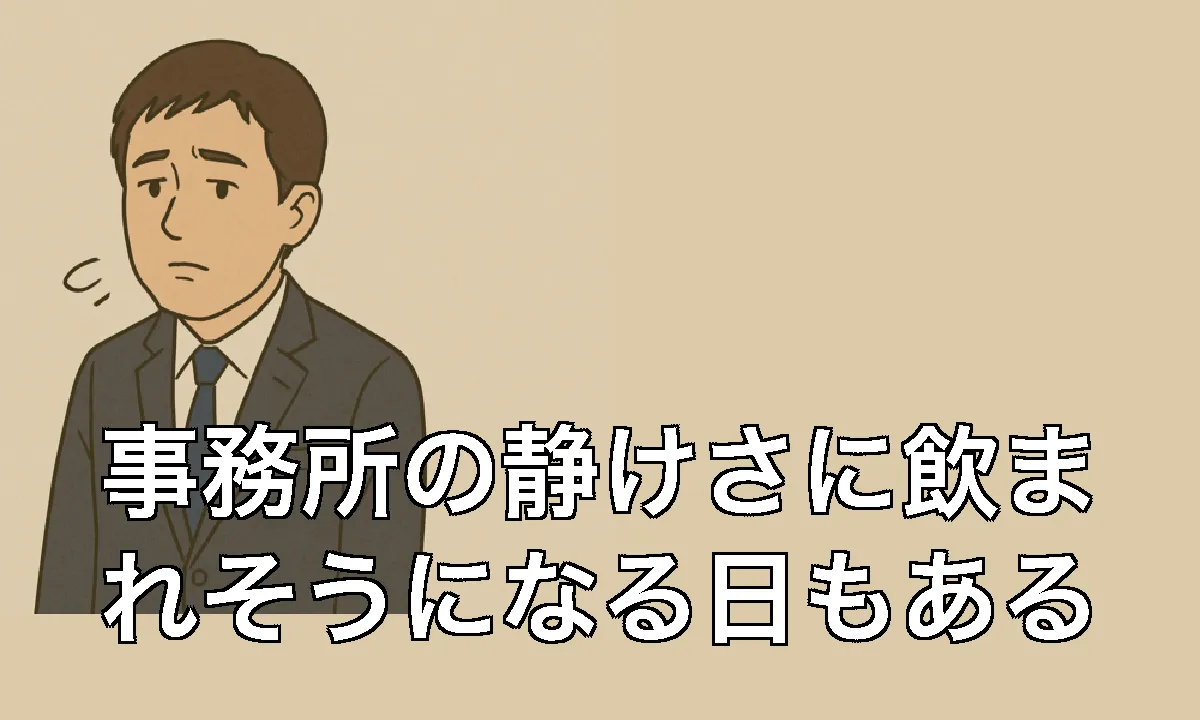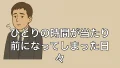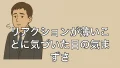誰も話さない空間が重くのしかかる朝
朝、いつものように事務所に入ると、パソコンの起動音とコーヒーメーカーのポコポコという音だけが響く。出勤してきた事務員が「おはようございます」と言ってくれるが、それっきり。会話らしい会話もなく、それぞれが自分の仕事に没頭する日が続くと、ふと「今日、誰とも喋らずに一日が終わるのでは」と不安になる。人付き合いが苦手なわけではない。むしろ、昔は野球部で声を張り上げていた自分だ。それでも、事務所という小さな空間で、たった二人で過ごす日々は、思っている以上に心に響く静けさをもたらす。
音のない空間に疲れる理由
静かな環境が集中には最適と言われるが、それが毎日続くと逆に集中力を奪われることもある。パソコンのタイピング音だけが部屋に響き、電話も鳴らず、外の音も聞こえない。ふと手を止めた瞬間、その「無音」に包まれた感覚がずっしりと胸にくる。仕事がないわけじゃない。むしろ山ほどある。でも、その仕事に取り掛かる気力が「音のないプレッシャー」に押し潰されそうになるのだ。
静寂が集中を生むとは限らない
ある日、静寂に耐えきれずBGMでも流そうかとラジオをつけたことがある。でも事務員が気を遣ってボリュームを下げたり、逆に「うるさくないですか?」と気を回してくれたりして、かえって居心地が悪くなってしまった。以来、音楽を流すのはやめた。静かだからこそ考えがまとまるという話もあるけれど、自分にとってはその静けさが、孤独を増幅させるスピーカーのようなものに感じる。
事務所の時計の音が妙に耳につく日
時計の秒針の「カチカチ」という音が、ある日突然うるさく感じたことがある。いつもなら気にも留めないような音が、やけに神経に触るのだ。これは、心が疲れているサインなのかもしれない。野球部時代は周りの声や音に囲まれて生きてきた。静寂に慣れていないのは当然かもしれない。でも、それでもこの静けさに適応していかなければ、この仕事を続けるのは難しいのだろう。
孤独と向き合うルーティンワーク
登記申請書類のチェック、郵便物の確認、電話対応、スケジュールの見直し。司法書士の仕事は決して派手ではない。黙々と、慎重に、確認作業を繰り返す。誰かとワイワイ話しながらする仕事ではないのは分かっている。それでも「今日も一日誰とも深く話さずに終わったな」と思う夜は、さすがにちょっと寂しさがこみ上げる。
「話す相手がいない」がこんなに堪えるとは
司法書士になって十年以上経つが、最近ようやく気づいた。「話す相手がいない」ことが、こんなにも精神的に堪えるとは思っていなかった。新人時代はとにかく覚えることが多くて、静けさどころではなかった。でも今は違う。仕事に慣れたからこそ、ふとした静けさが心の隙間を突いてくる。孤独というのは、ある日突然忍び寄ってくるものなのだ。
事務員との会話も最小限になる理由
うちの事務員は真面目で、黙々と仕事をしてくれる。ありがたい存在だ。でもその分、無駄な雑談は少ない。こちらも話しかけるタイミングを失いがちだ。お互いに気を遣い合って、結果として会話が減る。別に仲が悪いわけではない。ただ「静かな時間」を壊すことに、どこか罪悪感を感じてしまうのだ。
寂しさを誤魔化す工夫たち
どうにかこの静けさを和らげようと、ささやかな工夫をしている。例えば観葉植物を置いたり、ランチにちょっと高めのパンを買ったり。でも、根本的な解決にはなっていないこともわかっている。ただ、それでも何もしないよりはマシ。寂しさをゼロにするのは難しいけれど、少しでも気を紛らわせる努力は続けたい。
音楽を流す勇気が出ない理由
「好きな音楽を流してみたらいい」と言われたことがある。でも、事務所という空間の性質上、なかなか気が引けてしまう。事務員の好みに合わなかったら? 仕事の邪魔になるのでは? そんなふうに考えてしまい、結局無音のまま時間が過ぎていく。これが自宅なら、自由に音楽をかけるのに。
事務所の空気を壊したくないという気遣い
音を足すことは、空気を変えることでもある。それが良い方向に作用するかどうかは分からない。だから、無難な静けさに甘んじてしまう。これが「気を遣いすぎる自分」の性格なんだろうなと、ちょっと嫌になる瞬間でもある。
BGMで満たされないものもある
実際、BGMを流したところで心の空白が埋まるわけではない。それは、会話の代替にはならないのだ。たとえば、昔の同級生と偶然スーパーで立ち話をした日、その日は妙に気持ちが軽かった。誰かと会話するという行為そのものが、心に響いているのだと、そのとき気づいた。
人との接点が少ない業務の現実
司法書士という仕事は、意外にも人とのやり取りが少ない。依頼者とはメールや電話が中心。訪問も減り、顔を合わせることも少なくなった。効率化の波に乗っている反面、「人間らしさ」が失われていくような寂しさを感じる。
お客様対応すらもメール中心になった
以前は来所されて、世間話をしながら手続きを進めることもあった。でも今は、ほとんどがメールで済んでしまう。便利になった反面、温度を感じないやり取りに、やや物足りなさを感じるようになった。ちょっとした雑談から信頼関係が生まれることもあるのに。
電話のベルが鳴るとちょっとホッとする
不思議なことに、あんなに煩わしかったはずの電話が、今では鳴ると少しホッとする。人とつながる音が、こんなにも嬉しいとは思わなかった。たとえそれが営業電話だったとしても、「誰かが自分にアクセスしてきた」という事実が、静寂の中では救いになるのだ。
この静けさを武器にできる日は来るのか
静けさに苦しみながらも、それを受け入れる努力をしている。もしかしたら、この無音の空間でしか見えないものもあるのかもしれない。孤独の中で、自分の仕事をもう一度見つめ直す。それもまた、司法書士という職業の深さだと思いたい。
無音から学べる集中と内省
音がないことで、逆に自分の心の声がよく聞こえるようになった。何に迷い、何を求めているのか。そういうことを冷静に考えられるのも、この仕事の特性かもしれない。煩わしさがない分、考えすぎてしまうこともあるけれど、それすらも悪くないと思えるようになってきた。
結局自分と向き合うしかないという話
誰とも喋らない日は、自分自身と喋る日なのかもしれない。「俺、これでいいのか?」とか、「なんで司法書士になったんだっけ?」とか、ひとりツッコミのように問いかける。自問自答が繰り返されるこの空間は、ある意味で修行の場でもある。
静けさの中にこそ仕事の本質があったりする
うるさい環境では気づけなかった細かなミスに、今なら気づける。静寂は、仕事に対して誠実であることを強いるものでもある。だからこそ、逃げ出したくなることもあるけれど、続けていればきっと意味があると信じたい。
一人で働くことの覚悟と希望
孤独がつらいと思う反面、自分の裁量で働ける自由さは何ものにも代えがたい。事務所の空気も、仕事のやり方も、自分のペースで整えていける。この静けさを「しんどい」から「ちょうどいい」に変えていけたら、それが一番いい。
元野球部が恋しくなる静かな昼休み
昼食を取る時、ふと部活時代のにぎやかな空気が恋しくなる。誰かの冗談に笑い合ったあの時間が、今の自分には少しだけまぶしい。でも、それは過去。今の静けさを否定せず、受け入れるしかない。野球部のような熱さがなくても、淡々とやっていけるのがプロだと思っている。
この道を選んだのは自分だった
司法書士という道を選んだのは、誰でもない自分自身だ。寂しさも、静けさもしんどさも、その全てを含めてこの仕事をしている。だったら、少しでも前向きに付き合っていきたい。今日も事務所は静かだ。でもその中で、確かに自分の仕事は進んでいる。