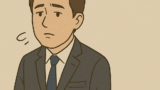朝の静けさを破った依頼
朝の事務所は、いつものように書類とコーヒーの香りに包まれていた。だが、その静けさを破るように、ガラガラと引き戸の音が響いた。扉の向こうに立っていたのは、見るからに緊張した様子の中年男性だった。
「あの……こちら、登記のことで相談に乗ってもらえると聞いて……」
その言葉に、私はうっすらとため息を漏らしながら手を止めた。
妙に緊張した来訪者
男は名刺も出さず、ただ「父の土地の件で」とだけ言った。上擦った声と不自然な目の動きが、何か隠していることを物語っている。私はソファを勧め、サトウさんにお茶を頼んだが、彼女は「自分で入れてください」と冷たく言い放った。
やれやれ、、、朝からこれか、と私は心の中で嘆いた。
だが、話の内容には司法書士としての勘が騒いだ。何かある。きっと。
旧家の土地にまつわる相談
依頼人の話によると、父親が亡くなった後に古い土地の登記が必要になったという。相続人は彼一人。だが、妙なことに、その土地にはなぜか二重の所有記録が残っていた。
「父が生前、知らないうちに売っていたんでしょうか」
依頼人はそう言ったが、表情はどこか曇っていた。
相続放棄か登記の罠か
サトウさんがひとこと、「この記録、怪しいですね」と呟いた。その言葉に、私はパソコンを叩いて登記簿の履歴を確認する。確かに、途中で奇妙な所有者変更がある。
しかも、その変更は相続発生日よりも後の日付で行われていた。
「ん?それって、、、」私は眉をひそめた。
亡き父の署名が語ること
後日、持ち込まれた父の署名入り委任状を見た私は目を疑った。それは、父の死後の日付が書かれていたのだ。つまり、この委任状は明らかに偽造されている。
「ええと……この署名、うちの父の字じゃないと思います」
依頼人はようやく打ち明けた。どうやら、実際に何が起きたのか本人も把握していないようだった。
登記簿の中にあった違和感
私は昔の漫画『名探偵コナン』のように、手元の資料に目を走らせた。あの作品なら、こういうとき何か決定的な証拠が見つかるんだ。そんな期待を胸に、ページをめくる。
すると、ひとつの決済書類の日付にズレがあることに気づいた。
「これだ……このズレが決定的だ」私は呟いた。
サトウさんの冷静な観察
「これ、コピーですよね。しかも、スキャンが雑。重ね印鑑もにじんでる」
サトウさんの観察力は恐ろしいほど的確だった。まるで怪盗キッドが仕掛けたトリックを見破るかのような鋭さに、私は思わず口をあんぐり開けた。
「やれやれ、、、君には敵わないな」
一枚のコピー用紙に潜むヒント
にじんだ印影、解像度の低い署名――それはすべて、元の書類が原本ではないことを示していた。依頼人の父の死後に誰かが登記を移すために偽造したのだ。
そして、その書類を提出したのは、依頼人のいとこである人物だった。
「これは完全に計画的ですね」とサトウさんが断言した。
元野球部の勘が働いた
私は昔の野球の試合を思い出した。最後の一球、投げるか牽制か迷ったときに頼りになったのは“勘”だった。今回も、直感が働いた。
「これ、家族ぐるみで仕組まれた詐欺かもしれない」
私は法務局と警察に相談を始めた。
書類の日付に潜む矛盾
該当の登記変更に使われた書類は、提出日よりも前に作られていた。だが、使用された印鑑証明の日付は、さらに後だった。時間が逆行している。
これでは、誰がどう見ても不正の証拠となる。
依頼人の顔が青ざめた。
やれやれから始まる行動
「やれやれ、、、こうなると書類の再提出も面倒だな」
私はぶつぶつ言いながらも、すでに対応策を考えていた。まずは登記の更正登記申請、その後に民事訴訟の準備が必要だ。
「サトウさん、証拠書類の整理お願い」
司法書士としての一手
私は静かに書類に判を押した。あとは、司法の場で真実が裁かれるのを待つのみ。だが、この一手が未来の不正を防ぐことになるのだ。
「正しい登記は、人の権利を守る」
自分に言い聞かせるように、私はそう呟いた。
サザエさん的隣人トラブルの真相
後日談として、いとこの家は隣人との境界トラブルを抱えていたという。どうやら、その土地を自分のものにして、売却してしまおうとしたらしい。
サザエさんで言えば、波平が隣の伊佐坂先生と境界で揉めるエピソードのような話だ。
だが、こちらは笑えない結末だった。
犯人は身近な人物だった
いとこは刑事告訴され、調査の過程で他にも数件の不正登記が発覚した。いわば登記を悪用した常習犯だったのだ。
「身内だからって油断しちゃダメですね」
サトウさんの言葉に、私は大きくうなずいた。
古い印鑑証明が示す犯行の証
証拠となったのは、期限切れ間近の印鑑証明書だった。それは通常なら提出されるはずのないもので、不正の痕跡をそのまま残していた。
印鑑という日本独特の文化が、今回の事件を解決へと導いたのだ。
私はその事実に、奇妙な感慨を抱いた。
故意か過失か見極めの瞬間
最後に争点となったのは、彼の行動が「故意」だったかどうか。だが、証拠が揃いすぎていた。過失を主張するには無理がある。
「このまま裁判ですね。ご協力ありがとうございました」
依頼人の声には、安堵と申し訳なさが混じっていた。
サトウさんの容赦ない指摘
「それにしても、先生が最初に気づいたの、缶コーヒーの賞味期限でしたよね」
サトウさんが皮肉交じりに笑う。確かに、日付の感覚には妙に敏感だった。
私は照れ笑いで誤魔化すしかなかった。
冷静に暴かれる嘘
全てが明るみに出たとき、私はふと思った。人がつく嘘は紙の中に必ず滲み出るものなのかもしれない。
登記簿は、ただの帳簿ではない。そこには、人の欲望と罪と、そして守るべき正義が刻まれている。
やれやれ、、、また一つ勉強になったな。
罪を背負う者と記録に残るもの
事件は終わった。依頼人は涙を流しながら頭を下げた。私は手を振って見送りながら、少しだけ空を見上げた。
「サトウさん、今日もお疲れ様」
「はい、先生も。ミスしないように」塩対応は変わらなかった。
登記簿が語ったのは真実だけ
紙の中には嘘があった。だが、それを照らしたのもまた、紙だった。
登記簿。それは、誰かの不正を照らし出す正義の鏡でもある。
私は机の上の資料を片付けながら、静かに次の来訪者を待った。