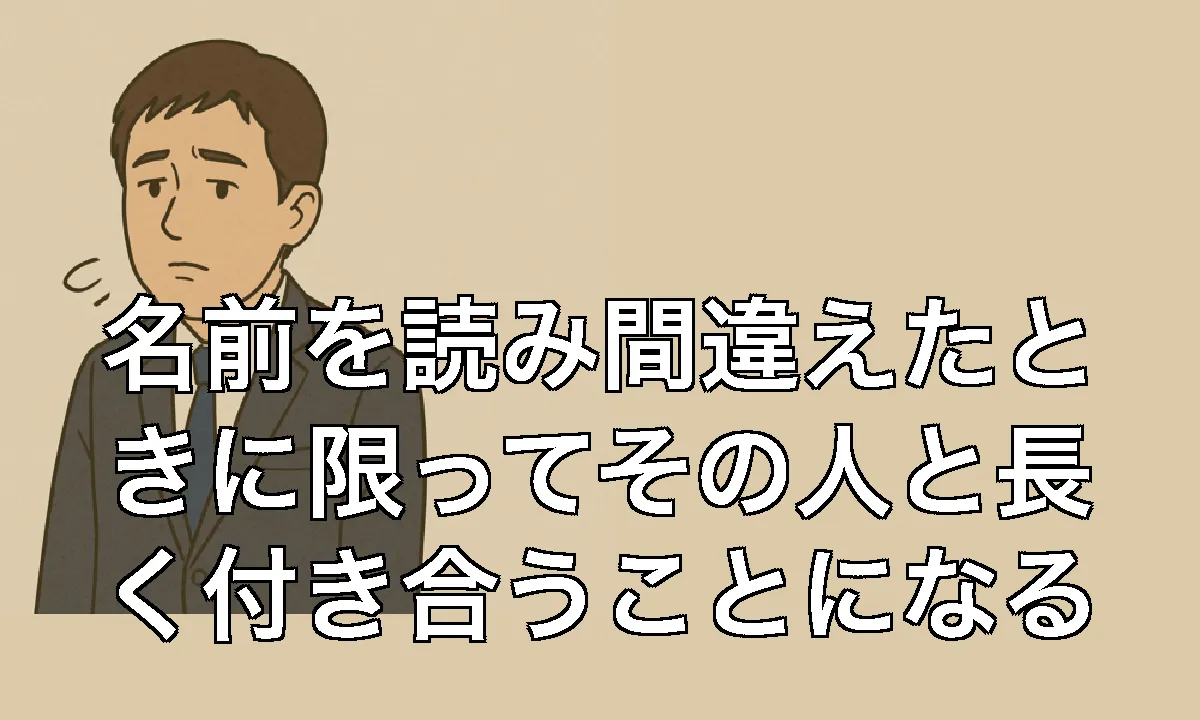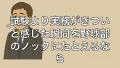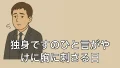間違えた名前は忘れられない
司法書士という職業柄、たくさんの人と接しますが、名前を読み間違えた時の気まずさはなかなか消えません。特に初対面のとき、ふとした油断で名前を間違えると、空気が一瞬で凍りつくのを感じます。私も何度か経験があり、そのたびに「なぜ確認しなかったんだ」と後悔するのですが、名前って見た目と読みが一致しないことが意外と多いんですよね。そして、そういう相手に限ってなぜかその後もずっと関わることになるから、なんとも皮肉なものです。
初対面でやらかすともう修正できない
たとえば以前「大久保さん」と書かれた名刺を見て「おおくぼさん」と呼んだら、「だいくぼです」と冷静に訂正されたことがありました。小声で「すみません」と返したものの、その後の打ち合わせの内容がまったく頭に入ってこなかった。名刺にフリガナがなかったのも原因ではありますが、やっぱり最初の一言が相手に与える印象は大きい。こっちは一生懸命対応しても、相手の中では「名前を間違えた人」になってしまうのがつらいところです。
「あ、そう読むんですね…」からの気まずい沈黙
この「そう読むんですね…」という返答がまた絶妙に気まずいんです。相手は責めているつもりはなくても、心の中で「調べてから来いよ」と思っているのが伝わってくる。沈黙の時間が長く感じられて、もう心の中では「リセットボタンがほしい」と何度も願ってしまいます。笑顔でごまかそうとしても、顔が引きつるだけ。これは本当に、どんなに経験を積んでも慣れることがありません。
自己紹介シーンに潜む罠 名前フリガナの落とし穴
最近はZoomや電話のやりとりも多いですが、音声だけでの自己紹介はさらに厄介です。フリガナが記載されていない名簿やデータだけで対応しないといけないことが多く、読み仮名に対する警戒が緩む。あとでメールで正式な読みを確認して赤面することもありました。とくに外字や当て字が多いご時世、「普通こう読むでしょ」という前提が通用しない。これはもう、油断した方が悪いとしか言えません。
その後の関係に与える微妙なダメージ
名前を間違えた直後は謝って終わりでも、実はそのあとが問題だったりします。何度も顔を合わせる相手なら、毎回その最初の失敗が心の中で蘇る。そして相手のほうも、表では普通に接してくれていても、どこか一線を引いているように感じてしまう。それが本当かどうかはわかりません。でもこちら側は、もう自分の中で「一度間違えた相手」としてずっと引きずることになるのです。
訂正するタイミングを逃すとこうなる
中には、相手が気を使って訂正してこないパターンもあります。こちらが間違った読み方を続けてしまい、数ヶ月後になって他の人との会話で正しい読みを知る、なんてことも。もうそのときには訂正するタイミングを完全に逃していて、今さら「すみません」とも言えず、ただただ申し訳なさが積み重なっていく。これは精神的にダメージが大きいです。
ミスした側だけが一生引きずる現象
不思議なもので、名前を間違えた側のこちらは何年経ってもその出来事を覚えているのに、相手はもう忘れていることが多い。でもこちらは、次に会ったときも「また名前を間違えたらどうしよう」と緊張してしまい、そのたびに余計な汗をかく。これって、ある意味ではトラウマです。名前を読み間違えるって、意外と深く心に残るものなんです。
司法書士という立場と名前の扱い
司法書士の仕事において、名前を正確に扱うことは命綱のようなものです。登記簿謄本や各種書類で一文字でも間違えると、取り返しのつかないことになります。そのため、私は人の名前には人一倍慎重になっているつもりですが、それでもときどきやらかす。どれだけ注意していても、疲れていたり焦っていたりすると、小さなミスが起きてしまう。それがまた、精神的にこたえるんですよね。
依頼者の名前を読み間違えたらどうなるか
登記の手続きでは、依頼者の名前を正確に記載しなければなりません。もし読みを間違えたまま進めて、たとえば印鑑証明と異なる形で書類を作ってしまったら、最悪の場合はやり直しになります。実際、昔一度だけ「斉藤」の表記を誤って手続きを進めてしまい、相手方から「違います」と連絡が来たときには血の気が引きました。それ以来、どんなに忙しくても、氏名は二重チェックすることにしています。
登記簿に誤記は許されない現実
登記の世界では、「ちょっとした間違い」が通用しません。一文字違えば別人になってしまいますし、仮に誤記のまま通ってしまっても、後から修正するのには手間もコストもかかる。依頼者からの信頼にも関わるので、毎回書類を作るたびに名前欄だけは異常なほど慎重になります。事務員にも「ここだけは三回見直して」とお願いしているほどです。
読み仮名ミスが信頼を失う引き金になる
特に電話やメールだけのやりとりで、こちらが先に名前を呼ぶ場合は緊張します。間違えた瞬間、「あ、適当な事務所かもしれない」と思われてしまうリスクがある。そういう小さなミスの積み重ねが、口コミや評価に響く時代です。だから私は、読みが怪しいときは正直に「失礼ですが、お名前の読みを教えていただけますか」と聞くようにしています。恥をかくのは一瞬ですが、信頼を失うのは致命的です。
封筒に書く名前で二重チェックする癖
封筒の宛名を書くとき、昔は正直「苗字だけでいいか」と思っていたこともありました。でもある日、「お名前、間違ってますよ」とやんわり指摘されたことで、自分の甘さを痛感。今では、封筒の宛名も必ず事務員と一緒にチェックするようにしています。失礼がないよう、丁寧に文字を整え、正確にフルネームで書く。こうした積み重ねが、信頼関係の土台になると信じています。
字は読めても音が読めないジレンマ
司法書士の仕事では書類が中心なので、名前の「字面」はよく見るけれど、実際に音読する機会は案外少ないんです。そのため、頭の中で勝手に読み方を決めてしまうことが多く、それがズレていると危険。だからこそ、フリガナの有無に関係なく、確認する習慣が必要です。目で見るだけではなく、声に出すことの大切さを日々実感しています。
事務員との確認会話が妙に慎重になる瞬間
「これ、なんて読むんだろう?」と事務員に聞くとき、私はちょっと緊張します。間違って覚えていたら恥ずかしいし、逆に事務員も曖昧なときがある。そこで「多分○○さんだと思いますけど、念のため確認しておきますね」と言い合う、あの独特の慎重さ。こういう小さなやりとりにも、事務所の文化が出るなと感じます。忙しい中でも、こうした確認のひと手間がミスを防いでくれるのです。
そういう人に限って仕事で長く付き合う
不思議なことに、名前を読み間違えた人に限って、その後ずっと仕事で関わることが多いんです。たまたまなのか、名前のインパクトが強くて印象に残るからなのかはわかりません。でも、一度失敗した相手ほど、なぜか二度三度と連絡が来て、最終的には「うちの登記は全部先生にお願いしてます」と言われる。あの初対面のミスが嘘のようです。人生って、ほんと皮肉だなと思う瞬間です。