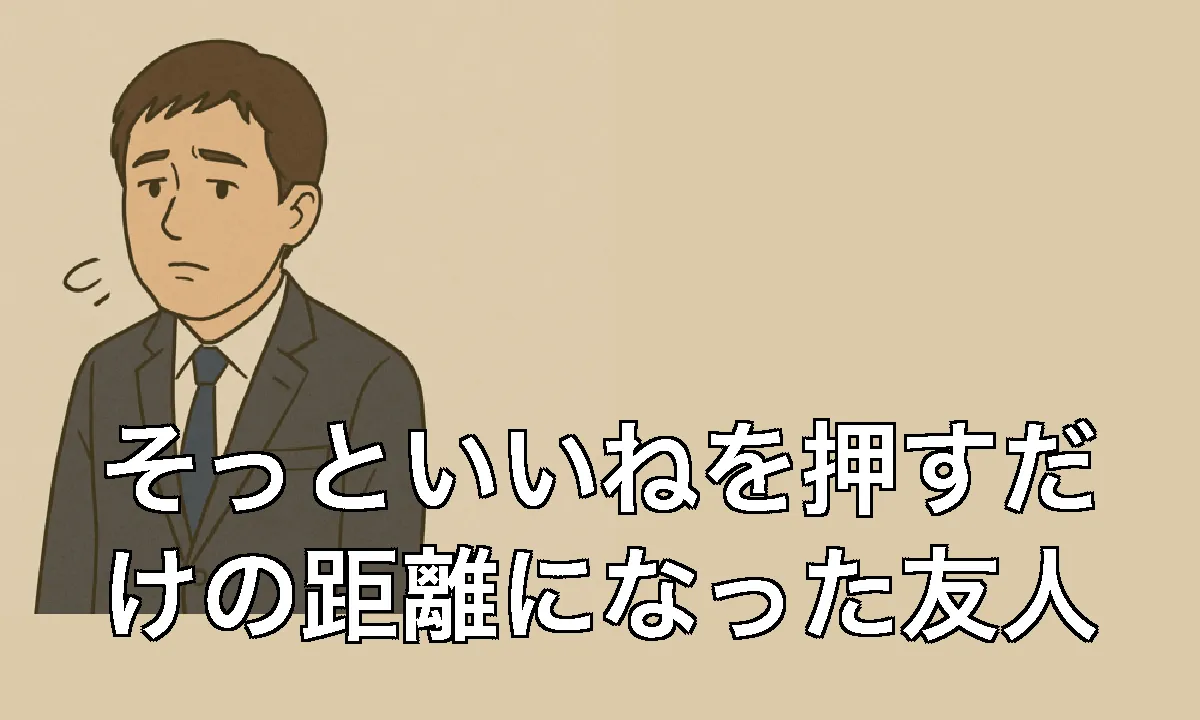そっといいねを押すだけの距離になった友人
司法書士として地元で事務所を構えて十数年。高校時代、汗を流した野球部の仲間たちも、今ではすっかり立派な父親になっている。SNSを開けば、そんな友人たちの子供の運動会、七五三、入学式の写真がずらりと並ぶ。そのたびに「いいね」をそっと押すのが習慣になっている。でも、それ以上の言葉が出てこない。「すごいね」「大きくなったね」とコメントしようとして、指が止まる。祝う気持ちはあるのに、なぜか胸がチクリと痛むのは、置いてけぼりにされたような気がするからかもしれない。
あの頃は一緒にふざけていた
今の彼らの姿を見て思い出すのは、くだらないことで笑い合っていた高校時代。野球部の練習終わり、コンビニの前でアイスを食べながら「将来は絶対プロ行く」とか真顔で語っていた自分たち。誰一人プロにはなれなかったけど、地に足つけて生きている。そんな彼らの家族写真は、なんだかまぶしくて、直視できないときもある。昔は同じ目線だったのに、今は彼らの人生のフェーズがひとつ先に進んでしまった気がして、自分だけが取り残されたような気分になる。
缶ジュースを賭けて野球の素振りをした夏
グラウンドに残って、夕暮れのなか素振りを繰り返した夏の日。外野のフェンスを越えたら缶ジュース奢り、とか言ってはしゃいでいた。あの頃は誰もが“今”を全力で生きていたし、“未来”なんてぼんやりしていた。まさか40を過ぎて、SNSの写真一枚に心が揺さぶられるようになるとは、あの時の自分には想像もできなかった。缶ジュースで勝った負けたと笑いあった仲間が、今では子どもの教育費の話をしている。その変化がうらやましいのか、寂しいのか、自分でもよくわからない。
グローブとバットと、くだらない話の記憶
今もたまに実家の押し入れからグローブを取り出すと、土の匂いと一緒に、あの頃の笑い声がよみがえる。バットの重さや、キャッチボールの時の「痛っ!」という声も。別に特別な才能があったわけじゃない。ただただ楽しかった、無駄な時間が愛おしかった。なのに、今は「お疲れ様です」「至急でお願いします」といった言葉ばかりが飛び交う毎日。そのギャップに、ふと、ため息が出ることがある。
投稿の中でだけ成長していく“誰かの子供”
友人たちの子供を、まるで親戚のような気持ちで見ている自分がいる。でも、どこか他人事でもある。会ったこともない子供たちの成長を、毎月のように写真で見せられ、「もう小学生か」「顔が親に似てきたな」と、なんとなく感じる。でも、画面越しの付き合いに過ぎないという距離感が、微妙に心をざわつかせるのだ。リアルな接点がないぶん、そこに“自分が存在しない”ことを突きつけられる気がする。
「大きくなったね」に込められた疎外感
「大きくなったね」とコメントしようとするたびに、指が止まる。画面の中の幸せは本物なのだろうし、それを見ている自分に嘘はない。でも、そのコメントの裏側にある「自分はそうじゃない」感情に蓋をしたくなる。結婚もしてない、子供もいない、自分の人生に“節目”らしいイベントがしばらくない。そう気づいてしまうと、誰かを祝う言葉すら重くなってくるから不思議だ。
本当は写真に映る自分も想像していた
本当は、写真のすみにでも自分が映っているような未来を、どこかで想像していたのかもしれない。友人の家族写真の中に「なぜか写ってる独身の友達」みたいな立ち位置でもいい、そういう場所があったら少しは気が楽だったのに。現実は、誰のアルバムにも映らない独りの背中。司法書士として仕事はしているけれど、人として誰かの記憶に残るような“人生の参加者”にはなれていない気がする。
なぜか“いいね”を押す指が重いとき
「いいね」ひとつ押すだけなのに、どうしてこんなに葛藤があるのだろう。友人の幸せを祝いたい気持ちはある。でも、その裏で、自分の現状を見つめざるを得なくなる。たとえば、子供を持つことの可能性や、老後の孤独、そういった未来を意識してしまう。そんなとき、つい「いいね」すら押せず、画面をそっと閉じる日もある。自分の中の“割り切り”が、まだ足りないんだろう。
祝う気持ちと、置いていかれる気持ち
「おめでとう」って気持ちはある。でも、心のどこかでは「置いていかれたな」という感覚がこびりついている。人生に勝ち負けなんてないと頭ではわかっていても、家庭を持つ友人たちの投稿は、なんとなく“勝者の証明”みたいに見えるときがある。だから余計に、自分が小さく感じてしまう。たぶん、それが「いいね」を押す指を重くしているんだと思う。
比べてないと言い聞かせても湧く感情
「人と比べないようにしよう」と何度自分に言い聞かせたかわからない。でも、SNSの世界は、常に“比較”を生み出す。自分の生活にはない光景を見せられ続けて、心が揺れない方が不自然だ。司法書士の仕事では、日々冷静であることが求められるけれど、人間としての感情までは制御できない。そういう“弱さ”があることも、自分の一部として認めることにした。
独身司法書士の休日は誰にも見られていない
誰にも見られない、誰にも共有されない休日。それは自由である一方で、少しの虚しさも伴う。仕事が終わったあと、誰かと飲みに行くこともなく、ひとり鍋をつついて終わる夜。誰かに「それもいいですね」と言われたら「まあ、気楽ですよ」と答える。でも本音は「たまには誰かと過ごしたい」ですらない。どうしていいかわからないまま時間だけが過ぎていく。
誰とも共有されない鍋焼きうどんの写真
日曜の夜、スーパーで買った鍋焼きうどんを、誰にも見せずに食べる。インスタにあげるような見栄えでもないし、見せる相手もいない。昔はラーメンを食べに行くだけでも、誰かを誘った。でも今は、黙って席に座り、黙って食べて帰るだけ。誰かと一緒に味わう喜びというのが、どれだけ特別なものだったのか、失ってから気づくのはだいたいこういう日常の中だ。
孤独に慣れたつもりの夜の静けさ
夜、事務所からの帰り道。街灯の下で、ふと立ち止まって空を見上げると、やけに静かだと感じる。ああ、自分は今日誰とも言葉を交わしていないな、と気づくことがある。独りでいることに慣れたつもりだったけど、慣れたのは「諦め」かもしれない。この静けさに、もう少し意味を見出せたらいいのにと思いながら、自宅の鍵を開ける。
モテなかった人生の延長戦で見つけた小さな居場所
学生時代から一貫してモテなかった。それが今の独身生活につながっているのは間違いない。恋愛に自信もなければ、押しの強さもない。でも、そんな自分でも司法書士という仕事を通じて、少しだけ人の役に立てていると思える瞬間がある。それだけが、今の自分を形作っていると言ってもいい。
事務員さんが笑ってくれるからまだ救われる
たった一人の事務員さん。彼女が時々笑ってくれるのが、地味に救いになっている。「先生、またコンビニ飯ですか?」なんて軽口を叩かれながら、どこかほっとしている自分がいる。恋愛感情とかじゃなくて、ただ“誰かと一緒にいる時間”があるということ。それだけで、どれだけ心が保たれているか、気づく人は少ないかもしれない。
「今日も大変ですね」の言葉が沁みる
夕方、疲れた顔で戻ってきたときに言われる「今日も大変ですね」の一言。気遣いでも社交辞令でもいい。でも、その言葉だけで「一人じゃない」と感じられることがある。言葉には力がある。たぶん司法書士としてじゃなく、人として、そういう“関わり”があるから、なんとかやっていけてるんだと思う。
それでも仕事に向かう背中は嘘じゃない
どんなに孤独であっても、仕事に向かう背中だけはごまかしていない。目の前の依頼に応える、その繰り返しが日々をつなげてくれている。誰にも見られない努力かもしれないけど、自分の中ではそれが“生きている証拠”になっている。誰かの人生に関わるという責任が、今日もまた自分を立たせてくれる。
誰かの役に立っている実感だけが支え
登記ひとつ取っても、その向こうには家族の生活や、夢がある。淡々と処理しているように見えて、ひとつひとつの手続きに意味がある。そう思えるから、この仕事を続けられている。たとえ“いいね”を押すだけの関係になった友人たちとも、同じように誰かの人生を支えているという意味では、どこかでつながっていると思いたい。
登記簿の文字の向こうにある“誰かの生活”
ただの文字の羅列に見える登記簿。それでも、そのひとつひとつが誰かの人生の証明になっている。今はそっと“いいね”を押すだけの距離かもしれない。でも、自分にも、自分なりの関わり方がある。独りでも、誰かの役に立てるなら、それでいい。そう信じて、また明日も仕事に向かうだけだ。