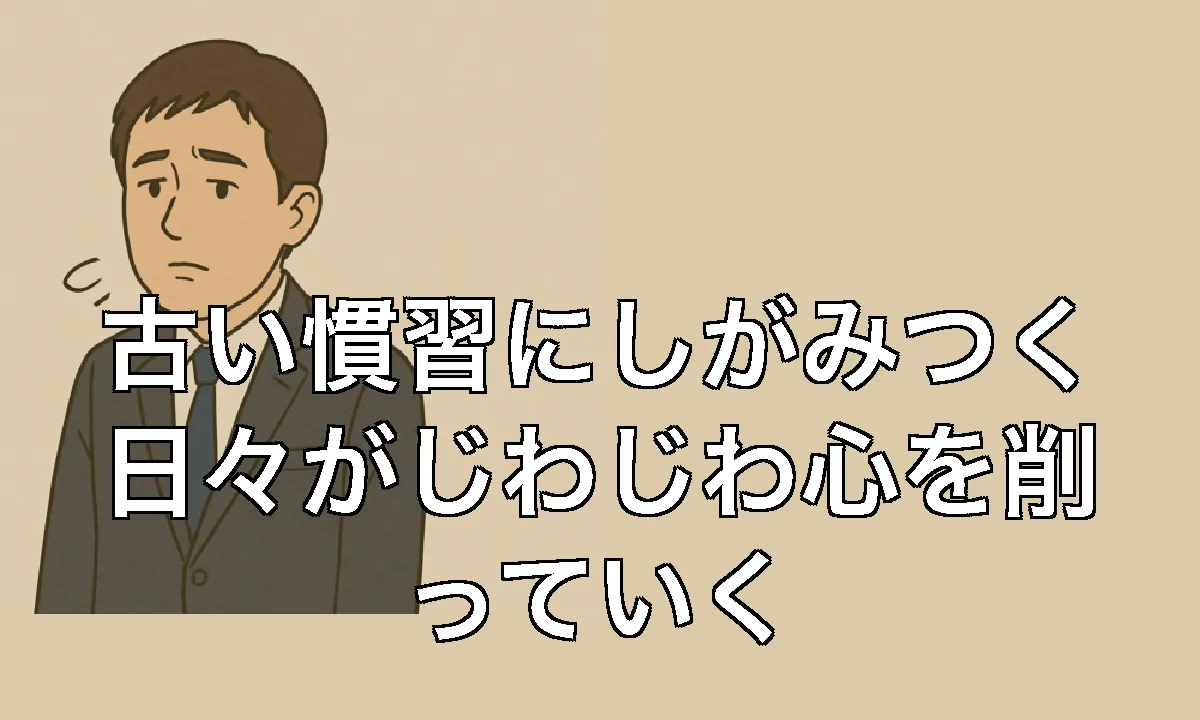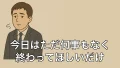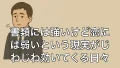古い慣習にしがみつく日々がじわじわ心を削っていく
慣習という名の無言の圧力
「前からこうしているから」。その一言が、どれだけ多くのことを諦めさせてきたか。司法書士という職業は、法律と制度に関わるからこそ、正確さや安定性が求められる。でもその裏には、長年変わらないやり方を当然とする空気がある。僕のような地方の司法書士事務所では、それがより色濃く残っていて、「変えること」そのものがタブー視される。気づけば、その空気に逆らう気力すら削がれていくのを感じる。
「前からこうしてるから」で片づけられる毎日
登記簿の写し一つ取るにしても、どこの法務局の誰にどう連絡するかまで、決まったやり方がある。電話のかけ方、書類の順番、封筒の書き方……全部「昔からこうしてる」で済まされる。改善しようと提案しても、「余計なこと言わないで」と笑われる。いや、笑ってるけど目は笑ってない。新しいやり方が必ずしも正しいとは思っていないけど、せめて考える余地くらいは持たせてくれてもいいんじゃないか。そう思いながら、今日も同じ順番で書類を並べている。
変えたいのに変えられない空気
実は何度か、電子申請の仕組みや、書類管理のクラウド化を事務所内で試みようとしたことがある。でも、「それって誰が責任取るの?」という言葉が必ず返ってきた。ミスが怖いのはわかる。でも、新しいものを取り入れることでしか、効率やミスの削減なんて見込めないと思うんだ。とはいえ、たった一人の事務員さんに無理はさせられないし、僕一人が張り切ったって変わらない。その無力感が、余計に心を重くする。
事務所の中にもある小さな固定観念
「司法書士の机はきちんとしていないといけない」「訪問者にはお茶を出さなきゃ失礼」……そういった細かなルールも、実は見えないプレッシャーになる。僕自身、元はずぼらな性格だったけど、職業柄きちんとしなきゃと自分を抑えつけるようになった。でもふと、誰のためのルールなのか分からなくなる瞬間がある。もしかしたら、ずっと昔に誰かが作った「正しさ」を、今でも惰性で続けているだけなのかもしれない。
若い世代との感覚のズレ
たまに地元の若い司法書士と話す機会がある。彼らは僕が経験してこなかったツールや仕組みを使いこなし、効率的に仕事を進めている。それは正直うらやましい。でも一方で、こちらのやり方を「古い」と笑われると、複雑な気持ちになる。時代に取り残されている感覚と、それでも変われない自分との板挟み。これはもう、僕の中にある“慣習”との闘いなのかもしれない。
昭和の空気を引きずる自分に気づく瞬間
「元気があれば何でもできる」「男は黙って仕事しろ」——こんな言葉を信じてきた。野球部で育った僕は、根性論と上下関係が染み付いていた。司法書士になってもその癖が抜けず、「後輩はまず黙って見てろ」と思っていた時期もある。でも、今は違う。話し合いが大事だって、ようやくわかってきた。でも気づくのが遅かったのかもしれない。昔のやり方にしがみついていた分、損していたのは自分だったんじゃないかと、今になって思う。
元野球部の上下関係が邪魔をする
どうしても、「言い返されたら負け」みたいな感覚が抜けなかった。だから若い人の意見を受け入れるのが苦手だった。でも時代は変わっていて、今は「話を聞く力」が求められている。それが頭ではわかっていても、体がついてこない。そんな自分にイライラする。でも変わるのが怖い。ずっとこのスタイルでやってきたから、変えた途端に崩れてしまいそうな気がして。そんな風に感じること自体が、もう古いのかもしれない。
でも後輩には優しくしたいという矛盾
実は後輩と飲みに行ったとき、「先生、もっと気楽に話してくださいよ」と言われたことがある。そのとき気づいた。僕は自分を固くしていたんだなって。本当はもっと柔らかく、フラットに接したいのに、勝手に“先生らしくあらねば”という殻をかぶっていた。自分で自分を縛っていたのかもしれない。そう思うと、少しだけ肩の力が抜けた。その後輩には、今でも感謝している。
仕事の効率を上げたいのに足を引っ張るもの
一人で事務所を運営していると、どうしてもすべての業務を自分で管理しなければならない。だからこそ、効率化は死活問題だ。でも実際は、効率を上げようとすると古い慣習が邪魔をする。たとえば紙文化。いまだに紙でのやりとりが中心で、PDFを送っても「紙でください」と言われるときがある。時代は進んでも、現場は変わらない。そんなギャップに、もどかしさを感じる。
紙文化との戦いはいつ終わるのか
「紙が安心」「原本が一番」——そんな言葉を何度聞いたか分からない。確かに、紙には紙の良さがある。でも、紙の保管、送付、印刷にかかるコストと時間を考えると、どう考えても非効率だ。特に繁忙期、紙が山積みになっていく机を見るたびに、デジタル化の夢が遠のく。僕の目の前にあるのは、未来じゃなくて紙の壁。それをどうにかしたくて、でもできなくて。結局、今日も紙に囲まれて過ごしている。
ハンコがいるのかいらないのか問題
最近では脱ハンコの動きもあるけれど、僕の周囲ではまだまだ「印鑑」が絶対の存在。とくに役所関係は、未だに印鑑の押し忘れで差し戻されることがある。電子署名も進んできてはいるけど、印鑑があることで“ちゃんとしている感”が出るという声も根強い。便利さと信用のせめぎ合い。どちらも大事だけれど、その狭間で現場は揺れ続けている。
電子申請の普及が遅れる現場のリアル
電子申請に対応しているはずの制度も、実際に利用するとなると「分かりにくい」「不具合が多い」など課題だらけ。サポートも限定的で、結局使いこなすまでに時間がかかる。結果的に「やっぱり紙の方が早い」となる悪循環。僕も何度かトライしたけれど、結局諦めたこともある。現場と制度の間には、まだまだ深い溝がある。その溝をどう埋めていくかが、これからの課題なのだろう。