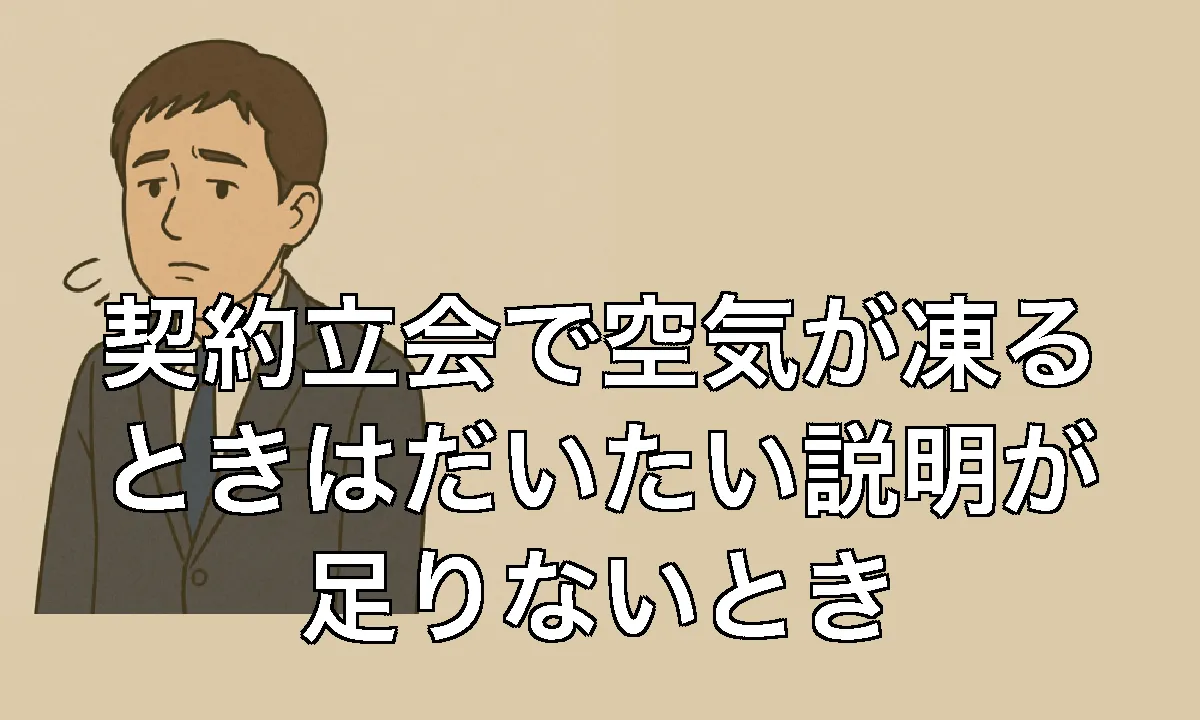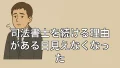予想外の展開は突然やってくる
契約の立会いというのは、たいていの場合は淡々と進みます。事前に必要な書類を揃え、段取りを確認し、時間通りに現地に到着する。それだけでホッとした気分になることもあります。しかし、気を抜いたときに限って、予想外のことが起きるものです。とくに、不動産業者と買主・売主の間に微妙な温度差があるとき、司法書士としての立場が一気に試される瞬間が訪れます。
和やかな開始から一転するあの瞬間
あるとき、売主さんがご年配の女性、買主さんが若いご夫婦という案件がありました。開始当初はお茶も出してくださって、和やかに話が進んでいたのですが、物件に関する引き渡し条件についての説明の最中に、買主さんの顔色が変わりました。「それ、聞いてないです」と一言。場が一瞬で凍りつきました。
「え?そんな話聞いてませんけど」
売主さんが悪びれる様子もなく、「業者さんから伝わってると思ってたわよ」と言ったことで火に油。買主さんは顔をしかめ、「この場でそんなこと言われても困ります」と憤慨し、僕はその間に座って「どう収めよう」と冷や汗をかいていました。間に立つって、こういうことか、と何度思ったかわかりません。
お客様が声を荒げると全員が黙る
普段温厚な買主さんが、思わず声を荒げた瞬間、同席していた全員が無言になりました。こうなると、司法書士である私にとっても冷静さを保つのが難しい。業者さんが横で「いや、ちゃんと伝えましたよ」と言えば言うほど、責任の押し付け合いが始まり、現場の空気はますます重たくなるのです。
原因はたいてい事前説明の甘さ
こういった事態になると、振り返るのは「どこで防げたか」。たいていの場合は、事前の確認や説明が不十分だったことが原因です。司法書士として、書類上のことだけではなく、契約内容の実務的な部分にも少し踏み込むべきだった、と反省することになります。
仲介業者任せにしていた自分への反省
業者さんがしっかりしているから大丈夫、とタカをくくっていたのが間違いでした。実際には、伝言ゲームのようになっていて、細かな内容が抜け落ちる。こちらが「当然伝わっているはず」と思っている内容ほど、相手にはまったく届いていなかったりします。事務所に戻ってからひとり反省会です。
書類の説明だけじゃ信用は生まれない
「この書類にサインしておいてください」だけでは、相手は納得しません。人と人のやりとりである以上、声のトーン、間の取り方、ちょっとした補足説明が安心感につながります。とくに高額な不動産取引に関わる立会いでは、そのひと言が信頼を左右します。
事務所に戻ってからの後悔とため息
帰り道はだいたい、反省とため息でいっぱいです。あの時ああ言えばよかったとか、もっと笑顔で対応すべきだったとか。契約が終わった後も、気分的には終わっていない。家に帰ってシャワーを浴びながらも、心の中では「失点」を悔やみ続けています。
「もっとちゃんと話せばよかった」が毎回の感想
場の空気が悪くなったとき、後で必ず思うのは「やっぱりあの時に一歩踏み込んで話しておけばよかった」ということです。準備不足ではなかったのに、想定不足。相手の気持ちにもっと敏感になっていれば…というのが、毎度毎度の反省パターンです。
落ち込むのは自分だけじゃない
現場でうまくいかないと、事務員さんにも無意識に影響を与えてしまいます。「大丈夫でした?」と気を遣ってくれる彼女に、「まあまあだったよ」と答えながら、自分のミスを思い返しては胃が重くなる。やさしい彼女にまで気を遣わせてしまう自分に、また落ち込むわけです。
事務員にも申し訳ないと思う夜
帰宅後、事務所の明かりを消しながら、「今日もまた迷惑かけたな」と思うことがあります。彼女は何も言わないけど、表情でわかることが多い。忙しい中でも一生懸命やってくれている彼女に、もっと良い環境で働かせたいのに、なかなかそれができない。それもまた、独身の司法書士としての葛藤です。
でも立ち会いが嫌いじゃない理由
毎回ドタバタしていても、なぜかこの仕事が嫌いになれません。うまくいかないことがあっても、そこに人間関係のリアルがある。書類を扱うだけの機械的な仕事では味わえない、現場の緊張感と、成功したときの充実感。それが自分をこの職業に引き留めています。
直接顔を見て話すことの意味
たとえば、書類だけのやりとりではどうしても無機質になりがちです。でも、実際にお客様と対面して話すと、表情やしぐさから多くのことが伝わってきます。「この人はちょっと不安そうだな」と感じたとき、ほんの一言でも声をかけると、表情が和らぐ。そういう瞬間が好きなのかもしれません。
書面では伝わらない温度感
同じ説明でも、口頭で伝えるとニュアンスが加わります。相手の反応を見ながら、「あ、ここはもっと詳しく説明したほうがいいな」と感じ取ることができる。そうしたライブ感のある対応は、司法書士として成長させてくれる場でもあります。
元野球部の自分が大事にしてる「現場」感
学生時代、野球部で汗まみれになっていたころを思い出します。練習でミスしても、グラウンドに立つと気持ちが引き締まった。いまはグラウンドが契約の立会現場に変わっただけ。やっぱり、自分は人と向き合う場が好きなんだな、と感じています。
誤解が解けるときの安堵感は格別
立会い中、緊張の糸がほどけて、全員が笑顔になる瞬間があります。それまで重かった空気が一気に和らぐ。司法書士としてその場に立ち会えることに、やりがいを感じるのです。だからこそ、説明不足で空気を凍らせるようなミスは減らしたい。
「やっぱり司法書士さんがいてよかった」
最後にそう言ってもらえると、「よし、なんとか役目は果たせたかな」と思えます。誰もが不安な気持ちを抱えている中で、その不安を少しでも和らげる存在になれたのなら、それだけで救われる気がします。そんな言葉が、次の現場へ進む原動力になります。
その一言でまた明日も頑張れる
たった一言でも、「ありがとう」「助かりました」と言ってもらえると、それまでの疲れがすっと消えていきます。どれだけ落ち込んでいても、その言葉を思い出せば、「まあ明日もやってみるか」と思える。司法書士という仕事は、そういう優しさに支えられていると感じます。