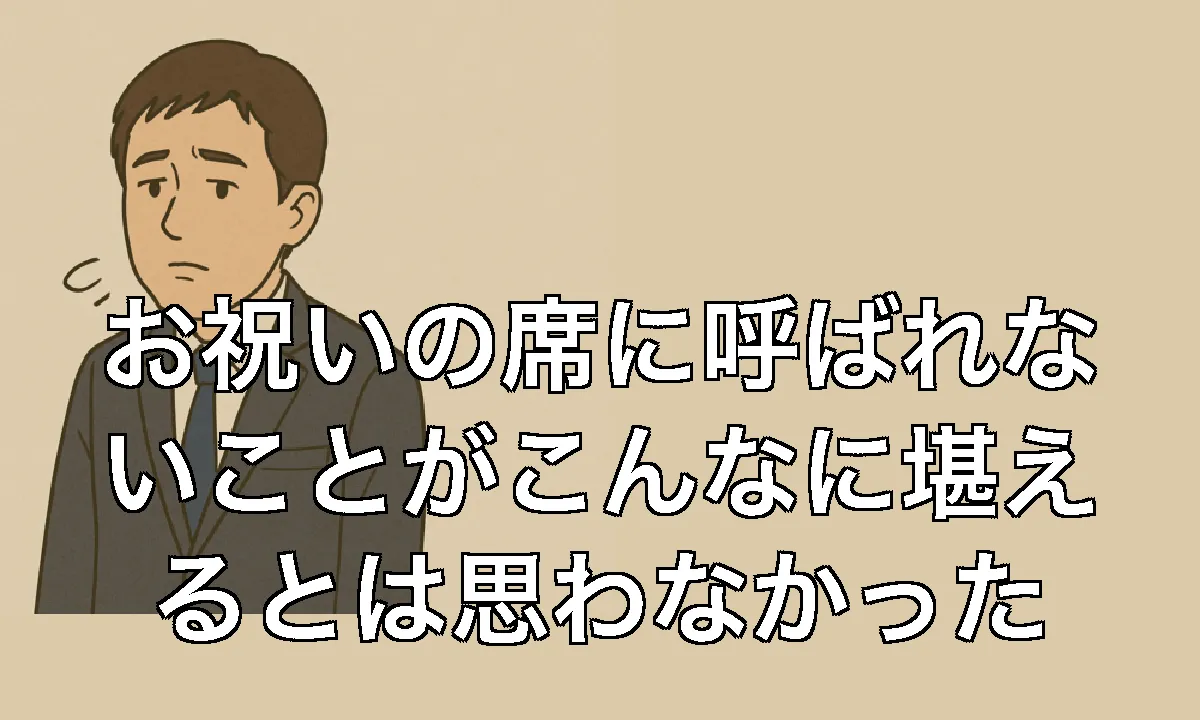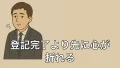お祝いの連絡が来ない日曜日の午後に
日曜日の午後、ひと息ついたタイミングでスマホを開く。SNSのタイムラインには、誰かの結婚式、赤ちゃんの誕生、同窓会的な集まりの写真がずらり。見た瞬間、「ああ、また呼ばれてない」と、胸の奥がチクリと痛む。別に行きたかったわけじゃない、なんて強がってみても、自分だけが輪の外にいるような感覚は、どうしても拭えない。司法書士として地元で開業して十数年、忙しい毎日を送ってきた。でも、だからといって孤立していい理由にはならないはずなのに。
タイムラインが賑やかなほど胸がざわつく
「みんな元気そうだな」と思いつつ、写真を指でスクロールする。楽しげな笑顔、乾杯する姿、ケーキカット。そんな投稿が続けば続くほど、どこか置いてけぼりにされた気持ちが膨らんでいく。正直、ちょっとした妬みすら混ざることもある。いやらしい感情だと自覚はしているけれど、それでも「なんで自分だけ呼ばれないんだろう」と思ってしまう自分がいる。誰かと繋がっていたい、けれど自分は呼ばれない。そのジレンマに、ふと疲れてしまうことがある。
「仲間外れ」というより「もう別世界の人間」
単なる仲間外れというより、「ああ、自分はもう別の世界に行ってしまったのかもしれない」と思わされるのがつらい。地元で仕事をしていても、世間の感覚とズレていく。結婚して家庭を持っている友人たちと、独身で毎日書類と向き合う自分。話題も、価値観も、自然と噛み合わなくなっていく。だから声がかからないのも当然だとわかってはいる。でも、理解と感情は別物だ。寂しさの波は、理解という堤防を簡単に越えてくる。
既読スルーのような感覚が胸に刺さる
誰かに忘れられているというのは、既読スルーに似ている。目の前で明確に拒絶されたわけではない。けれど、「あなたのことは気にしていませんよ」という無言のメッセージが漂ってくる。地味にこたえる。特に、こちらからは定期的に近況報告や連絡をしているのに、相手からの反応が薄いとき。「自分だけが関係を維持したいと思っているのかな」と虚しさが募る。相手に悪気がないだけに、余計にしんどい。
昔は呼ばれていた記憶が逆につらい
若い頃は、呼ばれることのありがたみなんて考えたこともなかった。高校時代、野球部の仲間たちとは、何かと理由をつけては集まっていたし、誰かの結婚となれば「当然来てくれるよな?」なんて言われたものだ。それが今は、何も言われないし、気づけば集まりすら知らされない。昔と比べてしまうからこそ、今の自分の立ち位置が際立ってしまう。思い出が美しければ美しいほど、現実との落差に打ちのめされる。
野球部時代は声をかけてもらえていた
当時の自分は、どちらかといえばムードメーカーだった。試合中もベンチで声を張り上げ、みんなを鼓舞していた。ミスしても笑って励ますタイプで、人の輪の中心にいるのが自然だった。そんな自分が、今では声もかからず、どこにも属していない。あのときの仲間たちと、今も何かしらの縁があると思っていた自分が甘かったのだろうか。あの頃の自分が、今の自分を見たらどう思うだろう。
地元にいるのに呼ばれない不思議
一番やるせないのは、自分がいまだに地元にいて、距離的には誰よりも「呼びやすい存在」であるはずなのに、呼ばれないことだ。東京や大阪に出た友人たちが呼ばれて、自分だけが呼ばれていないことすらある。たまたまかもしれない。でも、何度も重なると偶然では片付けられなくなる。なにか理由があるのか?自分に嫌われるようなことをした覚えはないのに、いつの間にか「呼ばれない人」になっていた。
司法書士という仕事が距離をつくっているのか
ふと立ち止まって考える。「司法書士だから」というのが一因なのかもしれない。人の相談に乗る仕事だからこそ、プライベートな部分には踏み込めないし、踏み込まれないことも多い。真面目で堅い印象があるこの職業が、自然と人を遠ざけてしまっているのではないかと、最近よく感じる。誇りを持ってこの仕事をしている。けれど、誇りだけでは埋められない空白が、確かに存在している。
「忙しそうだから」という断り文句に含まれる温度差
「忙しそうだから声かけづらかった」——よく言われる言葉だ。一見気遣いに見えるけれど、裏を返せば「あなたの存在がそこまで重要じゃない」ということなのかもしれない。善意で言ってくれているのは分かる。けれど、その気遣いの中には、温度差がある。仕事を理由に誘われないというのは、ある意味一番切ない理由だ。忙しいのは事実。でも、誘われるだけで、きっと心が少し軽くなる。
本当に忙しいけど、声だけでもかけてほしい
確かに、日々の業務はハードだ。書類、調整、提出、対応、毎日がフル回転。それでも、「声だけでもかけてほしい」と思うのは、わがままだろうか。予定が合わなくてもいい、参加できなくてもいい。でも、「来る?」と一言あるだけで、全然違う。呼ばれること自体が、存在を認められているようで、嬉しいものなのだ。気づいてほしい、仕事人間にも心があるということを。
士業という職業への誤解と壁
司法書士というと、どうしても「堅い」「偉そう」「冷たい」といった印象を持たれがちだ。実際、仕事柄、プライベートでも話題が重くなりがちだし、冗談も控えめになってしまう。でも、本当は普通の人間だ。笑うし、落ち込むし、誰かと飲みに行きたいと思う夜もある。だけど、「司法書士だから」という色眼鏡を通して見られることで、自然な関係が築けないことも少なくない。
「先生」という肩書きが逆に孤独を招く
ありがたいことに、「先生」と呼ばれることは多い。でも、そこに潜む距離感が時にしんどい。「先生」ではなく「○○君」と呼ばれていた頃の方が、ずっと気楽だった。肩書きが重荷になる瞬間が、確かにある。呼ばれるのは敬意かもしれない。でも、それが「親しみを持って接することの障壁」になるのなら、そんな肩書きはいらないとも思ってしまう。