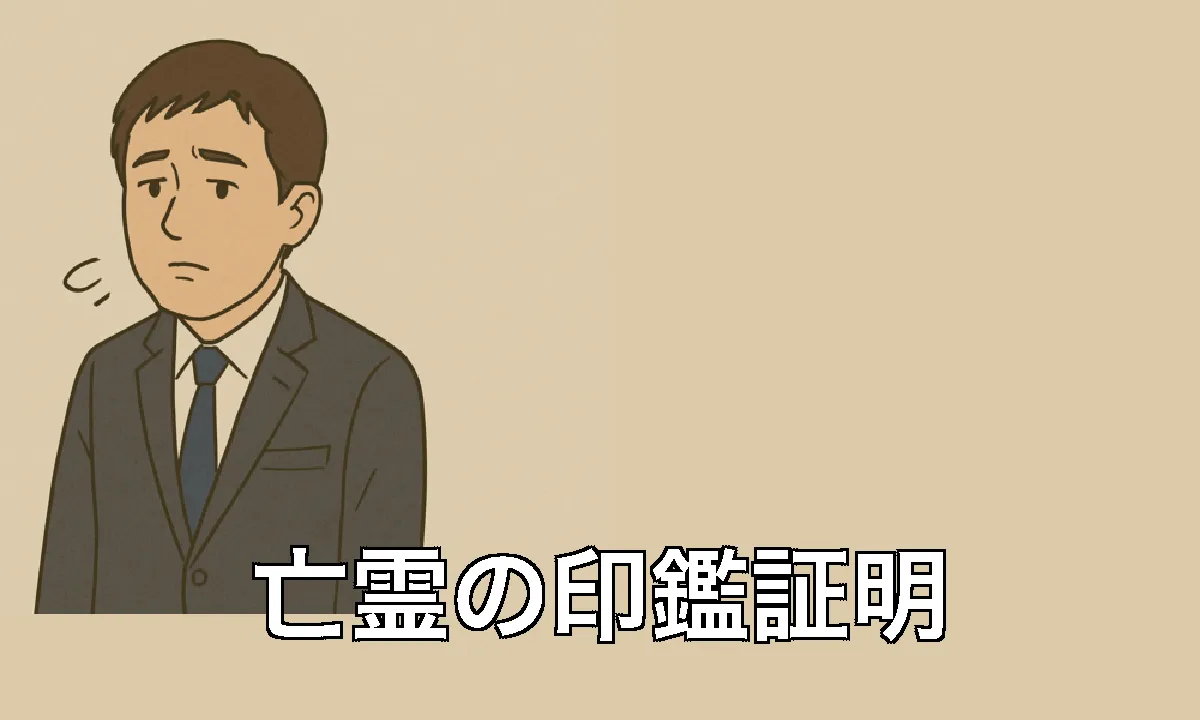亡霊の印鑑証明
午前10時。夏の日差しは遠慮なく窓から差し込み、机の上の書類を焼いていた。エアコンは壊れたままで、扇風機が生温い風をかき回している。そんな中、例によって「厄介そうな依頼」が届いた。
それは一通の契約書。差出人は、名前だけ見れば見覚えのある人物。だが、それが問題だった。その人物――は、三年前に死亡していたのだ。
朝一番の違和感
封筒を開けた瞬間、インクの匂いに混じって、どこか古ぼけた紙のにおいがした。依頼内容は不動産の売買契約で、署名捺印もばっちりだ。だが、それがどうにも妙だった。
「この名前……確か、あの事故で亡くなったって話だったよな」
資料棚から過去の登記簿を引っ張り出し、照らし合わせると、やはり一致している。しかも、その契約書の日付は、亡くなった日の翌日だった。
契約書に浮かぶ死者の名
「幽霊がハンコ押したってことですか?」サトウさんが鼻で笑う。ツンと澄ました声に、こちらの背筋がしゃんと伸びる。
「ま、可能性としてはゼロじゃないけど……それより誰がこれを作ったか、が問題だ」
私は机の上に広げた契約書を睨みつけた。筆跡は綺麗すぎて、むしろ偽物のようにも見える。が、それより問題なのは、印影だ。
依頼人は三年前に死亡していた
印影と照合した印鑑証明書は、確かに役所の発行スタンプ付き。偽物には見えない。でも発行日が、契約書の日付より一週間も前だ。
「この発行日、変ですよね。死亡届が出てるなら、印鑑証明の取得はできないはず」
サトウさんがすぐに役所に問い合わせてくれた。結果、驚くべき事実が発覚する――死亡届の提出はなぜか契約の一ヶ月後になっていた。
実印か偽印かそれが問題だ
つまり、生きていることになっていた期間に印鑑証明は取得できていたということ。だが、それは家族の誰かが、死亡を隠していた可能性を示唆していた。
「まるでルパン三世の変装トリックみたいですね。死人を生きているように見せかけるって」
サトウさんの声は少しだけ楽しげだった。彼女はこういう謎が好きなのだ。
塩対応の推理開始
「じゃあ次は、誰が印鑑証明を取ったか調べましょう。委任状があれば、それを悪用した人間がいます」
サトウさんはパタパタとキーボードを叩き、過去の委任状の写しを見つけ出す。差出人の名前も被相続人と一致。だが筆跡が違っていた。
「この筆跡、子供の頃の連絡帳みたいな字ですね。大人の字じゃない」彼女は冷たく言い放った。
亡霊が登記を急ぐ理由
なぜ、死者の名で契約書を?――その理由が次第に明らかになってくる。問題の不動産は、相続人の一人によって売られようとしていた。
相続放棄をしていたはずの長男が、父親名義のまま売却すれば金が入る。死亡届の提出を遅らせ、父親名義での登記を可能にしていたのだ。
「やれやれ、、、ほんとに幽霊より怖いのは、生きてる人間だな」
古びた印鑑証明書の罠
印鑑証明書は間違いなく本物。でも、その取得に使われた委任状は偽造。役所は本人確認をしないから、形式上は通ってしまう。
「実家の押入れから出てきた印鑑と通帳が、きっかけだったようです」
サトウさんが提出した調査メモは簡潔にして鋭い。まるでコナン君のような推理力だった。
元野球部のうっかり発動
ところが、ここで私がやらかす。印影をファクスで送る際、上下逆に送ってしまったのだ。確認の電話が鳴り、全てが一瞬にしてバレる。
「シンドウさん、まさかまたやらかしました?」
塩の効いたその声に、胃がキリキリと痛んだ。
やれやれ書類は嘘をつかない
だが、そのミスが逆に突破口となった。上下逆さの印影に、実は微細なズレがあることが判明し、印鑑自体が後年彫り直されたものだとわかったのだ。
「亡くなった本人の印じゃありません。これは第三者が偽造した証拠になります」
書類は嘘をつかない、とはよく言ったものだ。
幽霊より怖い生きている人間
長男は、すべてを認めた。借金の返済に困り、実家を勝手に売っていたのだ。死亡届を出さずに時間を稼いだのも、悪意によるものだった。
「幽霊が契約書にサインするわけないでしょ」
サトウさんのその一言で、事件は締めくくられた。
サトウさんの一点突破
「司法書士って、幽霊相手でも仕事できるんですね」
皮肉っぽく笑うサトウさんに、私は疲れた顔で頷いた。「書類がある限り、な、、、」
でも正直、書類の山にもううんざりだ。野球部だった頃のグラウンドの土の方が、まだマシだった気がする。
契約書の中の密室トリック
今回は、死亡を隠したことで生じた一種の「契約上の密室トリック」だった。署名はある、印影もある、でも実体がいない。
それは、まるで怪盗キッドが盗みに入った後の博物館のように、完全に仕組まれた舞台だった。
「お前じゃなきゃ気づけなかったろうな、シンドウさん」
封筒の中の死者からの手紙
事件の後、遺族から改めて謝罪の手紙が届いた。中には亡くなった依頼人が生前に書いた感謝の手紙のコピーが入っていた。
「きっと、天国の依頼人も怒ってると思いますよ」
サトウさんの言葉に、少しだけ胸が痛んだ。
真相と供述調書と胃痛
警察への供述調書は、まるで卒論のような厚さになった。胃薬を飲みながら、私はせっせとまとめる。すべて法務局にも報告済みだ。
「やれやれ、、、また胃に穴が開きそうだ」
でも、これが私の仕事なのだ。
やっぱり最後は俺がやるしかない
誰もやりたがらない面倒な案件。だが、最後に書類に判を押すのは、やっぱり私しかいない。
印刷された登記完了通知を見ながら、私は深くため息をついた。
次はもっと静かな一日でありますように――そう願いながら。
印鑑登録簿に残る亡霊の名
事件は解決したが、印鑑登録簿にはしばらくその亡霊の名前が残る。生前に刻まれたその名前が、まだどこかで仕事をしているかのように。
「サトウさん、明日こそ休もうな」
「……それ、10日連続で聞きましたけど?」