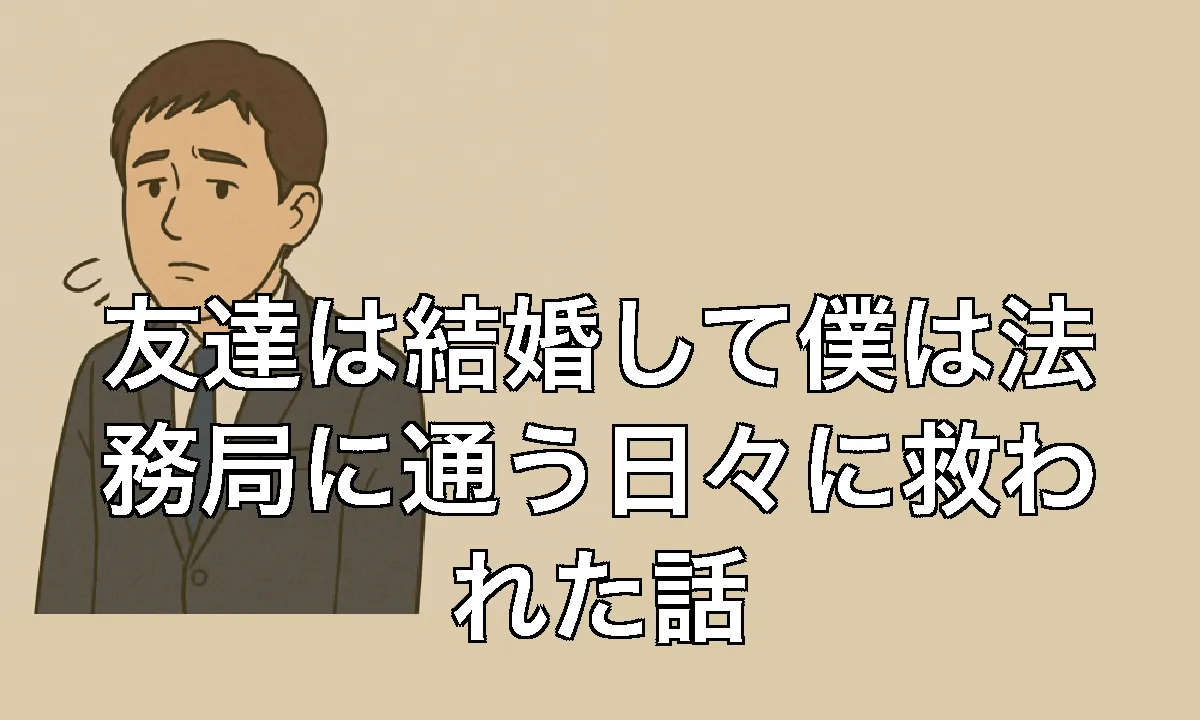気づけば法務局通いの日々が心の拠り所だった
昔は、毎日のように誰かと飲みに行ったり、休日は予定が埋まっていたのに、気づけばそんな生活とは無縁になっていた。結婚式の招待状が届くたびに、「ああ、また誰かが人生の節目を迎えたんだな」とぼんやり思う。でも不思議と、羨ましさや嫉妬というよりも、自分が置いていかれてるような感覚だけが胸に残る。そんな中で、日々の業務の一環として通っている法務局の存在が、なんだか自分を支えてくれているように感じるようになった。誰かと比べることなく、必要とされる場所があるという事実が、ほんの少しだけ救いだったのかもしれない。
誰かのために動いているという感覚が救いだった
司法書士として働いていると、依頼人の人生の大事な場面に立ち会うことがある。不動産の相続、会社の設立、離婚による名義変更。どれも他人の人生の分岐点だ。自分のことは置いておいて、ひたすら書類を整え、登記簿とにらめっこしながら、期限までに手続きを終わらせる。その作業のなかで「自分が役に立ってる」という手応えを得られるのがありがたかった。感謝の言葉がなくてもいい。ただ、誰かの一部を担えている、その感覚が、僕には必要だった。
結婚式の招待状が届くたびに心がざわつく
同級生や元同僚からの結婚式の招待状が届くと、いつも少し心がざわつく。出席するたびに「そろそろお前もどうだ?」なんて冗談混じりに言われるが、笑ってごまかすのがやっとだ。地元では結婚して子どもがいて当たり前。そんな空気の中で独身の自分は、どこか取り残された存在のように感じる。特に冬の寒い朝に、家族の話をする依頼人と会うと、自分の部屋の静けさが余計に重たくのしかかってくる。でも、そんなときほど、誰かの役に立てる仕事があってよかったと心底思う。
祝福する気持ちと置き去り感が入り混じる
もちろん友人たちの幸せは心から嬉しい。学生時代からの仲間が笑顔で式場に立つ姿を見れば、胸が温かくなる。でもその反面、自分だけ時間が止まっているような感覚にも陥る。祝福の言葉をかけるたびに、「自分もあの輪の中に入りたい」と思ってしまうのは、贅沢だろうか。そんな思いを、法務局での作業や日常業務に埋もれさせるようにして、今日もまた登記の受付番号を握りしめている。
法務局の静けさが心を落ち着けてくれる理由
法務局のあの静寂さには、なんとも言えない安心感がある。カウンター越しのやり取り、機械的な番号呼び出し、硬い椅子。すべてが決まりきっていて、余計な感情を必要としない空間だ。人間関係に疲れたときや、自分の価値が見えなくなったとき、その「事務的な空間」に救われる。居場所というのは、必ずしも温かい場所じゃなくていい。ただ、存在を否定されない場所であれば、それだけで十分だった。
機械的な受付にもなぜか安心感がある
「次の方どうぞ」という声に従って、窓口に進み、事前に準備しておいた書類を提出する。間違いがあれば指摘され、訂正印を押し、再提出する。その一連の流れは、まるで作業のように進むが、僕にとっては「誰かと関わっている」感覚を思い出させてくれる。仕事としての接点でしかなくても、それが日常における貴重な交流なのだ。無駄話もなく、ただ粛々と進むやり取りが、なぜか心地よく感じるようになってきた。
書類の不備に怒られても人と繋がっている実感がある
ときには、法務局の担当者に「これじゃダメです」ときつく言われることもある。昔の僕なら、そんなことで心が折れそうになっていたが、今は違う。「ああ、今日もちゃんと人と接しているな」と思える。怒られるのも、褒められるのも、無視されるよりはずっとマシだと感じてしまうのは、少し寂しい性格なのかもしれない。でもその一言で、また自分の仕事に向き合うきっかけになるなら、悪くないと思っている。
野球部だった頃の僕が見た夢と今の現実
高校時代は野球部で、グラウンドを駆け回っていた。汗まみれで声を張り上げていた頃は、自分が司法書士になるなんて夢にも思わなかった。もっと違う道に進むつもりだったし、人生はもっと華やかになるとどこかで信じていた。でも今は、パソコンと書類とにらめっこし、ひとり黙々と判を押す日々。夢とは違っても、今の現実が悪いとは言えない。あの頃の仲間が家族を築くなか、自分は違う場所で違う責任を果たしている。それでいいと思えるようになった。
仲間は家庭を持ち 僕は印鑑証明を持ち歩く
久しぶりに集まった野球部の仲間たちは、誰もが家庭を持ち、子どもの話題で盛り上がっていた。僕はというと、今日申請する会社設立登記の話をしそうになって、慌てて口をつぐんだ。話題が合わないわけじゃない、でも「今の自分」をどう話していいか分からなかった。みんなが家族の写真をスマホで見せ合ってる間、僕はかばんの中の印鑑証明を思い出していた。
昔はモテたのになと言い訳した夜
学生時代はそれなりにモテた。応援に来た後輩の女子たちに差し入れをもらったり、文化祭の後に誘われたり。今となってはすっかり昔話だけれど、ふとした瞬間に「昔はな…」と口にしてしまう夜がある。だけどそれは、今の自分に自信がないから出る言葉なのかもしれない。モテなくなった今も、誰かに必要とされる存在でいたい。そう願いながら、今日もひとり事務所の電気をつけている。
勝ち負けでは測れない人生の価値を考える
野球では勝ったか負けたかが全てだった。だが社会に出てからの人生は、勝ち負けだけでは測れない。誰かと比べて自分を落ち込ませるのではなく、自分なりの役割を見つけていくしかない。家庭がない、子どもがいない、それでも誰かの支えになれる。それが司法書士という仕事の大きな意味でもあると、ようやく思えるようになってきた。
独身司法書士の心の支えとは
ひとりで生きているように見えるかもしれないが、実際には日々の小さなつながりに助けられている。事務員さんとの何気ないやり取りや、クライアントの感謝の言葉。そうした日常の一つひとつが、支えになっているのだ。家に帰っても誰もいないけど、「また明日も頑張ろう」と思えるのは、きっとその小さな支えがあるからだろう。
事務所の小さな日常に込められた意味
朝、事務員さんが「おはようございます」と言ってくれるだけで、事務所の空気が和む。電話対応に追われながらも、ふとしたタイミングで差し入れてくれるお茶や、印刷ミスに一緒に苦笑いしてくれる瞬間。そのどれもが、僕の心を少しずつ温めてくれる。結婚していない僕にとって、職場こそが「家庭」に近い存在なのかもしれない。
事務員との他愛のない会話が今日を作っている
「この前のテレビ見ました?」「あのパン屋、行ってみたんです」そんな他愛もない会話が、仕事の合間にふと交わされる。それがあるだけで、今日はなんとかなると思える。事務員さんは、僕の孤独を埋めてくれる存在ではないけれど、同じ空間で共に働く仲間として、確かにそこにいてくれる。人はそれだけで救われることがある。
誰かと過ごすよりも誰かを支える日々
寂しさを感じることはある。でもそれ以上に、今は誰かの役に立てることがうれしい。結婚して誰かと一緒に暮らすことが幸せだとは限らない。僕は僕のやり方で、誰かを支えることで自分を保っている。それは、さみしくないと言えば嘘になるけれど、確かに価値ある日々だ。
これからの生き方に名前をつけるなら
結婚していないから不幸だとは思わない。ただ、自分の生き方に誇りを持つには時間がかかった。法務局に通い、書類を提出し、判を押し、また歩き出す。そんな繰り返しの日々が、いつのまにか自分の心を整えてくれていた。これからの人生に名前をつけるなら、「地味だけど確かな日々」だろうか。それでも悪くない。そう思えるようになった。
さみしさも仕事に混ぜて進んでいく
誰かに必要とされたい。そう願う気持ちは、さみしさの裏返しかもしれない。でもその感情を、仕事に混ぜ込んで前に進んでいく。クライアントの「ありがとう」の一言が、今日一日の疲れを癒してくれる。自分の存在価値を感じるたびに、少しだけ胸を張れるようになった。
法務局の帰り道に空を見上げる理由
手続きが終わって、帰り道の車の中でふと空を見上げる。曇っていても、晴れていても、それがその日の気持ちを映しているような気がする。何も変わらない日々の中でも、自分の心が少しずつ変化している。そう感じられることが、今の僕の生きがいになっている。
今日もひとり でも悪くない
誰かと一緒に過ごす時間も、きっと素敵だろう。でも今の自分の生活も、捨てたもんじゃない。今日もひとり、でも法務局に行って、書類を提出して、事務所に戻ってきた。そんな一日を、誰よりも大切に思っている。ひとりでも、悪くない。そう思えた時、僕は少しだけ自由になれた気がした。