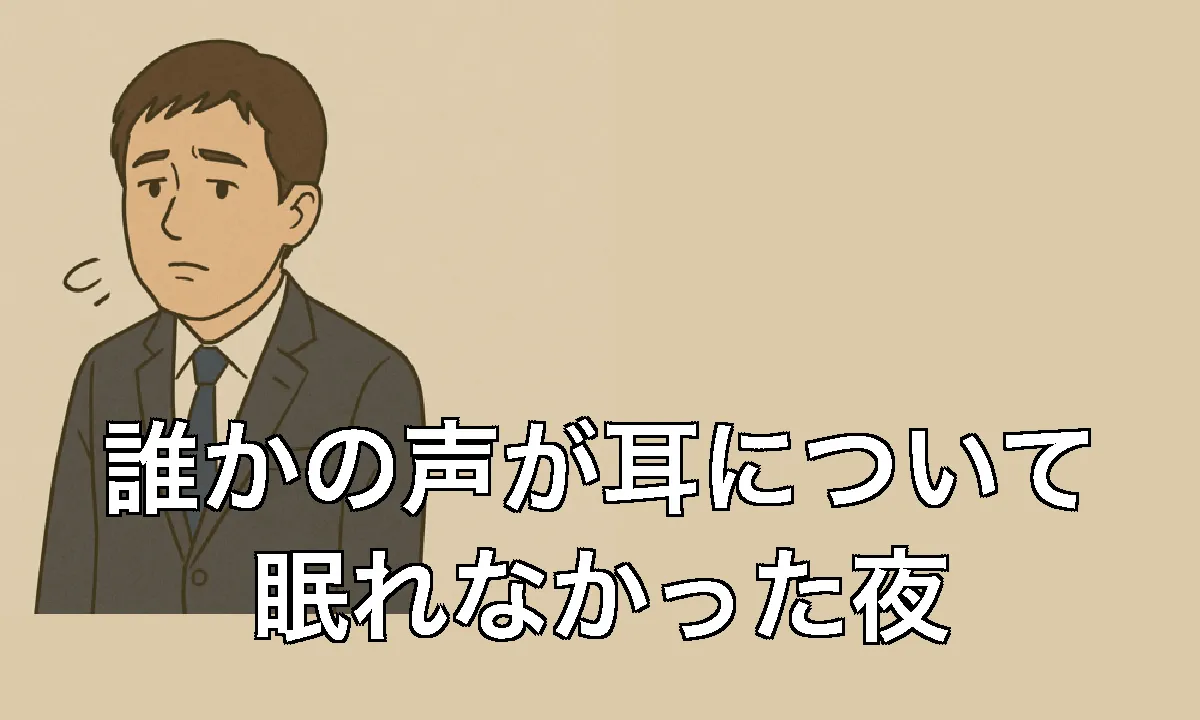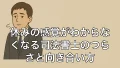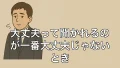誰かの声がうるさく感じたあの夜のこと
ある晩、珍しく早く布団に入ったのに、なぜか眠れなかった。隣の部屋から聞こえるテレビの音、通りすがりの話し声、どれも普段なら気にならないはずなのに、その夜ばかりは、やけに耳について仕方がなかった。「うるさいな…」とつぶやいた自分の声が、むしろ一番うるさかった気がする。心に余裕がないと、こんなふうに音に敏感になるものなのか。司法書士という仕事のストレスが、じわじわと溜まっていたのかもしれない。
静けさを求めていたはずの自分がなぜか苛立つ
自分の中に「静かにしてくれ」という気持ちがあったはずなのに、いざ静かになると今度は心がざわついて落ち着かなくなる。テレビを消しても、スマホを遠ざけても、心の中の雑音が消えてくれない。司法書士としての一日の終わりには、頭の中に“やり残し”や“気がかり”がぐるぐると回っている。特に、依頼者との対応に気を遣いすぎた日は、ちょっとした声にも神経が過敏になるようで、自分が自分じゃないような感覚すらあった。
テレビの音すら許せなくなる夜の心理状態
その夜、隣の部屋のテレビが微かに聞こえていた。音量は小さいのに、セリフのひとつひとつが耳に刺さるようだった。実際、翌日になって確認すると、普段と何も変わっていなかったらしい。つまり、うるさかったのは相手の声ではなく、心の状態だったのだ。忙しさに追われ、ひとりで黙々と登記の書類をこなし、ミスしないように張りつめていた神経が、ようやく緩んだ途端に、音に反応してしまったのかもしれない。
「うるさい」と思ったのは本当にその人の声か
後になって思った。「本当にうるさかったのは誰の声だったんだろう」と。テレビの音? 通行人の話し声? いや、たぶん違う。うるさかったのは、心の中で鳴り響く“自分自身の声”だったのかもしれない。「ちゃんとやらなきゃ」「失敗しないように」「明日はあの手続きを忘れずに」…そんな内なる声が、外の音と重なって聞こえてしまっていた。あの夜の“誰かの声”は、結局、自分の焦りや不安が投影されていただけだった。
疲れがピークに達するとき心の余裕がなくなる
忙しさが続くと、身体より先に心が擦り切れてくるのを感じる。特にひとりで事務所を回していると、自分が止まるとすべてが止まるようなプレッシャーがある。頼れる人が事務員ひとりというのも正直しんどい。最近では、1日中誰かと話すだけで、夜には“誰の声も聞きたくない”という状態になることすらある。声がうるさく感じるのは、きっと限界のサインだった。
仕事に追われすぎて感情がむき出しになる瞬間
自分でもわかっている。ああ、今、機嫌悪いなって。依頼者に理不尽なことを言われた直後や、期日に追われて焦っているとき、ふとした一言にカッとなることがある。普段なら受け流せるようなことが、急に引っかかってしまう。それがそのまま“声”に現れる。相手の話し方が気に障る、語尾が不快、そんなふうに感じてしまうのは、決して相手が悪いわけじゃない。心に余裕がないと、人の声すら敵に見えてしまう。
司法書士という職業の“終わりなきタスク”
この仕事、終わりが見えない。登記の期限は決まっているけれど、終わったと思ったら次の案件。誰かの声に対応し続ける職業だからこそ、自分の感情を切り離すのが難しい。依頼者に寄り添うことも大切だが、寄り添いすぎると自分が沈んでしまう。書類を見ながら、その人の人生が垣間見えるような瞬間があるからこそ、余計に気を遣ってしまう。気を遣いすぎた夜には、ほんの些細な「声」が心に響きすぎる。
事務員にさえ優しくできなかった自分への反省
その夜、たぶん自分は少し尖っていた。帰り際に事務員が「お疲れさまでした」と声をかけてくれたのに、うまく返せなかった。あとから考えると、あれは完全に自分の余裕のなさだったのに、まるで相手の声がうるさかったかのように感じてしまっていた。思いやりが欠けていたのは自分のほうで、事務員の声はむしろ優しかった。反省するのは決まって“ひとりの夜”だ。そしてまた、誰かの声がうるさく感じてしまう。
自分の機嫌を他人に委ねていたことに気づく
その夜を境に、自分の中にひとつの気づきがあった。「自分の機嫌を、他人の声で左右されていないか?」という問いだ。人の言葉に一喜一憂している時点で、主導権を渡してしまっている。静かであることにこだわって、誰かの声にイライラするのは、結局“コントロールしたい気持ち”の裏返しだったのかもしれない。司法書士である前に、一人の人間として、心のゆとりを取り戻す必要があると感じた。
声が気になるのは自分が乱れているサイン
普段は気にならない音が気になるのは、体調不良と似ている。「なんか今日は調子が悪いな」というとき、音や匂いに過敏になるのと同じだ。精神的なバランスが崩れているとき、耳が敏感になり、言葉が鋭く感じられるようになる。それは、自分が「もう限界だよ」と発しているサインかもしれない。誰かの声に反応したその瞬間に、自分の心の状態を振り返る習慣を持つことで、少しは穏やかに過ごせるのかもしれない。
他人を変えようとするよりも先にできること
どうしても誰かの話し方が気になったり、声のトーンにイラッとしてしまうことがある。でも、他人の話し方を変えさせるなんて無理だ。だったら、自分の聞き方や受け止め方を変えるしかない。耳を塞ぐことではなく、心の“聞き方”を整える。それには、まず自分を満たすこと、つまり休むこと、誰かに話すこと、食べたいものを食べること。司法書士だって、人間だから感情がある。そのケアを忘れてはいけない。
耳をふさぐよりも心に余白を持たせる努力
昔、野球部の監督がこう言っていた。「疲れてるときこそ、周りの声が力になる」。あの頃は意味がわからなかった。でも今、ようやくわかる。声がうるさく感じるのは、自分が疲れているから。だったらまず、自分を労わってやらなければ。耳をふさぐのではなく、心に余白を作って、声を受け入れられるようにしていきたい。司法書士として、また一人の大人として、自分の感情をうまく扱うことが、きっと仕事にもつながっていくはずだ。