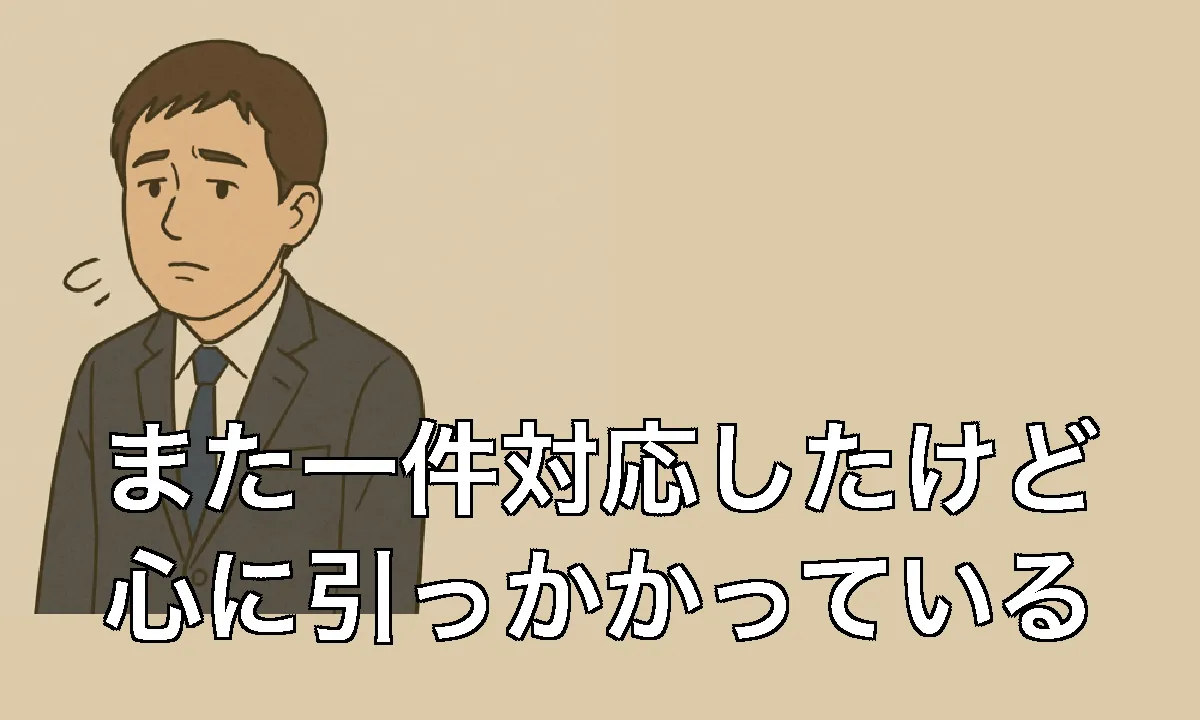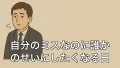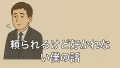仕事は片づいたはずなのに心が重い
登記の申請が無事に終わり、依頼者には完了の報告をした。その瞬間は「これで一件落着」と思った。だけど、心のどこかに小さな石のようなものが残っている。言葉にするのは難しいが、「本当にこれで良かったのか」という問いがずっと頭の隅にある。書類上は問題なし、依頼者も納得、でも自分の中では妙にひっかかっている。この感じ、年々増えてきた気がする。
「解決」は本当に依頼者のためになったのか
今回の案件は、兄弟間の遺産分割だった。兄弟仲は良いとは言えず、依頼主である弟さんが積極的に動いていた。一方で兄は口数少なく、私の目には諦めたように映った。法律的には弟さんの提案は問題なかったし、書面も整った。だが、兄のあの沈んだ表情がずっと頭から離れない。もしかすると、私は「手続きの正しさ」にばかり目を向けすぎて、心情的なバランスを見逃してしまったのかもしれない。
形式的な終わりと感情的な未完了
登記簿が正しく更新されたことで「仕事」としては完了する。それが司法書士の役割だと理解しているし、それで良しとしなければならないのもわかる。ただ、気持ちの上では終わっていない。依頼者の笑顔より、沈黙していた家族の表情の方が記憶に残ってしまう。法務局の受付印と引き換えに、自分の中に積み重なる「何か」。これが「心残り」なのだと、最近はよく思う。
「これでよかったんですよね」の問いかけに返せなかった言葉
帰り際、弟さんがふと「これでよかったんですよね」と口にした。その声色は、確認というより、自分を納得させようとするような響きだった。私は「もちろん問題ありません」と即答したが、心の中では「どうなんだろう」とつぶやいていた。言葉が上滑りしていく感覚。あの瞬間、自分は何か大切な部分から目をそらしてしまった気がした。
事件処理が終わっても考え続ける夜
依頼が終わったあとの夜、たいていはビールでも飲んで気を抜くようにしている。だが、今回のような「心に残る」案件の後は、なぜか寝つきが悪くなる。布団に入っても、頭の中で依頼者との会話を何度も繰り返す。昔は「慣れれば忘れる」と思っていたが、歳を取るにつれて逆に引きずるようになってしまった気がする。
家に帰っても思い浮かぶあの依頼者の顔
独身ということもあって、家では一人だ。テレビをつけても気が紛れず、パソコンの前に座ってメールチェックをしても集中できない。ふとした瞬間に、依頼者のあの顔が浮かんでくる。しかもそれが「ありがとう」と言ってくれた人ではなく、無言だった人の方なのだ。自分でも不思議だが、感謝よりも沈黙の方が心に強く残る。
「仕事」と「感情」の切り離しがうまくできない
元々、感情に引きずられるタイプではなかった。野球部時代は、試合で負けても切り替えが早い方だった。だが、司法書士の仕事を続けていくうちに、だんだんと感情の整理が難しくなってきた。たぶん「人の人生に関わっている」という実感が重くのしかかってくるからだ。だからこそ、「割り切る」ことがどんどんできなくなっている。
元野球部的気質の「全部引き受けてしまう癖」
チームプレーに慣れ親しんできたせいか、誰かが困っていたら無意識に「自分がなんとかしなきゃ」と思ってしまう。事務所でもその傾向は強く、依頼者の事情に必要以上に感情移入してしまうことがある。合理性より気持ちを重視してしまうのは、司法書士としての弱さかもしれない。でも、それが「自分らしさ」でもある気がして、なかなか変えられない。
事務員との雑談で気づかされること
うちの事務員は、気が利くけれどズバズバ物を言うタイプだ。年下だけど、こちらが頼りにしてしまっている。先日も、心残りだった案件の話を何気なく口にしたら、「気にしすぎじゃないですか?」と軽く笑われた。でもその一言に救われた気もした。
他人は軽く見えて自分だけが重く抱える
同じ案件でも、受け取り方は人それぞれだ。事務員にしてみれば、「書類が通ればOK」「依頼者が納得してるならOK」という感覚。自分が必要以上に背負いすぎているのかもしれない。それでも、どうしても引きずってしまうのは、自分がそういう性格だからだと割り切るしかないのか。
「割り切れないのがあんたの良さでしょ」
たまに言われるのがこの一言。「そのくらい気にするからこそ、依頼者も安心して任せてくれるんじゃないですか」と事務員は笑う。それを聞くと、ちょっとだけ気持ちが楽になる。割り切れなさも悪いことばかりじゃない。自分なりの「仕事のやり方」があっていいと思えるようになる。
ネガティブさも誰かの役に立つかもしれない
ネガティブな気持ちに引っ張られてしまうこともあるけれど、それが誰かの気持ちに寄り添うことにつながるなら、悪くないのかもしれない。たとえば、少しでも違和感があれば見逃さずに確認する。それだけでトラブルを未然に防げたこともあった。優しさと弱さは紙一重。だけど、それでもいいと思う。
心残りを減らすための試み
完全に「心残りゼロ」にはできないかもしれない。でも、少しでも和らげる工夫はできる。最近は、自分なりにいくつかの取り組みを始めてみた。
一言添える手紙を書くようになった
依頼完了の報告書類に、手書きで一言添えるようになった。「何かあればいつでもご相談ください」「お身体にお気をつけて」など、ありきたりではあるけど、自分の気持ちを込めている。これだけで、少しだけ気持ちの整理がつくことがある。不思議なものだ。
自分のためにも書く、という感覚
実はこの一言は、依頼者のためというより、自分自身のために書いているようなところがある。「自分はこれで精一杯やった」という証のようなもの。自己満足かもしれないが、それでも「終わった」と思える何かが残る。この作業が、自分にとっての一区切りになっている。
それでも残る引っかかりとの付き合い方
それでも、全てがスッキリするわけではない。心に残ることは残る。でも、逃げずに向き合うことで、その重みとも少しずつ共存できるようになってきた気がする。司法書士という職業は、きっとそういう「答えの出ない気持ち」と付き合い続ける仕事なのだと思う。