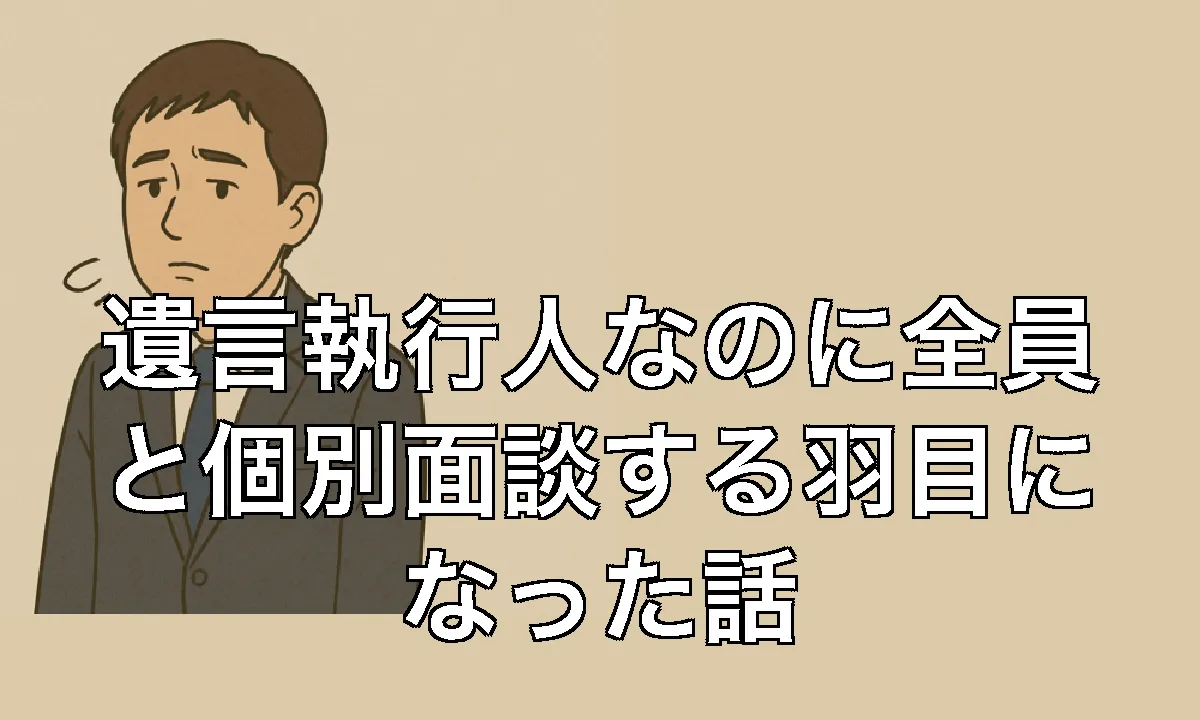遺言執行人なのに全員と個別面談する羽目になった話
遺言執行を引き受けたはずがなぜか調整係に
遺言執行人というのは、亡くなった方の意思を法的に実現する立場であって、基本的には粛々と手続きを進める仕事のはずだ。ところが現実はそう甘くなかった。ある案件で遺言執行人に選任され、内容自体はそれほど複雑なものではなかったのに、相続人がそれぞれバラバラに動き始めてしまった。兄弟姉妹で連絡を取り合うのが嫌だと言い始め、結果として、全員と「個別に」面談する羽目に…。気づけば、私は遺言の実行者というより、まるで感情の調整係になっていた。
相続人全員と個別に話すことになった経緯
きっかけは、長男と三女が顔を合わせたくないと言ったところからだった。他の相続人もそれに便乗するように「私も個別に話したい」と言い出した。これが一人二人ならまだしも、全員が同じスタンスを取ってくると、ただの一回の説明が五回六回と膨れ上がる。合理的に一堂に会して話し合えば済むはずなのに、それぞれが感情的なわだかまりを抱えていて、どうにもならなかった。「あの人が来るなら行かない」という言葉に、予定表が真っ黒に染まっていった。
兄弟同士が話したくないという地獄のスタート
まるで中学時代の部活の派閥争いを思い出した。「あいつとは口もききたくない」といった類の感情的な対立を、大の大人たちが真顔で私にぶつけてくる。「兄弟なんですから」と言いたいのを飲み込み、私は一人ひとりに日を変えて説明するしかなかった。面談のたびに過去の確執が語られ、話が脱線していく。遺言の中身より、家族の歴史のほうが重たくのしかかってきた。すでに業務の枠を超えていた。
誰の味方でもないのに全員からの牽制を受ける
私はあくまで中立の立場だ。それなのに、「あの人に有利になるようにしてるんじゃないか」とか、「どうせ◯◯さんに言われて動いてるんでしょ?」などと、まるでスパイ扱いされることもあった。どこにも立場を置かずにバランスを取ることが、どれほど疲れるか…わかってもらえない。何をしても誰かから不満が出る。そのたびに「いや、私はただの執行人で…」と説明を繰り返す虚しさが、心にじわじわと染みてきた。
時間も心も削られる一日三件の面談スケジュール
個別面談となれば、当然時間がかかる。1日で2件こなすのが限界だろう…と最初は思っていたが、依頼者の都合で3件連続となった日もあった。1件あたりの面談が1時間半から2時間。昼飯をコンビニおにぎり1個で済ませて、次の面談に向かう日々。しかも内容は全員同じなのに、それぞれに最適な言葉選びと気遣いを求められる。終わる頃にはどっと疲れて、事務所に戻る気力すらなかった。
書類じゃ済まない感情のぶつけ合いに巻き込まれる
書類だけで済むなら、こんなに疲弊することはなかった。だが実際には、「どうして私の名前が遺言に少ししか出てないのか」とか、「生前の介護をもっと評価してほしい」といった、気持ちの問題ばかりが噴き出してくる。泣き出す人もいれば、怒り出す人もいる。その感情のはけ口が全部こちらに向いてしまうのだ。司法書士って、ここまで心のケアを求められる職業だったのか?と何度も思った。
法律だけでは解決できない空気の重たさ
どれだけ条文を引用して説明しても、「納得できません」の一言には勝てない。それが感情だ。法律は正義を与えるかもしれないが、感情のもつれを解く道具にはならない。家族の関係がこじれているほど、正論は逆効果になる。私は何度もそれを痛感した。何が正しいかではなく、どう受け取られるかが全てになる現場。それが遺言執行という仕事の裏側だと初めて思い知らされた。
司法書士としての立場と人間としての限界
法的なプロフェッショナルでありながら、個人としては悩みを抱えるただの人間でもある。その両面を行ったり来たりする中で、ふと限界を感じる瞬間がある。遺言執行という重要な役割を任されたはずなのに、その重責が私の心身を徐々に削っていく。冷静にこなすべき仕事のはずが、いつの間にか私の感情も巻き込まれていた。
「先生が決めてください」と言われた瞬間のプレッシャー
一番困るのが、「もう先生が決めてください」と言われる場面。立場上、判断はできても最終決定は相続人自身がすべきものだ。しかしそれを放棄して、丸投げされると、まるで私が遺産を分配する独裁者のようになってしまう。責任を押し付けられ、誰かの不満を背負うことになる。そのプレッシャーは想像以上で、胃がキリキリと痛む。
公正中立という言葉がどれだけ虚しく聞こえたか
「私は公正中立です」と繰り返しても、それが通じない相手には全く響かない。むしろ「中立っていう人ほど信用できない」とまで言われたこともある。誤解されることが積み重なると、自分の立ち位置がどこにもないような感覚になる。自分が透明人間になったかのように、誰からも信頼されず、ただ業務を機械的に進めるだけの存在になる。これは思った以上に精神的に堪える。
うまくやる=誰にも恨まれない は成立しない現実
全員を納得させること、それができれば理想だ。でも現実には、誰か一人が納得すれば、別の誰かが不満を漏らす。「全員に好かれる」のは無理な話だ。だからこそ、自分の中で最低限の正義と公平性を保ちながら、腹をくくるしかない。「誰かに嫌われても仕方ない」と思えるようになるまでには、何度も凹んだし、自信を失いかけた。
愚痴を吐ける相手もいない静かな夜
事務所を出たあと、夜道を歩くとやっと一人になれた気がする。けれど、愚痴を言える相手がいないのが一番つらい。独身だし、気軽に弱音を吐ける人もいない。事務員に話しても気を遣わせてしまうだけ。心の中で何度も「しんどい」と呟く。そんな日が続くと、自分の存在意義すらわからなくなってくる。
一人事務所の孤独と責任の板挟み
小さな事務所を一人で回すには、ある程度の覚悟がいる。でも、覚悟ってなんだろうと思う日もある。全部自分の責任で、失敗も成功も一人で受け止める。それは強さでもあるが、孤独でもある。特に今回のような感情の渦に巻き込まれる案件では、「誰かに相談したい」と思っても、それができないことが苦しい。
事務員に話しても気を遣わせるだけだから我慢
事務員は若い女性で、性格もまじめだ。こちらが辛そうな顔をしていれば、そっと気遣ってくれる。でも、そんな優しさに甘えるのも申し訳なくて、つい「大丈夫です」と言ってしまう。自分の弱さを見せると、彼女の働きやすさにも影響してしまうかもしれない。そう思うと、結局何も言えず、ひとりで夜の事務所に残る日が増えていった。
SNSも使えず共感を求める場もない現実
気晴らしにSNSを見ても、ポジティブな投稿ばかりが並んでいて、余計に気が滅入る。愚痴を書きたくても、仕事の守秘義務があるから詳細も書けない。誰かと繋がりたいのに、繋がる術がない。そんなジレンマが、日々の疲れを何倍にも増幅させる。「誰かこの気持ちをわかってくれ」と心の中で叫ぶしかなかった。
それでも仕事をやめなかった理由
辞めようかと思ったことは、正直何度もある。でも結局、やめなかった。なぜかと言えば、ほんの一言の「ありがとう」で救われたからだ。それは重荷の中にある、かすかな光だった。どんなに大変でも、その一言があれば、もう少しだけ踏ん張れる。司法書士という仕事には、それだけの価値があると信じたい。
感謝された一言でやっと報われた気がした
面談の最後に、「本当にありがとうございました。先生がいてくれて助かりました」と言われた。その瞬間、涙が出そうになった。たった一人でも、そう言ってくれる人がいるなら、やってきたことは間違ってなかったんだと思える。苦しみはなくならないけど、意味はあったんだと胸を張れる。そんな瞬間のために、また明日も頑張ろうと思える。
苦労が無駄じゃなかったと思える瞬間が救い
報酬ではなく、人の心に触れられたときの感覚。これは士業をしていて、何よりも嬉しい瞬間だ。正直、報われることは少ない。でも、それでもいい。たった一人でも誰かの力になれたなら、今夜のしんどさも、あの地獄のような個別面談も、全部意味があったんだと思える。そう思える日が、また来ると信じたい。
誰かのためにできる仕事の価値を信じたい
この仕事は、孤独だ。でも、誰かの人生にそっと関われる仕事でもある。その尊さを、少しでも感じられるなら、きっと続けていける。自分の人生に誇りを持つためにも、「あのとき、あの人がいてよかった」と思ってもらえるような仕事をしていきたい。今日の疲れも、未来の誰かの「ありがとう」につながっていると信じて。