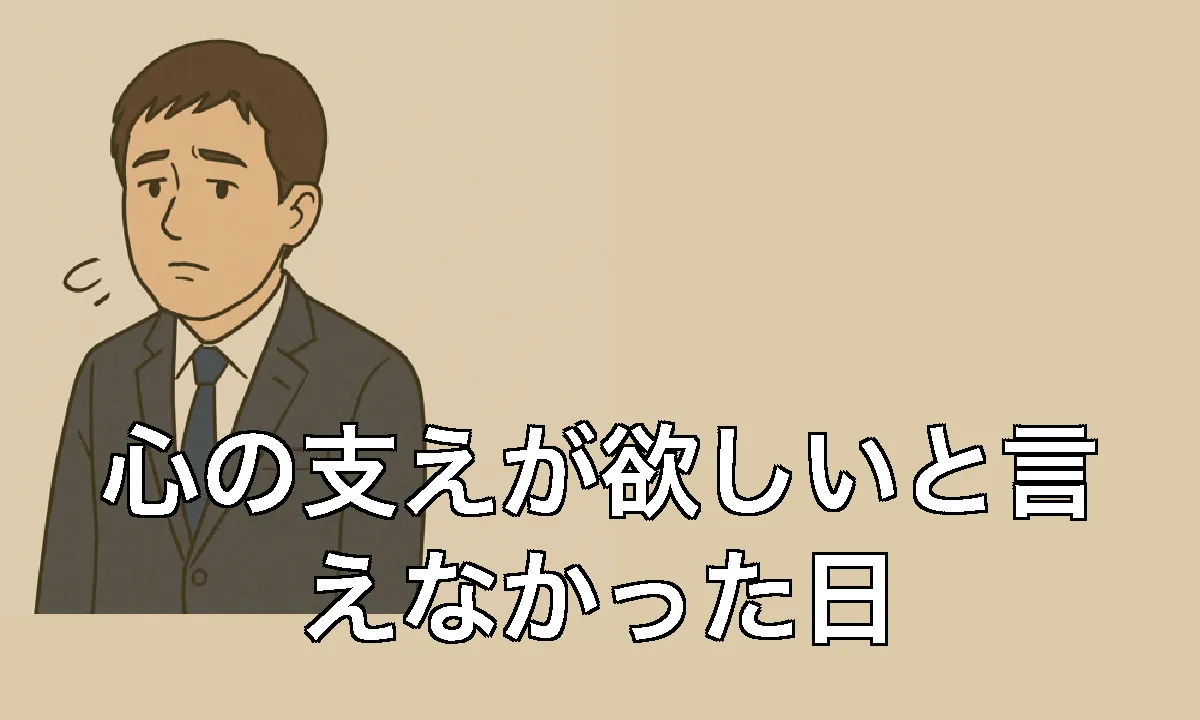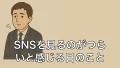心の支えが欲しいと思っても言い出せないときがある
「もう少し誰かに頼れたらなあ」と思うことはある。だけど、実際にその言葉を口に出したことは、たぶん一度もない。司法書士として独立して十数年、気がつけば「弱音を吐かない」が自分の美徳になっていた。苦しい日も、眠れない夜も、それでも「自分でなんとかしなきゃ」と踏ん張ってきた。だけど、年を重ねるごとに、ひとりで抱える重さに足が取られるようになった。誰かに言えたらどれだけ楽になるだろう。でも、「そんなことを言うなんて、情けない」と思ってしまう自分がいる。
ひとりで頑張り続けることに慣れてしまった
開業してからずっと、相談も判断も処理も全部ひとり。事務員さんには細かいことは任せられても、結局最後は自分が背負う。そんな生活が当たり前になってくると、「誰かに任せる」「相談する」という発想自体が抜け落ちてしまう。昔、部活ではキャプテンタイプではなかったけれど、今では「自分がなんとかする」ことに変な誇りさえ感じていた。だけど、それって本当は不自然な状態なのかもしれない。
「頼る」という選択肢が最初からない
正直に言うと、「助けて」と言える相手がいないというより、最初からその選択肢が頭に浮かばない。仕事中にトラブルがあっても、誰かに「ちょっと手伝って」とか「一緒に考えて」と言う発想がなく、自動的に「自分でなんとかするモード」に入ってしまう。これが癖になっているのか、性格なのかもう分からないけれど、とにかく誰かに頼るという感覚がどこか遠くなってしまったのは確かだ。
「大丈夫」と言ってしまうクセがしんどい
「大丈夫ですか?」と聞かれることはある。でもそのたびに「大丈夫です」と答える自分がいる。口ぐせのように出る「大丈夫」だけど、本当は大丈夫じゃないことの方が多い。たぶん、そういうときに「いや、ちょっとしんどいです」と言えたら、少しは気が楽になるのかもしれない。でも、長年積み上げた“ひとりで耐えるスタイル”はそう簡単には崩せない。しんどいのに、それを見せない自分にまた疲れていく。
誰にも迷惑をかけたくないという気持ちの裏側
「迷惑をかけたくない」というのは、司法書士という職業柄、誰もが口にする言葉かもしれない。でも、ふと気づいたのは、それが本当に「相手を思っての気持ち」なのか、自分の弱さを隠すための言い訳なのか分からなくなる瞬間があるということだ。誰かに助けを求めることは、迷惑ではなく信頼の表現だと頭では分かっていても、心がついてこない。そこには長年染みついた“プロらしさ”という呪縛がある。
正しさを求めすぎて心が枯れていく
「こうあるべき」「責任を果たすべき」「迷惑をかけるべきではない」。正しさを盾にして、自分の感情を押し殺す場面が多くなった。それは間違っていないかもしれないけれど、正しさを追い求めるあまり、心の柔らかさをどこかに置いてきてしまったような気がする。たまには正しさよりも、「今日は疲れたからもうやめたい」と言ってしまえる自分でいたいのに、言葉が喉で詰まってしまう。
感情を置き去りにした日々の仕事
日々の業務は淡々と進める。登記の申請、不動産の調査、相続の相談。感情を介入させない方が効率もいいし、ミスも減る。それは分かっているけれど、感情を置き去りにしすぎた結果、ふとした瞬間にぽっかり心に穴が開いたような感覚に襲われる。業務上は問題ない。でも、人間としてはどこか壊れていくような、そんな危うさがある。
司法書士としての孤独は想像以上だった
この仕事は、どんなに人と関わっていても、どこか孤独だ。クライアントとの距離、同業者とのライバル意識、事務所の責任。すべてが「ひとり」にのしかかってくる。そして、どこかで「愚痴ってはいけない」「甘えてはいけない」と自分を追い込んでしまう。だれかの言葉で救われたい、そんな気持ちを持っている自分に気づくのが、怖かった。
相談される側であっても本音は誰にも言えない
司法書士という職業は、人の悩みや不安を聞く側に立つことが多い。だからこそ、自分の弱音を誰かに吐くという発想がそもそもなかった。「プロなんだから」「感情に流されるな」と自分に言い聞かせてきた結果、どんどん自分の心の声が小さくなっていった。話すことが苦手なのではなく、聞いてくれる人がいないだけなのだと思う。
愚痴を吐ける相手がいないつらさ
元野球部時代は、誰かと愚痴を言い合ったり、冗談を飛ばしたりできた。でも今は、事務員さんとの会話も仕事の話が中心で、愚痴をこぼす場もない。飲み屋に行くことも減ったし、友人とも疎遠になった。「そういう年齢だよな」と思いつつも、本当は誰かに「今日は疲れたよ」とだけ言いたいだけなのに、それすら言えない自分がもどかしい。
人に弱さを見せられない職業病
たぶん、これは職業病なんだと思う。常に冷静に、的確に、論理的に。そういう姿勢が求められる仕事を長年やっていると、弱さを見せることに強い抵抗感が生まれる。でもそれって、本当に健康的だろうか。たまには「無理です」「助けてください」と言ったっていいじゃないかと、心のどこかで思っているのに、口には出せない。
事務所の看板を背負う重みと責任
たとえ規模が小さくても、看板を掲げるということは重い。クレームも判断ミスも、最終的にはすべて自分の責任。だからこそ常に気を張っている。だけど、その緊張状態がずっと続くと、心が麻痺してくる。自分の感情に鈍感になって、ただ義務をこなす毎日。そんな日々に、心の支えを求めることすら忘れてしまっていた。
誰にも気づかれないプレッシャー
外から見ると「順調そう」「しっかりしている」と言われる。でもその裏で、常に「この判断は本当に正しかったのか」「万一のトラブルには耐えられるか」と自問自答している。誰にも分かってもらえないプレッシャーが、じわじわと心を圧迫していく。それに気づいてくれる人がいればいいのにと、ふと思うことがある。
仕事が減る不安を誰かに言いたい夜
月末が近づくと、今月の売上、来月の見込み、資金繰りのことばかり考えてしまう。SNSでは「順調です!」と投稿する同業者が目につき、自分だけが取り残されているような気になる。そんな夜、ふと「大丈夫かな」と不安になる。だけどそれを誰かに言ったところで、何も変わらない気もして、結局ひとりで抱えてしまう。
「心の支えがほしい」と言えたときから変わったこと
あるとき、ふとしたきっかけで、昔の友人に「最近ちょっとしんどい」とだけLINEで送った。返ってきたのは、「分かるよ」「俺もそうだよ」という短い言葉。それだけで、なぜか涙が出た。たったそれだけのやり取りなのに、自分はどれだけ言葉を求めていたのかと実感した。心の支えは、立派な言葉じゃなくて、ただ「聞いてくれる誰か」の存在だった。
言えた瞬間の安心と涙
そのLINEのあと、久しぶりに電話をした。他愛のない話をしながら、最後にポロッと「実は最近ちょっと限界だった」と言ってしまった。すると相手は「なんだ、俺もだよ」と笑った。その瞬間、肩の力がすっと抜けた。誰かに気持ちを聞いてもらえることが、こんなに安心につながるとは思わなかった。
弱さを見せたからこそ救われた
「強くなければならない」と思い込んでいたけれど、実は弱さを見せることで救われることもある。むしろ、弱さを隠すことが孤独を深めていたのかもしれない。自分の中で一番しんどかったのは、「誰にも頼れない」という思い込みだったのだと、ようやく気づけた。
他人の言葉で気づいた自分の限界
「ひとりで抱えすぎだよ」と言われて初めて、自分が限界だったことに気づいた。そのときは笑ってごまかしたけれど、心の中では「やっぱり無理してたんだな」と思った。支えてもらうことに、もっと素直になってもいいのかもしれない。
これからの自分にとって大切にしたいこと
弱さを受け入れ、誰かに頼ること。それができるようになったら、もっと自然に生きられる気がする。司法書士という仕事を続けるうえでも、人として健やかでいるためにも、「支えてもらうこと」を否定しないようにしたい。これからは、もっと人とのつながりを大事にしていこうと思う。
心のよりどころを持つ勇気
心のよりどころは、いつも目の前にあるとは限らない。だからこそ、自分から少し勇気を出して手を伸ばすことが大切なのかもしれない。頼ることは恥ずかしいことではなく、人間らしくあるための自然な行動なのだと、今なら思える。
独りじゃないと思えるだけで軽くなる
不思議なもので、「独りじゃない」と思えるだけで、心はふっと軽くなる。重さが消えるわけではないけれど、持ち上げやすくなる。そんな感覚を、少しずつ増やしていけたらいい。仕事も人生も、ひとりで背負い込まずに、分かち合って進んでいけたら、それだけで十分なのかもしれない。