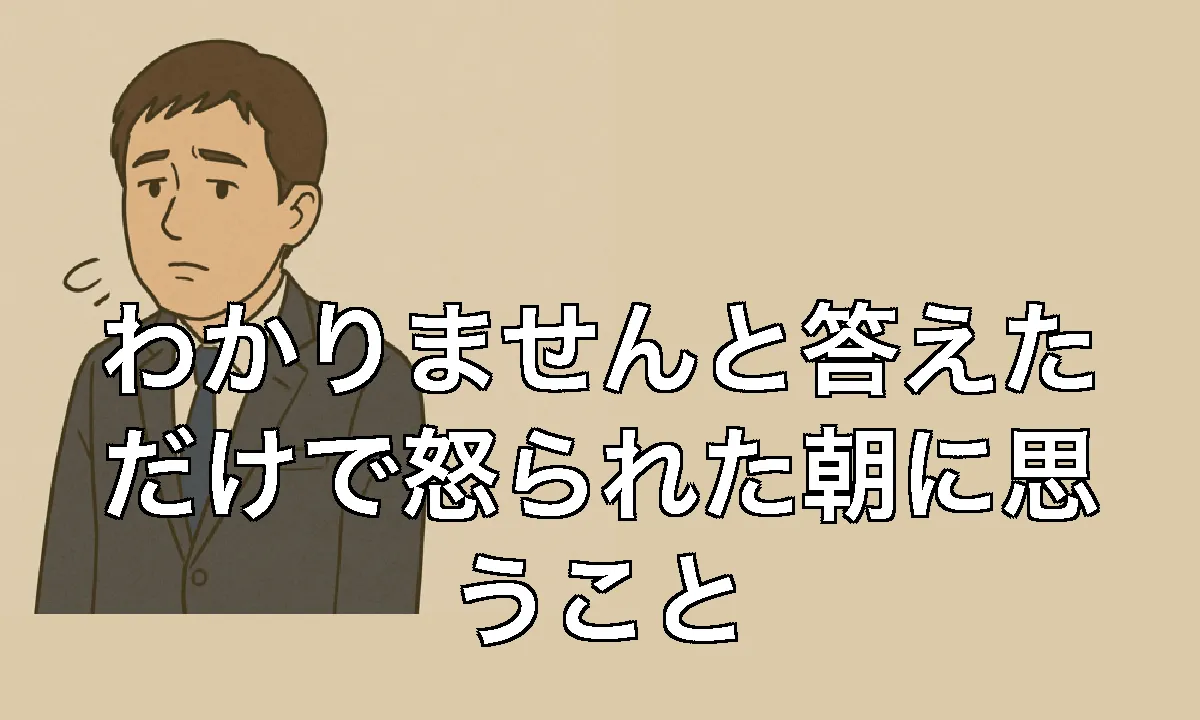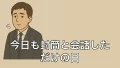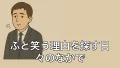静かな朝に降ってきた雷のような言葉
朝の事務所は、いつもより少しだけ静かだった。コーヒーを淹れて、デスクに座ってメールを確認していたとき、事務員から「この書類の処理って、どう進めたらいいですか?」と聞かれた。まだ把握できていなかった業務で、私は正直に「わかりません」と答えた。すると、思いもよらず、「え?わからないんですか?」と不機嫌そうに言われ、その後しばらく無言になった。たった一言でこんなにも空気が悪くなるのかと、心の中でため息をついた。
たった一言がここまで怒られるものか
「わかりません」という言葉は、そんなに罪深いのだろうか。確かに、司法書士として責任ある立場で仕事をしている以上、わからないことがあってはいけないのかもしれない。でも、すべての事案を瞬時に把握することなんて不可能だ。ましてや、朝一番のタイミングで、昨日の夕方に届いたばかりの資料に対して即答できる人間なんて、果たして存在するのか。私は不器用なタイプだし、事務処理も完璧じゃない。だけど、誠実には向き合ってきたつもりだ。
相手の期待に応えられない自分が情けない
怒られたこと自体よりも、「期待に応えられなかった自分」が情けなかった。事務員は若く、経験も少ない。だからこそ、自分に頼ってくれているのもわかっている。でも、その信頼に応えきれなかったことが胸に刺さる。こういう場面で「大丈夫、あとで調べて対応するから」と返せればよかったのかもしれない。正直に「わからない」と言うことは、自分にとっては誠意だったけど、相手にとっては不安や不満に変わることがあるのだと、改めて実感した。
でも本当に全部を把握している人なんているのか
いつも思う。「あの先生は完璧」と言われるような司法書士でも、きっと心の中では「わからない」と思っている瞬間があるはずだ。ただ、それを表に出さないだけで。自分だけが劣っているような気がして、時々押しつぶされそうになる。でも、実際にはそうじゃない。全部を把握しているふりをすることが本当に良いことなのか?嘘をつかずに「わからない」と言える勇気も、専門職には必要なんじゃないかと、自分に言い聞かせている。
説明不足で怒る側にも問題があると思ってしまう
全部自分の責任とは思っていない。相手の態度にも問題はあった。例えば、質問の仕方が曖昧だったり、前提情報が共有されていなかったりするのに、「なんでわからないんですか?」と詰め寄られても、それはちょっと違うだろうと思ってしまう。お互いに補い合う関係であるべきなのに、一方的に責められると、信頼関係も揺らぐ。そう感じるのは、私の心が狭いのだろうか。
察してほしいという圧力のしんどさ
「察して動け」という文化は、司法書士業界にも根強くある。でも、それは経験豊富な人間同士だから成り立つことで、若手や異業種から来た人にとっては負担でしかない。なのに、「言わなくてもわかるでしょ?」という無言の圧が事務所には漂っている。自分自身もその空気に飲まれていたのかもしれないし、無意識に同じようなプレッシャーを与えてしまっていたのかもしれない。
忙しい人ほど説明を端折る矛盾
忙しいと、人は説明を端折る。そして、その端折られた説明の中で「わからない」と言うと怒られる。これ、かなり矛盾していると思う。説明を省略された結果「わかりません」となるのに、それが無能と見なされる。理不尽だが、現場ではよくある話だ。自分も忙しくなると、つい説明を短く済ませてしまうが、そこに思いやりが欠けていたことを反省した。今後は「忙しいけど、説明は丁寧に」を意識していきたい。
「わかりません」は敗北なのか
この仕事をしていると、「わかりません」と口にすることが一種の敗北のように感じてしまう。何でも即答できるのがかっこいいし、信頼もされやすい。でも、それを装ってミスをすれば、結果的に迷惑をかける。だったら、「わかりません」と一度正直に言って、責任を持って調べて対応したほうが、長期的には信頼につながるんじゃないか。そう思っていても、やっぱり朝から怒られると心が折れそうになる。
元野球部のノーサインスイングの後悔
高校時代、元野球部だった私は、監督のサインを見落としてノーサインでバントを失敗したことがある。その時の怒号がいまだに耳に残っている。「勝手な判断をするな!」と。だけど、今は逆の立場で、指示を出す側になっているのに、「わからない」と言ったら怒られる。この矛盾が不思議でならない。どっちなんだよと思うけど、要するに「空気を読んで、適切な判断をしろ」という無理難題が課されているのだ。
正直者は損をするを地で行く瞬間
「わからない」と言ったら怒られ、「わかったふり」をしたらミスに繋がる。じゃあ、どうすればいいのか?この問いに対しての答えはいまだに見つからない。ただ、自分の性格的に、嘘をつくのはもっとしんどい。だから、怒られても「正直でいたい」と思ってしまう。だけど、その代償として信頼を失うなら、それは本末転倒かもしれない。こんなジレンマに、日々、静かに苦しんでいる。
地方の司法書士に求められる謎の全知全能感
地方でひとり事務所を切り盛りしていると、「何でも知ってる人」として扱われることが多い。登記だけじゃなく、相続、税務、成年後見、不動産、さらには市役所の制度まで、まるで町の知恵袋のような存在を求められる。でも、私は人間であってAIではない。知らないことはあるし、調べる時間も必要だ。それなのに、「先生ならわかるでしょ」と言われるたび、心の中で「いや、わかんねーよ」と叫びたくなる。
お客様も事務員もみんな頼ってくる
それが悪いわけじゃない。頼ってもらえるのは、ありがたいことだ。でも、全部を自分で抱えるのは難しい。ひとり事務所で、事務員さんも1人。しかもその人に気を使いながら、自分の感情を押し殺して業務をこなすのは、思っている以上に消耗する。「これ、私が答えて大丈夫なのかな?」と不安になりながら、それでも答えを出し続ける毎日。正直、たまには誰かに頼りたい。
でもこっちにも限界がある
人には限界がある。それは、仕事の量だけじゃなく、心のキャパシティにも言える。余裕がない朝、余裕がない言葉を投げられると、たった一言で心が折れそうになる。今回の「わかりません」事件も、まさにそうだった。きっと、事務員にも不安や苛立ちがあったのだろう。だけど、それをぶつけ合っても、いい職場にはならない。お互いに、「余裕がないときこそ、優しくなろう」と思える関係になりたい。
「全部知ってるでしょ?」という目線の怖さ
「先生なんだから知ってるでしょ?」という目で見られるのは、本当にプレッシャーだ。そう言われるたびに、胃がきゅっと縮まる感覚になる。期待されるのは悪いことじゃない。でも、それが「間違えられないプレッシャー」になってしまうと、仕事がどんどん苦しくなる。もっと「一緒に考える」「一緒に悩む」という姿勢でいられたら、司法書士という仕事も、少しはやりやすくなるんじゃないだろうか。