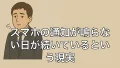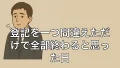遺言書がもたらした想定外の嵐
司法書士として働いていると、遺言に関する相談は日常茶飯事です。けれど、ある日届いた依頼は、まさかここまでこじれるとは思ってもみなかった――そんな出来事でした。故人が残した公正証書遺言は形式的には何の問題もなく、登記もスムーズに進むはずでした。ところが、それを目にした親戚たちがまるで爆弾が投げ込まれたかのように怒り出したのです。中には机を叩いて「こんな遺言、信じられるか」と叫ぶ人までいました。あの瞬間、私は「正しさ」が人を救うわけではないことを痛感しました。
きっかけは一通の封筒だった
依頼者は亡くなった方の甥でした。しっかりとした口調で「遺言の通りに進めてほしい」と言われ、私は通常通りに手続きを進めるつもりでした。けれどその後、親戚筋にあたる別の方々が次々と事務所にやってきて、「こんなの納得いかない」「生前にそんな話は聞いていない」と反発。聞けば、被相続人とある家族の間には長年の確執があり、それが遺言にまで影を落としていたのだとわかりました。一通の封筒が、長年の蟠りを一気に吹き出させてしまったのです。
「争族」は突然に
テレビや雑誌では「争続」なんて言葉を見かけることがありますが、まさか自分がその最前線に立たされるとは思いませんでした。親戚たちは口を揃えて「うちの家が軽んじられている」と訴え、しまいにはそれぞれが弁護士を立てる事態に。私は司法書士としての立場を守りながら、中立性を保つ必要がありましたが、それがかえって「どっちの味方なんだ」と誤解を招くことにもなりました。人間関係のヒビは、一度入ると簡単には埋まりません。
誰も悪くないはずなのに空気が殺伐とした
この件で一番辛かったのは、「誰か一人が悪いわけじゃない」と分かっているのに、空気がどんどん悪くなっていったことです。亡くなった方にはその人なりの考えがあり、それを形にしたのが遺言だった。ただそれだけの話だったのに、それが「不公平」と映った瞬間、家族だったはずの人たちが敵味方に分かれてしまう。何年も会っていなかった兄弟たちが、罵声を飛ばし合う姿は、見ていて本当に胸が苦しくなりました。司法書士として、何もできない自分が無力に思えました。
司法書士という立場のジレンマ
このような案件に携わると、自分の役割について深く考えさせられます。私たちはあくまで「法的手続きの専門家」であって、調停役でも裁判官でもない。でも、現場では往々にして感情の矢がこちらに向いてくる。「中立であること」が逆に「冷たい」と捉えられてしまうのです。理屈で割り切れない世界に足を踏み入れた瞬間、ジレンマが生まれます。
法的には正しいでも感情が納得しない
法的には遺言書が有効であれば、それに従って手続きを進めるだけ。それが司法書士の仕事です。けれど、現場では「そんな冷たい話じゃ済まない」と迫られることもあります。遺言の内容に納得できず、涙を流しながら「なんで自分だけ除け者にされたのか」と訴える方の姿に、こちらの心も揺れます。正論は感情を癒やさない。それがこの仕事の難しさでもあります。
「あんたもグルか」と言われたあの日
一番堪えたのは、ある親族の方に「あなたもグルなんじゃないの」と言われたときです。冗談ではなく、本気の目つきで言われました。何度も説明しても、私が相続人の一人と仲が良いと疑われたのです。身の潔白を証明する術もなく、ただじっと耐えるしかありませんでした。あの日は、事務所の帰り道、ひとり車の中でしばらく動けませんでした。
事務所の空気にも影響する
仕事の現場が荒れると、当然ながら事務所の雰囲気も悪くなります。事務員にも気を遣わせることになり、自分のミスじゃないのに謝ってくれたりする。そんな姿を見ると、余計に自分のふがいなさを痛感します。狭い事務所の空気は濁っていき、電話の音すら神経に触るようになる――そんな日々が続きました。
事務員の前でため息ばかり
いつもは笑って世間話をしてくれる事務員が、その日は少し距離を取っているように感じました。無意識に、ため息ばかりついていたのかもしれません。話しかけにくい空気を出してしまっていたんでしょう。「先生、ちょっと休んだほうが…」と気を遣われる始末。誰にも当たれないまま、自分の感情をどこにもぶつけられずにいるのが、なによりもしんどい。
依頼者の怒号が壁を突き抜ける
とある日、依頼者が怒鳴り声で抗議に来たときのこと。壁の薄い事務所なので、隣の部屋までその声が響きました。事務員がそっとドアを閉めてくれましたが、それでも空気は重たくなるばかり。お互い気まずくて、しばらく無言。仕事なんて手につくわけもなく、ただ時間だけが過ぎていきました。こういうときこそ「笑い飛ばせる強さ」が欲しいと思いました。
自分の正義が通じない虚しさ
私はこの仕事を「人を助ける仕事」だと信じてきました。だけど、実際の現場では、誰一人笑っていない。むしろ関わったことで関係が壊れてしまったのでは、と自問自答する日々でした。正しいことをしても、誰の救いにもなっていない。そんな気持ちが、じわじわと心を蝕んできます。
ルールを守っても誰も救えない感覚
「法律通りにやってください」——それが私の役割。けれど、その通りに動いても、依頼人から「冷たい人ですね」と言われることがあります。誰かが泣いて、誰かが怒って、そして誰も納得していない。ルールは確かに必要だけど、人の心には届かない。それが積み重なると、「この仕事、意味あるのかな」と思ってしまう日もあります。
「正しさ」よりも「納得感」が求められる場面
ある年配の女性が、「納得できるかどうかなんですよ」とぽつりと言った言葉が忘れられません。法律の話を丁寧に説明しても、その人の心には届いていなかった。人は感情の生き物です。「なぜ私だけが損をしたように感じるのか」を解きほぐすには、法的知識だけでは足りません。その現実に、何度となく突きつけられています。
それでも前を向くために
こんなことがあるたびに、「もうやめたいな」と思う瞬間があります。だけど、ふとしたきっかけで救われることもある。たとえば、同業の仲間のひと言や、昔の依頼者から届いた感謝の手紙。そういう小さな光があるから、なんとか踏みとどまっているのだと思います。
共感できる同業者の存在が支えになる
先日、昔一緒に研修を受けた同業者と電話で話しました。内容は他愛もないものでしたが、「そういうの、あるよね」と共感してくれただけで、なんだか気が楽になったんです。わかってくれる人が一人でもいる、それだけで孤独感は少し薄れます。誰かとつながっているという感覚が、前に進む力になります。
元野球部の気持ちで踏ん張る
中学高校と野球部だった自分を思い出します。あの頃、毎朝のランニングも、理不尽な練習も、正直きつかったけど、チームで耐えてきた。あの経験があるから、今も「ここが踏ん張りどころだ」と思えるのかもしれません。どんなに気持ちが沈んでも、次の日の朝にはまたユニフォーム――いや、スーツを着て、事務所の鍵を開ける。そんな繰り返しを、今日も続けています。