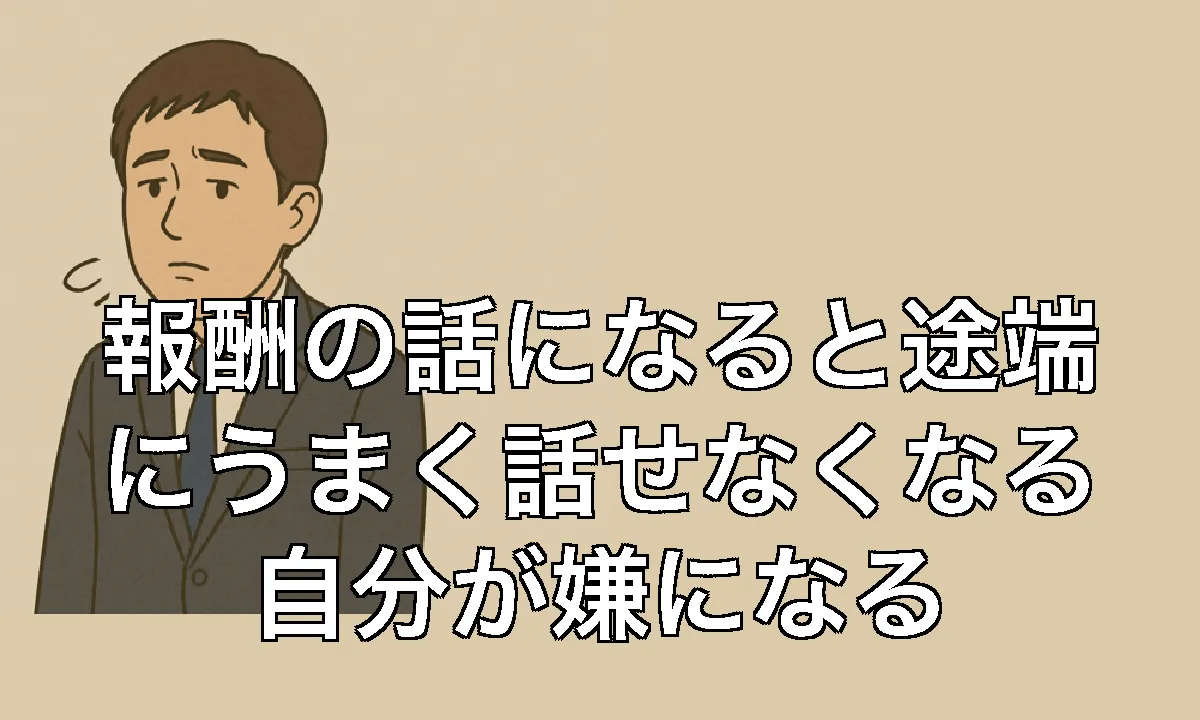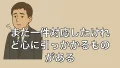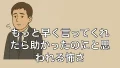報酬の話になると途端にうまく話せなくなる自分が嫌になる
報酬説明が苦手な自分を自覚した瞬間
司法書士として独立してから十数年、依頼の内容にも対応の仕方にも慣れてきたはずなのに、どうしても苦手な場面がある。それが「報酬の説明」だ。業務内容を丁寧に説明した後、「で、報酬は…」という空気になったとたん、頭の中が真っ白になる。なんとも情けない話だが、本当に言葉が詰まってしまう。これは新人時代だけの話ではなく、未だに続いている困ったクセである。
「いくらですか」と聞かれてフリーズする
たとえば、電話で問い合わせがあったとき。「相続登記をお願いしたいんですが、おいくらぐらいですか?」と聞かれると、内心ドキッとしてしまう。あらかじめ料金表を準備しているにも関わらず、声が小さくなったり、要領を得ない説明になったりする。結果、「うーん、ちょっと検討してまたお電話します」と言われるパターンが多い。報酬そのものに問題があるわけではなく、伝え方に問題があるのだと思う。
値段の話になると空気が変わる
事務所に来てくれたお客様との面談中でも、報酬の話に入った瞬間に少し空気がピリッと変わるのを感じる。「それは私のせいかもしれないな」と思うこともある。こちらが申し訳なさそうに話すと、相手も身構えるのだ。値段の話=対立の始まり、のように錯覚してしまう自分がいる。これは性格の問題か、あるいは過去の苦い経験の積み重ねなのか。いずれにしても、この話題になると心が萎縮してしまう。
なぜ報酬の話がうまくできないのか
司法書士の報酬は、自由に決められる部分が多い。だからこそ、基準があいまいで伝え方が難しい。お客様ごとに状況も異なるため、見積もりも一概には言えない。それが報酬説明を複雑にしてしまっているのかもしれない。ただ、それ以上に「断られたらどうしよう」「高いと思われたら嫌だな」という心理的なブレーキが自分の中にある。
断られるのが怖いという心理
報酬の説明をするとき、頭の中には常に「これで引かれたらどうしよう」という不安がよぎる。過去に、「それってちょっと高すぎませんか?」と苦い顔をされたことが何度かある。それが尾を引いている。別に法外な金額を提示しているわけではないし、相場から逸脱しているわけでもない。でも、一度でもそう言われると、自信がなくなってしまう。自分の価値を数字で伝えるのは、なぜこうも難しいのか。
「高いですね」と言われた日のトラウマ
何年か前に、知人の紹介で来てくれた依頼人がいた。相続登記と名義変更の一連の作業で、明細付きの見積書を渡したのだが、「…結構かかるんですね」とポツリ。笑ってごまかしたが、その後、その依頼はキャンセルになった。きっと金額の問題というより、「説明下手」が原因だったと今なら思う。あのときもっときちんと話していれば、という後悔がずっと残っている。
正当な報酬への自信のなさ
どうしても「こんなにいただいていいのだろうか」と思ってしまうのは、自己肯定感の問題かもしれない。ちゃんと仕事して、責任も背負って、時間も使っているのに、「申し訳ない」という感情がどこかにある。お客様のことを思えばこそ…と自分に言い聞かせるが、それが結局、自分の首を絞めているような気がする。
自分の価値をうまく伝えられない
報酬の中には、「作業時間」や「書類の正確性」だけではなく、「責任」や「リスク管理」も含まれている。でも、それを言葉にして伝えるのが本当に難しい。「登記をするだけ」と思っている人には、「なんでそんなにかかるの?」と感じられてしまう。そのギャップをどう埋めるか。ここが報酬説明の核心だと思う。
依頼人との温度差に悩む
私たちにとっては日常の業務でも、依頼人にとっては一生に一度の手続きだったりする。だからこそ、金額に対する敏感さも違う。こちらは「当然かかる費用」と思っていても、相手は「そんなに必要なの?」と感じている。説明の仕方ひとつで、不信感に変わることもある。そこが難しい。
「全部でそれだけですか?」という誤解
以前、見積書を渡したときに「それで全部ですか?」と聞かれた。そのときは「はい」と答えたが、後日、印紙代や登録免許税について「聞いていなかった」と言われた。見積もりに明記していたとはいえ、説明不足を反省した。お金のことは、言葉で伝えて、目でも確認してもらう。それくらい丁寧にやらないと伝わらない。
サービスの範囲と料金の境界が曖昧になる
たとえば、相続の案件で戸籍の取得から不動産の調査、登記まで一貫して請け負うと、どこまでがサービスでどこからがオプションなのか、自分でも曖昧になることがある。「ついでにこれもお願い」と頼まれて断れず、後から「あれ、料金に入ってたっけ?」となることも。結局、自分が損をする形になる。これは完全に説明不足のツケだ。
説明下手が招いた信頼の揺らぎ
報酬の説明が曖昧だと、信頼を損なう。悪意がなくても、「後出しじゃんけん」みたいに思われてしまうからだ。それが一番怖い。誠実に仕事をしているつもりでも、説明が足りないと意味がない。自分では丁寧にやっているつもりでも、相手の立場に立てていないことに気づかされる。
あとからトラブルになる不安
業務が完了してから「え、そんな金額聞いてないです」と言われるのが一番困る。言ったつもり、書いたつもりでも、相手が納得していなければ意味がない。説明の時点で「念のためにもう一度言いますが…」としつこいくらい伝えるのが、やはり大事なのだと思う。
事務員にも迷惑がかかる
うちの事務員は、私よりも説明が上手かもしれない。お客様への電話や郵送物のやりとりで、丁寧にカバーしてくれている。でも、報酬説明のモヤモヤを残したまま業務に入ると、彼女にも余計なストレスがかかる。それも申し訳ない気持ちになる。だからこそ、最初の説明は私の責任でしっかり果たさねばと、反省するばかりだ。
それでもやっぱり言いづらい日はある
何度練習しても、場数を踏んでも、やっぱり言いづらいときはある。忙しい日や、気分が沈んでいるときは特にそうだ。自信を持って言い切れない自分が情けない。でも、こういう「言いにくい」を乗り越えるたびに、少しずつ成長している気もする。報酬の話は、ある意味で自己肯定の訓練でもあるのかもしれない。
報酬の話は信頼の一歩目
お金の話は、決して避けるべき話題ではない。むしろ、それを最初にきちんと伝えることで信頼が生まれる。誠実に、わかりやすく、堂々と。そうありたいと思いながら、今日も事務所の電話が鳴る。報酬の説明は、私にとって永遠の課題かもしれない。でも、逃げずに向き合いたい。