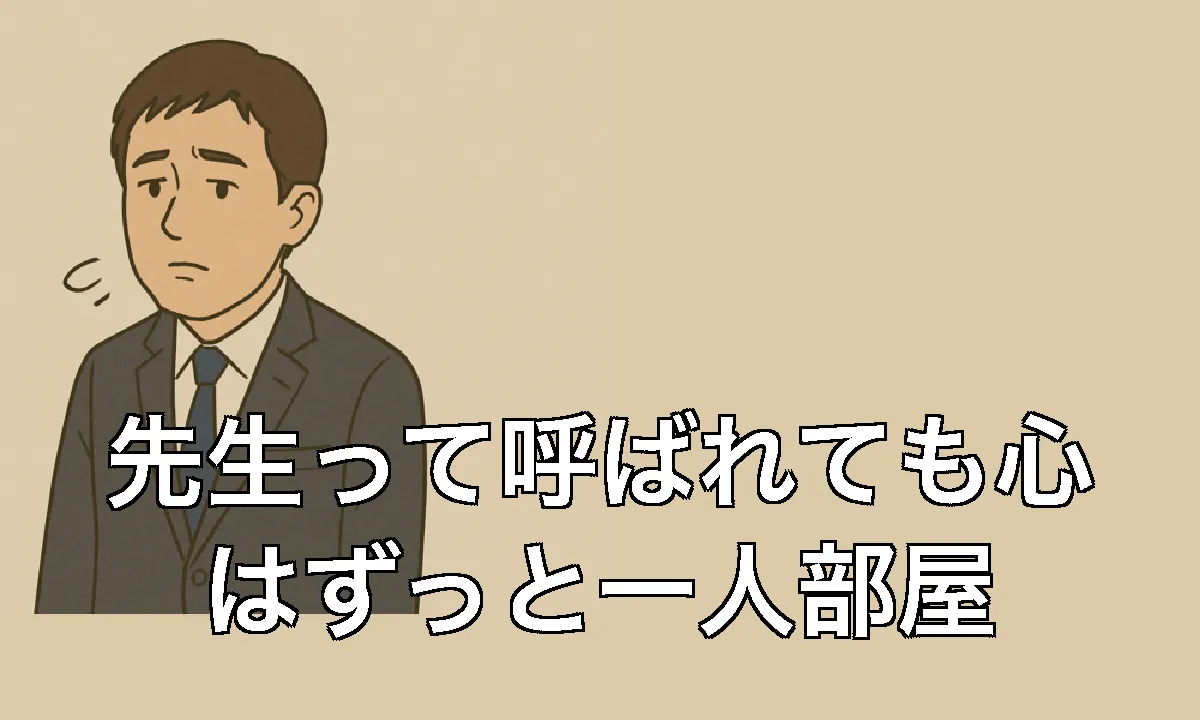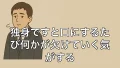先生という肩書きは立派に見えるけど
司法書士として開業して十数年。名刺にも看板にも「司法書士 稲垣」と堂々と肩書きが書かれているし、依頼者からは「先生」と呼ばれる。だが、その響きが時にむなしく感じるのはなぜだろう。誰かに頼られ、信頼されている証であるはずなのに、自分の内側はいつも「一人部屋」にいるような感覚がある。肩書きだけが先行して、心の実態とはどこか乖離している。そんなふうに感じるのは、自分だけだろうか。
呼ばれ慣れたはずの言葉が重く響く朝
朝、事務所に入ると電話の留守電ランプが点滅していて、事務員さんが「おはようございます、先生」と声をかけてくれる。その挨拶に、自然に「おはよう」と返す。でも内心では、まだ「先生」と呼ばれることに慣れていない気持ちが残っている。名前を呼ばれることがなくなり、人格より役割で見られるようになった気がしてしまうのだ。「先生」という言葉には信頼と尊敬が込められているのだろうけれど、それだけに自分の不完全さが際立って見える瞬間でもある。
「おはようございます先生」の声に返す愛想笑い
「先生、お茶淹れましょうか?」そんな優しい声をかけられても、どこか自分は「上に立たされている」ような居心地の悪さがある。昔は、上司にお茶を出す側だった。立場が変われば関係性も変わる。だが、自分の中身はあの頃のまま、野球部でグラウンドを駆け回っていた青年のようなままで、ちっとも偉くなんかない。そう思いながらも、反射的に愛想笑いを浮かべて「ありがとう」と返してしまう。役割と素の自分とのズレに、時折ふとした疲れを感じる。
本音を見せる相手がいないまま一日が始まる
事務所に流れる空気は穏やかだ。でもその中で、自分の本音を話す相手は誰もいない。「今日ちょっと気が重い」とか「昨日の相談、正直きつかったな」と、ぽろっと言える誰かがいれば少しは楽なのに。結局、心に鍵をかけたまま、案件ごとの対応に追われ、電話を取り、書類を見て、また次の予定へと移っていく。淡々と始まる毎日に、心の温度がどんどん低くなっている気がしてならない。
事務所には自分と一人の事務員だけ
都会の大手事務所とは違って、うちの事務所は小さな町の一角にある。人員も最小限で、自分と事務員さんの二人三脚。ありがたい存在である反面、気軽な雑談や気を抜いた会話はあまりない。日々の業務に集中するあまり、「雑談の間」がないとも言える。そんな静けさが心にじわじわと染み込んでいく。
静かすぎる昼休みと気まずい沈黙
昼休み、電子レンジで弁当を温める音が響く。それ以外の音は時計の針の音と、外から聞こえる車の音くらい。事務員さんはスマホをいじり、自分はなんとなくネットニュースを眺める。それだけ。話すことがないわけじゃない。でも話すきっかけがない。こんなに人が近くにいるのに、心の距離は遠い。そんなことを考えると、弁当の味がどこかぼやけて感じられる。
雑談すら気を使う小さな職場
雑談ひとつ取っても、こちらが「先生」という立場だからか、事務員さんも言葉を選んでいる気がしてならない。「先生のご趣味は?」なんて聞かれることがあっても、正直なところ答えに詰まる。昔は野球だったけど、今は趣味と言えるものが思いつかない。そんな自分に気づくと、ますます会話の糸口が見えなくなる。距離が近いようでいて、どこか壁があるのが小さな事務所の現実だ。
「先生」って呼ばれるたびに壁ができていく
「先生」と呼ばれるたびに、相手が一歩引くのがわかる。そうなるとこちらも一歩引いてしまい、結果として心の距離はどんどん広がっていく。本当はもっとフランクに話したいし、笑いたい。でも「先生」という肩書きが、自然な関係性を邪魔しているように感じることがある。壁を作っているのは自分かもしれない。そう思っても、簡単に壊せるものではないのが現実だ。
頼られるのは嬉しいけど本当は苦しい
「先生にお願いしてよかったです」そんな言葉をもらうたびに、嬉しさと同時に「次も完璧にやらなきゃ」というプレッシャーがのしかかる。自分一人で背負いすぎていることに気づいても、頼れる人がいないから結局全部やってしまう。相談された時の責任感は強く、逃げ出したいと思ったことはない。でも、「誰かに頼られっぱなし」という状態が、じわじわと心を削っていく。
全部自分で背負い込んでしまう性分
「人に任せるのが苦手」それが昔からの性格だった。学生時代、野球部でキャプテンをやっていたときもそう。自分がエースで4番、試合の作戦まで一人で考えていた。でもそれで失敗すると、全部自分のせいになる。それでも、人に頼むよりは自分でやったほうが気が楽だった。今もその感覚が抜けない。だから、仕事も自分で背負い込み、結局どこかで疲れが爆発する。
弱音を吐いたら先生失格なのか
「先生って、いつも冷静ですね」と言われたことがある。その言葉の裏に「感情を表に出さない人」というイメージがあるとしたら、それは誤解だ。本当はしんどい時もあるし、不安で眠れない夜もある。でも、相談者の前で「疲れました」なんて言えない。だからいつも元気なふりをする。それが「先生」の仕事なのだと、どこかで自分に言い聞かせている。
人のことは聞けても自分のことは話せない
人の悩みには寄り添えるのに、自分の悩みは誰にも言えない。この矛盾が一番つらい。専門家としての自覚があるからこそ、弱音は見せられない。でも、誰かに「それは大変だったね」と言ってもらえたら、救われる気がする。たまには自分も、話す側になってもいいのかもしれない。だけどその一歩が、なかなか踏み出せないままだ。
それでも「先生」と呼ばれる意味
「先生」と呼ばれることに、今でも違和感はある。でも、その言葉に込められた期待や信頼を、ないがしろにはできない。自分を必要としてくれる人がいる限り、役割を果たすしかない。だけど、心がすり減っていくばかりでは続かない。「先生」である前に、自分自身を大切にすることも必要だと、最近ようやく思えるようになってきた。
誰かの支えになるという役割の責任
司法書士という職業は、人の人生に深く関わる仕事だ。登記、相続、遺言、成年後見…。一つひとつに人の思いや背景がある。だからこそ、気を抜けないし、真剣に向き合う。でも、支えるばかりではこちらももたない。自分自身の支えがなければ、いずれ折れてしまう。責任を持つことと、自分を守ることは、両立していいのだと信じたい。
肩書きに飲み込まれずに自分を保つには
「先生」ではない時間をどう過ごすかが、今の自分にとっての課題だ。趣味を持つ、誰かとご飯を食べる、愚痴をこぼせる相手を探す。そんな小さなことが、肩書きに飲み込まれないための支えになるのだろう。昔のようにバッティングセンターにでも行ってみようか。そんなふうに思える日は、少しだけ心に余裕がある証かもしれない。
先生も人間だと言える勇気を持ちたい
完璧じゃなくていい。強がらなくてもいい。「先生」も人間なのだから。そう言える勇気を持つことが、これからの自分に必要なのかもしれない。弱さを受け入れることで、人にも優しくなれる。誰かに支えてもらうことで、もっと深く支え返せる。そんな循環が生まれるように、自分を見つめ直す時間も、きっと大事なのだろう。