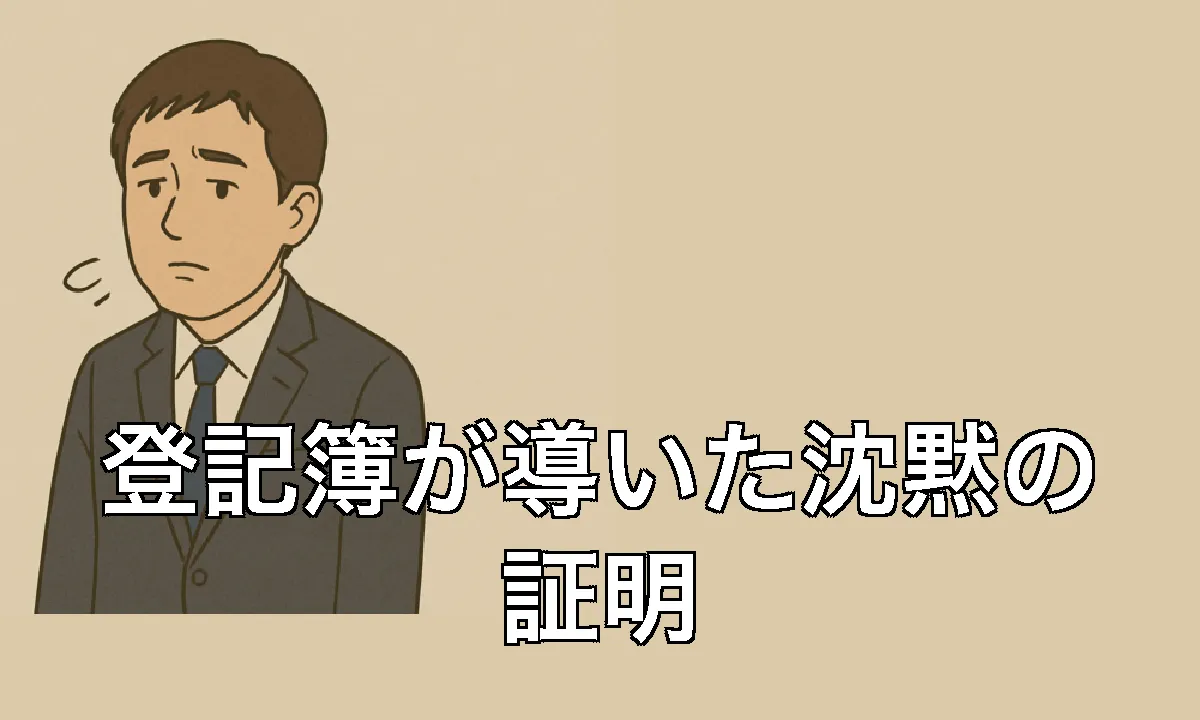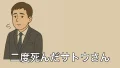朝の来客と古びた謄本
午前9時。まだコーヒーも飲みきらぬうちに、事務所のドアがキィと重たく開いた。入ってきたのは、古びたカバンを抱えた初老の女性だった。
「この土地、父の名義だと思ってたんですけど、登記簿を見たら違うんです」そう言って差し出されたのは、色褪せた登記簿謄本のコピーだった。
目を通した私は思わず眉をひそめた。一見なんの変哲もない名義変更だが、そこには妙な不一致があった。
一冊の謄本がもたらした違和感
住所表記、地番、日付。いずれも正しいように見えたが、筆跡に違和感がある。筆記体のように崩れた文字が、まるで何かを隠すようにしていた。
「サトウさん、これ見てみてくれ」呼びかけると、サトウさんは無言で近づき、謄本に目を走らせた。
「これは、、、直筆じゃないですね。筆跡が混ざってる」冷静な分析が、事務所に緊張を走らせた。
サトウさんの冷たい推理
「この登記、平成十年の名義変更に不自然さがあります。登記原因が“遺産分割”なのに、当時の登記官の押印がない。つまり、、、」
「つまり、提出書類そのものが偽造されていた可能性があるってことか」私はつい口を挟む。
「ええ、たぶん、遺産分割協議書の作成日が嘘です。日付が平成十年になってますが、書式が令和以降のものです」
依頼人の名義に潜む疑惑
彼女の父が死亡したのは平成六年。四年後に名義が変更されたというが、それにしてはあまりにも協議が早い。そして協議書には他の相続人の署名も印鑑もない。
「他の相続人とは話してないんです。父が死んでからは音信不通で……」と依頼人は言う。
「その時点で登記申請したのは誰か、覚えてますか?」私が尋ねると、女性は黙ったまま首を振った。
一字違いの登記簿の正体
地番をよく見ると、依頼人が言う「三番地」ではなく「三番地一」になっていた。つまり、彼女の父が所有していたのは隣の土地だったのだ。
登記簿のずれは、申請時のミスでは済まされないレベルだった。意図的に「隣地」を狙った形跡すらある。
「これ、意外と派手な事件になるかもしれないですね」とサトウさんは呟いた。
遺産分割協議の落とし穴
私は市役所の戸籍係に電話をかけ、相続関係図を取り寄せる手続きをした。そして、念のため協議書の提出先法務局にも照会をかけた。
「協議書は原本還付済みで、法務局には写しも残っていないんです」担当者の声は申し訳なさそうだった。
「やれやれ、、、またか」小声でつぶやいた私は、電話を切って机に突っ伏した。
名義変更の手続きと過去の登記
サトウさんが閉鎖登記簿の取得を申し出てくれた。その判断の早さには驚くしかない。元野球部の勘より遥かに優秀だ。
昭和時代の登記簿を確認すると、所有権移転が一度も行われていないことが判明。つまり、三番地のまま放置されていた土地だった。
「誰かが意図的に、取り残された土地を利用して名義変更を図った」私は確信に近い感覚を覚えた。
昭和時代の謄本に記された影
昭和五十五年の記載には、依頼人の祖父の名があり、その後一切の登記がなかった。通常なら相続のタイミングで何らかの移転が発生する。
だが、この土地は登記上ずっと“生きたまま”放置されていたのだ。所有者不明土地問題が、ここにも忍び寄っていた。
「昭和の謄本は、今でも立派な証拠になるんですね」サトウさんがつぶやいた。
サザエさん一家と似た家族構成
依頼人の父は長男で、妹が二人。サザエ、カツオ、ワカメの三兄弟構成と同じだ。だが、家族仲はそうはいかなかったらしい。
「昔は兄弟でよくケンカしてて、相続の話なんてとてもできなくて……」依頼人の声は寂しげだった。
「波平さんみたいな父親がいれば違ったんでしょうけど」私は妙にリアルな例えを口にしてしまった。
司法書士会での地味な調査
法務局での照会のあと、私は司法書士会の相談センターに赴いた。過去の申請者に同姓同名の司法書士がいないか調べるためだ。
「平成十年当時、この登記を担当した司法書士はいません」調査結果は意外なものだった。
つまり、登記が“無資格者”によって行われた可能性が浮かび上がってきた。
閉鎖登記簿の罠と地番の罠
閉鎖登記簿にあったのは、まさに依頼人の祖父の名前だった。しかし、書き換えられた協議書には彼の名前が見当たらない。
つまり、最初から「存在していない土地」であるかのように演出されていたわけだ。
私は、地番のずれと閉鎖簿の記録から、誰かが土地を乗っ取ろうとした意図を読み取った。
静かに崩れていく証言
再度訪れた依頼人は、祖母から聞いたという話を語り始めた。「父の死後、どこかの行政書士が来て、印鑑だけ押させたって言ってました」
それが事実なら、協議書の署名も内容も、すべてが作為的に書かれたものとなる。
行政書士の名は残っておらず、既に引退していた。真相はすでに風化しかけていた。
おばあちゃんの記憶が揺らぐ瞬間
「うちの父ちゃん、三番地の横に畑持ってたんじゃよ。だけん、そっちの話かと思って、、、」
祖母の証言は決定打となった。三番地一の名義変更は、まさにその畑を狙った動きだったのだ。
しかし、土地の境界は当時の地図では曖昧で、第三者の立証は難しい状況だった。
サトウさんのひと言と気づき
「これ、登記されたときにわざと隣地を申請したんじゃないですか。境界の杭が動かされてる」
サトウさんの言葉に私ははっとした。現地確認を怠っていたことに気づいた。
境界杭の一つが明らかに傾いており、しかも最近掘り返されたような跡があった。
土地の一部にだけ違う何かがある
地目が畑であるにも関わらず、一角にだけコンクリートが敷かれていた。その上には、古いプレハブが置かれていた。
誰が置いたのか、何の許可も取られていない。まるで土地の権利を誤魔化すかのような作りだった。
私は「これは警察に言ってもいいかもしれん」と、久々に真顔でつぶやいた。
沈黙が語るもう一つの相続
後日、依頼人の兄が現れ、驚きの事実を明かした。「父が死んだあと、地主のことで親戚ともめたんだ。誰が名義を取るかでな」
結果、名義変更の必要に迫られた兄が、書類を勝手に作成し、無資格の者に提出を頼んだというのだ。
「俺たちは争いたくなかった」と兄は言ったが、すでに争いは始まっていたのだった。
真の権利者は誰だったのか
名義上の正当性と、実質の所有との乖離。それをどう立証するかが、司法書士としての最後の仕事となった。
私は、調査報告書をまとめ、登記の是正に必要な手続きに入った。依頼人は涙を流して「ありがとうございます」と頭を下げた。
私は内心で、「元野球部でもたまには三振じゃなくて、サヨナラヒットを打つこともある」と思った。
やれやれとつぶやく暇もない結末
時計を見ると、午後八時を過ぎていた。サトウさんは無言で帰り支度をしている。私はようやく、椅子にもたれた。
「やれやれ、、、」とつぶやいたものの、疲労感に押しつぶされて声は出なかった。
事件は終わった。でも、登記簿が語る沈黙は、いつも次の謎を連れてくるのだ。