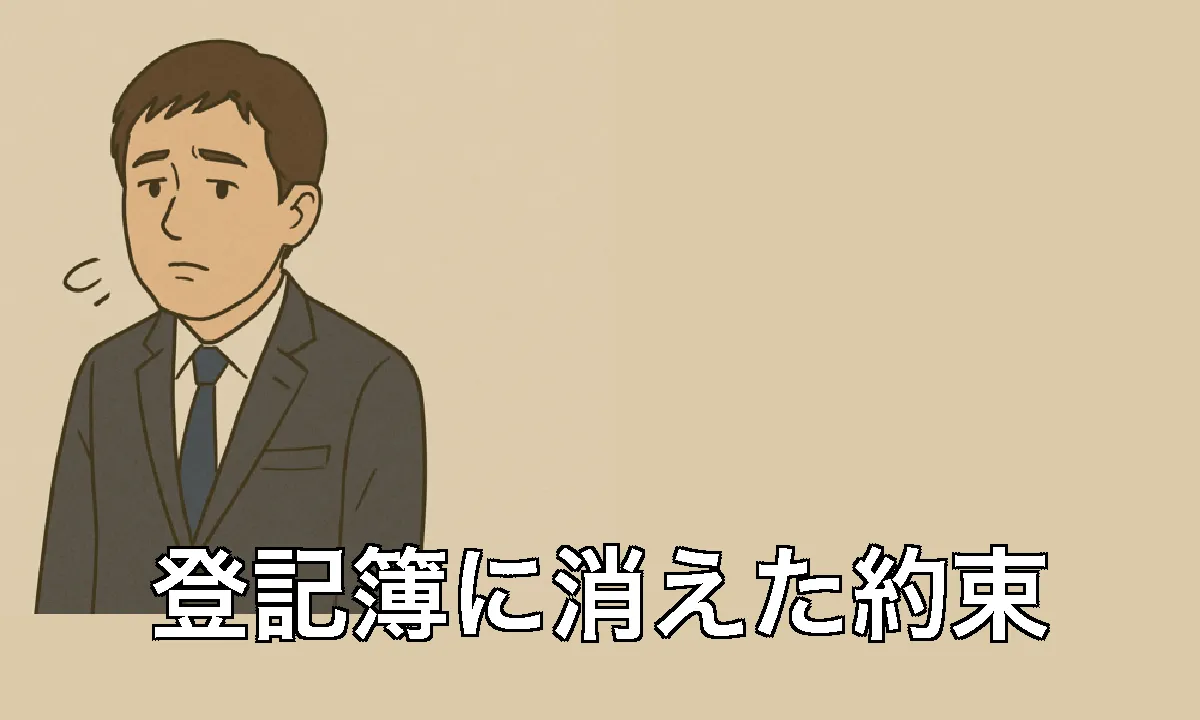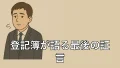朝の訪問者
旧家から届いた一通の手紙
朝のコーヒーに口をつけたところで、事務所のドアが静かに開いた。背筋の伸びた老紳士が手に一通の手紙を持って立っていた。封筒の端が擦り切れていて、長い間どこかにしまわれていたことを物語っている。
「祖父の土地に関して、どうにも腑に落ちない点がありまして」と老紳士は言った。聞けば、最近になって相続の話が持ち上がり、登記簿を確認していたところ、名義が誰のものでもないような妙な状態になっているらしい。
依頼者の口から出た違和感のある一言
「不思議なんです。祖父は、確かに亡くなる前に“約束した”と言っていたんです」その一言が、妙にひっかかった。約束とは法的な意味を持つ契約なのか、それとも単なる口約束なのか。司法書士としては、聞き逃せない言葉だった。
私はうなずきつつ、封筒から出てきた一枚の古びたメモを手に取った。そこには震えるような文字でこう記されていた。「正義は記録されないが、登記は真実を語る」。
古びた登記簿の中で
土地の名義に記された奇妙な注記
法務局で取得した登記事項証明書には、不思議な仮登記が残っていた。所有権移転の仮登記でありながら、登記原因も登記義務者も不明。さらに“条件付き”との注記が手書きで記されていたのだ。
その手書きの部分は明らかに正式なものではない。にもかかわらず、妙に存在感があった。まるで誰かが後から追加したかのような違和感がある。昭和の終わり頃にされた登記らしい。
仮登記の裏に潜む意図
仮登記というのは、本登記を行うための準備段階だ。にもかかわらず、そのまま何十年も放置されているということは、何かしら本登記できない理由があったのだろう。だが、調査を進めても手がかりが見つからない。
そんな中、ふとしたことで、ある時代の法改正に気づく。昭和62年、仮登記に関する運用が大きく変わったその年。そこに何かがある。いや、何かを隠した者がいる。
サトウさんの分析
塩対応と冷静な洞察
「これは、、、まあ、明らかにおかしいですね」デスク越しにサトウさんが言った。こちらの苦悶の表情とは裏腹に、彼女の声は涼しい。まるで天気予報でも話すような調子だ。
「仮登記に“条件付き”なんて、聞いたことないです。昭和62年あたりの改正前なら、もしかすると無理矢理通したのかもしれませんけど」彼女の指摘は正確だった。私は小さくうなずいた。
昔の登記慣行と今の落とし穴
「昔はさ、地元の登記官もいい加減だったんだよ」と私はつぶやいた。まるでサザエさんの波平のように説教じみた口ぶりだったが、サトウさんは「へえ」としか返さなかった。
当時の“慣行”で済まされていた処理の数々が、今の制度では通用しない。それがこの土地をめぐる混乱の原因であり、また闇でもあるのだ。
現地調査と行方不明の証人
朽ちた長屋と失踪した元所有者
依頼人の祖父が所有していたという場所を訪れた。そこには、かつて長屋があったらしいが、今は基礎部分がわずかに残るだけ。あたり一面、夏草が茂っていた。
「ここに住んでた人、今どこにいるんでしょうね」と私はぼそりとつぶやいた。近所の住人に聞き込みをしたが、みな「知らない」「昔の話だ」と首を振るばかりだった。
空き家に残された一本の鍵
調査中、取り壊されていない隣接する空き家に入ったときのことだ。埃をかぶった靴箱の中に、古い鍵が一本だけ転がっていた。革のタグに「山下」と書かれていた。
その名前は、登記簿に仮登記義務者としてかすかに読み取れる文字と一致していた。ようやく点と点がつながったような気がしたが、それだけではまだ証明には足りなかった。
記録にない取引
公正証書と登記簿の不一致
古い公証役場に保管されていた文書を取り寄せると、「土地使用に関する覚書」というタイトルの公正証書が見つかった。そこには祖父と“山下”の名前があった。
だが、その取引内容は所有権の移転を前提としておらず、「一定期間使用を認める」というだけのものであった。仮登記とは、まったく結びつかない内容だ。
関係者の証言とその矛盾
町内会の古老に話を聞くと、「山下さんはずっと“この土地は俺のもんだ”って言ってたよ」と証言してくれた。だがその一方で、「でも、誰も登記はしてなかった」とも語った。
どうやら、勝手な思い込みが年月を経て“真実”のように語られるようになったらしい。その誤解が、登記簿の中にまで染み込んでしまったのだ。
過去の約束が語る真実
十年前の契約書の行方
調査の末、依頼人の家の仏壇の引き出しから古い封筒が見つかった。中には祖父と山下の間で交わされた「譲渡の合意書」があった。日付は昭和62年。
そこには「諸般の都合により、名義変更は仮登記とする」との文言が明記されていた。ようやく謎の仮登記の理由が明らかになったのだ。
サインが示すもう一人の当事者
さらに文書には、見覚えのない第三者のサインがあった。調べてみると、それは当時の仲介業者のもので、彼が間に入ったことで、条件付きの仮登記が通ってしまった可能性がある。
そして、その業者は現在、近隣の町で不動産会社を営んでいることが判明した。サトウさんが電話で話をつけ、明日、訪問することになった。
シンドウの推理
やれやれと言いつつ辿り着いた仮説
やれやれ、、、また古い話に巻き込まれた。私はそうつぶやきながら、事件の全体像を整理していた。仮登記の正体は、曖昧な関係と未完の約束の産物だったのだ。
だが、それを法的に処理するには、過去の書類と今の証拠を丁寧につないでいくしかない。司法書士という仕事の面倒な部分でもあり、また一番の醍醐味でもある。
一見無関係な出来事の連鎖
鍵、公正証書、仮登記、口約束、そして仏壇の封筒——すべてがばらばらに見えて、実は一つの軸に沿っていた。その軸こそ、祖父が交わした“約束”だった。
私は手続きの筋道を整理し、依頼人に必要な登記手続きの進め方を説明した。「この仮登記、解除できますよ。時間はかかりますけどね」と付け加えて。
真犯人との対峙
動機は過去に交わされた口約束
真犯人と呼ぶべき人物は、誰かを騙した者ではなく、曖昧な言葉に縛られた者だった。山下という男は、口約束を過信し、正式な手続を怠っただけなのだ。
しかし、その過信が結果として依頼人の人生を狂わせかけていた。記録に残さなかったこと、それがこの事件のすべてだった。
遺産と土地を巡る誤解と欲望
依頼人の親族の中には、「あの土地は本当はウチのものだ」と言い張る者もいた。しかし法的根拠はどこにもなかった。登記こそが、唯一の“言い分”を形にする方法なのだ。
結局、仮登記を抹消する手続きを進めることになった。私はその申請書を作成しながら、いつもより丁寧に書式を確認した。
解決とその代償
登記の力がもたらす正義と虚しさ
仮登記の抹消が完了した日、依頼人は静かに頭を下げて帰っていった。土地を得たわけではない。だが、過去の曖昧さが整理されたことに、ある種の安堵を覚えていたようだった。
私もまた、あの封筒の中の一言を思い返していた。「登記は真実を語る」それは、時に冷酷で、時に人を救うものでもある。
サトウさんの一言が胸に刺さる
「やっぱり紙より口頭のほうが信じてる人って、案外多いんですよね」サトウさんがぼそりと呟いた。その声はいつもより少しだけ優しかった。
私はうなずき、疲れた肩を回した。事件は終わった。でも、この仕事が終わることは、たぶんない。
その後の事務所
静かな日常と依頼の山
再び静けさを取り戻した事務所で、私は山積みの書類にため息をついた。夏の陽射しが窓から差し込み、紙の白さを照らしていた。
「また役所行かなきゃだな……」とつぶやきながら、次の登記簿に手を伸ばす。コーヒーはもう冷めていた。
「また妙な依頼が来ましたよ」と塩対応
そのとき、奥からサトウさんの声が響いた。「また妙な依頼が来ましたよ」私は肩をすくめた。「やれやれ、、、こっちはまだ一息ついてないのに」
事務所の時計が、静かに午後二時を告げていた。