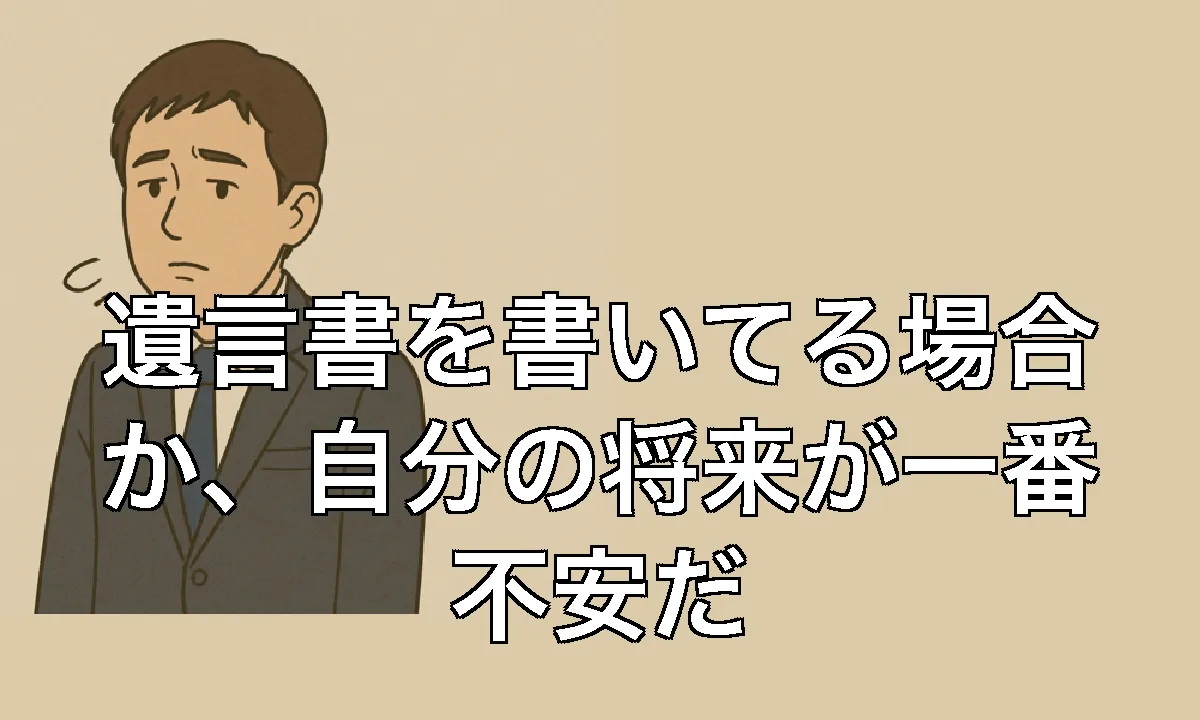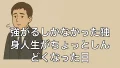遺言書の相談を受けながら、ふと我に返る
ある日、60代の女性が「そろそろ遺言書を作っておきたいんです」と相談に来た。自分の持ち家の処分、子どもたちへの財産分与、そして残された家族への思いやり――話を聞きながら、こちらは何度もうなずき、手際よくヒアリングを進めていく。けれど、ふと心に冷たい風が吹いた。「この人、ちゃんと自分の人生を設計してるな」と。それに引きかえ、自分はどうだ。誰に何を残すわけでもなく、年金の見込みも薄く、結婚もしておらず、毎日ぎりぎりで仕事をこなしているだけの毎日。遺言書よりも、むしろ自分の生活そのものが危ういのでは、と気づいてしまった。
「財産をどう分けるか」より、「生きていけるか」が先
世の中には遺すべき資産があり、残すべき人がいる人も多い。でも自分にはそういったものがほとんどない。そうなると「誰にどう分けるか」の前に、「そもそもこれから生き延びていけるのか」という不安が襲ってくる。年金も微々たるもの、貯金も心許ない。さらに独身で子どももいないとなると、老後の生活は一層不透明になる。相続の書類を作成している最中、自分が書く側に立った時のイメージがまったく湧かない。生きるために必要なことの方が、今ははるかに差し迫っている。
年金も不透明、預貯金も雀の涙
司法書士という職業は、外から見ると安定しているように思われる。でも実際にはフリーランスに近く、収入は年によってまちまち。年金も国民年金だけ、厚生年金のように手厚くはない。加えて地方の事務所では案件数も限られており、毎月の支払いがギリギリというのも珍しくない。預貯金も、経費や突発的な支出にすぐ消える。家賃や光熱費、事務員への給料を払ったら、手元にはほとんど残らないこともある。「もし明日、病気で倒れたら?」と考えると、背筋が寒くなる。
お客様の未来設計と自分のギャップ
遺言書を作る方々は、しっかりした老後のプランを持っている。子どもや孫の顔を思い浮かべながら、どうすれば揉めずに財産を渡せるかを真剣に考えている。その姿に感動すら覚える。でも同時に、自分にはそんな「誰かの未来のために今から準備をする」という行為ができていないことに、焦りを感じる。誰かのためではなく、自分の生活の維持で精一杯な現実が、ぐさりと突き刺さるのだ。
地方の司法書士、仕事はあるけど心が渇く
田舎でも登記や相続の仕事はある。むしろ都会より、戸籍の古い案件や土地の問題などで依頼が絶えないこともある。でも仕事がある=幸せ、というわけじゃない。人間関係の薄さ、相談者との距離感、日々の孤独感――どれも精神を少しずつ削っていく。終わった後の達成感はあるけれど、机に戻ったときの空虚さはどうにもならない。誰かと語り合うでもなく、肩をたたいてくれる人もいない。そんな日が何年も続いている。
相談件数はある。でもなんだろうこの空虚さ
「忙しいですね」と言われるたび、嬉しい気持ちと同時に虚しさも感じる。たしかに依頼は来るし、書類も山積みだ。でもそれが何になる?達成感よりも「また一日が終わったな」という疲労感だけが残る。お客様に感謝されることもあるが、その場限りの感情だ。事務所を出て帰宅しても誰もいないし、誰かに今日の出来事を話すわけでもない。ただテレビの音が部屋に反響するだけだ。
孤独感と「代わりがきかない仕事」のプレッシャー
司法書士の仕事は専門性が高い分、代わりが効かない。自分が体調を崩せば、その日から業務は止まる。休むことが怖くなり、無理して働くようになる。そして気づけば、どこにも逃げ場がない状態になる。周囲に頼れる人もいない。プライベートもほとんどなく、病院に行くのも後回しになりがちだ。自分ひとりが抱えすぎて、どんどん壊れていく感覚がある。
事務員さんの何気ないひと言に救われる日も
そんな中でも唯一の救いは、事務員さんの存在だ。とくに優しい言葉ではなくても、「お昼どうします?」のような何気ない一言が、驚くほど心を軽くすることがある。人の存在って、こんなにも大きいのかと実感する瞬間。誰かがいるだけで、仕事の孤独感が和らぐ。とはいえ、事務員にすべてを依存するわけにもいかない。そのバランスもまた、難しいところだ。
「自分の遺言書」なんて書けるほど、整ってない
人には「今のうちに作っておいた方がいいですよ」と言っているくせに、自分のことになるとまるで手がつけられない。遺言書どころか、エンディングノートすら白紙だ。いざ書こうとしても、「誰に何を?」という段階で詰まってしまう。書くことがないというより、書ける未来が想像できない。そんな現実に向き合うのが怖くて、結局後回しになってしまっている。
実家暮らしのまま、気づけばアラフィフ
独立してからも、実家に住み続けている。家賃を浮かせる意味もあるし、親も高齢なので一緒にいた方が安心だという理由もある。でも気づけば、自分は何も変わっていない。10年前と同じ場所で、同じ生活をしている。変わったのは年齢と体力だけ。独立して自由になったはずなのに、どこかで時間が止まっているような感覚がある。
残す相手も、守る家族もいないリアル
遺言書の要点は「誰に何を残すか」だ。でも、自分にはその「誰か」がいない。結婚もしていないし、子どももいない。兄弟もそれぞれ家庭があり、関係も希薄。財産があったとしても、残して喜んでくれる相手がいないのだ。そんな現実を直視すると、「果たして自分の人生って何だったんだろう」と、深い溜息が出る。
それでも「今日もなんとかやってる」人に伝えたい
毎日がギリギリでも、心が乾いていても、それでも仕事に向かっている人はたくさんいる。自分もその一人だ。誰にも言えない不安や、どうにもならない孤独を抱えながら、それでも誰かの役に立とうとしている。そんな人に「あなたは一人じゃない」と伝えたくて、この文章を書いている。誰かが共感してくれるなら、それだけでも救いになる。
相談を受ける側だって、悩んでる
「先生だから安心して話せます」と言われることがある。でも本当は、こちらだって不安を抱えている。プロとしての責任はあるけれど、人間としての弱さも消えるわけじゃない。悩みながら、それでも前に進もうとしている。完璧じゃない自分を許しながら、今日も書類と向き合っている。そういう姿勢もまた、ひとつのプロのあり方かもしれない。
「ちゃんとしなきゃ」に押しつぶされそうな日もある
資格を取ったから、独立したから、「ちゃんとしてなきゃ」と思い込んでいた。でもそれが自分を追い詰めていたことに、最近ようやく気づいた。理想の自分と、現実の自分。そのギャップに苦しむ日もあるけれど、それでも毎日仕事をこなしているなら、それで十分じゃないか。そんなふうに思えるようになってきたのは、失敗や苦しみをたくさん経てきたからかもしれない。
誰かと分かち合うだけで、少しラクになる
悩みは、話すことで軽くなる。愚痴でも、ため息でもいい。心の中にため込まずに、誰かと分かち合うだけで、少しだけ前を向けるようになる。もしあなたが今、同じような不安を抱えているなら、この文章を読んで「自分だけじゃない」と思ってもらえたらうれしい。司法書士も、一人の人間なんです。