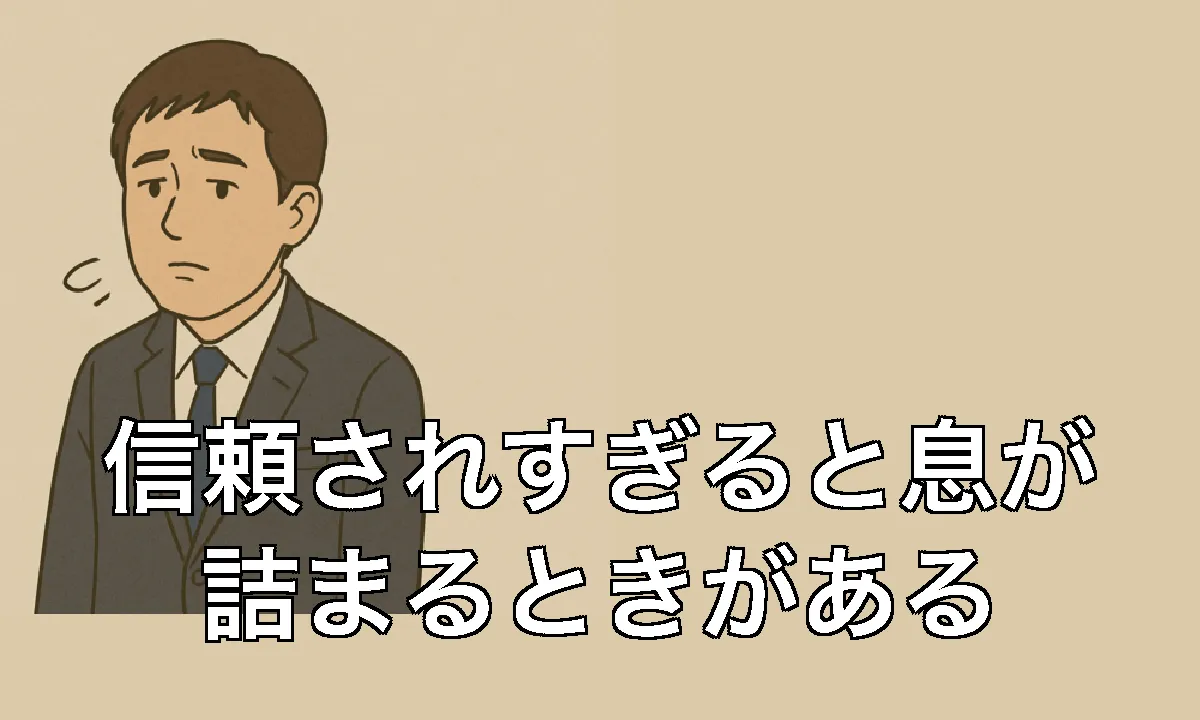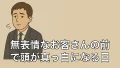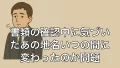信頼はありがたいはずなのに息苦しい
司法書士という職業は、ある意味「信頼されてナンボ」なところがあります。依頼人から信頼されることは、この仕事に就いた当初こそ誇りでした。けれど、長く続けていくうちに、それがだんだんと重く感じられてくる瞬間があるんです。「先生なら大丈夫」「任せて安心です」と言われるたびに、期待に応えなきゃというプレッシャーが自分の肩にずしりと乗ってくる。ありがたい言葉のはずなのに、それがいつしか重荷になる。そういう日々の中で、「信頼」って何だろうと考え込むようになりました。
頼られることが前提になる日々
「○○先生に相談すれば間違いない」──そんな言葉が当たり前のように飛び交う日常。地域でやってると顔も名前も覚えられて、何かあればすぐに相談が来るんです。飲みの席でも、法的な話を振られる。ちょっとした会話でも気が抜けない。事務所にいるときだけじゃなく、生活そのものが“司法書士モード”になってしまう。頼ってもらえるのはうれしい。でも、四六時中そういう目で見られていると、気が抜ける時間がどこにもないんですよね。
「先生なら大丈夫ですよね」と言われ続けて
実際、トラブルが起きたときや相続の相談などで、「先生にお願いして本当に良かった」と言われると、心からうれしいです。でも同時に、「この人の人生の一部を自分が背負ってるんだ」と思うと、一歩踏み出すのが怖くなる瞬間もある。失敗できないし、感情的な揺らぎも見せられない。そんなふうにして、だんだんと“普通の自分”が隠れていく感じがしていました。
不安も弱音も出せない雰囲気に押しつぶされる
ふと気づけば、「弱音を吐くこと」が許されていない自分になっていました。いつも冷静で、答えを持っていて、解決してくれる存在であることを期待される。だからこそ、「実は自分も不安なんです」とは言えない。そんな毎日が続くと、自分の感情の出口がわからなくなって、どこかでポキッと折れてしまいそうになるんです。だけど、それを誰にも言えない。これが“信頼の罠”なんだと、ある日気づいたときには、かなり追い詰められていました。
気づけば逃げ場のない立場に
開業して10年近く経ちました。最初は右も左もわからなかったけど、少しずつ仕事が軌道に乗ってくると、「ちゃんとやってるんだろうな」という周囲の安心感みたいなものが生まれてくる。でもそれって、裏を返せば「もう大丈夫な人」という扱いを受けるということでもあるんです。実際は毎日が手探りで、書類の山と格闘しながら「間違ってませんように」と願い続けてるのに。
事務員にすら心配かけられない
うちの事務所には事務員さんが一人います。若いけどしっかり者で、すごく助けられてます。でも、だからこそ、彼女に心配かけたくないって思ってしまう。愚痴を言えば気を使わせるし、疲れた顔を見せれば不安にさせてしまう。そう思って我慢を重ねるうちに、自分の「平気なふり」が板についてしまってました。たぶん、これも「信頼される人」の裏側なんですよね。
全部背負う性格が災いしてるのか
昔から、何でも「自分がやらなきゃ」と思い込んでしまうタイプでした。野球部でもキャプテンじゃなかったけど、いつもチームをまとめる役回りをしていた記憶があります。あの頃から、誰かの感情のバランスを取ることが自分の役目だと思ってた。でも仕事になると、それがより強烈になって、「誰かに任せる」とか「自分が間違えてもいい」と思えなくなる。今思えば、それが自分を追い詰めてたんでしょうね。
信頼=孤独になる瞬間
信頼されるということは、ある意味“壁”を作ることでもあると気づきました。強く見える人、安心感のある人、ミスをしない人──そんなイメージが自分のまわりにどんどん積み上がって、本当の自分がその奥に隠れていってしまう。ふとした瞬間に、「誰も本当の俺のことなんて知らないんじゃないか」と思ってしまうことすらある。それでも仕事は待ってくれない。誰かが困っていれば、自分が立たなきゃいけない。それが司法書士という職業のつらさでもあります。
誰にも頼れない構造がしんどい
困ってる人の話を聞いて、「大変でしたね」と受け止めるのは得意です。でも、じゃあ自分が同じように誰かに話せるかというと、それができない。司法書士同士でも、「疲れた」と言えば、「じゃあもうやめれば?」みたいな空気になることがある。だからこそ、何も言えず、何も出せず、どんどん孤独になっていく。正直、これは仕事の内容よりもしんどい部分かもしれません。
元野球部だった頃はチームで戦っていた
野球をやっていた頃は、ミスをすれば誰かがカバーしてくれたし、打てなければ次のバッターが打ってくれた。みんなで勝って、みんなで負ける。そんな「分担」が当たり前だった。でも司法書士は基本的に個人プレー。しかも責任は重い。誰にも振れない仕事を一人で担う日々。元野球部としては、「チームが恋しい」と思うことがしょっちゅうあります。
今は独りで受け止め続けるキャッチャー役
例えるなら、ずっとピッチャーのサインを読みながら、誰にもバッテリーを組まずにキャッチャーをやってる感じです。ボールは飛んでくる、審判の目もある、観客も見てる。でもこっちは誰にも相談できない。たまにはピッチャーが必要だし、監督もいてほしい。でも現実にはそういう存在がいない。それでも試合は続いていく。まさに、そんな感覚なんですよね。
「モテない」のと同じ構造かもしれない
ふと思うんですけど、これって恋愛がうまくいかないのと似てる気がします。自分の感情を隠して、いい人でい続けて、相手の期待に応えることに必死になっていると、「本音の自分」がどんどん遠くなっていく。結局、誰にも本気で自分を見せられないから、心が通わない。「信頼」と「愛される」は違うって、歳を重ねてからやっとわかってきました。
人の期待に応え続けることの副作用
人の期待に応えるのって、達成感もあるし、やりがいもある。でもそれが“常態化”すると、自分がどんどん消耗していく。無理して笑って、無理してこなして、「すごいですね」って言われて。でもその裏側で、自分の素の部分がすり減ってる。だからこそ、最近は「期待に全部応えなくていい」と思うようにしてます。たまには、期待を裏切ることも必要なんじゃないかと。
誰かに甘える勇気を持てるようになった話
そんなふうに日々しんどさを感じていたある日、ちょっとしたきっかけで、同業の先輩と雑談する機会がありました。何気なく「最近、全部しんどいです」って言ったら、「ああ、俺もしょっちゅうそう思ってるよ」と言われて拍子抜けしたというか、救われた気持ちになったんです。信頼されることって、完璧でいることじゃない。自分の弱さも出していい。それを初めてちゃんと認められた瞬間でした。
本音を言える相手がいないと壊れる
この仕事って、どれだけ能力があっても、本音を言える人がいないとダメになります。制度や知識じゃなく、感情の処理の問題。自分の気持ちをちゃんと扱えないと、仕事の精度にも影響が出てくる。だから今は、意識して月に1回は誰かに愚痴をこぼす時間をつくるようにしています。たったそれだけで、驚くほど気持ちが軽くなるから不思議です。
ちょっと愚痴をこぼすだけで変わったこと
本音を言うって、相手を信じることでもあるんですよね。以前は「そんなこと言ったら嫌われる」と思ってたけど、実際は逆だった。素直な弱音を聞いた人は、むしろ自分を理解してくれたり、共感してくれたりする。信頼を“作る”ために強くなるんじゃなくて、信頼を“深める”ために弱さを見せる。今はそんなふうに考えるようになりました。
信頼は受け止めすぎなくても大丈夫
結局のところ、信頼って全部抱え込むものじゃないんです。受け止めきれないときは誰かに頼っていいし、期待に応えられないときは「無理です」と言っていい。完璧な司法書士じゃなくていい。ただ、真摯であればいい。それだけで、十分信頼される資格があるんだと思います。そうやって少しずつ、肩の力を抜いて生きていくのが、今の自分の目標です。