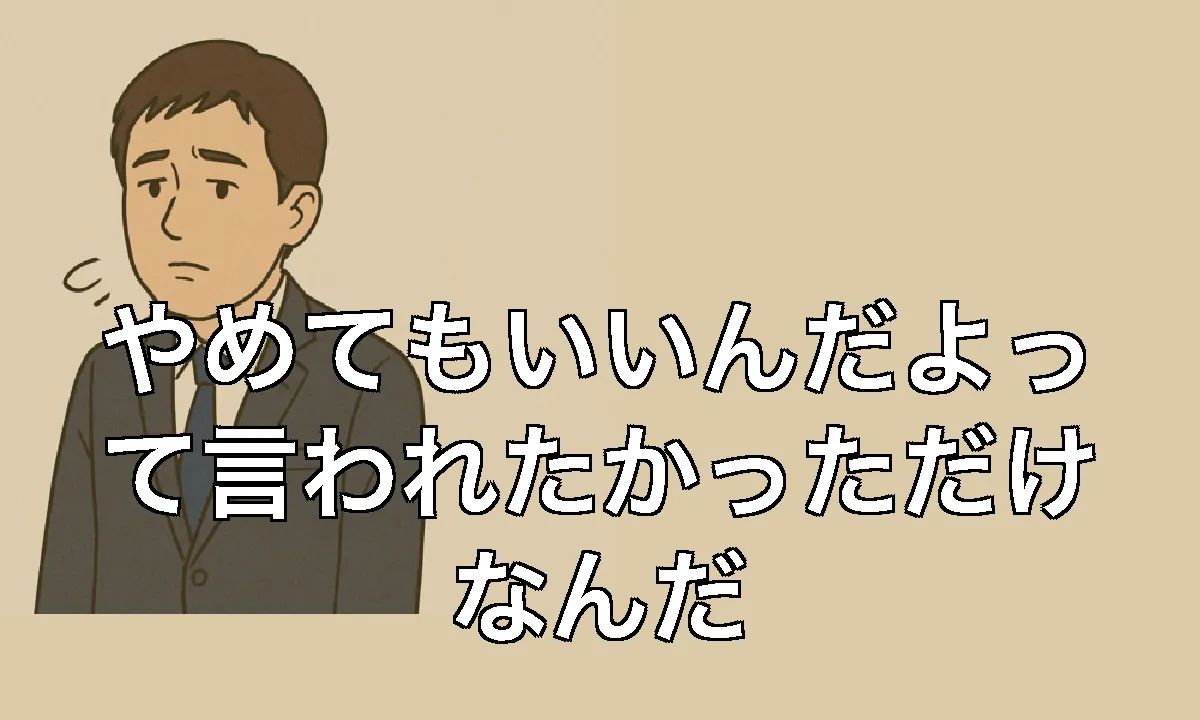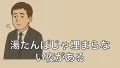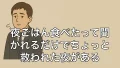続けることが正しいと思い込んでいた日々
司法書士という職業を選んだあの日から、「やめる」という選択肢は頭のどこにもなかった。とにかく前に進むこと、立ち止まらないことが美徳だと信じてきた。朝から晩まで登記や相続の書類に追われ、休日も電話やLINEでの対応に明け暮れ、それでも「これが仕事だ」「自分で選んだ道だ」と言い聞かせてきた。気づけば笑う余裕も、深呼吸する瞬間もなくなっていた。地方で一人事務所を構え、雇っている事務員にも気を遣い、背中を丸めてパソコンに向かう自分を見ながら、心の奥でずっと「やめてもいいんだよ」と誰かに言ってほしかった。
頑張ることしか選べなかった自分
小さな頃から「努力は報われる」と教えられてきた。元野球部だったこともあり、「やめたい」と口にすることは「甘え」だと思っていた。どれだけ辛くても、歯を食いしばって耐えれば何とかなると信じていた。だけど、現実は違った。努力しても報われないことは山ほどあるし、頑張り続けることが必ずしも正解ではないと、身をもって知った。事務所の経営も思うようにいかず、士業の競争は厳しい。それでも「やめます」とは言えなかった。
司法書士という肩書きに縛られていた
合格まで何年もかけて、やっとの思いで手に入れた司法書士という肩書き。それがあるから、親にも安心してもらえたし、地元での信頼も得られた。でもその「肩書き」が、いつしか自分を苦しめる鎖になっていた気がする。「せっかく資格を取ったのに」「今さら辞めるなんてもったいない」と周りの目を気にして、気づけば身動きが取れなくなっていた。
弱音を吐くことに罪悪感があった
「疲れた」「もう無理かもしれない」と思っても、それを言葉にすることはなかった。言えば自分が崩れてしまいそうだったし、事務員に余計な心配をかけたくなかった。ネガティブなことを吐き出すと、なんだか「負けた」ような気がしてしまって。だからこそ、心のなかでは「やめたい」と何度もつぶやいていたのに、表面上は「まだ大丈夫です」と笑ってしまう自分がいた。
「まだ頑張れる」は呪文になっていた
疲れているのに、「まだ頑張れる」と自分に言い聞かせる癖がついていた。これはある意味、自分を守るための呪文だったのかもしれない。頑張っていないと、存在価値がなくなる気がしていた。でも、どこまで頑張れば終わりが見えるのか、いつまで耐えれば楽になれるのか、それがまったく見えなかった。
誰も止めてくれない孤独な現実
一人で事務所を切り盛りしていると、当然だが誰も止めてはくれない。上司もいなければ、同僚もいない。黙って働いていれば、「あの先生は頼れる」と思われるだけ。誰かが「無理しすぎじゃないですか」と声をかけてくれたら、少しは違ったかもしれない。でも、田舎の人間関係はそう甘くない。弱みを見せれば噂され、敬遠される。だから今日も無言で仕事を続けていた。
休むことに理由を求めてしまう癖
本当はただ、休みたかった。何の理由もなく、誰の目も気にせず、数日間ぐうたらしていたかった。でもそれには「体調不良」や「急ぎの用事」など、正当な理由が必要だと思い込んでいた。だから、何もないのに「今日は休みます」とは言えなかった。自分に休む価値があるとは思えなかったのかもしれない。
やめることへの恐怖と抵抗
「やめる」と口にすることは、全てを失うような怖さがあった。これまで積み重ねてきたもの、人間関係、信頼、収入、そして自分自身の誇りまで手放すことになる気がしていた。だからこそ、どんなに苦しくても「やめたい」とは言えなかった。それが、結局自分をどんどん追い詰めていたんだと思う。
「投げ出したら終わり」だと思っていた
子どもの頃、練習がしんどくてサボろうとしたら、監督に「逃げるやつは一生逃げる」と言われたことがあった。それ以来、「投げ出す=負け」という感覚が染み付いてしまった。司法書士として独立してからも、「逃げるわけにはいかない」という思いが強く、やめたいと思っても踏み出せなかった。でも、今思えば、無理して続けることが正解じゃない場面もあるのだ。
元野球部の根性論が抜けない
野球部の頃は、怪我してても「気合いでなんとかしろ」と言われるのが当たり前だった。根性がすべて、気持ちで負けるな。そんな教えが身体に染みついてしまっているせいか、大人になっても「気持ちでなんとかする」ことに固執していた。だから、心が折れそうになっても「気合いが足りないだけだ」と自分を責めていた。
事務員にも迷惑をかけたくないという責任感
小さな事務所で働く事務員は、私の右腕であり、時には相談相手でもある。彼女に迷惑をかけたくないという思いも、やめることを遠ざけていた。私が倒れたら彼女の生活にも影響が出る。そんな責任を勝手に背負い込んで、余計に自分を追い込んでいた。誰もそんなこと求めていないのに、勝手に自分の中で義務化していたのだ。
他人の目が気になって決断できなかった
やめたいという気持ちは本物だった。でもそれを口にした瞬間、「逃げた」と思われるのが怖かった。親戚や近所の人、同業者や依頼者、みんなの目が気になって、踏み出せなかった。誰かに否定されるのが怖くて、やめることを「失敗」と捉えてしまっていた。でも実際は、自分の人生を守るための選択肢のひとつだったのだ。
田舎ならではの目線と評価
田舎は狭い。人と人との距離が近く、良くも悪くも噂はすぐに広まる。「最近あの先生、元気ないね」「仕事減ったんじゃない?」そんな声が聞こえてきそうで、どこにも逃げ場がなかった。小さな町の中では、自分の立場が崩れることへの恐怖が常に付きまとっていた。
もしあのとき誰かがやめてもいいよと言ってくれたら
「やめてもいいよ」その一言が、どれだけ救いになるか。もしあのとき、誰かが真剣にそう言ってくれていたら、私はもっと早く楽になれたかもしれない。何も解決しなくてもいい。ただ「あなたが無理しているのは伝わってるよ」と認めてくれる人がいれば、それだけでよかった。
言葉ひとつで心が救われることがある
実際、ある日ふと会った同期に「無理してない?やめたって誰も責めないよ」と言われたことがある。その瞬間、張り詰めていたものがぷつんと切れて、気づけば涙が出ていた。たったそれだけの一言で、心の中のもやが晴れていった。「認めてもらえた」感覚が、あれほど心にしみたのは初めてだった。
本音を受け止めてもらえる安心感
本音を誰かに話すって、本当に怖い。否定されるんじゃないか、笑われるんじゃないか、そんな不安でいっぱいになる。でも、受け止めてくれる人がいるとわかった瞬間、世界の見え方が変わる。司法書士だからって、全部ひとりで抱え込まなくていい。そんなふうに思えるようになったのは、あの一言があったからだ。
相談できる存在の大切さを痛感した
今までは、相談すること自体が「弱さ」だと思っていた。でも、それは間違っていた。誰かに話すことで、自分の気持ちを整理できるし、新しい視点も得られる。一人で抱え込んでいても、答えは出ない。だからこそ、身近に相談できる人を持つことの大切さを今は強く感じている。
いまだから言えるやめてもいい自分への言葉
あのときの自分に声をかけられるなら、こう言いたい。「やめても、逃げても、大丈夫だよ」って。続けることだけが正義じゃない。やめたからこそ見える世界だってある。人生は一度きり、頑張ることも大事だけど、自分を守ることのほうがもっと大切だ。
頑張ることも立派だけど頑張らない選択も尊い
頑張ることは素晴らしい。でも、頑張らないという選択も、同じくらい尊い。自分の心を大切にして、立ち止まったり、戻ったりすることも必要だと思う。むしろ、無理に前に進むことで傷つくくらいなら、少し遠回りでもいい。自分のペースで、自分らしく生きることを選べる自分でありたい。
やめることは逃げじゃない次の一歩
「やめる」と決めたその先に、新しい景色が待っているかもしれない。逃げることじゃなくて、切り替えること。やめた先に、また別の道があると信じること。それができるようになった今の自分を、少しだけ誇らしく思えるようになった。
自分の心に正直に生きるという選択肢
もう、人の目ばかり気にして生きるのはやめたい。これからは、自分の心の声に正直に生きていきたい。司法書士という職業に誇りを持ちつつも、それに縛られず、自分らしい道を選べる勇気を持っていたい。そして、もし同じように悩んでいる誰かがいたら、こう声をかけたい。「やめてもいいんだよ」って。